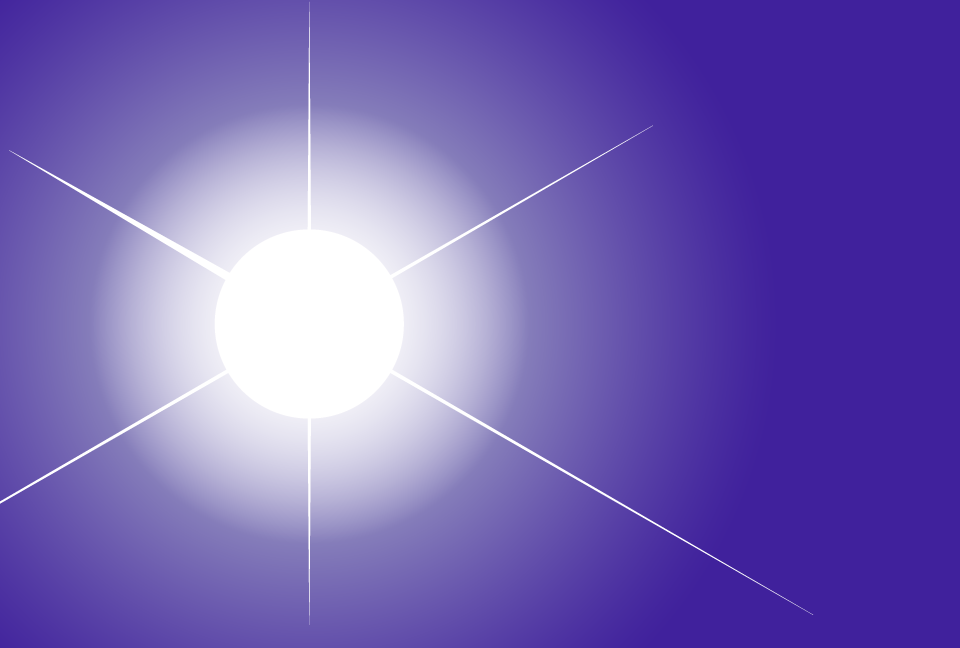解説
自分自身に対して知っていることと、知らないこと。
この物語は村上自身がこれまでの一人称の総決算であり里程標としています。物語の文中に作家志望のすみれを借りて記す場面があります。
文章が「うまく書きとおせる」自身があったことなんて、生まれてこの方一度だってなかったのではないか。
何かについて考えるには、その何かを文章にしてみる必要がある。そして結論を出すには時間がかかり、大人になってもずれを感じつづけていた。しかし私たちの世界にあっては「知っていること」と「知らないこと」は分かちがたく、混沌として存在している。
理解というものは、つねに誤解の総体に過ぎない。
デビュー作の『風の歌を聴け』のなかで、文章を書く動機を自己への癒しとした村上だが 理解とは誤解の総体であると、さらに進めている。
そして知と非知を分けることを放棄してみて「知っていること」と「知らないこと」を同居させるには、思考をすることが大切という。そのために自分をどこかにつなぎ止めておくことが大切という。
そうしなければ、わたしたちはまず間違いなく、ろくでもなく罰当たりな「衝突コース」を進んで行くことになる。
つまり、思考なしに「知っていること」と「知らないこと」を同居させると互いが理解できずに、混乱し、見失い、何かに衝突するという。
この物語の執筆の前に、村上はオウム事件を取り上げた『アンダーグランド』と『約束された場所』の二つの作品をインタビュー形式で仕上げ発表している。
この未曽有の惨劇を<こちら側>と<あちら側>の間で起こった人間社会の闇が放出した事件として捉える。それは別々のものではなく内在され鏡像であるとします。この衝撃は<デタッチメント>から<コミットメント>へと村上文学を転換させた。
その時期に書かれた『スプートニクの恋人』では、22歳の「すみれ」の39歳の「ミュウ」への思い、24歳の主人公である「ぼく」の「すみれ」への思いを、人工衛星の軌道に見立ててファンタジーで展開していきます。物語のなかの「ぼく」は傍観者のような位置づけです。
そしてまじめに思考することもせず、しかも衝突を免れるためには、人はいったいどんなことをすればいいか?と物語の中で問いかけます。それは、
夢を見続けること。夢の世界に入って、永遠に出てこないこと。そこで永遠に生きていくこと。
としています。夢の中では物を見分ける必要もなく、境界線も存在しない。だから夢の中では衝突はほとんどないし、あっても痛みはないというわけです。
そして『スプートニクの恋人』の世界に誘います。それは読者にフィクショナルな物語を提示して、フィジカルに体験し理解することで、生きる苦しさや辛さから救い、良識を確認させる役割を果たしているのかもしれません。
現実は違う。現実は噛みつく。そんな事実を我々は知っています。
観覧車の中で起こった、ミュウの見たドッペルベンガー。
ミュウは幼い頃からピアノの演奏に優れ、将来は明るかったが、ある時を境に二度と鍵盤に手を触れなくなる。それは彼女が14年前に経験した奇妙な出来事と深い関係があった。
その後、ミュウはスイスの町にいたが、フェルディナンドという50歳前後のハンサムなラテン系の男とカフェで知り合い軽く世間話をする。二日後にまたカフェで出会い、その視線に肉体的に求められていることを感じとる。
彼女は性欲の匂いを嗅ぎ、怯え、彼から遠ざかるためカフェに近寄らなくなる。彼女はそれ以来、フェルディナンドの姿を町でよく見かけ跡をつけられているように感じる。ミュウは少しずつ不安の混じった苛立ちを覚えるようになる。
あるとき観覧車に乗り、老人の係員の手違いで一晩閉じ込められてしまう。助けを求めるが夜も更けていき、諦めて、興味本位で、観覧車の中から自分の部屋を双眼鏡で覗く。そこには一糸まとわぬ裸のフェルディナンドがいた。
彼女は腹を立て、そして激しく混乱する。それから一人の女が姿を見せる。ミュウは双眼鏡を握りしめ、目を凝らす。
それは、ミュウ自身だった。
ミュウが身に着けているものと同じものを双眼鏡の向こうの彼女も身に着けていた。そして服を脱がされフェルディナンドと激しく性行為をしている。部屋の中のミュウは喜んで彼を受け入れている。
まるで計算されたように彼らはそれをミュウに見せているのだ。それはとてもおぞましいことだった。
自分の「もうひとりの自分」を見るドッペルベンガーで気を失う。
わたしはこっちにいて、もう一人のわたしがあっちにいて、彼は、そのフェルディナンドは、あっち側のわたしに対してあらゆることをした。
とミュウは言う。汚すことだけを目的に行われる、意味もない淫らな行為。そして最後には、それはフェルディナンドですらなくなっている。
気がつくとミュウは病院のベッドに横になっていた。そして25歳のミュウは、この時たった一晩で、髪が一本残らず真っ白になった。そうしてミュウは失われた。
それから<こちら側>のわたしは、ぬけがらのようになってしまった。黒い髪と性欲と生理と排卵と、生きる意志を持ったわたしは<あちら側>に行ってしまった。
わたしという人間が、決定的に二人に引き裂かれてしまったのよ。
そうミュウは語る。それは奪い去られたのではなくて、向こう側に存在し一枚の鏡によって隔てられている。ただしその隔たりを永遠に越えることができない。そして、
鏡のどちら側のイメージが、わたしという人間の本当の姿なのか、わたしにはもうそれが判断できなくなってしまっているということなの。
この体験の後、ミュウは音楽をつくり出す力を失ってしまったのだ。
それは、自立心が強く、きまじめな性格で強く生きていこうとするあまり、弱い人々や幸運じゃない人、健康でない人、立ちすくんでいるような人々への温かい心を欠いた自分自身がつくり出したものかもしれないと思った。
この事件以来、ミュウは結婚しても性欲を感じず、その後、誰とも肉体関係を持てなくなった。そしてミュウはスイスでの出来事は自分がつくり出したものかもしれないと思う。
ミュウの全てを知ることは、すみれ自身を知ること。
ミュウが観覧車の話をすみれに話すことを躊躇する場面での言葉がある。
わたしがもしここで箱のふたを開いてしまえば、あなたもこの話に含まれてしまうかもしれない。
そしてミュウはすみれに、忘れてしまいたいと思っている話を知りたいのかと聞く。ミュウはその話をすることで、分裂した<あちら側>をもう一度、認識することを避けたいし、話をすれば、すみれもそのなかに含まれてしまうことを避けたいとする。
その話を聞いたすみれは思う。
わたしはミュウを愛している。言うまでもなく<こちら側>のミュウを愛している。そしてたとえどんなことでもいい、あなたと共有したい。何も隠してほしくないと思う。
でもそれと同じくらい、あちら側にいるはずのミュウのことも愛している。
そう考えると自身が分割されるような軋みを身の内に感じる。ミュウの分割が、わたしの分割として投影され、降りかかってくる。そしてミュウがいる<こちら側>が、本来の実像の世界ではないのなら、私はいったい何者なのか?と思う。
すみれに起こった出来事は、<あちら側>のすみれに会いに行くことだった。
すみれはギリシャのこの小さな島に来てから、何度も繰り返し若くして死んだ母親の夢を見る。4日目の夜、すみれはミュウの寝室を訪れ、自分を抱いてくれるようにお願いする。
ここですみれのプロファイルをもう一度、確認する。
すみれの母親は31歳の若さで亡くなっている。そのときすみれはまだ3歳にもなっていなかった。すみれには母親の思い出が少ない。父親も母親の思い出話をほとんどしない。すみれが「わたしのお母さんはいったいどんな人だったの?」と質問すると、父親は「とても物覚えがよくて、字のうまいひとだった」と答える。そこには情緒的なものはなく、すみれには母親の愛情が記憶にない。
文書1の<すみれの夢>には、
でも母親はどういうわけか、家族アルバムの写真に映っている母親とは別人だった。本物の母親は美しく、若々しかった。やはりあの人はわたしの本当のお母さんじゃなかったんだ、とすみれは思った。
とある。継母はすみれに親切で公正な人で、思春期を通して揺らぐことなく愛してくれた。それでも実母へのすみれの想像は膨らんでいく。すみれの母親も<あちら側>に存在しているのである。
ミュウは39歳。すみれのレズビアンの思いは恋をしたミュウに母親をだぶらせる行為でもある。そして性欲を<あちら側>に奪われ失っているミュウは、これに応えることはできない。レズビアンとしてのすみれの恋は<こちら側>のミュウには受け入れられなかった。
ミュウに失恋して、次の朝に、すみれはいなくなっていた。
そしてきっとすみれは<あちら側>の性欲のあるミュウを取り戻しに行ったのだった。それは<あちら側>にいるすみれの母親を知ることでもあり、すみれ自身を知ることでもあった。
神秘の入口に佇む「ぼく」と、思索しそこから逃れる「ぼく」
僕は<すみれの夢>と<ミュウの分裂>。2つのディスクともに異なった世界であることが分かる。
文書1の<すみれの夢>は、死んだ母親に会いに行くが、彼女は<あちら側>の世界に向けて去ろうとしてすみれはそれを止めることができない。そして行き場のない塔のてっぺんで異界のものたちにとりかこまれる。
文書2の<ミュウの分裂>は、ミュウが体験した14年前の不思議な事件。スイスの小さな町の遊園地で一晩観覧車に閉じ込められ、双眼鏡の中にもう一人の自己を見る。そしてその体験はミュウという人間を破壊し、一枚の鏡を隔てて<こちら側>の世界と<あちら側>の世界に分割された。
その両方の文書に共通しているモチーフは、
明らかに「こちら側」と「あちら側」の関係だった。
そしてきっと、すみれはどこかにそのドアを見つけたのだと考える。
夢を見ることだ。夢を見つづけること。夢の世界に入って出てこないこと。そこで永遠に生きていくこと。
すみれはあちら側に行ってしまったのだ。おそらく<あちら側>のミュウに会いに行ったのだと、ぼくは考える。そして眠ってしまう。
ぼくは音楽の音で目がさめた。大きな音ではない。聞こえるか聞こえないか、そんな遠い音楽の響きだ。
外に出る。ギリシャの音楽が集落もない山の頂きから聞こえてくる。月光に導かれて山の頂きに行く。青白い月の光を受けた身体が異界に入ろうとする体験をする。
月の光が地表を洗っている。ここが<異界>への入口なのだ。
すみれも今どこかで、同じ音楽を耳にしているのではと思う。そしてすみれも同じように、音楽に誘われて坂を上ったのではと思う。
ぼくは空を見上げ、それから月の光の下で、なにげなく自分の手のひらを眺めてみた。そして出し抜けに、それがもうぼくの手ではなくなっていることに気がついた。
とにかくひと目でぼくにはそれがわかった。
この段階で主人公も同じように異界の入口まで来て神秘体験をしている。そして激しい悪寒に襲われ、誰かが細胞を並び替え、意識の糸をほどいているように感じる。
しかしそこで主人公は避難をする。それは思索の底に沈むこと。
ぼくにできるのは、いつもの避難場所に急いで逃げこむことだった。ぼくは息を思いっきり吸い込み、そのまま意識の海の底に沈んだ。
そして石にしっかりと掴まり、目を閉じ、息をつめ、耐える。時間が前後し、絡み合い、崩壊し、並べなおされる。ぼくは固く心を閉ざし、闇の混沌の行列をやり過ごす。
身体の中にあった奇妙な乖離の感覚は、もうあらかた消えてなくなっていた。
心を閉ざしやり過ごす。身体の中にあった奇妙な乖離の感覚は消えて無くなる。音楽が本当に聞こえたのか、それとも音楽なんて存在しなかったのか。月は驚くほど間近に、そして荒々しく見えた。
月の光はそこにあるあらゆる音をゆがめ、意味を洗い流し、心のゆくえを惑わせていた。それはミュウに自らのもうひとつの姿を目撃させた。すみれの猫をどこかに連れ去った。それはすみれの姿を消した。それは(おそらく)存在するはずのない音楽をかなで、ぼくをここに運んできた。ぼくの前には底の知れない闇がひろがり、背後には淡い光の世界があった。
これは現実と異界を結ぶ境界での体験である。
スプートニクの恋人が、にんじんの話で救われる。
物語の扉に1957年10月4日の、世界初の人工衛星スプートニクの打ち上げの話がある。そしてその翌月、ライカ犬を乗せたスプートニク2号は人類に先駆けて宇宙を旅したとある。
ぼくがギリシャの小さな島でミュウに会い、ミュウがすみれとのスプートニクの会話のいきさつの話をする場面。
ねえ、あなたはスプートニクというのがロシア語で何を意味するか知っている?それは英語でtravelling companionという意味なのよ。『旅の連れ』。
ミュウはひとりぼっちでぐるぐると地球を回っている金属のかたまりに過ぎない人工衛星に、どうしてそんな奇妙な名前をつけたのかと訝しがる。
そしてミュウがすみれと身体を交わらせることができなかったときの感情を吐露する場面。
わたしはそのときに理解できたの。わたしたちは素敵な旅の連れであったけれど、結局はそれぞれの軌道を描く孤独な金属の塊に過ぎなかったんだって。遠くから見ると、それは流星のように美しく見える。でも実際の私たちは、ひとつずつそこに閉じこめられたまま、どこに行くこともできない囚人のようなものに過ぎない。ふたつの衛星の軌道がたまたまかさなりあうとき、わたしたちはこうして顔を合わせる。あるいは心を触れ合わせることもできるかもしれない。でもそれは束の間のこと。次の瞬間にはわたしたちはまた絶対の孤独の中にいる。いつか燃えつきてゼロになってしまうまでね。
人間はみなひとりひとりが孤絶し、一瞬、出会うだけで、他と交わることなく、各々の人生を生きていることの象徴となっている。
東京に戻る前、アテネで一泊した夜。ミュウのいる<あちら側>に行ってしまったすみれと、<あちら側>へ行くすべを知らず居場所のないぼくは深い喪失感のなかにある。
それでもぼくは結局のところ、時間の継続性の中から出ていくことを求めなかった。
どうしてみんなこれほどまでに孤独にならなくてはならないのだろう、ぼくはそう思った。どうしてそんなに孤独になる必要があるのだ。これだけ多くの人々がこの世界に生きていて、それぞれに他者の中に何かを求めあっていて、なのになぜ我々はここまで孤絶しなければならないのだ。何のために?この惑星は人々の寂寞を滋養として回転をつづけているのか。
そう考える。そして地球の引力を唯一つの絆として天空を通過し続けるスプートニクの末裔、つまり今を生きる我々、現代人のことを思う。
彼らは孤独な金属の塊として、さえぎるものもない宇宙の暗黒の中でふとめぐり会い、すれ違い、そして永遠に分かれていくのだ。かわす言葉もなく、結ぶ約束もなく。
「ぼく」はすみれに恋をしている。でもすみれには「ぼく」の恋は届かない。
ケルアックの詩の<人はその人生のうちで一度は荒野の中に入り、健康的で、幾分は退屈でさえある孤絶を経験するべきだ。自分が全く己ひとりの身に依存していることを発見し、しかるのちに自らの真実の、隠されていた力をするのだ>の一節に強く憧れるすみれに対して、「ぼく」は現実的で凡庸な見解を述べている。
すみれはミュウに対して竜巻のような激しい恋をした。ミュウは39歳の素晴らしい女性だが不思議な出来事に会う。それ以来、ミュウは<こちら側>と<あちら側>に分裂し、<あちら側>に現実の自分が置き去りにされ、<こちら側>はぬけがらのように生きている。
そして性欲を持たない<こちら側>のミュウを愛しながらも、性欲のある<あちら側>のミュウに抱かれるために、すみれは<あちら側>に消えてしまった。
ここで挿入される中村警備主任とにんじんの話で「ぼく」は救われる。
物語はギリシャの小さな島から東京に戻る。9月の新学期がはじまった日曜の午後、電話が鳴る。それは教え子の母親であり肉体関係を持つ「ぼく」のガールフレンドからで、息子のにんじん(教室での愛称)のことだった。
にんじんは、スーパーマーケットでホッチキスを8個、万引きしようとして警備員に捕まった。以前にもコンパスやシャープペンシルを万引きしようとしてこれで3回目だった。
面談に行った「ぼく」に中村警備主任は、「しかし、いつも思うんですが、先生というお仕事はまったくうらやましいですね、夏休みは1カ月以上とれるし、日曜は休みだし、夜勤もないし、付け届けはあるし」と嫌味を言われる。
「ぼく」は自分の注意不足を認めながらも、子供の万引きの場合は犯罪性よりは精神的な微妙な歪みから来ることが多いと話す。その話を聞いて中村警備主任が続けて言う。
「精神的な微妙な歪みって、いったい何なんですか、それ?ねえ先生、わたしは警察官として朝から晩まで、微妙じゃなく歪んだ人間を相手に暮らしてきました。世の中にはそういう人たちがいっぱいいるんです。掃いて捨てるほどです。そんな人たちの話を長い時間かけて丹念に聴いて、そのメッセージはいったい何だろうなんて真剣に考え込んでいたら、私の身体に脳味噌が一ダースあっても足りません」
そして子供の心は奇麗だとか、体罰はいけないとか、人間はみんな平等だとか、成績で人は評価できないとか、時間をかけて話しあって解決しましょうとか言うが、世の中が何か良くなっていますか? むしろ悪くなっているじゃないか ! という。
この挿話こそが、夢ではない現実。噛みついてくる現実 なのである。
途中、別の誰かが保管庫の鍵を借りに来て、探すが鍵が見当たらない。「最後にひとつ」と中村警備主任は、疑り深くぼくに向けて言う。
「先生を見ているとどうも何か釈然としないところがあるんですよ。若くて背が高くて、感じがよくて、きれいに日焼けして、理路整然としていている。おっしゃることもいちいちもっともだ。きっと父兄の受けもいいんでしょうね。でもうまく言えないんですがね、最初にお目にかかったときから何かがわたしの胸に引っかかるんです。うまく呑み込めないものがあるんです。」
そう言われ、そして解放され、「ぼく」とにんじんは二人きりで話し、「ぼく」はたったひとりの大切な人を失ってしまったことを話す。川にさしかかり、にんじんは盗んでいた保安庫の鍵を「ぼく」に差し出す。僕はこの鍵を川に捨てた。
そして「ぼく」はこの不思議な少年のことを思う。
にんじんは思春期である。脆い心が揺らぐ中で、悪質な万引きを三回も行い心を閉ざしている。ぼくの中に、にんじんの母親と関係を持つことへの大きな罪悪感が襲う。ぼくはガールフレンド(にんじんの母親)の夫婦関係のみならず、未来のある「にんじん」の人格をずたずたに傷つけ損なっていることを知る。そしてガールフレンドと別れることを決心する。
すみれが消えて半年以上たって、東京の街で一度だけミュウの姿を見かける。見事な白髪で以前と変わらず美しかったが全く別の人間のように見えた、まるで ぬけがらみたいだった。存在ではなく不在、姓名の温もりではなく記憶の静けさだった。
この状態は、<あちら側>に行ってミュウと会ったすみれは、彼女とうまくいかず、彼女を<こちら側>に取り戻すことができなかったことを示唆する。
そして「ぼく」は夢を見る。夢を見ること、夢の世界に生きること。でも長く続くことなく覚醒がぼくをとらえる。そしてすみれから電話がある。
このすみれからの電話が実際にあったか否かを考えると、すみれはミュウを追いかけて<あちら側>に行き、含まれてしまっているので、実際の電話と捉えることができるかどうかは難しい。
しかしすみれが消え、激しい孤独の中にいる「ぼく」がにんじんにも打ち明け、語らうことで赦しを得て、神秘的ではあるが<こちら側>とひとつの線(電話)で現実に繋がっていると感じる。
それは交換可能な記号的な昔懐かしい古典的な電話ボックスからというのも象徴的である。
わたしには、あなたが本当に必要なんだって。あなたはわたし自身であり、わたしはあなた自身なんだって。
このときのすみれは<あちら側>の世界でミュウとの関係が終わっている。そして象徴的にすみれは包丁を研いで石の心をもって何かを切ったのだ。
人が撃たれたら血は流されるものだ、そして血は流されたのだ の言葉通りに。
すみれは精神的にこの訣別を心の中で実行した。そしてすみれは沈思し熟考し、自分の人生にミュウから離れることを選ぶ。しかし<こちら側>に戻るためには、受け止めてくれる相手が必要だ。
これまでずっとミュウに相手にされなかった「ぼく」は、万引きの一件で「にんじん」の気持ちを知ることになる。ぼくはにんじんに母親との不倫の赦しを得て、<こちら側>の世界でほんとうの意味で、普通の姿になってすみれを待つ準備ができたことになる。
<あちら側>の世界に行ったスプートニクの恋人である「すみれ」が、帰る場所として<こちら側>の「ぼく」を必死で探し、お互いが電話という線で繋がったのである。
それは母親との不倫で「にんじん」を傷つけてしまった主人公の「ぼく」が、その関係を改悛して良識を取り戻すことによって、「すみれ」とのこころ(線)が繋がった ことを意味する。
村上文学の回復のための要素として、今回も思春期の「にんじん」を登場させる意味は大きい。「ぼく」と「すみれ」が巡り、こころが繋がって、スプートニクの恋人(「すみれ」と「ミュウ」)の結末が、にんじんのおかげで出口を見出し救われる。
ぼくはもうどこにでも行くことができる。現実的で凡庸な生き方を大切に、<あちら側>に行くことを阻止して、<こちら側>のすみれを守ろうとする。そしてぼくはすみれを迎えに行く。
※村上春樹のおすすめ!
村上春樹『風の歌を聴け』解説|言葉に絶望した人の、自己療養の試み。
村上春樹『1973年のピンボール』解説| 魂の在り処を探し、異なる出口に向かう僕と鼠。
村上春樹『羊をめぐる冒険』解説|邪悪な羊に抗い、道徳的自死を選ぶ鼠。
村上春樹『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』解説|閉ざされた自己の行方、心の再生は可能か。
村上春樹『ノルウェイの森』解説|やはり、100パーセントの恋愛小説。
村上春樹『ダンス・ダンス・ダンス』あらすじ|生きる意味なんて考えず、踊り続けるんだ。
村上春樹『眠り』解説|抑制された自己を逃れ、死の暗闇を彷徨う。
村上春樹『国境の南、太陽の西』あらすじ|ペルソナの下の、歪んだ自己。
村上春樹『ねじまき鳥クロニクル』あらすじ|時空を繋ぐ、人間の邪悪との闘い。
村上春樹『スプートニクの恋人』あらすじ|自分の知らない、もうひとりの自分。
村上春樹『海辺のカフカ』あらすじ|運命の呪縛に、どう生き抜くか。
村上春樹『アフターダーク』あらすじ|損なわれたエリと危ういマリを、朝の光が救う。
村上春樹『1Q84』あらすじ|大衆社会に潜む、リトル・ピープルと闘う。
村上春樹『パン屋再襲撃』解説|非現実的で不思議な、襲撃の結末は。
村上春樹『象の消滅』解説|消えゆく言葉と、失われる感情。
村上春樹『かえるくん、東京を救う』解説|見えないところで、守ってくれる人がいる。
村上春樹『蜂蜜パイ』あらすじ|愛する人々が、新たな故郷になる。
村上春樹『品川猿の告白』解説|片想いの記憶を、熱源にして生きる。
サリンジャー『キャッチャー・イン・ザ・ライ/ライ麦畑でつかまえて』あらすじ|ホールデンの魂が、大人のインチキと闘う。
フィッツジェラルド『グレート・ギャツビー/華麗なるギャツビー』あらすじ|狂騒の時代、幻を追い続けた男がいた。
カポーティ『ティファニーで朝食を』解説|自由を追い求める、ホリーという生き方。