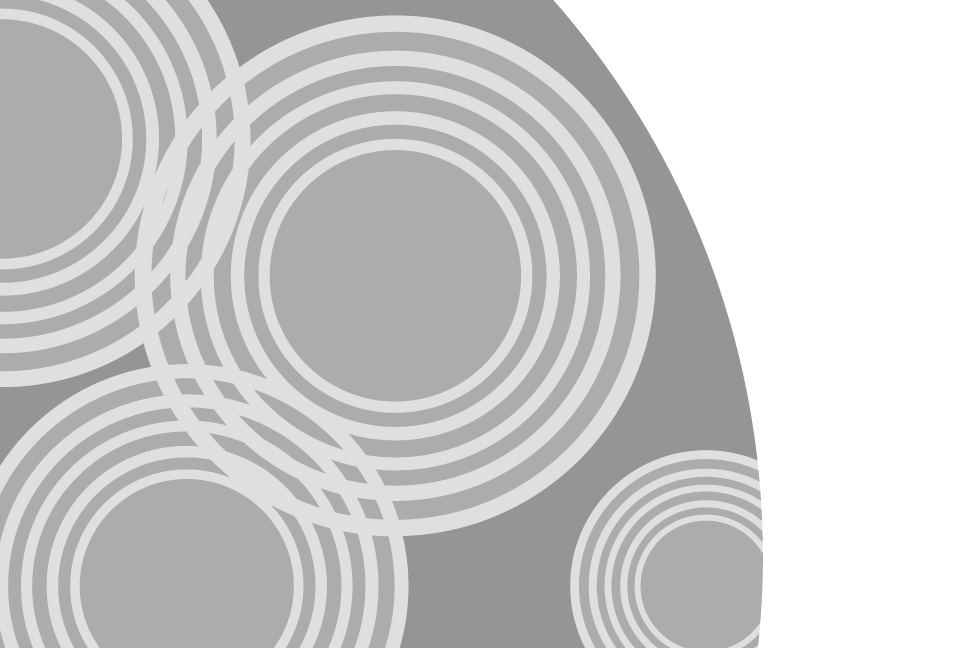親から譲り受けた財産で無為徒食の生活をする妻子ある島村は、雪国の温泉町で駒子と出会い、一途な生き方に惹かれる。その一方で、献身的に尽くす葉子の儚い美しさを知る。怜悧で虚無な島村の心の鏡に映る<駒子の情熱>と<葉子の透明さ>を哀しく美しい抒情で描く。
登場人物
島村
東京の下町出身で妻子持ち、親の財産で無為徒食の生活をしており雪国の越後に向かう。
駒子
十九歳から三年の間、行男の許婚との噂で療養費を稼ぐために温泉町で芸者をしている。
葉子
行男の恋人らしく病気の看病を寡黙に甲斐甲斐しくしている、駒子とも親しい間柄の様子。
行男
二十六歳の病人。三味線の師匠の息子で葉子の恋人、駒子とは幼馴染の許婚との噂がある。
あらすじ
国境の長いトンネルを抜けると雪国、そこで別世界と出会う。
十二月、島村は東京から越後湯沢の温泉場へ駒子に会いに行く。
雪国に向かう汽車の中で病人の男に付き添う若く美しい女、葉子に出会い興味を持つ。それは娘のようでもあり、年上の男をいたわる夫婦のようでもあった。
島村はこれから会いに行く女を、生々しく覚えている人差し指を動かしている。
その人差し指で蒸気で曇った窓ガラスに線を引くと女の片眼が浮き出た。顔を窓に寄せ掌でこすると、斜めに向かいあう二人が鏡のように映った。葉子が病人を世話する姿を見ながら、二人は果てしなく遠くへ行く者の姿のように思われる。
鏡に流れる夕景色は女と二重写しに動き、この世のものではない象徴の世界を描く。特に野山のともし火が、彼女の顔のなかを流れて通るとき彼女の眼と光が重なり、夕闇の波間に浮かぶ妖しく美しい夜光虫のようだった。
それから半時間して葉子達も島村と同じ駅に下りた。そこは極寒の雪景色だった。
駒子に会いに来た島村だが、駒子は濃い青のマント姿で先ほどの駅のホームに来ていたことを客引きの番頭から聞く。夕景色に葉子にいたわられていた病人は駒子の踊りの師匠の息子で、駒子はその息子を迎えに来たのだった。
「指が覚えている女」と「ともし火をつけていた女」との間に、何があり何が起こるか、島村には心のどこかで見えるような気がして、あの夕景色の流れは時の流れの象徴のように思う。
新緑の頃 初めて駒子と会い、不思議なくらい清潔な印象だった。
あの時 ―島村は最初に来た時のことを思い出すー それは五月、新緑の登山季節に入った頃だった。
無為徒食な島村は国境の山歩きをして七日ぶりに温泉場に下りてきて芸者を頼んだ。あいにく道路普請の落成式で芸者の手が足りず、島村の部屋にお酌に来たのは芸者ではないが、三味線と踊りの師匠の家にいる娘だった。
女の印象は不思議なくらい清潔だった。それが十九歳のときの「駒子」だった。
駒子はこの雪国の生まれで東京でお酌をしているうちに旦那に受け出され、やがては日本踊りの師匠として身を立てさせてもらうつもりのところ、一年半ばかりで旦那が死んだという身の上だった。
歌舞伎の話などすると、女は俳優の芸風や消息に精通していた。根が花柳界出の女らしく、打ち解けて夢中になって話をする。
島村は芸者を呼ぶよう女に頼む。すると女は「ここにはそんな人ありませんわよ」と言う。
島村はこの女とはさっぱりつきあいたいから男女の仲ではなく友情でいたかった。彼女は素人で清潔すぎたのである。女は島村の話に同意した。
やがて十七歳くらいの肌の底黒く、腕が骨ばった、初々しく人が好さそうな芸者がやってきた。島村は興ざめた顔をすまいとするが、ものを言うのも気だるくなってしまい、うまく帰して若葉の匂いの強い裏山を荒っぽく登って行った。
ほどよく疲れたところで下りてくると、女が「どうなすったの」と聞くので、「止めたよ」と答えた。はじめからこの女をほしいだけだ。遠回りしていたのだと島村は知ると、自分が厭になる一方、女がよけい美しく見えた。小さくつぼんだ唇はまことに美しい蛭の輪のように伸び縮みがなめらかで、美人というよりも清潔だった。
その夜の十時ごろ、女が廊下から大声で島村の名を呼んで彼の部屋に入ってきた。
別の座敷で芸者を呼び大騒ぎとなり飲まされたという。やがて座敷に戻ったが、一時間ほどすると長い廊下にみだれた足音で、あちこちに突きあたり倒れたりして入ってきて島村の体にぐらりと倒れた。外の雨の音が俄かに激しくなった。「いけない。いけない。お友達でいようって、あなたがおっしゃったじゃないの」と幾度、繰り返したかしれなかった。
夜の明けないうちに帰らねばならないと言って、ひとりで抜け出して行った。そして島村はその日、東京に帰ったのだった。
再会して一夜を過ごし、駒子の家を訪れ行男と葉子の関係を知る。
冬は初めてだった、十二月だった。島村が内湯から上がると、帳場の曲がり角に裾を冷え冷えと黒光りの板の上に拡げて女が立っていた。女は「駒子」という名前の芸者になっていた。
あんなことがあったのに、手紙も出さず会いにも来ず、本を送るという約束も果たさず、詫びを言うのが順序だったが、駒子は島田を責めるどころか体いっぱいに懐かしさを感じてくれた。
翌日、島村は駒子が前夜、見下ろしていた坂道を下りてゆくと、葺いた上に石が置き並ぶ家々があり、芸者が五六人立ち話をしていた。今朝、宿の女中から芸名を聞いた駒子もそこにいそうだった。
島村が歩いてくるのを見て、駒子が走ってきて「うちへ寄っていただこうと思って」と言い、島村は「君の家、病人がいるんだろう」と言い、「昨夜の汽車に自分も乗っていて、病人の近くに座っていたこと、駒子が濃い青のマントを着て迎えに来たこと、親切に病人の世話をする娘が付添っていたこと」を話すと、駒子は「そのこと昨夜どうして話さなかったの。なぜ黙っていたの」と気色ばんだ。
島村は駒子に誘われ、彼女の住む踊りの師匠の家の屋根裏部屋に行き梯子を登らされた。「お蚕さまの部屋だったのよ。驚いたでしょう」と駒子が言う。家は朽ち古びていたが清潔感が感じられた。蚕のように駒子も透明な体でここに住んでいるのかと思われた。
「病人の部屋からだけれど、火は奇麗だって言いますわ」と炬燵の灰を掻き起す。病人は腸結核で故郷で死ぬために帰って来たのだった。師匠の息子で行男といい今年二十六歳という。すると煤けた襖があいて葉子が現れた。ガラスの尿瓶をさげていた。山袴をはいていて、島村は葉子はこの土地出身だろうと思った。
葉子はちらっと刺すように島村を一目見て土間を通り過ぎた。それは遠いともし火のように冷たく、野山のともし火と瞳が重なった昨夜の印象を思い出した。それを思い出すと鏡のなかいっぱいの雪に浮かんだ駒子の赤い頬も思い出されてくる。
駒子の家を出て島村は声をかけた女の按摩に温泉宿で揉んでもらいながら話を聞く。駒子の三味線が達者になったこと、この夏に芸者に出たこと、師匠の息子が東京で長患いをしたため病院の金を工面していること、駒子と 師匠の息子は許婚という噂であることなど。
もし駒子が息子の許婚だとして、葉子が息子の新しい恋人だとして、駒子が許婚の約束を守り通し、身を落としてまで療養させたとしても、やがて死ぬとすれば徒労ではないかと島村は思った。そう考えると駒子の存在が純粋に感じられてくるのだった。
駒子の勧進帳の撥に、一途な女の情念と徒労な純粋さを知る。
島村は温泉宿で虚しい切なさに曝されていると、温かい明りのついたように駒子が入ってきた。
駒子は少し酔っぱらっていて「もう知らん。頭痛い。難儀だわ、水飲みたい、水頂戴」と言い楽しげに笑い続けたあとに、静かな声で「八月いっぱい神経衰弱だったと話す。何か一生懸命、思い詰めてたけれど何を思いつめているのか自分でも分からず、気ちがいになるのかと心配だった」と言う。
翌朝、島村が目を覚し湯から戻ると、駒子は部屋の掃除をしていた。島村が朝らしく笑うと、駒子も笑った。島村は「君はあの息子さんの許婚だって?」と聞くと、駒子は「許婚は嘘よ」と否定する。
そして駒子は「お師匠さんが、息子と私が一緒になればいいと思った時があったかもしれない。心のなかだけのことで口には出さないけれども。お師匠さんの心のうちは息子さんも私も薄々知っていたけれど、二人は別になんでもなかった。ただそれだけ」と言う。
そして「人のこと心配しなくてもいいわよ。もうじき死ぬから。あんた、そんなこと言うのが良くないのよ。私の好きなようにするのを、死んでいく人がどうして止められるの?」と言われ、島村は返す言葉がなかった。
しかし駒子は葉子のことに一言も触れないのは何故だろうかと思う。
島村が遠い空想をしていると「駒ちゃん、駒ちゃん」という葉子の美しい呼び声が聞こえた。三味線と稽古本を駒子が頼んだのを葉子が持ってきた。
さぁと身構えして島村の顔を見つめた。島村ははっと気おされた。勧進帳であった。
島村は頬から鳥肌が立ちそうに涼しくなり腹まで澄み通る。全く彼は驚いてしまった、と言うよりも叩きのめされてしまった。敬虔の念に打たれ悔恨の思いに洗われた。山峡の自然を相手として孤独に稽古するが、その孤独が哀愁を踏み破って野生の意力を宿していた。
雪の晴天を見上げて「こんな日は音がちがう」と 駒子が言っただけのことはあった。音は純粋な冬の朝に澄み通って、遠くの雪の山々まで真直ぐに響いて行った。
島村には虚しい徒労とも思われ、遠い憧憬とも哀れまれる駒子の生き方が彼女自身への価値で、凛と撥の音に溢れでるのであろう。三曲目の都鳥は艶な柔らかさのせいもあって温かく安らいで駒子の顔を見つめた。そうするとしみじみ肉体の親しみが感じられた。