 夏目漱石
夏目漱石 夏目漱石『草枕』全ての謎と物語の構造を解く「謎解き草枕」その1
冒頭文に隠された主題「智・情・意と芸術」夢幻能に見立てられた物語、画工と那美の芝居合戦を丁寧に読み解き、誰も語らない複雑な『草枕』の筋と構造を明らかにする全6回のシリーズです。
 夏目漱石
夏目漱石  ヘルマン・ヘッセ
ヘルマン・ヘッセ  ヘルマン・ヘッセ
ヘルマン・ヘッセ  情報
情報  フランツ・カフカ
フランツ・カフカ 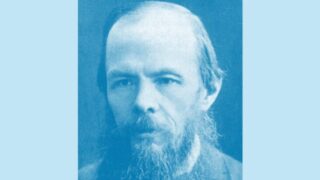 ドストエフスキー
ドストエフスキー 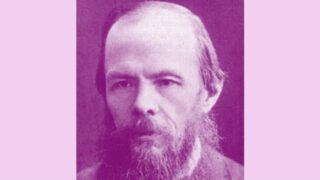 ドストエフスキー
ドストエフスキー 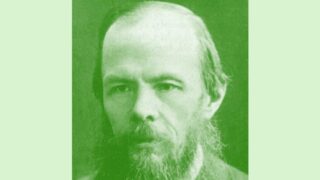 ドストエフスキー
ドストエフスキー  ヘルマン・ヘッセ
ヘルマン・ヘッセ  ヘルマン・ヘッセ
ヘルマン・ヘッセ  ウィリアム・フォークナー
ウィリアム・フォークナー