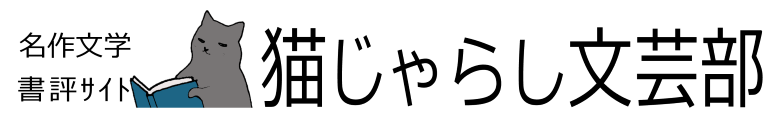死も生の一部であるなかで、人は人に恋をして生きていく。三十七歳の僕が思春期を回想する。直子、キズキ、レイコ、そして緑。震えるような深い哀しみの中で、固い殻に閉じこもる自己を遠い記憶が揺さぶる。死に呼び寄せられながら命を生きることをもがき、再生しようとする魂の叫びを描く。
登場人物
ワタナベトオル(僕)
主人公で三十七歳、十九歳の「僕」を回想する。神戸の高校を出て、直子と東京で再会する。
キズキ
神戸の高校時代の唯一の僕の親友。直子と付き合っていたが、十七歳の時に理由なく自殺する。
直子
キズキの幼少の頃からの恋人。キズキの死後、偶然、東京で傷心のなか僕と再会し付き合う。
小林緑
ワタナベと同じ大学で同じ授業を受講、彼がいるがワタナベと気が合い仲良くなっていく。
永沢
ワタナベと同じ寮の上級生。東大法学部で意識が高く、女漁りに独自の人生哲学を持つ。
ハツミ
永沢の恋人。とびきりのお嬢様が通う東京の女子大生で、上品な装いの理知的な女性。
レイコ
三十八歳で直子の良き理解者。阿美寮のルームメイトでかつてピアニストを目指していた。

あらすじ
飛行機がハンブルグ空港に着陸しようとしたとき、BGMでビートルズの「ノルウェーの森」が流れる。僕は一九六九年秋の出来事が蘇り、激しく混乱し動揺する。それは十七歳の時に遺書も残さず自殺した親友のキズキと、ひとり残された幼い時からの彼の恋人の直子、その直子に恋をした僕の思春期を通しての出来事。そして二十歳の時、直子もキズキの後を追って自らの命を絶ってしまう。僕は直子を失った深い喪失感のなかで、同じ学部の緑を愛することで心の再生を求め、もがき苦しんだ昔の思い出だった。三十七歳のワタナベトオルは遠くせつない恋愛の記憶を反芻する。
※ブログ文中の表記は、村上春樹 講談社文庫<ノルウェイの森>から
動画もあります、こちらからどうぞ↓
解説
死は生の対極ではなく、生の一部として存在する。
この作品「ノルウェイの森」は「生」と「死」の物語であると同時に、大人への通過儀礼として思春期の精神と肉体の葛藤の物語でもある。
死は僕という存在の中に既に含まれているのだし、その事実はどれだけ努力しても忘れ去ることのできるものではないのだ。あの十七歳の五月の夜にキズキを捉えた死は、その時に僕を捉えてもいたからだ。(二章)
死は生の対極としてではなく、その一部として存在している。
この物語の主題である。
性的に成熟し子供から大人へと変化する思春期の<ココロ>と<カラダ>の魂の叫びでもある。
変化とは前後であり、前が死んで、後が生まれることである。
外形的には昆虫の変態ほど明確ではないが<カラダ>の変化は捉えられる。阿美寮で直子と再会した夜、ワタナベは大人になった直子を月の光の中でみる。
これはなんという完全な肉体なんだろうと僕は思った。直子はいつの間にこんな完全な肉体を持つようになったのだろう?そしてあの春の夜に僕が抱いた彼女の肉体はいったいどこに行ってしまったのだろう?(六章)
変化は肉体の儀式を伴う。そして精神を揺さぶる。等身大として抱えきれず、生が死に呑み込まれることもある。
<ココロ>の変化は捉えにくい。思春期の<ココロ>を汲み取るのは難しい。学校や社会で対応不能な問題となれば特別の配慮が必要になってくる。その意味では阿美寮は閉ざされた世界であり、死の暴発を未然に防ぐプログラムを持っている。
物語は「生」と「死」を主題とし、変化する<ココロ>と<カラダ>をめぐる思春期の葛藤のなかで、<愛する>という強いエネルギーに向かう魂の彷徨の軌跡を綴っていく。
たくさんの登場人物が「生」から「死」の方向へ呑み込まれていく。キズキ、直子、直子の姉、直子の叔父、ハツミ・・・。
そして三十七歳の主人公はこの当時の思い出を、
生のまっただ中で、何もかもが死を中心に回転していたのだ。(二章)
と述懐するのである。
十七歳のなかに棲む<ココロ>と<カラダ>について。
思春期の<ココロ>と<カラダ>の変化は、時代や大きく影響する。
一九六九年は政治のの季節。学生運動が華やかなこの時代は、言葉による表現が、扇動的であったり、虚しかったりする。それを特徴的に説明している箇所がいくつかある。
おいキズキ、ここはひどい世界だよ。と僕は思った。こういう奴らがきちんと大学の単位をとって社会に出て、せっせと下劣な社会を作るんだ。(四章)
ストの状況を見たワタナベが、ストを主導する学生たちがやがて社会の中心世代となり、何もなかったかのような顔をして世の中を動かす。このご都合主義に辟易しながら、死んでいったキズキに現実世界の卑劣さを訴える場面だ。
キズキを失ってからのワタナベは、友をつくることの意味を失い、現実世界から距離を置くデタッチメントな生き方を選ぶ。対して自己の内側と外側のバランスが崩れるとき、精神と肉体の異常をきたす。
直子の内側の世界は、ワタナベに宛てた二通目の手紙に記される。
外の世界では多くの人々は自分の歪みを意識せずに暮らしています。でも私たちのこの小さな世界では歪みこそが前提条件なのです。(五章)
外側の世界を遮断して神経を休めることが求められる直子の体調。哀しいほどに自分自身を不完全な人間として捉え、そして次のようにワタナベを評する。
私はあなたのように自分の殻の中にすっと入って何かをやり過ごすということができないのです。あなたが本当はどうなのか知らないけれど、私にはなんとなくそう見えちゃうことがあるのです。(五章)
それはワタナベの自己本位のエゴだ、直子はそう理解している。それはキズキの弱さとは対象的だ。ワタナベとキズキは正反対の性格だった。
直子は神経を病んでおり、異変は<ココロ>に表れている。
「うまくしゃべることができないの」(中略)何か言おうとしても、いつも見当ちがいな言葉しか浮かんでこないの。見当違いだったり、あるいは全く別だったりね。(中略)まるで自分の体がふたつに分かれていてね、追いかけっこをしているみたいな感じになるの(中略)ちゃんとした言葉っていうのはいつももう一人の私が抱えていて、こっちの私は絶対にそれに追いつけないの」(二章 )
そんな直子のことをワタナベは「言葉探し病」と名付ける。
直子の体の半分は死に引き寄せられ、半分は生を彷徨っている。異変はずっと前に<カラダ>に現れている。「直子」にとって「キズキ」は、まさに物心がついた時からずっと一緒だった。
私たち三つの頃から一緒に遊んでいたのよ。(中略)はじめてキスしたのは小学校六年生のとき、素敵だったわ。私がはじめて生理になったとき彼のところに行ってわんわん泣いたのよ。(六章)
キズキと直子の関係は、どこかの部分で肉体がくっつき合っているくらいに密着していて、遠く離れても特殊な引力でもとに戻るくらいの親密さだった。
普通の成長期の子供たちが経験するような性の重圧とかエゴの膨張の苦しみみたいなものを殆んど経験することなくね。(六章)
二人は思春期の辛さを経験していないという。ところが直子の<カラダ>はキズキを性交のときに迎え入れることはできなかった。このことが物語の大きな謎になっている。直子はキズキへの<愛>を示せなかった責任で<ココロ>は絶望的に悩んだであろう。
「たぶん私たち、世の中に借りを返さなくちゃならなかったのよ」(中略)「成長のつらさのようなものをね。私たちは支払うべきときに代価を支払わなかったから、そのつけが今、まわってきてるのよ。だからキズキ君はああなっちゃったし、今私はこうしてここにいるのよ」(六章)
大人になるための思春期という洗礼を受けていない二人は、代償を払わなければならないのだと直子は考えていた。
さらに直子の家系は、姉が十七歳で縊死し、叔父も十七歳で引きこもりとなり二十一歳で電車に飛び込み自殺をしている。そのとき直子の父親は「やはり血筋なのかな、俺の方の」と語っていた。
思春期の頃から自身の家系からくる死の恐怖もあり直子はゆっくりと<ココロ>と<カラダ>に変調をきたしはじめる。そして次第に外の世界を拒絶し孤独の中に閉じこもっていったのである。
そして<血筋に呪われた直子の十七歳>のときに、何も告げずにキズキが自殺した。
遺書も動機もなく恋人だった直子に何も告げず、十七歳で死んでしまったキズキ。直子はキズキのもとに行くのが、自分の運命だと考える。直子にとっては、キズキの親友であり、唯一、キズキが心を開く人間だったワタナベに、運命に従うように一瞬、二十歳の大人になった儀式として性交が叶った。それはキズキに対しての性交の思いがワタナベの身体を媒介として実現したのであった。
相手はキズキではなかったが、直子の<カラダ>は喜びを感じた。しかし<ココロ>は無く、直子はワタナベトオルを愛してはいない。
「そして僕のことは愛していたわけでもないのに、ということ?」「ごめんなさい」と直子は言った。(六章)
ワタナベにとっては残酷な返答だが、直子は嘘の愛を告げるわけにはいかない。そして、彼女は自殺するための<ココロ>と<カラダ>の準備を阿美寮でする。
「私はもう誰にも私の中に入ってほしくないだけなの。もう誰にもみだされたくないだけなの」(十一章)
直子はワタナベの手紙で緑とのことを知り、ワタナベと緑の二人が恋愛関係に進むことで、ワタナベが生き続けて大人になることに安心し、自らの死の時期を確認し実行したのである。
恋人同士の二人とホモソ-シャルな男同士という三人の関係。
ワタナベにとって、直子は親友キズキの恋人だった。直子にとって、ワタナベは恋人の親友である。 お互い、キズキを真ん中においた関係である。
直子とワタナベが再会したのはキズキの死後一年で、場所は東京の中央線の車内。直子は自身の死の恐怖の中でキズキの自殺を迎え、その後も病状は進行していた。再会した直子は不気味な野井戸の話をワタナベにする。目には見えないけれどもすぐ傍にあるという。
「本当に深いの。でもそれが何処にあるのかは誰にもわからないの。このへんの何処かにあることは確かなんだけれど」(一章)
穴の中には世の中のあらゆる種類の濃密な暗黒がつまっているという。異常な会話である。深い井戸は異界を象徴している。それはキズキの死に導かれる、直子自身の精神の危うさを表している。
さらに直子は続ける。
あなたは盲滅法にこのへんを歩きまわったって絶対に井戸には落ちないの。そしてこうしてあなたにくっついている限り、私も井戸には落ちないの」(一章)
直子はそれでも生きようとしていた。再会した最初の頃のデートは、いつも直子は先を歩き、ワタナベが後についていった。やがて二人は並んで歩くようになり、直子の横顔がワタナベを幸せにするようになる。ただ直子の気持ちはワタナベには無かった。
一方で、ワタナベとキズキはホモソ-シャルな関係である。
思春期の男同士の関係は恋人同士とは次元を異にする。ビリヤードを終えた後のキズキの自殺がそれを象徴する。それはあたかもキズキが直子の後見をワタナベに委ねるように。しかし直子は愛するキズキが最後に会ったのは自分ではなく、ワタナだったことを不満に思う。
あるいは直子が僕に対して腹を立てていたのは、キズキと最後に会って話をしたのが彼女ではなく僕だったからかもしれない。(二章)
直子の感情からすれば、愛する人の最後が自分でなかったことは辛い。しかし死にゆくホモソーシャルなキズキの感情が、恋人を親友に頼む行為と考えれば頷ける。ワタナベとの別れと直子を託す儀式が、ビリヤードで、ゲームに勝ったのはキズキだ。だからワタナベはキズキの頼みを引き受けなければならない。やがてワタナベは直子を守ることが、キズキへの約束であり、責任であると考える。
ところが実際はワタナベは直子とは気まずく疎遠になっており、一年後、偶然に再会しそして男女の関係を持ってしまう。それは二十歳の誕生日を過ごした夜で、直子は死の恐怖から言葉を失い神経が高ぶり混乱し、それを鎮めてもらいたがっていた。
「ねぇ、どうしてあなたあのとき私と寝たりしたのよ?どうして私を放っておいてくれなかったのよ?」(一章)
直子は動揺する神経のなかで、成人の儀式として僅かな命の炎を燃やしたのである。しかし<ココロ>の弱さから孤独に押しつぶされ死んだキズキを、誰よりも理解できる直子が、キズキではない、キズキの友人のワタナベと<カラダ>の関係をもってしまう。
生きようとした直子の本能の仕業なのかもしれない。
「私のことを覚えていてほしいの。私が存在し、こうしてあなたのとなりにいたことをずっと覚えていてくれる?」(一章)
ささやかな命の灯のなかで、直子は死を予感している。そして困惑しながらも自分の生きた命の瞬間をワタナベに刻んでいて欲しかったのである。
ワタナベにとって直子は、キズキを通して常に意識せざるを得ない存在である。
ワタナベはキズキの死の理由はわからない。しかし二人は強い友情で結ばれていた。キズキとワタナベは正反対の性格だが、お互いかけがえのない関係だ。思春期のホモソーシャルな関係は人生の貴重な記憶のひとつだ。
ワタナベは自分の心を閉ざし外部との関わりを避ける。異性に対しても人を愛することができない人間である。直子はキズキと小さなときから付き合い愛しあってきた。
「これまで誰かを愛したことはないの?」と直子は訊ねた。「ないよ」と僕は答えた。(三章)
ワタナには、キズキと直子以外には打ち解けあえる友人も異性もいない。
人を愛することができず固い殻に閉じこもり<ココロ>を開かないワタナベと、キズキを失った深い哀しみと自身の<ココロ>と<カラダ>の矛盾に苛まれながら苦悩する直子の物語が紡がれていく。
死者だけがいつまでも十七歳であった。(三章)
「キズキ」「直子」そして「ワタナベ」の三人で過ごした青春のとき。友達の恋人の直子は美しい。そして傷ついている。いたわりや癒しが好意に発展し、責任となり二人は繋がっていくのである。
しかし直子の心の病は深くなり回復が難しくなっていく。そしてワタナベは思う。
おいキズキ、と僕は思った。(中略)俺は今よりも強くなる。そして成熟する。大人になるんだよ。(中略)俺はもう十代の少年じゃないんだよ。俺は責任というものを感じるんだ。なあキズキ、俺はもうお前と一緒にいた頃の俺じゃないんだよ。俺はもう二十歳になったんだよ。そして俺は生きつづけるための代償をきちっと払わなきゃならないんだよ(十章)
キズキを失くした三年後、そして直子に七ヵ月遅れて二十歳になったワタナベは、キズキが愛し残していった直子を自分も好きになり、好きになった代償(=責任)として、直子と生きることを決める。
直子への<愛だと思いたい>ワタナベと、ワタナベを<愛していない>直子。
直子は二十歳の誕生日の夜、ワタナベと結ばれてから、その後、姿を消す。そしてしばらくして届いた手紙には、
「いろんなことを気にしないでください。たとえ何が起こっていたとしても、たとえ何が起こっていなかったとしても、結局はこうなっていたんだろうと思います(中略)私の言いたいのは私のことであなたに自分自身を責めたりしないで欲しいということなのです。これは本当に私が自分できちんと全部引き受けるべきことなのです。」(三章)
直子は最初からワタナベのことは愛していない。愛せないのだ。直子がキズキを愛した代償は、キズキのもと(=死)へ行くことである。そして直子は<ココロ>と<カラダ>が別だった二十歳の初体験の喜びを「レイコ」に告白する。直子がキズキのもとへ行くことを決心していることを、阿美寮で直子と同様に患者でもあり、音楽の先生でもあり、ルームメートとして支えてきたレイコは、直子のその思いを知っていた。
「あの子もう始めから全部しっかりと決めていたのよ。だからきっとあんなに元気でにこにこして健康そうだったわね。きっと決めちゃって、気が楽になったのね。」(十一章)
「キズキ」「直子」そして「ワタナベ」の三人は三つのピースを埋めることで、かろうじて不完全な世界を生きることができる関係でもあった。しかし責任や代償の払い先の相手がそれぞれに異なっていた。三人の関係はひとつのピースが欠ければ成立しない。
「私のことをいつまでも忘れないで。私が存在したことを覚えていて」(一章)
キズキが自殺し、後を追うようにキズキに引き寄せられた直子の自殺を、ワタナベは止めることはできなかった。直子はキズキを愛しワタナベを愛せなかった。
この “私が存在したこと” とは ワタナベの心に刻まれた直子の記憶である。
ワタナベがレイコに宛てた手紙に緑のことが書いてあった。秘密を隠さないルールの阿美寮では、直子はワタナベと緑の関係を知ったはずである。それは直子にとって裏切りではなく、安心になった。
生きることでワタナベには、直子とキズキと三人の思春期の記憶を永遠に抱き続けて欲しかった。そのためにはワタナベは愛する人と出会うことが必要になる。緑の出現で、それが実現したのである。
直子を失ったワタナベは一ヵ月ほど見知らぬ土地を彷徨い続ける。深い哀しみと喪失感のなか、自分なりにベストをつくしたことを思う。
そしてキズキに呟く。
彼女はもともとお前のものだったんだ。結局そこが彼女の行くべき場所だったのだろう。(中略)なぁキズキ、お前は昔俺の一部を死者の世界に引きづりこんでいった。そして今、直子が俺の一部を死者の世界に引きづりこんでいった。(十一章)
唯一<ココロ>を開くことのできた三人。ホモソーシャルな同性の<ココロ>、そしてその恋人を引き受け生きようとした異性への<ココロ>。キズキと直子、二人を失ったワタナベはひとり現実の不完全な生者の世界で、固い殻に閉ざされて生きるしかなかった。
しかしレイコがワタナベの<ココロ>を覚醒させる。レイコは直子の精神の回復を期待したが、途中からそれが困難なことも知っていたのである。
ワタナベが直子への哀しみをレイコに綴った後、レイコからの返信にこう記される。
あなたはときどき人生を自分のやり方にひっぱりこもうとしすぎます。精神病院に入りたくなかったらもう少し心を開いて人生の流れに身を委ねなさい。(十章)
やがてレイコは阿美寮を出てワタナベに会いにくる。外の世界に解放されたレイコはワタナベと二人だけの直子の葬式をやりなおす。ワインを飲みギターを弾き温かく葬る、そして二人は体を重ね合う。
レイコはこのとき三十八歳である、ワタナベとは十八、年が離れている。年上の大人の女性でかつ精神の病を克服したレイコのワタナベへの言葉の持つ意味は大きい。意識して遺服を着て直子の化身となったレイコは、ワタナベに直子を忘れさせようとする。
それはレイコが考えた、ワタナベを大人へと通過させる儀式であった。
直子を失くし壊れそうなワタナベの<ココロ>を慰撫するために、レイコは<カラダ>を媒介にしたのである。レイコはワタナベに「流れること」そして、「もう終わったこと」を教える。
やがてワタナベは付きあい始めた緑を離さず、きちんと掴まえていなければいけないと考える。
直子とは正反対の明るく活発な緑は、自由奔放で性にまつわる話を無邪気にするが、家族への愛情や恋人への礼儀を持ち、何よりも生命が漲っている。
緑は母を亡くし父も長い看病の末に失くしている。彼女のはしゃぎかたは死に呑み込まれないための彼女なりの孤独を退ける方法なのだ。
ワタナベは緑を愛しているが、直子の回復を待ち、愛し続けなければならないという自分の責任との狭間で、まだ悩んでいた。そこにレイコはワタナベを諭す。
「だってあなた直子が死ぬ前からもうちゃんと決めていたじゃない、その緑さんという人とは離れるわけにはいかないんだって。直子が生きていようが、死んでいようがそんなの関係ないじゃない。あなたは緑さんを選び、直子は死ぬことを選んだのよ。あなたもう大人なんだから、自分の選んだものにはきちんと責任を持たなくちゃ。そうしないと何もかも駄目になっちゃうわよ」(十章)
レイコはワタナベに、緑が好きなのなら「責任を持つように」、「大人になるように」と言う。直子の死の痛みから、きちんと学び、緑と幸せにならなければならないと言う。ワタナベは直子への深い哀しみのなかで、緑を<愛>することを選び、生きていくことを決心する。
あなたの痛みは緑さんとは関係ないものなのよ。これ以上彼女を傷つけたりしたら、もうとりかえしのつかないことになるわよ。だから辛いだろうけれど強くなりなさい。もっと成長して大人になりなさい。(十章)
そしてワタナベは緑に電話をする。
君とどうしても話がしたいんだ。話すことがいっぱいある。話さなくちゃいけないことがいっぱいある。世界中に君以外に求めるものは何もない。君と会って話したい。何もかも君と二人で最初から始めたい、と言った。(十一章)
緑から「あなた、今どこにいるの?」と静かな声で言われたとき、ワタナベは自分が今、どこにいるか分からない。
僕はどこでもない場所のまん中から緑を呼びつづけていた。(十一章)
自我の固い殻を突き破る、声にならない振り絞るような魂の叫びである。そして、その叫びはまだどこにも着陸せずに、三十七歳の主人公の回想のなかを浮遊し続けている。