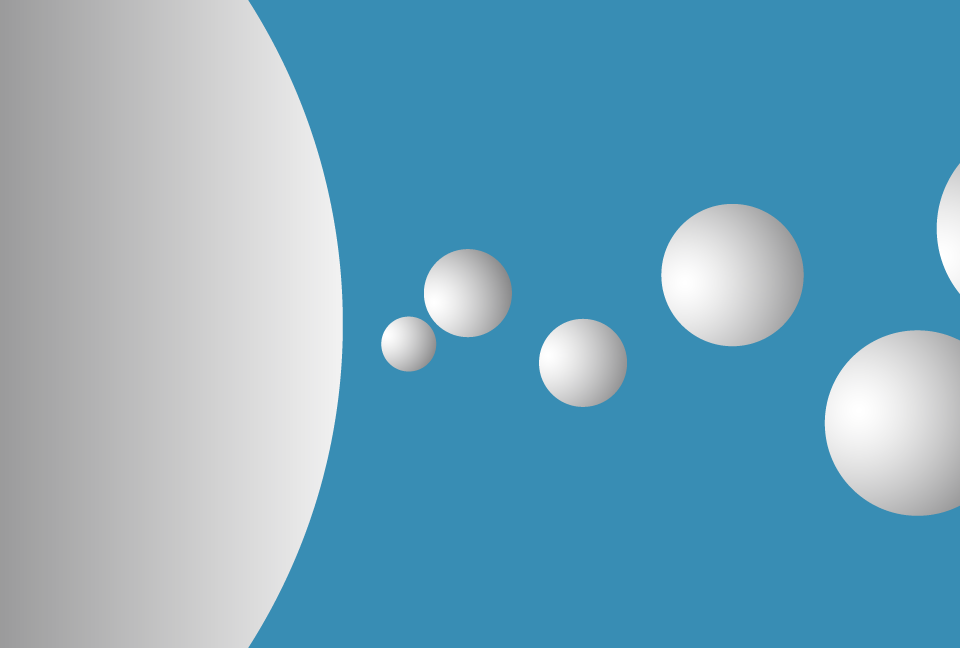直子の自殺で自責の念に囚われる「僕」は、ピンボールの呪縛に憑りつかれ魂を探す旅をする。そしてついに異界に棲む直子の死霊と邂逅し語らうことができた。言葉の絶望を超えて繋がった僕は、直子と決別し、透き通った日常を取り戻す。一方、鼠は暗鬱の日々の中、出口を求め深い眠りに陥る。「僕」と「鼠」、二人の漂流をパラレルに描く第二弾。
※文中のページ表記は、村上春樹 講談社文庫<1973年のピンボール>から
登場人物
僕
友人と一緒に英語の翻訳事務所を開き、女の事務員と三人で仕事をしている。
鼠
大学をやめて以降、故郷で暗鬱な日々を送り現実とのバランスを崩している。
双子の女の子
胸に208・209とプリントされたトレーナーを着て「僕」の部屋に同居する。
直子
1969年に「僕」と付き合っていた女の子、1970年に僕を残して自殺する。
ジェイ
ジェイズ・バーのマスター。中国人で独身、片手の猫と暮らしている。
鼠の女
美術学校の建築学科を卒業し、設計事務所に勤める。鼠の新しい恋人。
あらすじ
デビュー作「風の歌を聴け」に続く、第2弾。時代の喪失感と自己回復の旅は続きます。
何故、直子は自殺したのか。もう考えるのを止めようとしても「僕」の自問自答は続く。言葉の絶望を超えて出口を求め彷徨い歩く「僕」。双子に誘われ、あのころのピンボールを探しに行く。そこで憑依した直子との邂逅。「鼠」もまた暗鬱な暮らしから出口を求めて街を出る。
1969-1973年、ひとつの季節が終わる。1973年9月、この小説はそこから始まる。
そして「僕」の話であるとともに「鼠」と呼ばれる男の話でもある。僕たちは700キロも離れた街に住んでいる。大学をやめた鼠は、現実とのバランスを見失い、新しい女の温もりに沈むが、その渇きは癒されることなく、ついにジェイズ・バーとも、故郷とも別れ、街を出る決心をする。行くあてのない旅だが、それが鼠の出口だった。
僕は東京で翻訳の仕事をしながら、自殺した「直子」を忘れることができず苦悶する。ある時、突然、僕の部屋に現れた「双子の女の子」。これはピンボールについての小説である。と最初にことわりがある。
僕は1970年の冬、ピンボールに夢中になり、ついに機械に憑りついた直子と交信することができた。その後、3年を経て双子に誘われるように僕は、3フリッパーのピンボール「スペースシップ」を探す。
そしてついに捜しあて、ピンボール台に憑依した直子と邂逅し懐かしく語らった。その後、双子はどこかに帰っていった。直子の自殺の理由は判明しなかったが、僕は直子と決別し、全てが透き通ってしまいそうな朝を迎えることができた。
★動画もあります、こちらからどうぞ↓
解説
直子を失った喪失と自責に苛む「僕」について。
プロローグに、『風の歌を聴け』に描かれた作家デレク・ハートフィールドの「火星の井戸」のつながりと、スペースシップに連想される星座として、金星や土星や双子座の話が出てくる。
学生運動の祝祭性を、コズミックを象徴しながら導入している。
主人公の僕は、見知らぬ土地の話を聞くのが好きで、誰も彼もが親切にそして熱心に語ってくれた。
彼らはまるで涸れた井戸に石でも放り込むように僕に向かって実に様々な話を語り、そして語り終えると一様に満足して帰っていった。(5P)
村上文学にとって「井戸」は、潜在意識の中の<あちら側>の世界に往く交信地点。しかし『1973年のピンボール』の段階では、まだその意味は明確になっていません。
理由こそわからなかったけれど、誰もが誰かに対して、あるいはまた世界に対して何かを懸命に伝えたがっていた。(6P)
「俺だって大学を出たら土星に帰る。そして、り、立派な国を作る。か、か、革命だ」(8P)
「行動が思想を決定する」がモットーの土星生まれの政治家のグループは、大学を出たら土星に帰ると言い、卒業して社会に組み込まれていった。当時の正義顔をした学生運動とその後の日和見主義への明らかに痛烈な風刺である。
この物語は、ピンボールを通じて僕が直子の魂を探す旅である。ここではデビュー作『風の歌を聴け』で明かされなかった「直子」のことが語られている。
直子も何度かそういった話をしてくれた。彼女の言葉を一言残らず覚えている。(中略)
一九六九年の春、僕たちはこのように二十歳だった。(9P)
1969年の春に、僕は直子から故郷の話を聞く。
「プラットホームの端から端まで犬がいつも散歩しているのよ。そんな駅。わかるでしょ?」「駅を出ると小さなロータリーがあって、バスの停留所があるの。そして店が何軒か。……寝ぼけたような店よ。」(10P)
彼女の死から4年後の1973年の5月に、僕は直子の故郷の駅を一人訪れる。そこは典型的な田舎の駅と駅前に広がる街のつくりだった。
1961年、12歳の時に直子はここにやってきた。冷たい雨がたくさん降る土地で、地底は甘味のある地下水で満たした。井戸掘り職人のおかげで土地の人々は美味い井戸水を心ゆくまで飲むことができた。しかし直子が17歳になった秋、職人が死んでそれ以来、美味い水の出る井戸は得難いものとなる。
これは冒頭の “涸れた井戸” へ放り込まれた人々の様々な話と対比されて、変わりゆく世界を象徴する。“美味い水の出る井戸” は、人々の生命の活力であり良き故郷だが、得難いものに変わっている。
直子の父は高名な仏文学者で、堕天使や破戒僧、悪魔祓い、吸血鬼といった類の書物を翻訳し気楽な生活を送り続ける。この土地には酔狂な文化人の集落が形成されていた。しかし東京オリンピックの前後に、駅を中心とした平板な街並みとなる。
都市化とは、都市に集まってくる人々を郊外に収容する開発をも含んでいる。辿り着いた直子の街に昔の面影はもう無い。平坦でのっぺらぼうな金太郎飴の断面のように削られ宅地開発されていく。
金星生まれの話も聞いた。雲に覆われた暑い星の金星では、暑さと湿気で大半が若死にする。三十年も生きていけない。だから彼らの心は愛に富んでいる。他人を憎まない、うらやまない、軽蔑しない。悪口も言わない。殺人も争いもない。あるのは愛情と思いやりだけ。
「たとえ今日誰が死んだとしても僕たちは悲しまない」「僕たちはその分だけ生きているうちに愛しておくのさ。後で後悔しないようにね」(24P)
土星生まれや金星生まれの話は、当時の学生運動家たちの理想郷だろう。それはまるで<涸れた井戸>へ投げこまれた雄弁な言葉のよう、しかし一方で、直子が住んでいた故郷に行ってみると、美味い水の出る井戸はすでに過去のもので、涸れた井戸となっていた。時は流れていったのだ。
そして雄弁だが空虚な言葉なんかでは埋めることのできない、直子を失った深い喪失のなかにいる「僕」にとって、象徴的なものである。
死んだ理由の分からない直子に対して、憎しみ、妬み、軽蔑、中傷などが自分にあったのか、愛情や思いやりが欠落したのか、何も理由が分からない「僕」は自責の念に苛まれている。
帰りの電車の中で何度も自分に言いきかせた。全ては終わっちまったんだ、もう忘れろ、と。そのためにここまで来たんじゃないか、と。でも忘れることなんてできなかった。直子を愛していたことも。そして彼女がもう死んでしまったことも。結局は何ひとつ終わっていないからだ。(24P)
この喪失の世界から抜け出すことができない。そしてその思いがピンボールの熱狂で、呪術となり直子に憑依し、彷徨い、そしてひとつの出口を模索する話に展開されていく。
双子は、現実と霊界との二つの世界の出入口の案内役。
双子が、僕の前に現れる。
違和感・・・・。そういった違和感を僕はしばしば感じる(中略)眼を覚ました時、両脇に双子の女の子がいた。(12P)
双子が、僕のもとを去っていく時には、
「何処に行く?」と僕は訊ねた。「もとのところよ」「帰るだけ」(182P)
物語の始めに忽然と部屋に現れ(入って)、物語の終わりに忽然と家に帰って(出て)いく双子は、「僕」を現世と霊界を繋ぐ境界点に存在している。胸に208・209とプリント(記号)されたトレーナー・シャツ以外はたいした持ちものはなく、いつも「僕」の両端に位置する。それは「入口」と「出口」の象徴。
「右と左」「縦と横」「上と下」「表と裏」「東と西」。「入口と出口」僕は負けないように辛うじてそう付け加えた。二人は顔を見合わせて満足そうに笑った。入口があって出口がある。大抵のものはそんな風にできている。(14P)
双子は、現世のことは何も知らない。何故僕の部屋に住みついたのか、いつまでいるのか、君たちは何なのか、年は?生まれは?何もわからない。
いつも何かしらの悪戯をしていている様子は、ニ匹の猫のよう。ロストボールを探しにゴルフ・コースを散歩したり、配電盤の葬式を提案したりする。
この双子が、物語の「入口」と「出口」の時空間の扉になっている。
この双子に誘われて、「僕」が直子の魂を探して、3フリッパーのピンボール台を探しあて再会して戻ってくると、双子はその役割を終えたかのように消えてしまう。
「本当に帰るところはあるのかい?」「もちろんよ」と一人が言った。「でなきゃ帰らないわ」ともう一人が言った。(182P)
きっと双子は人間ではなく、異界に誘う天使のような使者なのだろう。
言葉の翻訳と交信、そして配電盤の葬式について。
中心となるテーマは、時空間を越えて、魂の在り処を探す旅であり、交信は大きな意味を持つ。
僕と僕の友人は、翻訳を専門とする小さな事務所を七二年の春に開く。英語とフランス語を翻訳する業務で、仕事は順調で僕にとって午後の日だまりのように穏やかで平和な日々。
アウシュビッツでならきっと重宝がられたことだろう。問題は、と僕は思う、僕の合った場所が全て時代遅れになりつつあることだった。仕方のないことだと思う。(106P)
「僕」はこれまで考え続けてきたことが時代遅れになっていることを自覚している。そして現在の僕は、果てしなく続く沈黙を歩いていると考えている。
十年前の僕は、そもそも見知らぬ土地の話を聞くのが病的に好きだったし、土星生まれや、金星生まれとも話をしている。直子の父親は仏文学者で、直子も大学では仏文科だった。
それはパリの学生革命に端を発し、隆盛したイデオロギーや抽象概念のこと。
さらに学生時代にアパートに住んだ頃の七〇年では、一階の管理人室の隣の部屋に僕は住み、管理人室の前の小さな机に電話が置いてあった。外からの言葉を内の言葉に繋ぐ交換機の役割を「僕」が一手に担った、つまり僕は人的な電話の配電盤の役割を担っていた。
探し求めた3フリッパーのスペースシップの在り処をつきとめてくれたのは大学の講師でスペイン語を教えている。
ここでは、歴史の連続性や交換性あるいは逆に断絶性などを捉え、概念の融合や闘いなど言葉での交信をちりばめている。
そして配電盤を取り替えに来た電話局の人は、旧式の配電盤を新しい配電盤と変えなければならないという。配電盤は、言葉と言葉を繋ぐ装置。
はじめは、旧式でかまわない、今ので不自由はないからと「僕」は抵抗するが、電話局の人はそういう問題じゃなくて、みんながとても困るという。
「どんな風に?」「配電盤はみんな本社のでかいコンピューターに接続されているんですよ。ところがお宅だけみんなと違った信号を出すとするとね、これはとても困るんだ。わかりますか?」「わかるよ。ハードウェアとソフトウェアの統一の問題だよね」(48P)
電話局の人は、やさしく説明をしてくれる。
「お母さん犬が一匹いてね、その下に仔犬が何匹もいるわけですよ。ほら、わかるでしょ?」(中略)「お母さん犬が死ぬと仔犬も死ぬ。だもんで、お母さんが死にかけるとあたしたちが新しいお母さんに取り替えにやってくるわけなんです」(50P)
「素敵」と双子が感心する。画一された標準の信号でなければ、相手と通じ合うことが出来ない。言語のシステムが変わる。それは旧いシステムは無くなるということ。だから旧い記憶も必要ない。10分で新しい配電盤に代えて、電話局の人は旧い配電盤を置き忘れて帰っていく。
旧い配電盤は死にかけている。「いろんなものを吸い込みすぎてパンクしちゃったのよ」と双子は言う。「死ぬことは土に還ることだ」と双子は言う。
僕は「死なせたくない」というと、双子の一人が言った、
「気持ちはわかるわ」(中略)「でもきっと、あなたには荷が重すぎたのよ」(91P)
僕の心の中にある配電盤は、直子への僕の心の震えの隠喩となっている。
直子の言葉を背負い続け忘れることのできない僕に対して、双子たちは旧い配電盤の葬式を提案する。
僕たちは車で貯水池に向かう。永遠に降り続くかのような十月の雨、世界が救いがたい冷ややかさに満ちた中、いよいよ旧い配電盤は、貯水池に葬られる。
「哲学の義務は」と僕は、カントの言葉を引用した。「誤解によって生じた幻想を除去することにある・・・・・配電盤よ貯水池の底に安らかに眠れ」(103P)
こうして僕は、双子に諭されて祈りの言葉を手向け鎮魂する。