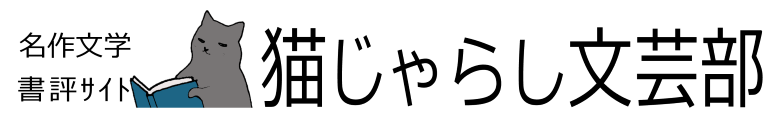昔は結婚して家庭に入る専業主婦が多かったが、1980年代末頃から急速に女性の自立が煽り立てられた。その後、未婚や晩婚も進む。『眠り』は、そんな時代背景の下、家庭の幸福と個人の幸福の板挟みとなる当時の女性たちの揺れ動く心の叫びである。それは自我と自己のズレから生じた、<こちら側>と<あちら側>の世界、つまり顕在と潜在の意識の往還。実験室で体から離され、電極に繋がれた<水槽の脳>が見る夢が現れる。主人公は、他者には見えないもうひとりの自分を生きているのだ。
動画もあります!こちらからどうぞ↓
解説
<死とは暗黒の中での永遠の覚醒> これは昏睡状況下での夢である
物語は<眠れなくなってもう十七日めになる>と冒頭の一行に前置きがある。種明かしは最初からされていて、寧ろ、その提示された世界を楽しむことになる。
哲学の世界で有名な<水槽の脳>という思考実験。生きた脳を特殊な培養液に入れコンピューターにつなぐ。そして仮想現実を体験させる。これと同じで、この物語で主人公が体験している世界は、水槽の脳が見ている夢なのです。
無意識下で自分は覚醒していると考えているのです。
十七日目、「自分は死ぬのだろうか」と「私」は思い、死の印象が綴られる。
「私」はそれまで、眠りというものを死の一種の原型として捉えていた。つまり私は眠りの延長線上にあるものとして、死を想定していたのだ。死とは要するに、普通の眠りよりはずっと深く意識のない眠り―永遠の休息、ブラックアウトなのだ。私はそう思っていた。<『眠り』より引用 >
でもあるいはそうじゃないかもしれない、とふと思った。
死とは、眠りなんかとはまったく違った種類の状況ではないのだろうか―それはあるいは私が今見ているような果てしなく深い覚醒した暗闇であるかもしれないのだ。死とはそういう暗黒の中で永遠に覚醒しつづけていることであるかもしれないのだ。<『眠り』より引用 >
こうして「私」は、<死>とは<眠りの延長>のようなではなく<深い覚醒した暗闇>ではないかと激しい恐怖に襲われます。
つまり永遠に眠れない状態なのです。
クライマックスで、私は地下駐車場に降り、愛車のシティーに乗り込み港まで車を走らせる。
自我と自己がズレていき、精神が乖離していくような恐ろしさが最高潮となる。深夜の港のパーキングに止めた車に、男が現れて窓を叩き、車を揺らし、ひっくりかえそうとする。「私」はひどいパニック状態に陥る。
この先はどうなるのか? というところで物語が閉じられます。
死を<暗黒の中での永遠の覚醒状態>としてパラドキシカルに表現しています。
これは後の『アフターダーク』(2004年)でTVの向こう側で眠り続ける「浅井エリ」であり、その予兆は『ノルウエイの森』(1987年)の深い井戸を恐れる「直子」なのでしょう。
十七日間、一睡もしないことは人間には不可能です。
そこで<昏睡状態で夢想している>と考えてみます。
そうです、<あちら側>の世界でずっと眠れずに覚醒している状態です。
単調な日々の連続の中で、ふと訪れる自我や実存の不安が潜在意識のなかにあり、無意識下で繰り広げられる バーチャル・リアリティの世界です。
そして、そこで起こっている現実に、何かが間違っていると主人公は考えているのです。
昏睡状態の医学的な原因は物語からは不明ですが、主人公は眠りという暗闇の中で覚醒し行動しているのです。病み始めた精神の兆候は、日常のそこ、ここにみられました。
それは三十になる 「私」 が感じ始めた<小さな違和感>。
夫と子供を送りだして買い物に行く。その後、掃除と洗濯をする。夫の職業は歯医者。「僕がハンサムなのは僕の罪じゃない」と夫は言って微笑む。いつも同じ言葉の繰り返し、私たちの間でしか通用しないつまらない冗談。
朝、八時十五分に車で駐車場を出る。「気をつけてね」と私が言う。「大丈夫」と夫が言う。いつも同じ台詞(せりふ)の繰り返し。長く一緒に暮らす日常に、<ふっと裂け目が入ってくる>。
夫は、世間のおおかたの人に好感を持たれ、安心感を抱かれ、私の女友達からも気に入られている。私は夫のことが好きで、愛している。が特に<気に入ってはいない>と考える。自分をどこか冷静に見始めている。
歳月とともに<生活の質は少しずつ変化>していく。「私」にとって、日常は制約となり、入り組んだものになっていく。私は体型維持のためにプールで泳ぐ。このひとときだけは、自分であるための大切な日課となる。
日記をつけても昨日と一昨日の区別もつかない。毎日がほとんど同じことの繰り返し。そんな人生に驚いてしまう。次第に、心からの幸せが感じられなくなる。自分が組み込まれているという感覚。
昏睡のなか<自我>を取り戻そうと、闇のなかを自由に彷徨う。
「私」は洗面所の鏡の前に立ち、自分の顔をじっと眺める。すると私の顔は、私自身から分離していく。つまり、自分の顔には ふたつの顔があることを改めて自覚する。
ひとつの顔が<自我>で、もうひとつの顔が<自己>である。ふたつの像の重なりが<自分>である。
<自我(ego)>がきっと、ほんとうの自分なのだろう。そして、自我のうえに他者からの見え方としての<自己(self)>がある。
ほんとうの自分と、妻であり母である役割を担った自分が完成している。
この重なりが、次第にズレを来きたし始めるのだ。
それは年月と共にゆっくりと訪れたのだろうか。それとも何かをきっかけに訪れたのだろうか。
結婚してからの「私」は、「妻」であり「母」である役割ができた。それが<存在価値>でもあった。
しかしもうひとつある、それは「妻」であり「母」である前の「私」。重なるふたつの像の最初にあったほうの「私」である。結婚をする前の自分一人の時間を持つ<自由な私>を確認し始める。
ある夜に金縛りに遭う。自分の足に水をかけ続ける不気味な老人を見る。この悪夢をきっかけに一睡もできなくなる。
結婚前の<自由な私>は、「お酒」も「読書」も「チョコレート」も楽しむことを許されていた。再び自我を開放して「自分の時間」を取り戻す欲求が膨張してくる。
「お酒」は、昔はそれなりに飲んでいたが、結婚してから飲まなくなっていた。夫は全く飲まない。『アンナ・カレーニナ』を読む。腰を据えてじっくりと本を読むなんて何年ぶりのことだろう。
「読書」を始めても、普段は「子供のこと」や「買い物のこと」が頭に浮かび中断させられる。結婚するまでは本を読むことは私の生活の中心だった。結局、朝まで本を読んだ。
でも私は全く眠たくならない。眠たくないのだ。
極めつけは「チョコレート」。夫が歯医者なので甘い菓子は禁止されているという束縛感。その反抗心で、欲求が大きくなり、チョコレートを欠かせなくなっていく。コンビニで買ってすぐに開けてバリバリと貪りながら道を歩く。
この物語は<あちら側>に往くことで、結婚で<抑制>され続けた「私」の自我を取り戻そうと17日間の自由の私を満喫する。
ただこれは、<暗闇の中での永遠の覚醒>つまりは<死>と同じなのだ。しかしこの状態を主人公の私は望んでいるのだ。
話は、惰性だけの日常生活に対して夫や家族の批判を始める。
「自由な私」を手に入れ始めた私は、夫のセックスを拒むようになる。夫への愛情が失われつつあることを知る。夫に対して興味・関心が無くなる。
プールに行って、何かを追い出したいと感じた。この何かとは、組み込まれたものの破壊、つまり家族の日常の崩壊であり、自由への回帰願望である。私はもう一度、一人を謳歌したい。
「私」は妻として母としての役割を「義務」と捉え、それを果たしている。私は買い物をし、料理を作り、掃除をし、子供の相手をし、セックスをする。難しいことではない、寧ろ簡単だ。
頭と肉体のコネクションを切ればいいだけなのだ。機械的に役割をこなすだけである。
私の変化に夫も息子も姑も気づかない。彼らは「自由な私」ではなく、「役割をこなしている私」を何の疑いもなく見ている。彼らは「私」の自我とは接していないのだ。
<自我>と<自己>を重ねて生きるか、引き離された死の状態を選ぶか。
私は眠れないのに、体は衰退することもなく、ますます元気になっていく。シャワーを浴びた後、裸のまま全身鏡の前に立つ。はちきれんばかりの生命力を湛えているのを発見して驚く。ますます艶がでてハリがあった。そして自分が奇麗になっていることに気づき、若返って見えた。
「私」は “眠りとは休憩である” と、ある本から学ぶ。人間は傾向的に思考し行動する、眠りはその傾向の偏りを調整し治癒する行為で、そこから外れると「存在基盤」を失うと、著者は書いていた。
「私」は、無感動で機械的に役割をこなしている傾向的な家事作業を思いつく。すると私は傾向的に消費され、治癒のために眠ることになる。
眠りなんかいらないと思う。「私」は、私が傾向的に消費されたくない。
「存在基盤」を失っても、自由を求めようとする。私は眠れないことを恐れなくなる。眠れない時間の分、人生が拡大しているのだと私は考え始める。
夫の寝顔を見ると、目の下のホクロが大きく、下品に見えた。瞼の閉じ方も品性が無く、阿保みたいに眠っている。傾向的に消費されるだけの夫に嫌悪感を抱き始める。思えば、子供の名前のことで私と姑との諍いがあり「私」を庇ってくれなかった夫の遠い記憶が蘇る。そこがひっかかりの最初だった。
すると「私」の息子に対する気持ちにも変化が生じる。夫に続いて息子の寝顔を見て、その寝顔の何かが神経を苛立たせる。寝顔が父親とそっくりだからだ。さらに姑の顔とそっくりなのだ。
そして「私」はいつか将来、息子を軽蔑するようになると確信する。
夫への愛情や子供への母性愛を失っている理由も、夫とその家族の血統的なかたくなさ、自己充足性からくる傲慢さが嫌いだからだと思う。優しさ、気配り、真面目、仕事熱心、誰にでも親切。そんな「文句のつけようのなさ」が、「私」の癇にさわり耐えられなくなる。
こうして「私」は、妻そして母としての「存在価値」の上での自分ではなく、現在の自分こそが<ほんとうの自分>であり、これまでの「私」はただ消費されていたことに気づく。
この17日間の<覚醒>で、私は剥き出しの<自我>が突き出てくる。
そして「私」は、地下駐車場に降り、シティーに乗り込み港まで車を走らせ、パーキングで止める。そして気がつけば眠りのない暗闇を眺めている。
誰かが車の外にいることに気づく、誰かがドアを開けようとしている。ドアはロックされている。人の姿が車の両側に見える。右側のガラス窓が拳でどんどん叩かれる。キーを回すがエンジンは点火しない。
何かが間違っている と「私」は気づいているが、何が間違っているのか、私にはわからない。濃密な闇が詰まっている。それはもう私をどこにも連れていかない。
私は眠れない、暗黒の中での永遠の覚醒に向かっていくようだ。つまりそれは<死>を意味する。
私は両手で顔を覆い泣く。泣くことしかできない。夜のいちばん深い時刻で男たちは私の車を揺さぶり続けている。彼らは私の車を倒そうとしているのだ。