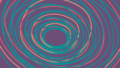詳しい解説動画シリーズを作成しましたので、ぜひご覧下さい。
動画には字幕が無いので、動画音声のテキストを以下に記載します。動画と併せてお読み下さい。
題名に秘めた主題「三と四」とは何か
こんばんは 猫じゃらし文芸部です。今夜は、夏目漱石『三四郎』について お話し致します。
『三四郎』といえば、東京帝国大学の新入生 九州から上京してきた、小川三四郎のキャンパスライフとほろ苦い片思いを描いた瑞々しい青春小説 という感じに説明されることが多いかと思いますが、夏目漱石は、ある目的があって この作品を書きました。
どういうことかと言うと、『三四郎』の新聞連載が始まる2年前、漱石は『草枕』という小説を発表しています。読んだことがない という方もタイトルはご存じでしょう。読んだことはあるけれど、ぼんやりとした印象しか残っていない という方も多いかもしれません。とても不思議で、どう解釈すれば良いかわからないところがある、ミステリアスな小説です。この謎めいた小説『草枕』の謎を解く手がかり ヒントを読者に提供するための物語として『三四郎』は書かれたのだ と考えられます。
『草枕』の物語を簡単に説明すると、画家である主人公が 旅先の温泉宿で出会う美しい若女将 志保田那美という女性をモデルにして、一枚の絵を 彼の頭の中で完成させる物語です。『三四郎』と似ていませんか?主人公、小川三四郎の心を惑わせたヒロイン里見美禰子を描いた絵画が完成し、展覧会で披露されます。『三四郎』と『草枕』は、ヒロインが絵に収まる というまったく同じ結末にいたる話を様々な点で「逆さま」に描いた小説です。分かりやすいところ一箇所だけ挙げれば、
『草枕』の主人公は、「東京から熊本にやってきた男」
『三四郎』の主人公は、「熊本から東京にやってきた男」
文体や雰囲気は、大きく異なる二つの作品ですが、よく読むと共通点とか逆さまになっている点が20か所以上もあって、そこが物語を読み解くヒント、手掛かりにもなります。『草枕』と『三四郎』二つ一緒に、あわせて考えてみると、いろんな謎が解けてしまう。お互いに補完しあっています。
二つの小説は、主題 テーマも同じです。何が面白いと言って、ここが一番面白いところなのですが、作者は、このテーマに名前というか、呼び名をつけています。数字の「三」と数字の「四」、「三と四」です。主題を「三と四」と呼ぶことにする と書いてある訳ではないのですが、作者は間違いなく「三と四」を意識して書きました。そう言い切れるだけの証拠が、たくさん見つかります。
『草枕』では、なるべく目立たないように、小説の中に「三と四」がいくつも隠されていて、その隠された「三と四」に注目すると草枕の構造と筋が見えてきます。そうして その逆さまである『三四郎』においては、ひとつだけ しかし一番目立つ場所 タイトルに「三と四」が堂々と飾られています。『三四郎』というタイトルは、小川三四郎という登場人物の名前からつけたのではなく、まずタイトルに「三と四」という数字を入れる必要があって、そこから主人公を小川三四郎と名付けたのです。
「三と四」は、謎を解くための 最大のヒントです。
では「三と四」の正体とは何か? 丁寧に説明すると、ものすごく時間がかかるので、とりあえず結論だけ先に言っておきます。三とは「智・情・意」です。知性の智、感情の情、意志の意。人間の精神の三つの働き「智・情・意」です。そして「四」とは、「真・善・美・壮」です。いわゆる「真善美」という、三つの理想としてよく聞く言葉に、夏目漱石が四つ目の理想として、「壮」と名付けた理想をつけ加えました。「壮」は、勇壮の「壮」です。簡単に言うと「壮」の理想というのは、勇気があることです。
漱石は『草枕』から約半年後に『文芸の哲学的基礎』という講演禄を発表しています。ここで「真・善・美・壮」の4種の理想は、芸術が もっと広く言えば、人間が目指す理想であり、これが人間の精神「智・情・意」とどのように関係するのか ということを詳しく説明しています。
「智情意」と「真善美壮」については いずれ丁寧に触れようと思いますが、『三四郎』を読むに当たっては 何となくの理解だけで大丈夫です。
『文芸の哲学的基礎』『草枕』『三四郎』は、テーマが同じ、3つの著作のテーマは、「三と四」すなわち「智情意」と「真善美壮」、このように仮定すると がぜん面白くなります。
あの 有名な草枕の冒頭を思い出してください。
山路を登りながら、こう考えた。
智に働けば 角が立つ。情に棹させば 流される。意地を通せば 窮屈だ。とかくに 人の世は住みにくい。
小説の最初の部分に、とても分かりやすい形で「智・情・意」すなわち「三」が出てきます。ということは、『三四郎』は『草枕』の「逆さま」ですから、小説の最後の部分に とても分かりにくい形で「真・善・美・壮」すなわち「四」が隠されている、ということになります。
「智・情・意」で『草枕』が始まり、「真・善・美・壮」で『三四郎』が終わる。
「三」で始まり、「四」で終わる。
という形になっています。『三四郎』のラストに、どんな風に「四」が隠されているのか?
次回、説明します。
こんな感じの「逆さまの仕掛け」が『草枕』と『三四郎』には、たくさんあります。この「逆さまの仕掛け」に注目すれば 物語の謎が解ける、というパズルのような楽しさがあります。格調高い文章で、ちょっと読みにくい『草枕』ですが、探偵的な人間を批判している漱石が、読者に探偵の真似をさせる推理小説。もしくは、唯一無二の形式で書かれた、奇書と言ってもいい、超絶ミステリーと夏目漱石の芸術論が合体した、すごい作品です。
漱石といえば、暗くてシリアスな『こころ』という作品が、一番多く読まれていると思いますが、『草枕』と『三四郎』こそ 作者が綿密な計画を企てて取り組んだ 最高傑作だと思います。その魅力をできるだけ解りやすく お伝えしたいのですが『草枕』はとにかくユニーク 独創的で普通の小説ではありませんので、説明がとても難しいです。だから まずは『三四郎』のほうから 取り掛かることにしました。それだけでも6回にわたる長い動画になってしまいますが、どうか最後までおつきあいください。
次回は、『三四郎』の構成についてお話し致します。
最後に明かされる作品の構成【美禰子と四人の男】
こんばんは 猫じゃらし文芸部です。今夜は、夏目漱石『三四郎』2回目です。この動画はシリーズになっていますので、ぜひ1回目からご視聴ください。2回目の今夜は、この小説の構成についてお話いたします。あらすじの説明は、他の方の動画やウィキペディアなどにもあるので省くことにしますが、代わりに、全13章、簡単な章ごとの概要を画面に載せます。
時間的構成
文庫本だとおおよそ300ページ近くある長編。時間的に言えば、当時の大学の新学期が始まる9月より少し手前、まだ夏休み中の8月から始まって、翌年1月まで6か月間の物語です。とくべつに印象的な事件が起きないので、なんだかダラダラしていて起伏の感じられない小説ですが、ポイントとして、菊人形展、運動会、展覧会、演芸会という、秋らしい催し物が配置されています。
全部で13章に分けられている、これも『草枕』との共通点です。これは偶然なんかではないと思います。意識して『草枕』に合わせて『三四郎』も13章にしたのです。『草枕』においては、章の分かれ目というのは非常に重要な意味があって、もし章分けが無かったら 読み解きが不可能です。絶対にここで区切らなければならないという箇所で 章分けがなされています。しかし『三四郎』は、ご存知のとおり新聞連載小説ですから、後日 本として出版する際に 13章に分けられたのかもしれません。『三四郎』の章分けには、それほど深い意味とか 必要性はないのです。
そうは言っても、肝心なおへそ部分だけは、きちんと『草枕』と一緒になるように揃えてあります。両方ともおへそは、9章です。9章で物語が転換をします。どちらも「転換をむかえる合図」というのがありまして、その合図として『草枕』では地震が起こり、『三四郎』では火事が起きます。火事と言っても、夜中に小川三四郎の下宿の近所で火事が起きて、半鐘の音で彼が目を覚ますだけですけれども 三四郎が気づかなかっただけで、この夜の何気ない出来事によって、ある人の運命が暗転しました。
登場人物の構成
半年間の学生生活 小川くんに多少精神的な変化はありましたが、特別に何かしたわけではありません。ただ美禰子に片思いをしていただけの6か月間です。小川三四郎は主人公ですが もっと正確に言うと、視点中心人物です。読者は、彼に感情移入をして一緒に物語を経験する。それは、美禰子のことを 考えること。
この小説のテーマを表現している真の主役は、里見美禰子です。小説内で起きる一番大きな変化は、独身だった彼女が結婚を決めたことであり、全体としては 里見美禰子を描いた小説 であるにも関わらず、美禰子の行動、美禰子の気持ちというのは、あまり描かれていない感じがしませんか?
これは作者が、あえて解りにくいように描いたからです。なぜならば、この小説は推理小説だからです。殺人事件も起きず 探偵も登場しないけれども、推理小説です。推理小説だと意識して読まなければ、その真価を知ることが出来ません。
ミステリアスなヒロイン美禰子は、どんな女なのか?誰を愛して、何を考えて、どう行動したのか?推理してみろ という問いが、作者から突きつけられています。美禰子という女の謎を解く推理小説です。読者は、小川くんのようにぼーっとした受け身な態度では、ダメです。探偵のように注意深く、作中から細かい情報を拾い集め、その細かな情報から自発的に推理を展開しなければなりません。その際に、どういう観点で美禰子を観察するべきか?という重要なヒントが提示されています。それが最終章 ラストシーンです。
13章 冬休みが終わり、帰省していた三四郎は、東京に戻ってきました。画家の原口が美禰子を等身大に描いた絵画「森の女」を展示披露します。
―――広田先生と野々宮さんと与次郎と三四郎と。四人は、余所を後回しにして、第一に「森の女」の部屋に入った。
ここからがラストシーンです。彼らは絵を見ながら、各々一言ずつ感想を述べます。四人が絵を見て、なんと言っていたか、抜き出してみましょう。
- 「素敵に大きなもの描いたな」と与次郎が言った。
- 「色の出し方がなかなか洒落しゃれていますね。むしろ意気な絵だ」と野々宮さんが評した。
- 「少し気がききすぎているくらいだ。これじゃ鼓の音ねのようにぽんぽんする絵はかけないと自白するはずだ」と広田先生が評した。
- 三四郎はなんとも答えなかった。ただ口のうちでストレイシープ、ストレイシープと繰り返した。
この四人のコメント 単なる絵の感想というのは 見せかけであって、これは作者から読者に提示された四つのヒントです。作者は、里見美禰子をどう描いたか。読者は、どこに注意を払って彼女を観察するべきか。四人のコメントを参考にしなさい。という作者からのメッセージです。
前回の動画を聞いていただいた方は、とっくに気づかれたと思います。前回お話した『草枕』と『三四郎』の主題「三と四」、「三」は「智情意」「四」は「真善美壮」。『草枕』は「三」で始まり、『三四郎』は「四」で終わるのだと述べました。四人のコメントは、「真・善・美・壮」という四つの観点から美禰子を表現したものです。誰がどの理想を担当していたのか、四人のコメントを読んで ちょっと考えれば なんとなく見当がつくと思います。そしてこのラストシーン 四人の男たちが等身大に描かれた美禰子を前にして、意見を述べ合うというラストシーン、これがそのまま 作品の構成そのものを表現しています。四人の男が 一人の女を観察する 鑑賞する物語 なのです。
ついでに補足しておきますと『草枕』と『三四郎』は、登場人物の構成という点でも、逆さまです。『三四郎』は、四人の男と一人の女。『草枕』はその反対 一人の男と四人の女、と言う事になります。『草枕』のヒロインと言えば志保田那美ですが、その他三人の女の存在に着目することが、謎を解く鍵になっています。
と言う事で、次回からは、四人のコメントをヒントに、美禰子の徹底的な検証を行っていきます。それは、同時にこの小説を、語りなおすことになるので、大変長くなります。13章でコメントを述べた順番どおり、与次郎 野々宮さん 広田先生 三四郎の順でいきます。
次回の為の準備として、美禰子がどういうお嬢さんなのか?人物設定を確認しておきましょう。
美禰子の人物設定
里見美禰子 年齢は書かれていませんが、三四郎と同い年位という表現がありますので、23歳でいいと思います。彼女の容姿 外見、美禰子の絵を描いた原口という画家が言うには、彼女の大きな二重瞼の目が 洋画の絵に相応しいので、モデルを頼んだ、とあります。美禰子に関しては、二重瞼の目の描写が多く、三四郎はしょっちゅう彼女の目を意識しています。彼は、大学の授業でグルーズという画家の絵を見たときに、これぞまさしく美禰子の目と同じ印象を受ける と言っています。画面にグルーズの絵画を載せました。美禰子の目は、グルーズが描く女の目に似て、ヴォラプチュアス つまり官能的、色っぽい「けれども卑しく媚びるのとは、違う。見られるもののほうが媚びたくなるほどに残酷な目つき」という表現をしています。色気はあるけれども、決して卑しく媚びる感じはしない。毅然とした態度 なのだろうと思います。
次に、美禰子の趣味、英語とバイオリンです。英語は、広田先生に習っています。明治のお嬢さんの趣味としては、お琴のほうが多いと思うのですが、美禰子はバイオリンを弾いている。さらに、日曜日には、キリスト教の教会 礼拝に通っています。まだほとんどの人が着物を着ている、もちろん美禰子だって着物を着ている明治時代ですが、彼女は、だいぶ積極的に、西洋の文化に浸っているハイカラさんです。西洋かぶれだと言ってもいいくらいでしょう。
西洋かぶれは、彼女が住んでいる住宅にもよく表れています。美禰子が住んでいる住宅は、瓦葺の門があるということなので 見かけは立派な和式住宅ですが、三四郎が通された応接間にはいると、マントルピース 暖炉があって、暖炉の上には金細工の蠟燭立てがおいてあるような、完全に洋風な内装の部屋です。
この家に、美禰子は、兄 恭助と、そして当時の事ですから当然 下女 お手伝いさんを置いて住んでいます。他の登場人物たちも、下宿している場合を除いては、みんな住み込みのお手伝いさんを置いて暮らしているようです。約100年前、電化製品も普及していませんから、家事には、とても手間がかかった。そして、貧富の差が現在よりも大きかった、ということですね。
美禰子の両親は、早くに亡くなっています。恭助の上にもう一人長男が居ましたが、彼も若くして亡くなっています。家族の中に、父親とか長男といった権威的な存在がいない、という点がポイントです。口うるさく行動制限する人もいない里見家で、誰に縛られることもなく自由に振舞ってきた彼女は、自分が好きに使えるお金も持っています。美禰子が持っていた預金通帳に入っているのは、両親の遺産を兄から分けてもらった分でしょう。金銭的にも自由な環境にいる美禰子ですが、彼女が自由でいられる時間は、いつまでも続くものではありませんでした。
次男の里見恭介は、美禰子の結婚相手を探していました。恭助自身に結婚するつもりがあって、自分が結婚する前に、妹の結婚をさっさとまとめようとしていた。という事情が7章で明らかになります。おそらく自宅を相続している兄がお嫁さんを迎えるので、小姑は、居ないほうがいいのです。でも、女性が独身のまま、実家を出て一人暮らしをするという選択肢は、考えづらい時代です。結婚も、家族や親せきが世話を焼いて、縁談をまとめるのが普通でしょうが、西洋流の美禰子が大人しくそれに従うだろうか?いや、とうていそうは思えない。という話を7章で、広田先生と画家の原口がしていました。
「あの女は自分の行きたい所でなくっちゃ行きっこない。勧めたってだめだ。好きな人があるまで独身で置くがいい」
「まったく西洋流だね。もっともこれからの女はみんなそうなるんだから、それもよかろう」
しかし、そんな予想を裏切って 彼女は唐突に縁談結婚を決めます。縁談の相手は、美禰子の兄の友人でした。金縁の眼鏡をかけて 黒い帽子を被った 背のすらりと高く 男らしい若い紳士 という描写から、美禰子にふさわしい ある程度の資産階級の人であることが なんとなく想像できます。けれども、その縁談というのは、野々宮宗八の妹 よし子が断った後に、たまたま美禰子のところへ回ってきたものであるということから、釣り合いのとれる適当な相手なら誰でも良い、単なる普通の縁談であったことが分かります。西洋流で、好きな人とでなければ結婚しそうもない、と思われていた彼女が、何故すんなりと縁談結婚を受けたのか?美禰子の行動 美禰子の気持ち 四人の証言をヒントに、推理していきましょう。
佐々木与次郎「素敵に大きなもの描いたな」
こんばんは 猫じゃらし文芸部です。今夜は、夏目漱石『三四郎』3回目です。この動画はシリーズになっていますので、ぜひ1回目から順番にご視聴ください。
今回からは、ラストシーン4人のコメントをヒントに里見美禰子を、徹底的に検証していきます。画面には引用文 もしくは本文の情報をまとめたもの等を提示しています。画面を見ずに、音声だけでお付き合い下さっても、十分お分かりになると思います。それでは、はじめましょう。まずは、与次郎の人物設定です。
与次郎の人物設定
佐々木与次郎は、大学で三四郎と同じ授業を受けている同級生、お調子者で快活な男です。真面目一辺倒で 大学と下宿を往復するだけだった三四郎に、東京での遊び方を教え、広田先生や美禰子と引き合わせてくれたのが与次郎でした。
同じ教室で机を並べる同級生ですが、二人の境遇には、色々と違いがあります。地方の地主のお坊ちゃまである三四郎は、親からの仕送りをもらって、下宿生活をしていますが、与次郎は、高校英語教師の広田先生の家に、書生として雑用をしながら、間借りしています。三四郎よりも、経済的には厳しい境遇だと思われます。三四郎が本科生であるのに、与次郎は選科である、という違いも、経済的な事情が関係しているのかもしれません。そういう事情は別にしても、与次郎は金銭面において 信頼できる人間ではありません。広田先生から預かった金を競馬で擦って、それを三四郎に穴埋めさせて、結局返しませんでした。というより、はじめから返すつもりも無かったのです。そのうえ、本人が言うには「関係した女」に、自分は医学部の学生だと嘘をつき通していた。女性経験ゼロの三四郎と違って、与次郎は女を騙して遊んでいる、不実な遊び人という一面もある男です。
そもそも与次郎は、最初から何か目的があって、三四郎に近づいてきたということに注意しましょう。大学で、与次郎のほうから三四郎に話しかけ、淀見軒という店でライスカレーを奢ってくれ、まだ東京をよく知らない三四郎を連れて電車に乗り、新橋や日本橋を案内し、寄席にも連れて行ってくれました。
が、与次郎がライスカラーを奢ってあげた学生というのは、三四郎ひとりではなかったのだ、という事が6章で判明します。まず最初に、ライスカレーを奢って、仲良くなるきっかけをつくる、というのは与次郎の常套手段であって、彼はある目的があって、学生たちをできるだけ数多く抱きこもうとしていたのです。一見ちゃらんぽらんに見える与次郎ですが、彼は、自分の目的を実現するために、新学期のはじめから計画的に行動していました。
彼の目的というのは、広田先生を盛り立てて有名にして、東京帝国大学の教授職につけること。建前上は、それが日本の大学教育ため、ですが、本音としては、個人的にお世話になっている広田先生をなんとかして世間に売り出してあげたい。この与次郎の運動は、なかなか大がかりなもので、広田先生を称える文章を雑誌に掲載したり、先生の顔を広めるために、上野のレストラン精養軒で会合を開き、有力な博士や評論家達を招いたり、とお金と手間をかけた運動を行いました。いつもふざけているように見える与次郎ですが、彼は、本気で真剣にこの運動に取り組んでいたのです。
しかし、これは先生の意向に従っていた訳ではなく、むしろバレないように内緒で、こっそり勝手にやったことであって、先生にとっては、大変な迷惑、余計なお世話でした。結果、彼の運動は失敗に終わり、かえって広田先生の不名誉になってしまいました。
与次郎は、面白そうなことを自分で見つけ出して、常に忙しく動きまわっている。広田先生の売り込みに失敗にした後もめげずに、演芸会の切符売りに励んでいます。大人しく、じっとしていることができない、愛すべきいたずら者 と表現されています。それ以上の裏はありません。広田先生は、そこを理解し、可愛いと言って許してくれています。与次郎の性格については、一緒に暮らしている広田先生がよく知っていて、美禰子と比較して評価していますので、広田先生の回でもう少し掘り下げることにします。
美禰子と与次郎
ちょろちょろと落ち着きのない与次郎と正反対なのが、上品で落ち着きのある美禰子。美禰子は、広田先生のお宅に英語のレッスンにやってくるので、与次郎とも顔見知り ということでしょう。与次郎は、美禰子のことを結構よく見ています。美禰子に見とれて、のぼせている三四郎とは違って、冷静に彼女の言動を観察し、意見を述べている場面が多いです。
与次郎が、小説の終わり近く12章で こんな風に美禰子を褒めていました。
「なぜというに。二十前後の同じ年の男女を二人並べてみろ。女のほうが万事上手だあね。男は馬鹿にされるばかりだ。女だって、自分の軽蔑する男の所へ嫁へ行く気は出ないやね。もっとも自分が世界でいちばん偉いと思ってる女は例外だ。軽蔑する所へ行かなければ独身で暮らすよりほかに方法はないんだから。よく金持ちの娘や何かにそんなのがあるじゃないか、望んで嫁に来ておきながら、亭主を軽蔑しているのが。美禰子さんはそれよりずっと偉い。その代り、夫として尊敬のできない人の所へははじめから行く気はないんだから、相手になるものはその気でいなくっちゃいけない。そういう点で君だのぼくだのは、あの女の夫になる資格はないんだよ」
美禰子は、尊敬できる男と結婚したい、というしっかりとした基準と意志を持っているから、偉いんだと与次郎が褒めています。「あの女の夫になる資格」という言い方をしていますが、じゃあその、資格を持っている男は、誰なのかというと、時間を遡った9章で、与次郎と三四郎がこんな会話をしています。
「そう云う事もある。然し能く分ったとして、君、あの女の夫になれるか」
『三四郎』9章
三四郎は未だかつてこの問題を考えたことがなかった。美禰子に愛せられるという事実そのものが、彼女の夫たる唯一の資格のような気がしていた。言われてみると、なるほど疑問である。三四郎は首を傾けた。
「野々宮さんならなれる」と与次郎が言った。
「野々宮さんと、あの人とは何か今までに関係があるのか」
三四郎の顔は彫りつけたようにまじめであった。与次郎は一口、
「知らん」と言った。三四郎は黙っている。
与次郎は、美禰子の夫になる資格があるのは、野々宮宗八であると断言しています。そして美禰子自身も、6章でこう言っています。
「宗八さんのようなかたは、我々の考えじゃわかりませんよ。ずっと高い所にいて、大きな事を考えていらっしゃるんだから」と大いに野々宮さんをほめだした。よし子は黙って聞いている。
学問をする人がうるさい俗用を避けて、なるべく単純な生活にがまんするのは、みんな研究のためやむをえないんだからしかたがない。野々宮のような外国にまで聞こえるほどの仕事をする人が、普通の学生同様な下宿にはいっているのも必竟野々宮が偉いからのことで、下宿がきたなければきたないほど尊敬しなくってはならない。――美禰子の野々宮に対する賛辞のつづきは、ざっとこうである。
12章 9章 6章と、時間を遡るように引用しました。美禰子は、尊敬できる男と結婚したい。彼女が尊敬しているのは、野々宮である。美禰子は、野々宮と結婚したいのだ、という事を読み取ることが出来ます。ここまでは、簡単です。問題は、9章で三四郎が与次郎に向かって、真剣な顔で尋ねた疑
「野々宮さんと、あの人とは何か今までに関係があるのか」
与次郎が「知らん」としか答えられなかった疑問です。これを推理しましょう。
と、いうことで与次郎の「森の女」の絵を見た感想「素敵に大きなもの描いたな」です。絵のサイズについて言及しているというのは、見かけ上の事であって、これは、里見美禰子のことを言っているのです。「大きい」ということ。これを人格上の言葉に翻訳してみてください。「人格上の言葉に翻訳してみろ」というのは、4章で広田先生が使った言葉です。人格として大きい、つまり美禰子を「大した女だ」と褒めている訳です。一体美禰子は、どういう所が「大したヤツ」なのでしょうか?
半年間、特に何にもしない主人公 小川三四郎の代わりに、必死に行動したのが、美禰子と与次郎です。二人とも、思い通りの結果は得られなかった。結局は、負けてしまったのですが、自分の意志を実現するために、精一杯頑張ったのです。読者にも三四郎にも、解るように活動していたのが与次郎で、その裏で誰にも気づかれないように、ひっそりと活動していたのが美禰子です。彼女は、尊敬できる男との結婚を目標に、現在で言う婚活に励んでいました。
美禰子の婚活【始点と終点】
秘密裡に行われた彼女の婚活、いつから始まっていたのか?教えてくれたのは10章の美禰子です。10章というのは、小川三四郎にとってのクライマックスです。美禰子と与次郎の活動は9章で終わり、後は結果を待つだけの状態になるのですが、三四郎はのんびりしているので、常に人よりワンテンポ遅れます。彼の唯一の活動は、美禰子への片思いですから、せめて彼女に想いを伝える、いわゆる告白を10章で行います。三四郎が告白に至る場面から見てみましょう。
三四郎は、美禰子から借りた30円を返すために、画家原口の家を訊ねます。美禰子は、原口のアトリエで絵のモデルを務めている最中です。美禰子を等身大に描いた、とても大きな絵に、原口は取り組んでいるのですが、三四郎の目には、あと少しで完成というところまで、仕上がっているように見えました。絵を描きながら ペラペラとよくしゃべる原口が、
「どうもならないのさ。だから結婚は考え物だよ。離合集散、ともに自由にならない。広田先生を見たまえ、野々宮さんを見たまえ、里見恭助君を見たまえ、ついでにぼくを見たまえ。みんな結婚をしていない。女が偉くなると、こういう独身ものがたくさんできてくる。だから社会の原則は、独身ものが、できえない程度内において、女が偉くならなくっちゃだめだね」という意見を述べます。
そこで美禰子が「でも兄は近々結婚いたしますよ」と報告すると原口は「おや、そうですか。するとあなたはどうなります」と尋ねます。兄の恭助が結婚をすると、美禰子さん あなたは身の置き所が無くなるでしょう?実家を出ていくのですか?という意味の原口の質問に、美禰子は「存じません」とまるで他人事のように、笑っていました。が、この時点で美禰子の縁談は、ほとんど決まりかけの状態であったということが、すぐ後で分かります。それなのに彼女は、実は私も結婚が決まるのですよ とこの場で報告しません。報告すれば当然、おめでとうと言われる訳ですが、彼女自身がおめでたい気分じゃないので、ここで報告する気になれないのです。この後 美禰子の顔が、どんどん疲れた様子になっていきます。
そんな美禰子を見て、原口は、今日はもうポーズをとるのは、やめにして、お茶でも飲んでゆっくりしましょう と提案しますが、彼女は、用事があるから帰る と言って、原口のアトリエを出ようとします。すると三四郎も原口のお茶を断って、美禰子と一緒にアトリエを出ます。そして美禰子に、二人で少し散歩でもしようと誘うのですが、断られます。彼女が、用事があるからと言ってお茶を飲まずに出てきたのに、三四郎は全く話を聞いていない、というより、この日の三四郎は、いつもと違って諦めません。粘ります。美禰子と並んで歩きながら、なんとかチャンスを得ようと、頑張って話しかけました。
そしてついに、「あなたに会いにいったんです」「ただ、あなたに会いたいから行ったのです」と言って、彼女の顔を覗き込みました。これが、度胸の無い三四郎が、なけなしの勇気をふり絞って、やっと口にした、精一杯の恋の告白です。この程度のさりげない言葉を口にするのが、彼にとっての限界でした。しかし、これを受けての彼女の反応は、三四郎の顔を見ることもせずに、微かな溜息をつきました。この時点で、美禰子の縁談は、もうほとんど決まりかけているのですから、いまさら三四郎が何を言っても遅いのです。
注目して頂きたいのが、この直後です。三四郎のやっとの思いの告白を溜息一つで受け流した美禰子が、気まずい空気を破って、話し掛けてきます。流れとしては、少し唐突で不自然な感じがします。
「原口さんの絵を御覧になって、どうお思いなすって」
答え方がいろいろあるので、三四郎は返事をせずに少しのあいだ歩いた。
「あんまりでき方が早いのでお驚きなさりゃしなくって」
「ええ」と言ったが、じつははじめて気がついた。考えると、原口が広田先生の所へ来て、美禰子の肖像をかく意志をもらしてから、まだ一か月ぐらいにしかならない。展覧会で直接に美禰子に依頼していたのは、それよりのちのことである。三四郎は絵の道に暗いから、あんな大きな額が、どのくらいな速度で仕上げられるものか、ほとんど想像の外にあったが、美禰子から注意されてみると、あまり早くできすぎているように思われる。
「いつから取りかかったんです」
「本当に取りかかったのは、ついこのあいだですけれども、そのまえから少しずつ描いていただいていたんです」
「そのまえって、いつごろからですか」
「あの服装でわかるでしょう」
三四郎は突然として、はじめて池の周囲で美禰子に会った暑い昔を思い出した。
「そら、あなた、椎の木の下にしゃがんでいらしったじゃありませんか」
「あなたは団扇をかざして、高い所に立っていた」
「あの絵のとおりでしょう」
「ええ。あのとおりです」
二人は顔を見合わした。もう少しで白山の坂の上へ出る。
向こうから車がかけて来た。黒い帽子をかぶって、金縁の眼鏡を掛けて、遠くから見ても色光沢のいい男が乗っている。この車が三四郎の目にはいった時から、車の上の若い紳士は美禰子の方を見つめているらしく思われた。二、三間先へ来ると、車を急にとめた。前掛けを器用にはねのけて、蹴込みから飛び降りたところを見ると、背のすらりと高い細面のりっぱな人であった。髪をきれいにすっている。それでいて、まったく男らしい。
今、引用して読み上げた部分、美禰子が三四郎に、急に絵の話をし始めるのは、すこし不自然なのですが、ここで作者は、美禰子の口を借りて、読者に重要なヒントを示しています。作者は、「森の女」と名付けられた絵が出来上がる期間の、始まりと終わり、始点と終点を、しっかりと読者に認識させたいのです。なぜならば、それが美禰子の婚活と同時進行していたからです。
完成間近に見える「森の女」いつから取り掛かったのか?美禰子は、あのナリ、服装でわかるでしょう?と言っています。絵の中の美禰子が夏物の着物を着ているから夏なんだ、で済ませそうになりますが、それでは不十分です。ここをよく考えてください。しかし、この場面だけでは、伝わりにくいので、作者は似たような状況をもう一度描いて、補足説明をしました。それが次の11章です。
11章、三四郎が広田先生の家に遊びに行くと、先生は、お昼寝をしていました。目を覚ました先生は、昼寝中に見ていた夢の話を、三四郎に話してくれました。先生は、もう40才くらいですが、20年も前の昔、一目見かけただけの13歳くらいの綺麗な少女が、突然先生の夢に現れたのです。この広田先生の夢のエピソードは、『草枕』とも関係しています。
夢の中の少女は、20年前とまったく同じナリ、服装で現れて、こんな意味不明なセリフを言います。「この顔の年、この服装の月、この髪の日がいちばん好きだから」分かりますか?「年、月、日」です。「年月日」というピンポイントの単位で、女の身なりが同一である。その身なりが一番好きだから、そうしている。これが作者からの補足説明です。
絵の中の美禰子のナリ 服装も、夏服を着ているから夏、という季節単位ではなくて、三四郎と美禰子が初めて出会ったあの夏の日と、ぴったり同じ。着物、帯、草履という細かな部分至るまで、まるっきりと同じなのです。どうして同じなのか?理由はひとつしかありません。原口からモデルの依頼を受けた美禰子自身が、あの夏の日の服装そっくりそのままに描いてもらうことを提案したから。なぜならば、あの夏の日は、美禰子にとって忘れられない特別な日だったから。
彼女の婚活スタート地点は、美禰子と三四郎が初めて出会った日であり、その終点、婚活の結果が今、向こうから人力車に乗ってやってきます。もうすぐたどり着く白山の坂の上が、美禰子の婚活のゴール地点です。しかし残念ながら、彼女の本意ではない結果だから、美禰子の顔色は、優れませんでした。
この、二人が一緒に白山の坂の上に向かって歩くシーン、なんでもないように見えて、小説全体を表す象徴的なシーンであることを意識してください。ドラマの始点と終点を読者にしっかりと認識させたい、そして結婚という運命に向かって坂を上る美禰子、その美禰子を三四郎は見つめてくれた 寄り添ってくれたのだ ということを表現したシーンです。では、二人が初めて出会ったあの夏の日、彼女は何をしたのか?ドラマの始まり、始点に戻りましょう。
美禰子はあの日 何をしたのか?
新学期が始まる前、夏休み中の三四郎は、故郷の母からの指示で、理科大学の野々宮宗八を午後4時頃、訪ねました。野々宮への挨拶を済ませ実験室を出ても、まだ明るい夏の夕暮れで、池の周りを散歩していると、丘の上に白い服を着た女と一緒に立っている、里見美禰子を見かけました。彼女の親戚が近くの病院に入院していて、そこへお見舞いの後、看護婦と一緒に池の周りで涼んでいたのだ、と6章で美禰子自身が説明しています。しかし、入院中の親戚のお見舞い、というのは、もっと大事な用事の序に過ぎませんでした。彼女はあの日、病院へ行く前に、まず野々宮宗八の実験室を訊ねていたはずです。彼に手紙を手渡しに行ったのです。
あの日、野々宮宗八のポケットに入っていた、封筒の表書きの字を三四郎が見ていました。彼は、それが美禰子の字である、という事に後日気付きました。三四郎も美禰子から2度手紙をもらいましたが、2通ともハガキでした。野々宮がもらったのは「ハガキ」じゃなくて、「封書」ですから、単なる季節の挨拶ではないでしょう。この手紙がどんな内容だったのか?というのは、本文にいっさい書かれていません。美禰子が野々宮に宛てた手紙の中身、この小説における最大の謎です。けれども 何度も述べましたとおり、この小説の逆さま世界である『草枕』をヒントにすれば、推理ができます。
『草枕』の登場人物の中に、見た目が渋くてカッコイイ、女にもてる泰安さんというお坊さん、禅寺の僧侶が、ヒロイン志保田那美に恋文を出すというエピソードがあります。けれど、彼の恋文は、お坊さんのくせに不真面で、不埒な内容だったらしく、手紙を読んだ志保田那美から、ふざけるな!と喝を入れられてしまうというエピソードです。
そうすると『三四郎』においては、このエピソードの逆さま、ヒロイン美禰子のほうから恋文を出す、それも泰安の手紙とは、正反対に 真面目で真剣に結婚を願う手紙であったということが、考えられます。『草枕』の文脈と照らし合わせると、美禰子の手紙の内容が「好きです」とか「お付き合いしてください」ではなくて、ストレートに「私と結婚してください」であることが推測できます。
美禰子の婚活の最初にして最重要の活動は、まず本命の野々宮に結婚を申し込む手紙を渡すこと。重要な手紙ですから、郵便で出さずに、直接手渡すために野々宮の実験室を訪ねた。当然、きちんと美しく装いました。美禰子は、いつも低い下駄を履いているという記述があるのですが、この日は、下駄ではなく、草履を履いています。下駄より草履のほうがかしこまったフォーマルな履物だからです。
彼女は、野々宮に無事手紙を渡した後、序に近くの病院に入院している親戚のお見舞いに行った。そして看護婦と一緒に池の周りを散歩していました。丘の上に立ち、夕日に向かって、眩しそうに団扇を額の所にかざしたポーズ。まさに、絵に描かれたポーズをとっている美禰子を三四郎が発見し、見惚れていました。これが三四郎が初めて美禰子を見た瞬間です。本文を読みます。
女はこの夕日に向いて立っていた。三四郎のしゃがんでいる低い陰から見ると丘の上はたいへん明るい。女の一人はまぼしいとみえて、団扇を額のところにかざしている。顔はよくわからない。けれども着物の色、帯の色はあざやかにわかった。白い足袋の色も目についた。鼻緒の色はとにかく草履をはいていることもわかった。
さて、この瞬間、団扇をかざして夕日を見ている美禰子は、どんな気持ちでしょう。意中の男性に、勇気を出して、結婚を申し込む手紙を手渡した直後です。決戦を終えて、まだ胸の高鳴りが収まらない、高揚した気分、きっとうまくいくはずという期待と、断られたらどうしようという不安。そういう矛盾した気持ちではないでしょうか。そうして、美禰子自身が、今こそ自分が最高に美しく輝いている瞬間なのだと、感じた。だから、後日原口から絵のモデルを頼まれたとき、この日の服装とポーズ、そっくりそのまま描いてもらうように提案した、という推理ができます。
「森の女」を描いたのは、原口ですが、衣装やポーズを決めたのは、美禰子です。彼女は、婚活の初日にして、クライマックスの瞬間を絵にしてもらった。あの瞬間の美禰子の美しさ、高揚した気持ちが、この絵に結晶しているのです。
美禰子の婚活 物的証拠
まだ続きがあります。丘の上に立って夕日に向かっていた美禰子。この後、一緒に散歩していた看護婦さんと二人で、坂を下り石橋を渡って、三四郎のいるほうに歩いてきました。三四郎は、椎の木の下にしゃがみこんで、美禰子に見とれていました。歩いてきた美禰子は、彼の目の前、あと2メートルのところで、急に立ち止まって、「これは何でしょう」と看護婦に訊ねて椎の木を見上げました。この時の美禰子。なんとも、わざとらしい仕草です。さらに、三四郎の前を通るときには、手に持っていた白い花を落としていくという、非常に思わせぶりな素振りでした。白い花を落とすという行為、これはもちろん三四郎が自分に見惚れている事に気付いたので、さらにしっかりと念入りに、自分を印象付けるために、計算してやっている事です。とりあえず、間に合わせとして白い花を落としましたが、この白い花というのは、名刺の代わりである、と考えられます。
三四郎が美禰子から名刺をもらう事ができたのは、三度目の再会を果たした時でした。広田先生の引越しの日、与次郎から教えられた場所で待っていると、美禰子が手伝いにやってきました。そこでようやく、彼女から名前と住所だけが記された、名刺をもらうことが出来たのです。
仕事をしているわけでもない美禰子が、わざわざ名刺を作って持っている。この名刺こそ、彼女が婚活を意識的に行っていた証拠品です。婚活に励むことを決意した美禰子は、第一に、本命の野々宮に手紙を書き、その上で 他にも夫として尊敬できそうな男性はいないかしら、と結婚相手を物色していたのです。広田先生の引越しの日、与次郎から、もう一人 東京帝国大学生が手伝いに来るよと聞いていたから、名刺を持参したのでしょう。与次郎からライスカレーを奢られたのは、三四郎ひとりではなかったように、美禰子から名刺をもらった男性も、三四郎ひとりでは、ないでしょう。
三四郎は、最初に美禰子の目を見た瞬間、「あなたは度胸の無い方ですね」言われたような感じを受けました。まったくその通りであって、彼よりも美禰子のほうが、ずっと度胸があって大胆です。周囲がきめる縁談結婚をするのが普通の時代にあって、自分自身で結婚相手を見つけたい、と決意して、具体的に行動した。その美禰子の強い意志と勇気を称えた言葉が、与次郎のコメント「すてきに大きなもの描いたな」です。与次郎の担当は、四つの理想「真・善・美・壮」のうちの「壮」の理想です。自分の意志をしっかり持って、成し遂げるために行動する勇気があるか?という点で、美禰子を、大きい 大した女だよと褒めています。
思い切って、野々宮に自分からプロポーズした美禰子でしたが、縁談結婚をしたということは、彼女は野々宮から降られた、ということです。次回は、美禰子を振った野々宮宗八。何故、野々宮は、美禰子と結婚しなかったのか?彼が、美禰子をどう見ていたのか、考えてみましょう。
野々宮宗八「色の出し方が中々洒落ていますね」
こんばんは 猫じゃらし文芸部です。今夜は、夏目漱石『三四郎』4回目です。この動画はシリーズになっていますので、ぜひ1回目から順番にご視聴ください。「里見美禰子と4人の男」二人目は、美禰子を振った野々宮さんです。
野々宮の人物設定
野々宮宗八 年齢は30歳 背が高く瘦せている 物理学の研究者です。年の離れた妹 よし子と一緒に暮らしています。里見美禰子との関係は、美禰子の兄 里見恭助が、野々宮と同級生 友人です。小川三四郎との関係は、三四郎の母の知り合いのいとこ というかなり遠い関係ですが、お母さんは独りぼっちで上京する息子が、東京で困った時に頼る相談相手として、ついでに息子が真面目にやっているかどうか監視してもらうお目付け役として、人づてに手をまわして頼んでおきました。それで三四郎は、上京して一番に、野々宮宗八の実験室に挨拶に行くように、とお母さんから指示されました。
野々宮は、ほとんど毎日大学の地下の実験室に、こもっています。彼が研究しているのは、放射圧と呼ばれるもので、太陽のように自ら光る星 恒星が放つ光の圧力、これは現在でも研究が進んでいて、太陽の光を風のように受けて宇宙を航行する宇宙ヨットとかソーラーセイル と呼ばれる形になっているようです。そういう難しい研究をしている科学者としては、とても有望らしいのですが、とにかくお給料が少ない。いつも着古した汚い背広を着ています。彼は、その汚い背広のポケットに、なんでも入れておく癖があるようです。
野々宮と美禰子
2章で、美禰子の手紙が、上着のポケットから覗いているのを、三四郎に見られた野々宮ですが、最後の13章で、彼のポケットから出てきたのは、美禰子の結婚披露の招待状でした。
美禰子の恋文が、数ヵ月後に、結婚披露宴の招待状に化けてしまいました。半年前に、プロポーズの手紙をよこした女の披露宴に、素知らぬ顔で出席してくれたのでしょうが、ほんの少しくらいは 面白くない気持ちがあったと思います。彼は、美禰子から手紙を受け取った日、とても機嫌がよくて嬉しそうでした。大学の建物を眺めて「いい景色でしょう。ね、いいでしょう?君、気が付いてますか?」と三四郎に熱心に、大学の建築の美しさを語っていました。野々宮は、三四郎と違って、物事を美的に鑑賞するセンスがある、というのが描かれています。
美禰子から手紙を受け取った直後、野々宮は、彼女へのプレゼントとして、蝉の羽の様なリボンを買いました。夏真っ盛りの時期でしたから、蝉の羽のようなシースルーの、涼し気なリボンを選ぶ。というも悪くないセンスでしょう。美禰子が、この蝉の羽リボンを髪に結んでいるところを三四郎が見つけたのは、3章です、
もう9月に入った秋の頃だったので、ファッションに疎い三四郎でさえも、不思議に思って与次郎に「君、今頃でも薄いリボンをかけるものかな。あれは酷暑に限るんじゃないか」と聞きました。季節外れなのにもかかわらず、美禰子が蝉の羽リボンを着けた理由は明らかです。それは、彼女が入院中のよし子をお見舞いに行った日でしたから、もしかするとよし子の兄である野々宮に、ばったり会えるかもしれないと思って、わざわざリボンを着けたのです。しかし残念なことに、病院に居たのは、野々宮からお使いを頼まれた三四郎でした。
美禰子がリボンを受けとったところまでは確かなのですが、彼女のプロポーズに、野々宮がどう返事をしたのか 本文には書かれていません。その後の二人のやりとりを推理してみましょう。
4章 広田先生の引っ越しの日、三四郎と与次郎と美禰子と広田先生、四人が先生の新居で荷物の片づけをしているところへ、野々宮がふらりと挨拶に来ました。そこで、野々宮の妹よし子が菊人形展に行きたがっている、みんなで一緒に行こう と言う話がまとまります。ほんのちょっと談笑をしただけで、野々宮がすぐに腰を上げると、広田先生が一言「この間のものは、もう少し待ってくれたまえ」と言います。これは、いったい何の話なのか?
8章で与次郎が説明してくれているのですが、広田先生は、今回の引っ越しではなく去年の引っ越しの際に、敷金が払えなくて、かつて自分の生徒だった野々宮から20円を借りていて、その金をまだ返していないのです。高等学校の教師の広田先生ですら、引っ越しのお金が足りないほどに、この頃東京の家賃はどんどん高騰していました。もちろん野々宮だっていつも金欠なのですが、妹のよし子がバイオリンを買うための費用として、実家から送ってもらった20円が手元にあったので、それを広田先生に貸してしまいました。そのせいで、よし子はいつまでもバイオリンを買ってもらえずにいる状態です。よし子のバイオリン代に始まるお金の流れは、登場人物たちの動きに影響を与える物語の縦糸です。流れを書き出したものを画面にまとめました。
話を戻します。広田先生から、20円の返済は もう少し待ってくれと言われた野々宮は「ええ、ようござんす」と返事をして庭から出ていきました。すると美禰子が思い出したように、「そうそう」と言いながら庭先に脱いであった下駄を履いて、野々宮の後を追いかけます。美禰子は、野々宮と二人だけで話したいことがあるから、彼を追いかけるのでしょう。彼女がプロポーズの手紙を手渡した日から一か月以上経っていますから、早く返事を聞きたいはずです。ここで、野々宮がなんと答えたか?三四郎には、聞こえなかったので、本文には書いてありません。でも、アナロジーで推理できるように書かれています。アナロジー、日本語でいうと類推です。ある事柄を考えるのに、他の似たような事、類似した事柄をヒントに、推しはかることです。ここでは、直前に、野々宮が広田先生から言われたセリフと同じ「この間の返事は、もう少し待ってくれたまえ」美禰子も「ええ、ようござんす」と答えるしかなかったでしょう。
でも彼女の婚活には、兄が縁談を決めてしまう前に、というタイムリミットがあるから焦っている、本当は早くはっきり返事をして欲しいのです。それなのに、野々宮は返事を引き延ばしました。
野々宮は、なぜ美禰子への返事を延期しているのでしょうか?野々宮の内情は、悪化していく彼の住宅環境でもって描かれています。みんなで賑やかに行われた広田先生の引っ越しの裏で、野々宮は半年間の間に、二度も引っ越しをしています。年の離れた妹よし子と一緒に、おそらく文京区あたりに住んでいたようですが、新学期始まってすぐの頃、大久保に引越しました。大学から遠くなってしまうのですが、家賃が安いからです。体の弱い妹よし子が入院をして、その費用がかかったせいで、経済的に苦しいのだろうと、三四郎が推察しています。しかし、せっかく引越したのに、退院して来たよし子が苦情を言います。兄の帰宅はいつも深夜になるのに、大久保は寂しくて不安だと言うのです。妹のよし子は、兄に対する要求が非常に多いのですが、野々宮はいつも何とかしてよし子の希望を叶えてくれます。お金が無いので仕方なく、よし子を美禰子の家に預け、自分は藁ぶきの汚い家に下宿生活をする事になりました。
美禰子は、そんな状態の彼を、「下宿が汚なければ汚ない程尊敬しなくってはならない」と言って、尊敬しきっていました。野々宮の月給が安いこと、美禰子は十分に承知している。 貧しい学者の妻になる覚悟を決めていたと思います。彼女は、ある程度の資産がある家のお嬢さんとして気ままな暮らしをおくっていますが、お高くとまった女でもなければ、恋愛結婚に憧れているだけの、ぼんやりとした娘でもない、なかなかしっかりしています。
広田先生の引越しの時も、ただ座ってぼーっと待っている三四郎にてきぱきと指示をして掃除を始めたり、与次郎からリクエストされた通りに 大きなバスケットにサンドイッチを詰めて持ってきてくれるような気さくところもある。でもこれ、本当は与次郎の為ではなく、新しく名刺を渡せるような男性へのアピールの為のお弁当だったのでしょう。どっちにしろ 行動力があるのです。
三四郎も、彼女はいつも派手で奇麗な着物を着ているのに、着物が汚れることを全く気にせずに、平気で汚い縁側や草の上に腰をおろすことに、驚いていました。
その美禰子が、苦しい経済事情を汲んだうえで、結婚を申し込んでいるのに、野々宮は、その経済事情を理由に、結婚できるかどうか慎重に見極めたい と答えを延期した。そう推理できる場面が、あります。さっきと同じ、アナロジーを使った推理です。
5章 みんなで菊人形展に行った日です。なぜか飛行機実験の話している美禰子と野々宮の会話を三四郎が盗み聞きしていました。
「死んでも、そのほうがいいと思います」と無謀でも飛んでみようという美禰子に対して、
「・・・高く飛ぼうというには、飛べるだけの装置を考えたうえでなければできないにきまっている。頭のほうがさきに要いるに違いないじゃありませんか」と飛ぶ前に、物理的な計算をしなければいけない。冷静な態度の野々宮は、暗に結婚も、経済的に成り立つかどうか慎重に計算してみなければならないと、言いたい訳です。「たとえ死んでも飛んでみたい」なんていうロマンチックなことを言う美禰子は、野々宮との結婚に決死の覚悟を見せているわけですけれども、野々宮は「女には詩人が多いですね」と笑いました。
野々宮からはっきりした返事がもらえない状態が何か月も続き、イライラする美禰子のストレスが爆発するのが、8章です。8章で彼女は、八つ当たりをします。美禰子八つ当たり、の8章です。被害者は、三四郎でした。その詳しい様子は次回説明しますが、今回は、そのストレス原因である、野々宮も、美禰子から詰められてしまう場面を見ておきましょう。
美禰子と三四郎が二人きりで、展覧会デートをしているところ。その会場でばったり野々宮に会ってしまいました。美禰子を連れた三四郎に、野々宮は「妙な連と来ましたね」と言いました。このセリフ、絶妙に野々宮の気持ちを表現していると思います。彼は、美禰子は自分に気がある、という事を充分に知っているから、三四郎が彼女を連れてデートしているのは、なんだか妙、変なんだけれども。野々宮としては、彼女と結婚する意志を表明していないのだから、それに抗議することは出来ない。そんな感じがよく表れています。
その瞬間を美禰子は見逃しませんでした。三四郎が何か答えようとする前に「似合うでしょう」と言いました。(私たち、お似合いでしょ。いっそのこと、私、小川さんと付き合っちゃおうかしら)と言わんばかりの煽り方をするわけです。そう当てつけられた、野々宮の反応が面白いです。彼は一言も云わずに、急いでくるりと後ろを向いてしまいます。この瞬間、彼は何を思ったでしょう。たぶん(おっと藪蛇、また早く返事をしろと、せかされるところだ!)と焦ったに違いありません。彼は美禰子の手紙に、まだきちんとした返事をしていない。あれから、3か月くらいたってしまいました。
次9章です。9章で与次郎と美禰子の活動は終了します。美禰子の婚活は、スタートダッシュ型、2章の初日に一番気合が入っていました。対する与次郎は、ラストスパート型。最終日が一番華やかで、上野のレストラン精養軒で、博士や有力者たちを集めて会合を開きました。
美禰子の婚活、最後の活動は、さりげなくそっとよし子に言付けを頼みました。野々宮の妹よし子は、この時美禰子の家に預けられていましたが、兄から話があると下宿先の先汚い藁ぶきの家に、呼びつけられました。そのよし子に頼んだ言付けは「文芸協会の演芸会に連れて行って頂戴」これが美禰子の野々宮への最後のお誘いでした。
しかし、それを伝えた直後、美禰子の望みを完全に断ち切る決定的な事件が起きます。野々宮が妹を呼びつけたのは、彼女に縁談話が来たからでした。が、よし子はその場で、スパッと縁談を断ってしまいました。兄の宗八が、美禰子のプロポーズに中々返事が出来ないのとは対照的に、妹はその場ですぐに決断できるのです。
この瞬間、美禰子が野々宮と結婚できる可能性は、ゼロになったのです。野々宮が、美禰子と結婚できない一番の原因は、経済的な事情ではなく、年の離れた妹よし子の存在です。よし子の年齢は、はっきりと書かれてないのですが、女学校に通っているとあるので、二十歳にもなっていないと思います。兄は、体の弱い妹を嫁に出すまでは、自分は結婚をせずに、妹を庇護しなければならない、見守ろうと考えているのでしょう。もし、よし子がこの縁談を受けていたら、野々宮は身軽になって、美禰子との結婚を考えることもできたかもしれません。が、よし子は、まだまだお嫁に行きたくないようで、即座に断ってしまいました。よし子が縁談を断った場面に、三四郎も居合わせました。この後の本文にこうあります。
その時三四郎は考えた。この風のなかを、野々宮さんは、妹を送って里見まで連れていってやるだろう。
このあっても無くてもいいような情報が、三四郎の考えとして差し込まれているのは、作者が読者にその続きを想像して欲しいからです。おそらく野々宮は、里見の家に妹を送ったついでに、美禰子と面会した。何か月も待たせていた手紙の返事、結婚は無理です というはっきりしたお断りを、ようやく伝えたと思います。野々宮が返事をしたとすれば、このタイミングしかありません。
そして、よし子が断った縁談の相手は、実は同時に美禰子のところにも縁談を申し込んでいたのでしょう。美禰子は、その翌日に兄と一緒に相手と会う約束になっていた。失恋の痛みの中、美禰子は、正式に縁談を受ける決心をしました。三四郎が近所で起きた火事によって、目を覚ました真夜中に、美禰子は、泣いていたはずです。そんなことも知らずに、三四郎が遅すぎる告白をしたのが、この次の日。前回説明した10章でした。
よし子は、美禰子の結婚が決まった時、なんだか美禰子に勝ち誇ったように、笑っていました。よし子が、兄を取られまいと美禰子を敵視していた訳ではないのですが、実際のところ、美禰子はよし子に完全に負けたようなものです。兄と妹の間に美禰子が入り込む余地は無かったのです。もっとはっきり言ってしまえば、野々宮は、それほど美禰子に心惹かれていたわけではなかった。結婚する気はないけれど、若くてきれいな女性から迫られて、きっぱり断ってしまうのは何となく惜しくて、彼女の気持ちをギリギリまで留め置いてしまった、ちょっと残酷なことをしました。野々宮には、美しい美禰子をただ心地よく眺める程度の気持ちしか無く、彼女の内面にまで興味はありません。だから彼が「森の女」を見た感想は、「色の出し方がなかなか洒落ていますね。むしろ意気な絵だ」
「お洒落で粋な女だ」と彼女の美的センスを褒めています。ここまでは、そんなに難しくありません。ここから、もう少しだけ考えてください。野々宮が言う、色の出し方とは、具体的に美禰子のどの部分を指して、洒落ていると言っているのか?作者は、読者に、ここまで踏み込んで考えることを期待して書いています。結論から先に言うと、これは、森の女としてポーズをとる美禰子の足元 草履の鼻緒の色を指しています。何故 そう言えるのか?
よし子と美禰子
野々宮の周りにいた二人の女、よし子と美禰子。作者は、二人のキャラクターを描き分ける小道具として、草履と下駄を使っています。草履と下駄の違いですが、草履は、底が平らで、改まった場面にも相応しいフォーマルな履物。下駄は、底に歯が付いていて、足場の悪い道でも歩けるカジュアルなものです。
よし子は、エレガントな草履派です。美禰子は、歩きやすい下駄派です。これは、意外に感じる方もおられるのではないでしょうか?美禰子の立ち振る舞いは、優雅で落ち着いていますが、外見は、健康的な印象の女性です。お化粧もその頃出始めた自然な肌色で、三四郎は美禰子の肌をきつね色と表現しています。病弱なよし子は青白い顔をしていて、与次郎に、らっきょうみたいな美人と言われてしまいます。
よし子は草履派 いつも草履を履くのだ、とよし子自身が主張する場面があります。
5章です。三四郎、野々宮、広田先生、美禰子、よし子の5人で一緒に菊人形展に行くために、広田先生の家で待ち合わせをしています。
縁側には主人が洋服を着て腰をかけて、相変らず哲学を吹いている。これは西洋の雑誌を手にしていた。そばによし子がいる。両手を後へ突いて、からだを空に持たせながら、伸ばした足にはいた厚い草履をながめていた。――三四郎はみんなから待ち受けられていたとみえる。主人は雑誌をなげ出した。
「では行くかな。とうとう引っぱり出された」
「御苦労さま」と野々宮さんが言った。女は二人で顔を見合わせて、ひとに知れないような笑をもらした。庭を出る時、女が二人つづいた。
「背が高いのね」と美禰子が後から言った。
「のっぽ」とよし子が一言答えた。門の側《わき》で並んだ時、「だから、なりたけ草履をはくの」と弁解をした。
のっぽ だから、なるべく草履を履くのだ と言うよし子のヘンテコな弁解。よし子は背高のっぽなのを気にして草履を履いている、という風にも聞こえますよね。でも、これは、そういう意味ではありません。前半部分を見てください。よし子が履いているのは、底が厚い草履 厚底草履です。
広田先生が難しい哲学の話をしている横で、縁側に座ったよし子が、足を伸ばした子供の様な仕草で、自分のはいた底の厚い草履を眺めているのは、どうしてでしょうか?それが、お気に入りの草履だから、お気に入りの草履を履いて、みんなとお出かけするのが嬉しいからでしょう。よし子は、菊人形展に行けるのを、とても楽しみにしていた。菊人形展は大人気のイベントで、人込みの中、団子坂の坂道をたくさん歩きますから、美禰子のように下駄を履くほうが、楽なのですが、どうしてもお気に入りの厚底草履でお洒落をしたかったのでしょう。
厚底草履は、草履のうちでもフォーマルなおめかし用の履物であり、背の高い女性に、よく似合うとされています。ハイヒールも背の高い女性のほうが似合うのと同じで、バランスの問題です。今日のよし子ちゃんは、背が高い自分をよりいっそうスラリと美しく見せる、底の厚い草履を履いて、ますます背が高くなっている。それで美禰子が「背が高いのね」と驚いています。よし子は、張り切っておめかししているのが、ちょっと気恥しい。それで、私ってのっぽだから、草履のほうが似合うでしょ?だからなるべく、草履を履くようにしているの。別に特別にお洒落をしたわけじゃないの。いつも草履を履いているんだから、という意味のしなくてもよい、変な弁解をしているのです。
よし子は、ちょっとわがままですが、口の利き方が面白い子です。三四郎が、よし子と一緒にいると「無邪気なる女王の前に出た心持がした」とあるように、彼女は、三四郎に対してもなぜか、ツンとした命令口調なのですが、それが少しも不愉快な感じを与えないのは、彼女は体が大きいだけでまだまだ幼い、生意気な口の利く可愛い子供にしか見えない、ということです。体が弱くて可哀そうなよし子ですが、きっと家族みんなに守られ、愛されて育ったのでしょう。病弱だからと言って、卑屈なところが少しもありません。わざとらしい遠慮や、謙遜なんてしない、のびのびとしたよし子の性格を表したセリフだと思います。歩きにくい厚底草履、というのは、背ばかり高くて精一杯大人ぶっているけれど、まだ周囲に甘えなければ生きていけないよし子を表現するのに ぴったりのアイテムです。
美禰子のほうは、どうでしょうか。美禰子のお洒落が、どういう感じなのか?彼女の服装、着物の柄や帯の色使い、というのを三四郎が、関心を持って観察しているのですが、三四郎は、着物の知識も無く、色の組み合わせの妙を表現するセンスが全く無いので、彼女がどんな趣味をしているのか、いまいちよくわかりません。美禰子の服装において、ファッションを見る目が無い三四郎にでもはっきりと言えたことは、一点だけ。彼女はいつも低い下駄を履いている ということです。美禰子が草履を履いていたのは、たった一度だけ、三四郎が初めて美禰子を見つけた日だけです。だから絵の中の美禰子は、草履を履いていますが、普段の彼女は、低い下駄を履いている。足場の悪い田舎道でもしっかりと歩ける、下駄の女です。そして、美禰子の下駄は、鈍い三四郎でさえ、認識できるような他とは違う特徴がある と10章に書いてあります。
彼女の下駄は、鼻緒の二本が、右と左で色が違うのです。これは水引鼻緒といって、足の親指側と人差し指側で違う色が見えるように組み合わせた、あまりみかけない、めずらしい鼻緒です。参考として画面にイラストを表示します。
ここで解ることは、美禰子は、下駄の鼻緒までこだわって選ぶ、お洒落さんであること。それを踏まえて、もう一度 2章 三四郎が美禰子を初めて見た瞬間、「森の女」のポーズをとった瞬間の文章を見てください。
「鼻緒の色はとにかく草履をはいていることもわかった。」とありますね。三四郎には、認識できなかった、草履の鼻緒の色。お洒落な美禰子の特別な日の草履ですから。鼻緒の色まで、美しいものだったはずです。その色を見て、洒落ている、粋だな と気付くことが出来たのが、野々宮宗八。彼の担当は、「美」の理想であり、美禰子の美的センスを評価しました。
定型詩的に出来ている
さて、里見美禰子と四人の男。半分、終わったところです。ここまで聞いていただいて、おそらく、こんなに細かい所まで普通は読まない、解る訳がない と思われるかもしれません。でも作者は、この結構な長さの小説、それも新聞連載小説として書いておきながら、読者には、これを何度も何度も読んで欲しい という思いで書いています。その思いを、またこんな風に分かりにくく、カモフラージュして表現しています。
6章で 与次郎が広田先生へのお土産として、馬鹿貝の剥身の干物をつけ焼にしたものを買ってきて、先生に食べさせています。馬鹿貝というのは、お寿司のネタとしては、普通あおやぎと呼ばれる貝ですが、ここは、あえて馬鹿貝という言葉を使いたいのでしょう。貝の干物ですから、とにかく固い。与次郎は、広田先生はこれを食べたことが無いから、と先生に食べさせます。当然、先生が「固いね」と言うと与次郎は「堅いけれどもうまいでしょう。よくかまなくっちゃいけません。かむと味が出る」と言います。広田先生は、「味が出るまで噛むなんて、歯が疲れてしまう。なんでこんな古風なものを買ってきたんだ」と言いました。
ここもアナロジーを使って読めば、この小説を何度も何度も、味が出るまで読んで欲しい。という作者の願いです。だけど広田先生は、そういう古典的な文芸を、好むタイプではありません。
先生は、自分のことを「それ程ロマンチックな人間じゃない。僕は君より遥かに散文的に出来ている」と三四郎に言いました。「散文的に出来ている」という表現ですが、散文と対になるのは定型詩、つまり和歌、俳句、漢詩、西洋だったら韻を踏むような詩のことです。要するに、僕は詩的な人間じゃない、ロマンチックな人間じゃない と言っています。
それを言うならば、夏目漱石は絶対に「定型詩的に出来ている」。漱石は、俳句とか漢詩をつくるのが大好きです。だから、小説を書くにあたっても、定型詩をつくるのとおなじくらい修辞 レトリックを駆使しています。まるで詩のように、ロマンチックに仕上がっている。まるで詩のように、何度も何度も読むほどに、味わい深い小説です。
次回は、詩的なものとか美的なものには、あまり関心がない。冷めた目を持つ皮肉な評論家、広田先生です。美禰子のことも、冷ややかに観察していて、彼女のちょっと感じの悪いところに目を付けて、鋭く批評している、広田先生の辛口美禰子批判です。
広田萇「少し気が利き過ぎている位だ」
こんばんは 猫じゃらし文芸部です。今夜は、夏目漱石『三四郎』5回目です。この動画はシリーズになっていますので、ぜひ1回目から順番にご視聴ください。
広田の言葉は予言的
里見美禰子と四人の男、三人目 広田萇です。広田先生と言えば、第一章 三四郎と初めて出会った汽車の中、あのインパクトあるセリフが印象に残っている読者が多いと思います。三四郎が「然しこれからは日本も発展するでしょう」というのに対して、「亡びるね」と予言しました。西洋列強に追いつくために、全速力で西洋化に取り組んでいた日本。こんなに猛スピードで社会を変化させていては、破滅してしまうのではないかという心配は、次回作の『それから』においても、述べられています。
広田先生の言葉というのは、まるで予言者とか占い師のように、その場にいない登場人物の心の中、時には、先生自身についても鋭く言い当てているので、その言葉の意味をよく考えながら、読む必要があります。
先生が「森の女」を見た感想は、「少し気が利き過ぎている位だ。これじゃ、鼓の音ねのように、ぽんぽんする絵はかけないと、自白するはずだ」
広田先生の担当は、もちろん「真」の理想です。表面的な見た目に惑わされず、情も切り捨て、知性のメスでもって冷徹に真実を暴く「真」の理想です。
「気が利いている」だったら褒めているのですが。「気が利き過ぎている」と言っています。「鼓の音のようにぽんぽんする絵」というのが、分かりにくいですが、これは以前に、広田先生と画家の原口の間で、鼓の音が話題になったからです。鼓というのは、小さな太鼓で、能楽の間に掛け声と一緒にぽんぽんと打つ楽器ですね。鼓の音というのは、古風で間が抜けていて、いいね、癒されるね という話をしていました。つまり、広田先生は、美禰子は気が利き過ぎていて、古風なところ ゆったりとした所が全く無い 油断も隙も無い女、食えない女だよ と言っているのです。これが美禰子のどういう部分を指しているのかを、見ていきます。
広田の【偽善と露悪理論】
皮肉な評論家 広田先生が、その巧みな論を振るうのは、7章です。7章で三四郎を相手に語る「偽善と露悪理論」、ここで登場人物たちの振る舞いを解説、評論しています。
「御母さんの云う事はなるべく聞いて上げるがよい。近ごろの青年は我々時代の青年と違って自我の意識が強すぎていけない。我々の書生をしているころには、する事なす事一として他を離れたことはなかった。すべてが、君とか、親とか、国とか、社会とか、みんな他本位であった。それを一口にいうと教育を受けるものがことごとく偽善家であった。その偽善が社会の変化で、とうとう張り通せなくなった結果、漸々自己本位を思想行為の上に輸入すると、今度は我意識が非常に発展しすぎてしまった。昔の偽善家に対して、今は露悪家ばかりの状態にある。――君、露悪家という言葉を聞いたことがありますか」
「いいえ」
「今ぼくが即席に作った言葉だ。君もその露悪家の一人――だかどうだか、まあたぶんそうだろう。与次郎のごときにいたるとその最たるものだ。あの君の知ってる里見という女があるでしょう。あれも一種の露悪家で、それから野々宮の妹ね、あれはまた、あれなりに露悪家だから面白い。昔は殿様と親父だけが露悪家ですんでいたが、今日では各自同等の権利で露悪家になりたがる。もっとも悪い事でもなんでもない。臭いものの蓋をとれば肥桶で、見事な形式をはぐとたいていは露悪になるのは知れ切っている。形式だけ見事だって面倒なばかりだから、みんな節約して木地だけで用を足している。はなはだ痛快である。天醜爛漫としている。ところがこの爛漫が度を越すと、露悪家同志がお互いに不便を感じてくる。その不便がだんだん高じて極端に達した時利他主義がまた復活する。それがまた形式に流れて腐敗するとまた利己主義に帰参する。つまり際限はない。我々はそういうふうにして暮らしてゆくものと思えばさしつかえない。そうして行くうちに進歩する。
善と悪ではありません。偽善と露悪。これは、心ではなくて態度の違いです。人間の心は、基本みんな汚い「悪」であり、その汚いもの臭いものが、野ざらしの丸見えになっているのが、露悪。それでは、まるで肥桶と一緒だから、そこをきちんとした形式で整え、取り繕って「お手洗い」ってことにしてあるのが、偽善です。美しい形式で取り繕った偽善と、正直で丸出しの露悪です。広田先生の若いころ、明治維新から20年後くらいの頃は、君主、親、国家、社会のために生きるべし という利他主義精神、偽善家スタイルが流行していたけれど、それでは、どうも嘘くさいように思われて来たところへ、西洋の自我とか個人主義の思想が少しづづ入ってきた。すると今度は、自我意識が発達しすぎて、みんなが利己的な露悪家ポーズを取るようになってきた。利他主義と利己主義、偽善と露悪。これが交互に流行しながら、社会は進歩している という理論です。
さて 広田先生は、何故、突然三四郎に向かって、こんな理論を話し始めたのでしょうか。先生が「偽善と露悪」理論を持ち出したタイミングに、注意しましょう。それは、三四郎が故郷の母から結婚を勧められている という話を聞いた直後です。先生は、にこにこして「できるだけお母さんのいう事を聞いてあげなさい」なんて言いながら、同時に「偽善と露悪」理論を持ち出しました。
この理論を聞いた三四郎は、我々若者がみんな露悪家なのは分かりますが、先生時代の人が偽善家なのはどういう意味ですか」と質問しました。先生時代の人というのは、40代50代くらいの年齢の人のことで、三四郎のお母さんもあてはまります。彼らが偽善家として、どういう振る舞いを見せるのか?という質問 まさに、先生の狙い通りの質問です。
すると先生は、正月の挨拶を例に挙げます。元旦にあけましておめでとうございます と言われて、実際お目出たい感じがするだろうか?つまり形式を守っているだけの挨拶なんて、別に有難くないように、お役目として親切にしてもらっても有難くはないだろう。教師は、生徒に教えているが、その目的はお給料を得ることにあるのであって、親切で教えている訳ではないよ と言うんです。「偽善家の態度」というのは、形式を守っているだけで、本当の親切ではない場合がある。
広田先生は、とっても遠回しに、ものすごく皮肉が利いたことを言う人です。先生が言いたいのは、三四郎の母がすすめる結婚は、親が子供の結婚の世話をしてあげるという形式的な親切の裏に、親にとって都合が良い結婚をさせる、という魂胆があるのだ。と警告をしてあげているのです。
実際に、三四郎の母がゴリ押ししているお光さんとの結婚は、小川家の財産の面からして、都合が良い訳です。母は三四郎が東京の女性を選ぶことを心配して「東京の者は気心が知れないから私はいやじゃ。」と手紙で念入りに釘をさしてきます。
露悪的な与次郎の可愛い所
こういうお為ごかしがなくてあけすけで正直なのが与次郎だ と先生は評価しています。与次郎は、露悪党のボス と呼べるくらいに露悪的なのですが、可愛らしいところがある というんです。実際は、与次郎だってライスカレーを奢りながら、学生たちを味方につける作戦を実行しているのですから、全部が全部、正直というわけではないのですが、先生がここで言いたいのは、アメリカ人が金銭に対して露骨なのと同じように、お金そのものが目的であることを隠さない点において、正直な与次郎は、かえって嫌みが無くてよい。これは、次の8章で起きること。8章で与次郎が三四郎に金を借りる時の態度を 前もって説明してくれています。
8章 与次郎が三四郎の下宿にやってきて、困ったことになった と訴えます。先生が去年、野々宮さんから借りていた20円を、やっと工面することができて、その大事な20円 野々宮に返すべき20円を与次郎に預けました。与次郎は、それを使い込んでしまった。三四郎が何に使ったのか?と聞くと、馬券を買った、競馬ですってしまった。
20円というのは、三四郎が貰っている仕送りの額、下宿代を含めた一か月の生活費と同じ。お人よしの三四郎は、ちょうど母からの仕送りが届いたところだったので、それを全部、与次郎に貸してしまいました。
この後、月末になって三四郎が下宿代を払わなければならない頃になっても、20円を返せない与次郎は、今度はそれを美禰子に頼んで、肩代わりさせる算段を自分でつけて来ました。三四郎にそのことを報告するのですが。その報告を終えた途端に、与次郎は、例の広田先生を大学教授職につける運動の進捗状況を話し始めます。運動には、とにかく暇と金が要るんだ、広田先生をもっと売り出すために、今度は上野のレストランで会合を開くんだ、等と話すんですね。与次郎は、この広田先生の売り込みに、金と暇を注ぎこんでいるのですから、競馬なんかやっていたとは思えません。じゃあ、なぜ競馬で擦ったなんていう嘘をつくのか?
そこが、広田先生の評価する 与次郎の可愛い所なのです。まったく返す当ての無い借金の言い訳に、先生のために使う金なんだよ という恰好をつけた弁解をしたくない。なんでもいいから金を貸してくれ、とにかく金を貸してくれ というのが正直な気持ちだから、与次郎としては、そこに嘘はないのです。偽善的な格好をつけないどころか、露悪的な言い訳までしてしまうのが与次郎です。
後日、運動が失敗した与次郎は、広田先生に迷惑をかけたことを痛感し、潔く一人で先生に謝りに行きます。けれども、三四郎に20円を返す気には、全くならないし、謝りもしません。小川家の経済的余裕の程度を見越して、これぐらいの迷惑をかけても構わない、と思っているのでしょう。彼のこういう所を許せない人もいると思いますが、与次郎にとっての正邪曲直、何が正しくて、何が間違っているのか?という善悪の基準は、判で押したような形式、借金は返すべき とか 嘘はいけない というような常識的な形式とは、違うところにあるのです。
ここまで、先生の偽善と露悪理論を聞いていた三四郎ですが、彼の頭の中にあるのは、美禰子の事です。すると先生は、まるで三四郎の頭の中を見通したかのように、最後に次のような論を展開します。
露悪的な美禰子の怖い所
その時広田さんは急にうんと言って、何か思い出したようである。「うん、まだある。この二十世紀になってから妙なのが流行る。利他本位の内容を利己本位でみたすというむずかしいやり口なんだが、君そんな人に出会ったですか」
「どんなのです」
「ほかの言葉でいうと、偽善を行うに露悪をもってする。まだわからないだろうな。ちと説明し方が悪いようだ。――昔の偽善家はね、なんでも人によく思われたいが先に立つんでしょう。ところがその反対で、人の感触を害するために、わざわざ偽善をやる。横から見ても縦から見ても、相手には偽善としか思われないようにしむけてゆく。相手はむろんいやな心持ちがする。そこで本人の目的は達せられる。偽善を偽善そのままで先方に通用させようとする正直なところが露悪家の特色で、しかも表面上の行為言語はあくまでも善に違いないから、――そら、二位一体というようなことになる。この方法を巧妙に用いる者が近来だいぶふえてきたようだ。きわめて神経の鋭敏になった文明人種が、もっとも優美に露悪家になろうとすると、これがいちばんいい方法になる。血を出さなければ人が殺せないというのはずいぶん野蛮な話だからな君、だんだん流行らなくなる」
先生は、三四郎、与次郎、美禰子、よし子。みんな、自分勝手に振る舞う露悪家なのだと、定義しましがた、この中に一人、もっと進化を遂げた露悪家が居るから気をつけろと忠告しています。もちろんそれは、美禰子の事を指しています。先生が「森の女」の感想として「気が利き過ぎている」と言いましたが、「気が利き過ぎる」というのは、「きわめて神経の鋭敏な文明人種」であって、血を流さずに人を殺せる優美な露悪家 つまり、ひとを攻撃する時にさえ、エレガントに偽善の形式を使います。
解りやすい具体例としてどういうのがあるか、考えてみました。京都の言葉にある「遠回りしすぎて解りにくい嫌み」なんかも、これと少し似ているのではないでしょうか。言いたい事をストレートに言って、その場の空気を一瞬で凍り付かせるようなことはせずに、後になって、よおく考えれば、じわじわと相手の真意が伝わってきて、怖くなるような遠回りな言い方。京都は東京なんかより、ずーっと昔から都で 都会ですから、京都の人は「きわめて神経の鋭敏になった文明人種」であって、洗練されたコミュニケーションの形式が発達している訳です。
しかし、こういう攻撃は、三四郎のようなぼんやりとした人間、鈍い人が相手だと、ほとんど伝わりません。だから、広田先生は、次の8章で美禰子は、善人ぶった陰険な攻撃を仕掛けてくるから、注意しろと三四郎に、いえ どうせ三四郎は気づきませんから、読者に向かって警告をしているのです。
と、いうことで、美禰子が三四郎をどんなふうに三四郎をいじめるか、8章を詳しく見ていきましょう。そうすれば、広田先生の言っていること、よおく理解できます。
三四郎をいじめる美禰子
与次郎に貸した20円は、とりあえず美禰子が立て替えてくれる、と与次郎から説明された三四郎は、美禰子の家に行って彼女と話をするのだ、ということで、前の晩から、ドキドキするのですが、なぜ美禰子は、与次郎に金を渡さずに、三四郎に直接取りに来させるのか?と考えるのです。
最後にうれしいことを思いついた。美禰子は与次郎に金を貸すと言った。けれども与次郎には渡さないと言った。じっさい与次郎は金銭のうえにおいては、信用しにくい男かもしれない。しかしその意味で美禰子が渡さないのか、どうだか疑わしい。もしその意味でないとすると、自分にははなはだたのもしいことになる。ただ金を貸してくれるだけでも十分の好意である。自分に会って手渡しにしたいというのは――三四郎はここまで己惚れてみたが、たちまち、「やっぱり愚弄じゃないか」と考えだして、急に赤くなった。もし、ある人があって、その女はなんのために君を愚弄するのかと聞いたら、三四郎はおそらく答ええなかったろう。しいて考えてみろと言われたら、三四郎は愚弄そのものに興味をもっている女だからとまでは答えたかもしれない。自分の己惚れを罰するためとはまったく考ええなかったに違いない。――三四郎は美禰子のために己惚れしめられたんだと信じている。
美禰子が与次郎ではなく、三四郎に金を取りに来させるのは、自分に会いたいから かもしれない。もしかしてだけど、彼女は、自分に好意があるんじゃないか?とつい、うぬぼれてしまうのですが、同い年の女の子に頭を下げて金を借りるなんて、やっぱり愚弄じゃないかと考えます。美禰子は、愚弄そのものに興味がある女、つまり人をからかうのが好きな女なのか。それも少しはありますが、彼女は、三四郎の己惚れを罰するために、彼をおびき寄せているのです。ひょっとしてワンチャンスあるかも、と期待している三四郎に(そんなわけないでしょ!)と、現実をバシッと突きつけるために、わざわざ彼に大金を貸してあげるのです。
三四郎が、美禰子の自宅を訪ねると、暖炉がある立派な西洋風の応接間で待たされました。大分待たされた後に現れた美禰子は、外出用の綺麗な着物を着て、にっこりと笑顔で「いらっしゃい」と迎えてくれます。それなのに三四郎は、挨拶もせずにいきなり「佐々木が」と焦って本題を切りだしました。
与次郎が競馬で金をすってしまったのだと、借金のいきさつを説明している途中で、競馬をしたのが、三四郎だと勘違いした美禰子が、「まあ」「悪い方ね」「馬券で当てるのは、人の心をあてるより難しいじゃありませんか。あなたは索引のついている人の心さえあててみようとなさらない呑気な方だのにと」言います。三四郎は、「僕が馬券を買ったんじゃありません」と訂正しました。
ここ さらっと流していますが、かなり意味深な発言をしています。
「あなたは索引のついている人の心さえ、あててみようとなさらない呑気な方」
(人の言動に注目して、よく観察していれば、その人の心は解るはずなのに、あなたはぼんやりしているからそれが解らないのよ)と言う意味ですが、若い女の子から、面と向かってこんなことを言われれば、当然、(私の事をよく見ていれば、私が誰のことを好きなのか、解るでしょ?当ててみなさいよ)という意味になります。この日の美禰子の行動は、三四郎にこれを教えるためですから、ここ、よく覚えておいてください。
しかし、いつも不注意でのん気な三四郎は、いざお金を借りる談になった時に「借りてもいい、しかし借りないでもいい。実家に言えば、一週間くらいで送ってくるから。」と言ってしまいます。実家に頼めば、すぐ送金してもらえるなんてことは、始めから分かっていることで、美禰子に金を借りるというチャンスを利用して、彼女とコミュニケーションをとってみようと、のこのこ家までやってきたくせに、ここでしっかり頭を下げて、困っているので是非貸してください。お願いします の一言が言えないところが、与次郎と比べて下手なのです。
だから美禰子も「御迷惑なら、しいて……」と引っ込んで、いったんは貸さないことにしました。三四郎はすぐに、ああ やっぱり借りておけばよかったと後悔します。
次に美禰子は、「私、ちょっと出て来ようかしら」と今から外出するようなことを言います。三四郎は、これは「帰れ」という意味だろうと思って、「もう帰りましょう」と立ち上がります。すると美禰子は、彼を玄関まで送って、「そこまでごいっしょに出ましょう。いいでしょう」」と言い、三四郎の耳元に唇をよせて「怒っていらっしゃるの」と囁きました。
「怒っていらっしゃるの」という言葉の意味をよく考えてみると、美禰子は三四郎を怒らせるために、わざと簡単に金を貸さない。そして、これからもっと彼を弄ぶつもりがあって、今の時点では、どれくらい怒ってるのかしら と確認しているのです。しかし三四郎の神経は鈍感なので、この程度では怒ったりせずに、外出する彼女に付いて歩きます。あまりにも従順な三四郎に、美禰子は、おかしくなって笑い「一緒にいらっしゃい」とここで美禰子が完全にリードを取りました。
銀行の前まで歩いて来ると、帯の間から銀行通帳と印鑑を取り出して、「お願い」「これでお金をとって頂戴」「30円」と言って、三四郎に通帳と印鑑を渡しました。三四郎が素直に一人で銀行に入って、30円を下ろして戻ってくると、なんと美禰子は彼を待つこともなく、40メートルくらい先に歩いて行ってしまっています。三四郎は、急いで彼女を追いかけました。
どう思いますか?この美禰子のお金の貸し方。通帳と印鑑をポンと渡されて、貸してあげるから自分で下してきなさいよ と言われたのも同然です。まるで親が子供にお金を与えるようなやり方です。しかも与次郎に貸したのは20円なのだから、20円で十分なのに、それが30円に増えている。美禰子にとっては、20円も30円も大して違わない金額であることを見せつけているのです。三四郎が、おろした30円をいったん美禰子に渡そうとすると、「預かって置いて頂戴」という、まるで年上の姐さんみたいな口の利き方で、同い年の三四郎を完全に格下扱いしました。ついさっきまで借りておけば良かった と後悔した三四郎もさすがに、「いささか迷惑の様な気がした。」とここでやっと、少しだけ気分を害します。
美禰子は、困っている人にお金を貸してあげるという偽善的な方法を使って、同い年の男 それも東京帝国大学生を相手に思いっきりマウントを取る、という意地悪、露悪をやりたかったのです。彼女は、あらかじめ、外出用の着物を着て、銀行通帳と印鑑を帯の間に入れて、展覧会のチケットも持って、彼を待ち構えていた。今日の行動計画、準備万端でした。大金を借りるにあたって、どのようにお願いすれば良いかさえ作戦無しの三四郎とは、全然違うのだから、格下扱いされても仕方がないでしょう。
しかしこれで、彼女の気持ちが収まったわけではなく、美禰子はもっともっと三四郎をいじめたい。今度は、原口さんから展覧会の招待券を貰ったから、一緒に行きましょうと、誘います。考えてみれば、この展覧会だって、本当は野々宮と行きたかったはずです。でも期日が迫っているから、仕方なく三四郎を誘ったのでしょう。展覧会場に向かいながら、原口が美禰子の肖像画を描いている という話になると、「ええ、高等モデルなの」とさりげなく、けれども自慢げに言います。もし与次郎ならば、ここで「さすが!美禰子さんは、美人だから」と適当に持ち上げて、少しは気分よくさせてあげることもできるのですが、三四郎はそんなお世辞の一言も言えずにただ黙っているから、美禰子は面白くありません。展覧会に場所を移して、彼女の意地悪は続きます。
二人で一緒に絵画鑑賞をするのですが、三四郎には、絵画を鑑賞するセンスというのがなくて、絵を見ながら彼女が、「これはどうですか?」とか「これは面白いじゃありませんか?」などと話しかけても、気の利いた返事がまったく出来ないでいます。
展覧会場の中で、きょうだいで画家、兄と妹の作品が一か所にまとめて飾ってあるコーナーがありました。そのコーナーの絵を二人でみている時です、三四郎は兄と妹の画風の違いなんて気付かずに、兄妹で苗字が同じなものだから、一人の画家が描いたもの、と勘違いをしていました。けれども美禰子は、なんでもよく気が付く女ですから、兄と妹の違いにしっかり気づいていました。ヴェニスの風景、ヴェニスの水辺とゴンドラを描いた風景画の前で、「ヴェニスでしょう」「兄さんの方が余程旨いようですね」と指摘します。三四郎は何のことだか分かりません。あっちが妹の作品で、こっちは兄の作品ですよ と教えると、え、違うんですか?一人だと思っていました。とぼんやりしています。二人は顔を見合わせて笑い出しました。
まあ、和やかな雰囲気と思ったら、次の瞬間、美禰子は、わざと目を大きく開けて驚いたような表情を見せた上、一段調子を落とした小声で、「随分ね」と言って、一人でさっさと先に歩いて行ってしまいました。三四郎が絵をちゃんと真剣に見ていないから、美禰子は怒った、のではなくて、三四郎を困らせるために、わざと怒ったフリをした。怒ったフリをして、ちょっと離れたところから、振り返ってそっと三四郎の横顔を熟視して、彼の反応を観察しました。
ところが、美禰子が怒ったことにさえ、気づかずにまだヴェニスの絵を見ています。芸術が分からない上に、女性の機嫌を損ねても気付かない、いつもぼんやりしている三四郎。これでは、いじめ甲斐がありません。もっと三四郎をいじめたい美禰子に、絶好のチャンス、彼を決定的に傷つけるチャンスが、その時ちょうど訪れました。
展覧会場に野々宮が現れたのです。前回、説明した場面です、前回は、美禰子と野々宮の気持ちに焦点を当てましたが、今回は美禰子と三四郎の気持ちを読み取りましょう。
野々宮の姿を見つけたとたんに、美禰子は、急いで三四郎のもとに戻ってきて、また耳元で何かを囁く。だけど三四郎には、それが全く聞き取れません。彼女またすぐに野々宮の方に引き返してしまいます。野々宮が三四郎に向かって「妙な連れと来ましたね」と言うと、三四郎が答える間もなく美禰子が、「似合うでしょう」と言いました。
この一連の行動の意味を三四郎は、理解できなかったので、しばらくたって「さっき何を云ったんですか」と尋ねると、美禰子は笑うだけで何も言いません。三四郎が変な顔をすると、
「野々宮さん。ね。ね。」「解ったでしょう」と言います。この直後、「美禰子の意味は、大波の崩れる如く一度に三四郎の胸を浸した」と、本文にあります。美禰子が、三四郎の耳元で何事かをささやいたのは、何か言いたいことがあった訳ではなくて、三四郎の耳元に唇を寄せて、二人がまるで恋人同士であるかのような演技をして、野々宮に見せつけるのが目的だった、というところまでを、たった今、彼は理解した。それで「野々宮さんを愚弄したのですか?」「なんで?」と言ったとたん、突然、次の言葉を言う勇気をなくして、無言のまま、歩きだしました。
三四郎が、聞きたかったのは「なぜ、野々宮さんを愚弄したのですか?」という質問ですけれども、質問しようとした瞬間に、その答えが解ってしまった。
美禰子の「解ったでしょう」という言葉は、(私が野々宮さんを愚弄する。つまり彼の嫉妬心を煽るようなことをするのは、彼の事が好きだからに決まってるでしょ。私が好きなのは、野々宮さんなの。あなたじゃないのよ。解ったでしょ?)という意味でしょう。それがたった今、三四郎の心をグサリと刺しました。彼は、無言ままで歩きだします。
すると美禰子は、三四郎にすがるようについてきて「あなたを愚弄したんじゃないのよ」と言います。三四郎は立ち止まって、美禰子を見下ろし、「それでいいです。」「なぜ悪いの」「だからいいです」「本当に宜いの?」というやり取りが続きます。博物館を出ると外は雨が降っていたので、二人は、大きな杉の木の下で雨宿りをします。杉は針葉樹なので、雨宿りできる範囲が狭いですから、二人の体はだんだん接近していきます。美禰子が「小川さん」「悪くってさっきのこと」とまた声をかけると「いいです」と三四郎が答えます。彼女は「だって」と言いながら近寄ってきて「私、何故だかああしたかったんですもの。野々宮さんに失礼する積りじゃないんですけれども」
女は瞳を定めて、三四郎を見た。三四郎はその瞳のなかに言葉よりも深き訴えを認めた。
――必竟あなたのためにした事じゃありませんかと、二重瞼の奥で訴えている。三四郎は、もう一遍、「だから、いいです」と答えた。
美禰子さん、綺麗に伏線を回収致しました。今日、出かける前に言った彼女が言ったセリフ「あなたは索引のついている人の心さえあててみようとなさらない呑気な方だのにと」=「私が誰のことが好きなのか。当てて御覧なさいよ。」これの答えが「野々宮さん、ね。ね。解ったでしょ。」ですね。そして「畢竟あなたのためにしたことじゃ、ありませんか。」(呑気なあなたにでも、よおく解るように、索引のついている人の心の読み方、わざわざ教えてあげたんだから、感謝なさい)と言う事なのです。大変遠回りな、でも強烈な意地悪です。
どうして美禰子は、三四郎をいじめたのか?それは、「私、何故だかああしたかったんですもの。野々宮さんに失礼する積りじゃないんですけれども」というセリフに隠れているでしょう。いつまでも返事をしてくれない野々宮に、いらいらしている。でもその怒りを彼にはぶつけられないから、三四郎に八つ当たりをした。自分に好意を寄せてくれる男に、つい甘えてしまったのでしょう。
雨の中、二人で体を寄せ合って、無言で雨宿りをしているうちに(今日は、かなり小川君を傷つけたなぁ)と自覚したのか「さっきのお金お使いなさい」「みんなお使いなさい」と言いました。(30円も貸してあげたんだから許してよね)と言っているわけですね。
8章をよく読むと、美禰子は、三四郎のことを完全に小馬鹿にしている。尊敬なんてしていないし、まったく恋愛対象では無いんだな というのがはっきりと解ってしまうのですが、三四郎だって、美禰子から名刺をもらった時点では、彼女の「尊敬できる男 夫候補生」のうちの一人だった。それなのに、いったい、どうしてこうなってしまったのでしょうか?
次回はいよいよ小川三四郎、三四郎が美禰子を失望させた理由、そしてストレイシープと表現された彼女の心理を考えましょう。
小川三四郎 迷羊ストレイシープ、迷羊ストレイシープと繰り返した。
こんばんは。猫じゃらし文芸部です。今夜は、夏目漱石『三四郎』6回目 最終回 里見美禰子と四人の男、最後の一人 小川三四郎です。
あなたはよっぽど度胸のないかたですね
小川三四郎は、主人公というよりも視点中心人物であり、彼の視点と主観を中心に、描かれています。6か月間の物語において 当人は、まったく気づかないうちに、里見美禰子の婚活の要所要所 大事な場面の目撃者になっていました。この小説を再読するときは、ぜひそこを意識しながら、読んでみてください。
小川三四郎はどんな性格なのか、読者がすぐに彼を理解できるように、作者は、第一章に強烈なエピソードを提示しています。九州から汽車で上京する際、乗客は名古屋で一旦下車して一泊しなければならないのですが、その際に、車内で近くに座っていた女性から、今夜宿泊する宿屋を探すのに、一人では不安だから付き添って欲しいと頼まれました。知らない女の人に、こんなことを頼まれて、三四郎は躊躇するのですが、断ることもできずに一緒に宿屋探しをしました。ところが、宿屋に入ったとたんに、二人は夫婦だと間違われて、同じ部屋で一つの布団に眠ることになってしまいます。三四郎は、ドギマギするばかりで、一言も抗議できずに、成り行きにまかせます。女性の方は、三四郎よりもちょっと年上で夫も子供もいる人なのですが、不思議なことに、三四郎と同じ部屋で眠ることを全然気にしていない様子。それどころか、三四郎がお風呂に入っていると、お背中流しましょうか?と言いながら、服を脱いで入ってくるんです。三四郎はびっくりして、大急ぎで風呂から出てしまいます。この女いったい何を考えているのか、全く分かりません。怖いです。
だから三四郎 就寝の際には、一枚の布団の面積をきっちり半分領土分けして、女性とは一言も口を利かないようにして、なんとかやり過ごしました。翌朝、宿屋で朝ごはんを一緒に食べて、駅の改札まで戻ったところで、女性とはお別れするのですが、彼女「色々御厄介になりまして、ではご機嫌よう」と丁寧にお辞儀した後、「あなたはよっぽど度胸のないかたですね。」と言って、にやりと笑いました。三四郎は、「プラットフォームの上へ弾き出された様な心持がした」という描写が、漫画みたいで、とっても面白いんですが、この名古屋でのへんてこなエピソード、いったい何のために描かれているのか?考えると、三つくらい目的があると思います。
一つ目は、もちろん『草枕』との共通点を設置するためです。男が旅館のお風呂に浸かっていると、女が全裸で入ってくるという、現実には滅多にあり得ないような場面が、草枕でも描かれています。主人公の画工が、一人でのんびりと温泉に浸かっていると、なぜか旅館の若女将 那美さんが真っ裸で入ってきます。
二つ目には、主人公の性質を表現するため。男性が入浴中に、突然全裸の女性が入ってきたら、どういう反応を示すか?これは、個人の性質によってかなり違うのではないでしょうか。
『草枕』の主人公は、あれ?もしかして誰もいないと思っているのかな?男が入っていることに気付いていないのかもしれない。一声掛けたほうがいいのかなぁと思いながらも、なあんにも言わずに、じっと湯船に身を潜めたまま、これは良い機会だと、女性の裸を上から下までひととおり観察します。彼はそういう性格です。でも三四郎は、違いますね。びっくりして飛び上がり、慌てて自分から風呂場を逃げ出しました。彼はそういう性格ですね。
三つ目には、別れ際の女のセリフ「あなたはよっぽど度胸のないかたですね」この言葉を三四郎に突きつけるためです。こう言われてショックを受けた彼は、列車の中で、べーコンの論文23ページを開いて読んでいるふりをしながら、昨夜のことを思い出して反省します。フランシス・ベーコン、イギリス経験主義哲学者、つまり小川三四郎23年間の経験と照らし合わせて、昨夜の出来事を振り返り、女の人って、ああいう時にも落ち着いていて、平気でいられるなんて、いったいどうなっているんだ。怖ろしい と思うのですけれども、三四郎は、あの女性に「困ったことになりましたね。どうしましょう?」と一言聞いてみれば良かったのでしょうが、それすらも怖ろしくて、できかった。だから「度胸が無い」と言われてしまった。このセリフは、この後何か月間も、彼の胸に刺さったまま残り、何度も何度も思い出します。
「23年間の弱点が一度に露見したような心持であった。親でもああ旨くいいあてるものではない」とこの時、三四郎は思っていましたが、本人が知らないだけで、彼のお母さんも、自分の息子は、度胸が無いってこと、とっくに分かっていました。7章で母からの手紙に「お前は子供の時から度胸がなくっていけない。」とはっきり書かれてありました。この手紙を受けての三四郎の返信が「東京はあまり面白い所ではない」というふうになるわけです。結局のところ、小川三四郎にとっての東京体験を一言で表現すると「お前は度胸が無い」という事実を突きつけられた。小川君にとってはそういう話と言えるでしょう。
「ストレイシープ」は「恋の試験」
彼は、与次郎のように、度胸とかやる気もないし、野々宮のように美的に物事を鑑賞するセンスもないし、広田先生のような鋭い分析的な知性もない。けれども、誰よりも心が優しい。小川三四郎の担当は、善の理想。善の理想というのは、愛情とか友情とか、相手の立場を思いやる心を大切にするものです。誰も気が付かなかった美禰子の心情を思いやってあげるのが、三四郎の役割です。「ストレイシープ」という言葉で表現された美禰子の心を理解する、というのが、本質的なところではあるのですが、ストレイシープには、他にも意味が込められています。
三四郎は、ストレイシープストレイシープと2回繰り返していますね。美禰子は2回、ストレイシープを使ったのです。彼女は、2回ストレイシープを使って、三四郎を「恋の試験」にかけました。しかし、2回とも白紙答案、まったくの無反応だったので、彼女をがっかりさせたのです。
「恋の試験」という言葉は、6章にでてきました。三四郎がノートに「ストレイシープ ストレイシープ」と書き続けた授業が終わった直後です。「粋なさばきの博士の前で 恋の試験がしてみたい」という都都逸を唄う学生がいたのだ、と与次郎が教えてくれました。都都逸というのは、ちょっと艶っぽい内容を、七・七・七・五 の句で唄うものです。「三世世界の カラスを殺し 主と朝寝が してみたい」という句が特に有名ですね。「粋なさばきの 博士の前で 恋の試験が してみたい」この何気なく出てくる都都逸は、作者からの大きなヒントでした。
一回目の「恋の試験」は、「ストレイシープ」という言葉を使った口頭試験。2回目は、「ストレイシープ」の絵葉書を使いました。言葉と絵つまり、詩と絵です。11章、広田先生が見た不思議な夢を思い出してください。20年前と全く同じ姿をした少女に、広田先生があなたは画だ と言うと、少女は、あなたは詩だ と言いました。ここにも出てくる「詩と画」という二つの芸術形式。これも草枕と三四郎に共通するテーマの一つであること、覚えておいてください。
「ストレイシープ」は「お貰いをしない乞食」
それでは、一回目のストレイシープ試験から見ていきましょう。5章です。菊人形展に行った章ですね。前回お話した8章では、美禰子が三四郎を舐め切った、完全に小ばかにしている様子が見て取れましたが、5章の時点の美禰子は、まだ三四郎に対して敬意を払っています。この時点では、夫として尊敬できる男 かもしれない候補の一人でした。4章で、一緒に広田先生の引っ越しを手伝いましたから、少し打ち解けていたし、彼女から名刺も貰っていました。もし、三四郎に美禰子の心をつかむチャンスがあったとすれば、この日だったわけです。しかも美禰子が、野々宮から良い返事を貰えなくて、すっかり落ち込んでしまい気分まで悪くなったところを三四郎が助け出したのです。込み合った菊人形展から二人きりで抜け駆けし、静かな田舎道を歩いて、小川の傍の草の上に一緒に腰を下ろしました。本文を読みます。
菊人形で客を呼ぶ声が、おりおり二人のすわっている所まで聞こえる。
「ずいぶん大きな声ね」
「朝から晩までああいう声を出しているんでしょうか。えらいもんだな」と言ったが、三四郎は急に置き去りにした三人のことを思い出した。何か言おうとしているうちに、美禰子は答えた。「商売ですもの、ちょうど大観音の乞食と同じ事なんですよ」
「場所が悪くはないですか」
三四郎は珍しく冗談を言って、そうして一人でおもしろそうに笑った。乞食について下した広田の言葉をよほどおかしく受けたからである。
「広田先生は、よく、ああいう事をおっしゃるかたなんですよ」ときわめて軽くひとりごとのように言ったあとで、急に調子をかえて、
「こういう所に、こうしてすわっていたら、大丈夫及第よ」と比較的活発につけ加えた。そうして、今度は自分のほうでおもしろそうに笑った。
「なるほど野々宮さんの言ったとおり、いつまで待っていてもだれも通りそうもありませんね」「ちょうどいいじゃありませんか」と早口に言ったが、あとで「おもらいをしない乞食なんだから」と結んだ。これは前句の解釈のためにつけたように聞こえた
今まで少し疲れた感じだった美禰子が急に調子を変えて元気よく「こういう所に、こうして座っていたら大丈夫及第よ」と言って面白そうに笑いました。「及第」というのは、試験に合格するということ。前後の文脈を探しても、いったい何に合格するのか書いていないのですが、これは「恋の試験」がもうすぐ始まることを予告しています。
さらに美禰子は、この直後「おもらいをしない乞食なんだから」と言いました。三四郎には、前句の解釈の為に付けた様に聞こえたたのでしょうが、前句ってどれですか?「大観音の乞食」でしょうか?違いますね。大観音の乞食は、「お貰いをする乞食」です。「お貰いをしない乞食」と言うのは、前句ではなく後句、この後に出てくる言葉の解釈であって、これからはじまる「恋の試験」の解答です。何と美禰子は、試験が始まる前に、三四郎に先に答えを教えてしまっているのです。
この成り行きに慌てて、急遽二人の前に出現したのが、謎の通行人です。この男、登場の仕方もかなり謎です。川を向こうへ渡ったはずなのに、不思議なことにだんだん二人の前に近づいてきました。洋服を着て、髭を生やして、年輩から言うと広田先生くらいな男が突然現れて、二人をにらみつけました。さて、これは誰でしょうか?洋服を着ていますから、近所の農家おじさんがたまたま通りかかったのでは、ありません。洋服を着て髭を生やして、広田先生と同じ40代の男性と言えば、ひとり思い当たる人がいるでしょう。そう、作者夏目漱石です。小説の中に突然、作者が乱入してきたのです。美禰子が三四郎に、試験の答えをすべて教えてしまいそう。このままでは、三四郎が試験に合格してしまうので、慌てて(二人とも、ちゃんと筋書き通りにやってもらわないと困るよ!)と注意するために、作者自身が登場したのです。
こういう手法、メタフィクションと呼びますね。この小説は、メタフィクション構造なのです。クラシックな文芸作品にそんなふざけたな手法が使われているはずはない と思われるかもしれませんが、夏目漱石は、あの滅茶苦茶に破天荒なメタフィクション小説として有名な、ローレンス・スターンの『トリストラム・シャンディ』という作品を日本に紹介していますから、こういう斬新な小説手法を取り入れていること、不思議はないでしょう。もちろん、真面目な漱石先生は、この手法を単なるおふざけではなく、きちんとした目的の下に使用しています。
実を言うと、広田先生もこの小説のメタフィクション構造にうっすらと気が付いているのです。11章 広田先生が不思議な夢を見た場面をもう一度、読みましょう。今度は、少し手前の部分です。
――そうその時はなんでも、むずかしい事を考えていた。すべて宇宙の法則は変らないが、法則に支配されるすべて宇宙のものは必ず変る。するとその法則は、物の外に存在していなくてはならない。
広田先生のことだから、何か哲学的な事でも考えているのだろう と思わせておいて、彼は、自分が棲んでいる世界は何かがおかしい と疑っている。彼が考えているとおり、『三四郎』という小説世界を支配している法則が、小説世界の外側に存在しています。広田先生は、お昼寝中に見る夢までハッキングされた。ある法則によってコントロールされたので、違和感を覚えました。
「この小説世界を支配している法則」とは、何か?
答えは、後回しにして、先に美禰子のストレイシープ試験のほうを片付けましょう。恋の試験 の部分を読みます。
「迷子」
女は三四郎を見たままでこの一言を繰り返した。三四郎は答えなかった。
「迷子の英訳を知っていらしって」
三四郎は知るとも、知らぬとも言いえぬほどに、この問を予期していなかった。
「教えてあげましょうか」
「ええ」
「迷える子——解って?」
迷子の英訳は、普通に考えれば、lost child ですね。美禰子は、広田先生から英語を習っています。三四郎だって、東京帝国大学の文科の学生だから、それぐらいは知っている、という前提のもとに、彼女は迷子を stray sheep と聖書的に表現しています。ここでいう迷子は、物理的な迷子じゃなくて、心の状態。精神的な迷子なの、そんな私の気持ちが分かりますか?と訊いているのです。彼女は、三四郎とちょっと精神的な深い対話ができるかどうか、試しているのです。これが美禰子のストレイシープ口頭試験でした。
ところが三四郎は、一言も答えずに、ただただ黙り込んでしまいます。すると美禰子は急に真面目になって「私そんなに生意気にみえますか」「じゃ、もう帰りましょう。」と言いました。その言い方は、決して嫌みのある言い方ではなく、(小川さんは、私に興味がないのね)と、諦めるような口調でした。この時の美禰子は、まさか三四郎が、どう答えればよいかまったく思つかない、それほどまでに鈍い男であるとは知りませんでした。大学生に向かって生意気な口を利くような女には、興味がないから、相手にしてもらえなかった と思ったのです。
さて、ストレイシープな美禰子の気持ちですが、さっき彼女が教えてくれたとおりです。ストレイシープは、言い換えると「お貰いをしない乞食」です。矛盾していて禅問答みたいですが、こちらの方が、解りやすいですね。乞食は、お金とか食べ物、施しを乞うているわけですけれども、「お貰いをしない乞食」である美禰子は、いったい何を乞うているのか?それはもちろん、愛ですね。美禰子は、愛を乞うている。でも、お貰いの愛は欲しくない。人に決められた結婚相手じゃ嫌、自分で選んだ相手と自由な恋愛結婚がしたい。だから美禰子は野々宮を選びましたが、野々宮からは、選んでもらえない。それが自由恋愛です。与えられるものに満足できず、欲しいものを得ることも出来ない、無いものねだりをし続けるのが「お貰いをしない乞食」の苦しいところです。
明治時代、封建社会が崩れ始め、若者は男も女も、家という束縛から少しずつ自由に生きる可能性を夢見ました。恋愛結婚の自由、職業選択の自由。しかし現実は厳しい競争社会です。そう簡単には、甘い夢は手に入りません。甘い夢を見た分だけ、勝ち得る現実の苦さに、心は引き裂かれるでしょう。夢と現実の間で迷子になって、葛藤するストレイシープです。ストレイシープであることは、三四郎も同じです。だから美禰子は、2回目のストレイシープ試験として、葉書に2匹の羊の絵を描いて送ってくれました。
三四郎も上京したての頃は、東京で学者として成功し、結婚して母を呼び寄せる なんていう未来を夢想することができました。しかし、ほんの数か月間の間に、いろんな人を観察して、自分には東京よりものんびりとした田舎のほうが合っている、ということに気付いてしまったのだと思います。野々宮のような優秀な学者でさえ、楽ではない暮らしを強いられるほどに、東京の物価は高く、ぼんやりしていると与次郎のようなちゃっかりした人に、お金をとられることもある。10章で、広田先生のところに遊びに来ていた友人、先生に柔道の技をかけていた地方の中学校の先生 なんとなく『坊ちゃん』の主人公と似たような境遇の人物が、ちらっと登場しましたが、彼は、教師を辞職した後、次の職探しが大変だと嘆いていました。実家を出て自力で生活の糧を得るのは、なんと大変なことだろう。二、三年年の気楽な学生生活を終えると、これほどまでに厳しい現実が待っているのか、ということを痛感したでのす。
だから「この冬休みには帰ってこい」という母の命令で帰郷した三四郎は、おそらく母の勧める、三輪田のお光さんとの結納を済ませたのでしょう。大学を卒業した後は、故郷に戻ることにしたのだろうと思います。野々宮からフラれた美禰子も、大人しく縁談結婚を受けました。美禰子の夫になった人、13章で一緒に絵を見に来ていましたが、どうやら夫の方が妻を尊敬している様子です。二匹のストレイシープは、希望通りには行かなかったけれども、収まるべきところに無事収まったのです。
デビル漱石が用いる法則
恋人同士には成れなかった三四郎と美禰子の関係に、作者は、まったく別の形式を与えています。それが描かれるのが、二人の別れの場面です。
12章 インフルエンザから回復した三四郎が、美禰子に30円を返しに行きます。里見の家に行くと、よし子が、美禰子さんはチャーチに行ったと教えてくれました。別れの場面の舞台として、チャーチ、教会という場所を設定しているのが、ポイントです。
三四郎が教会の前で、待っていると、礼拝が終わり、美禰子が出てきました。三四郎は、美禰子に30円を返し、「結婚なさるそうですね」「ご存じなの」という会話を交わした後です。
女はややしばらく三四郎をながめたのち、聞きかねるほどの嘆息をかすかにもらした。やがて細い手を濃い眉の上に加えて言った。
「われは我が愆を知る。我が罪は常に我が前にあり」
聞き取れないくらいな声であった。それを三四郎は明らかに聞き取った。三四郎と美禰子はかようにして別れた。
「われは我が愆を知る。我が罪は常に我が前にあり」というのは、随分と、仰々しいセリフですが、これは旧約聖書の詩編に出てくる懺悔の言葉です。美禰子は罪の告白、懺悔を行い、そして三四郎はそれを聞いてあげるカトリックの司祭 という役割を演じているのです。この時の三四郎の服装ですが、着物の下に防寒の為にシャツを着る という明治時代の書生スタイルです。その上に、着物の上から羽織るマントのような外套を着ているのですから、白い襟が司祭のカラーみたいに見えている様子も、想像してみてください。
二人がこんな風に唐突に、告解シーンをプレイ 演じているのは、何故でしょうか?答えは、広田先生が考えていたとおり、この小説世界の外側から支配している法則に従っているのです。支配者は、もちろん夏目漱石です。作者は普通「神」と呼ばれる存在ですが、美禰子は、作者を「神」ではなく「悪魔」デビルと呼んで、二匹のストレシープをデビルが監視している絵葉書を書きました。デビル漱石が、この小説に用いる法則は、「草枕の逆さま」です。この小説をなるべく『草枕』の逆さまになるように描きたいという作者の遊びなのです。
『草枕』は、日本の伝統的な、演劇である能とりわけ「夢幻能」の仕組みを利用した物語です。対する、『三四郎』は、西洋の演劇を意識してもらいたいので、本文に何度もノルウェイの劇作家イブセンの名前を出してきます。そして、日本の夢幻能には、僧侶が死者の魂を慰める「鎮魂」という形式があり、それに則って、『草枕』の主人公は鎮魂を行います。だから『三四郎』では、カトリックの神父を登場させたいのです。神父に懺悔する「告解」という形式を借りて、美禰子は三四郎の心を弄び、傷つけたことを謝罪しました。1回目の動画で述べましたとおり、『三四郎』は、『草枕』の謎を解く鍵になる小説です。『草枕』と比べながら、読めば、もっともっと楽しめます。
『三四郎』という小説は、筋だけ見れば、なんてことの無いお話ですが、重要なのは、それをどんな風に描いたかです。古典的な修辞法だけではなく、ミステリーとかメタフィクションという新しい要素も取り入れた 超絶技巧なのにまったく嫌みが無い、甘くて苦い、美しい作品だと思います。6回にもわたる長い長い動画 ここまで辛抱して、聞いて下さったくださった方は、かなり夏目漱石がお好きなのだと思います。もし、『草枕』の解説にも興味がある、という方がおられましたら、グッドボタンをお願い致します。また、『三四郎』で心に残る場面などあれば、ぜひコメント欄で教えてください。
最後までご視聴、本当にありがとうございました。またいつか、お会いしましょう。