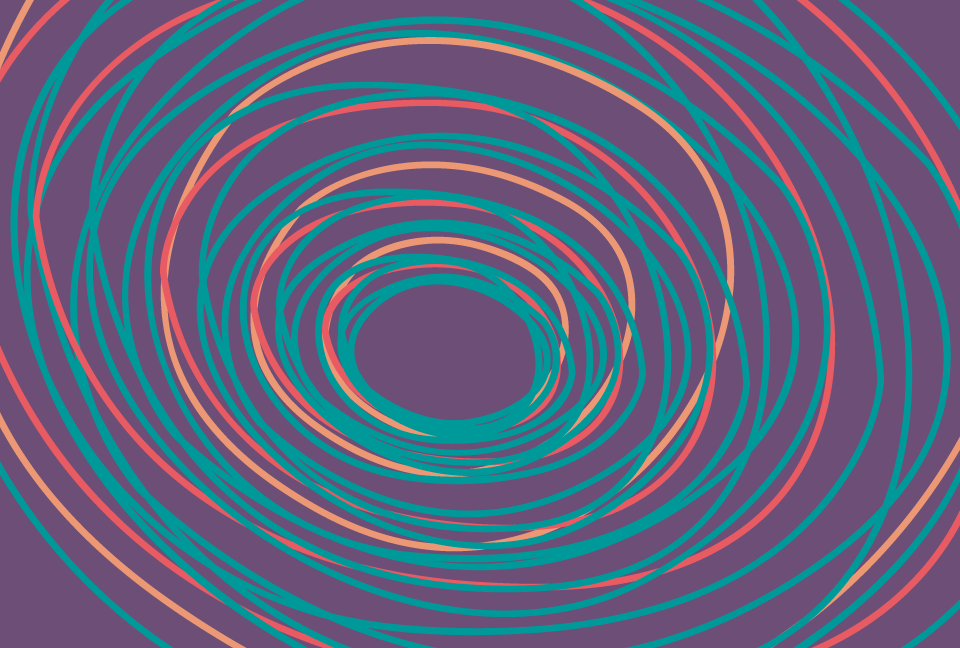解説
いきなり後方から、「檀那、そこまで入れてってよ。」といいさま、傘の下に真白な首を突込んだ女がある。油の匂で結ったばかりと知られる大きな潰島田には長目に切った銀糸をかけている。
永井荷風:濹東綺譚より
老小説家の大江と、私娼の雪子が、初めて出逢う有名な一節である。
六月末の或る夕方。梅雨はまだ明けてないが朝からよく晴れていた。夕方になりいつの間にか天気が変わってしまった。玉の井の盛り場を歩く大江だが、散策好きの習慣で傘を持参していた。そこへ大きな島田に結った雪子が、髪結い店から出て来て、雨に降られて大江の傘に入ってきたのだ。
吹き荒れる風と雨とに、結立の髷にかけた銀糸の乱れるのが、いたいたしく見えたので、わたくしは傘をさし出して、「おれは洋服だからかまわない。」
永井荷風:濹東綺譚より
と、さすがに相合傘に照れて、大江が言うと、
「じゃ、よくって。すぐ、そこ。」と女は傘の柄につかまり、片手に浴衣の裾を思うさままくり上げた。 稲妻がまたぴかりと閃き、雷がごろごろと鳴ると、女はわざとらしく「あら」と叫び、一歩後れて歩こうとするわたくしの手を取り、「早くさ。あなた。」ともう馴れ馴れしい調子である。
永井荷風:濹東綺譚より
『濹東綺譚』は現在の墨田区の東向島辺りに位置する玉の井を舞台に、梅雨明けから秋の彼岸までの詩情あふれる失恋の話である。
荷風は、近代化から取り残された迷宮のようなこの地「玉の井」を好んだ。
明治・大正・昭和の時代を生きた荷風だが、早くからアメリカ、フランスに遊学し西洋の個人主義や伝統を重んずる文化に親しんでいる。そんな荷風は日本の伝統文化は江戸にあるとして、明治の皮相な近代化を批判した。
物語は明治期に導入された活動写真の話題に始まり、震災後の西洋銀座を嫌い、浅草公園辺りを散策する。ポン引きを逃れ、吉原から廓外の裏町の古本屋を訪ねる。
ここで戯作者、為永春江の書いた明治の古雑誌に「生命が延びるような気がするね」と大江は語り、老主人との会話に下町の生粋の情味を感じる。
そこから玉の井に迷いこみ激しい夕立ちにあい、異界へ誘われるきっかけになっている。
突然の雨の中、油の匂をさせ髪を島田に結った浴衣姿の容貌の良い女が現れる。大江にとっては思いがけなくも遭遇した江戸の情緒である。この場面は木村荘八の挿絵(*岩波文庫版)でも有名である。
それは滅びゆくものへの哀惜の情と、忘れられていく江戸の憧憬であった。
『濹東綺譚』の小説の構造は<入れ子>になっておりメタフィクションが展開される。
大江匡という麻布区御箪笥町に住む五十八歳になる老作家が、小説『失踪』を書こうとしてその題材を求めている。大江はまさに老境に入っている永井荷風自身である。
『失踪』の主人公は 種田順平という私立中学校の英語の教師の設定。
初婚の恋女房に先立たれ三、四年にして、継妻に光子を迎える。光子は有名な政治家某の家に雇われる小間使だったが、主人に欺かれて身重となる。後の始末をその執事 遠藤某にさせる。子供の成人までの養育費と光子が他へ嫁する場合に相当の持参金を贈ると云う条件を付けた。
光子が男の児を生むと、種田順平は友人である遠藤某の仲立ちで後妻とする、光子は十九、種田は三十歳だった。種田は金にふと心が迷って再婚する。内縁の光子と男の児を籍に入れ、その後、女の児、男の児と新たに二児をもうけたが、気が弱く交際嫌いな種田は家内の喧騒に耐えられなくなり、五十一歳の春、教師の職を辞し、退職金を手に、家に帰らず行方をくらます。
その後、種田は下女奉公に来ていた女すみ子と偶然電車の中で邂逅し、彼女が浅草駒形町のカフェに働いている事を知り、一二度おとずれてビールに酔う。
退職金をふところにした夜、種田は初めて女給すみ子のアパートに行き、事情を打明けて一晩泊めてもらった……。という腹案まではできた。
※
こうして大江は、種田がその家族を棄てて世を忍ぶ場所を、本所 深川あるいは浅草の外れや、近くの陋巷の地を考えている所に、たまたまの乗合自動車で辿り着いたところが玉の井であった。早速、実地調査にあたる。
土手を降りると玉の井の盛場を斜に貫く繁華な横町の路地口には「ぬけられます」とか、「安全通路」とか、「京成バス近道」とか、或は「オトメ街」或は「賑本通」など書いた灯がついている。
浅草から東武伊勢崎線で東向島駅の東側に『濹東綺譚』の舞台となる私娼の町、玉の井はあった。もともと玉の井は町名ではなく通称である。浅草寺や凌雲閣の裏手の銘酒屋が道路拡張で隅田川を越えてここに移る。それは春をひさぐだけの魔窟だった。
通りが迷路のように続き、人々の往来に肩をぶつけるほど道幅は狭く行き止まりのようだが、あちこちに「抜けられます」という看板があり、玉の井の象徴となった。そこに娼婦の家が立ち並ぶ。
ここで小説の構想から現実に戻ってくる。
おでん屋台のおやじが「降ってくるよ」と叫ぶと、稲妻が閃く。割烹着の女や通りがかりの人々が駆けだす。驟雨と雷鳴のなか、雪子がいきなり後ろから大江の傘の下に、真っ白な首をにゅっと突っ込んでくる。そして傘の柄につかまり、片手で浴衣の裾を思うさま、まくりあげる。
小説世界と現実世界が入れ子となり、大江の小説の創作過程を読者も追体験できる。
路地へ這入り、小径を曲り、溝にかかる小橋を渡り、軒並一帯に葭簀の日蔽をかけた家の前に立留る。そこは貧しく見すぼらしい異界だが、時運に取り残された大江にとっては安息処であり隠れ家となりそうだ。
お雪に誘われて家に上がった大江は、さらに深く、女と部屋を観察する。
荒い大阪格子を立てた中仕切、鈴のついたリボンの簾。上框に腰をかけて靴を脱ぐと、女は雑巾で足をふき、端折った裾もおろさず下座敷の電燈をひねる。
大江の遊び慣れた吉原が江戸三百年の公娼街なら、迷いこんだ玉の井は新開地の湿地に出現した私娼街であった。
お雪は年は二十四五、なかなかいい容貌である。鼻筋が通った円顔で、黒目がちの眼の中も曇っていず唇や歯ぐきの血色を見ても健康である。
簾越しに、両肌をぬぎ、折りかがんで顔を洗う。肌は顔よりもずっと色が白く、乳房の形で、まだ子供を持った事はないらしい。
単衣物に赤い弁慶縞の伊達締めを大きく前で結び、大きな潰島田の銀糸と釣りあい、お雪は明治年間の娼妓のように見えた。
そして為永春水の小説を引用しながら、正直で純朴なお雪との出会いと雨やどりの宿の風情のなかで、玉の井を題材に小説への意欲を高める。
こうして大江は、『失踪』の一節にこの体験から創作を続けていく。
※
吾妻橋の真ん中の欄干に身を寄せ種田順平はすみ子を待っている。種田は今夜すみ子のアパートに行き、今後のことを考えるつもりだった。今日まで二十年の間、家族のために一生を犠牲にしてしまった事が、いかにもにがにがしく腹が立ってならない。
すみ子がやって来てアパートに向かう。秋葉神社の近くで玉の井の方角だ。神社の石垣について曲ると片側は花柳界の灯が続く横町の突当り。俄に暗い空地の一隅に、吾妻アパートという灯がある。
すみ子は引戸をあけて内に入る。種田は別居や今後の離婚のこと、すみ子は身の上話などを語らう。
こうして現実は小説のなかに取り込まれ、合わせ鏡のようになっていく。
※
梅雨があけて暑中になる。大江は鄰家のラジオの音に苦しめられる。
『失踪』の草稿はラジオに妨げられ中絶しており、感興も消え失せてしまいそうである。
銀座も物騒で行くことも無くなり、散策の方面を隅田川の東に替え、溝際の家に住むお雪をたずねて憩むことにした。
お雪はわたくしの職業を秘密の出版を業とする男だと思ったらしい。そこで悪銭の出処もおのずから明瞭になったらしい。すると女の態度は一層打解けて、全く客扱いをしなくなり、二人はさらに親しみを深めていく。
わたくしの憂慮するところは、この町の附近、あるいは東武電車の中などで、文学者と新聞記者とに出会わぬようにする事だ。
この心持は『失踪』の主人公種田順平が世をしのぶ境遇を描写するには必須のことであろうと考える。
わたしがふと心易くなった溝際のお雪の住む家は、大正開拓期の盛時を思い起こさせ、時運に取り残された身には深い因縁のあるように思われる。
大江の感覚を刺戟し、三四十年むかしに消え去った過去の幻影を再現させてくれる。
お雪が飯櫃を抱きかかえ飯をよそい、さらさら音を立てて茶漬を掻込む姿を、明くない電燈の光と、溝蚊の声の中にじっと眺めると、青春のころ親しんだ女達の姿やその住居を思浮べる。
まさに老境の大江にとって遠い日の懐かしい情景なのである。
ある時、大江はお雪の家の二階に一緒にいると、窓の敷居に座っているお雪が暫く空を見ていたが、
「ねえ、あなた」と突然わたくしの手を握り、「わたし、借金を返しちまったら。あなた、おかみさんにしてくれない。」
永井荷風:濹東綺譚より
と言う。大江は「もう十年若けりゃ」と茶ぶ台の前に坐り巻煙草に火をつけた。
「あなた。髪結いさんの帰り・・・もう三月になるわねぇ」とお雪は言う。
初めて逢った日を思い返すのは、その時の事を心に嬉しく思うためだからだろう。
お雪は毎夜、数知れぬ男に応接する身でありながら、どうしてわたくしと逢った日の事を忘れずにいるのか分からなかった。わたしのような老人に好いたの惚れたのというような柔らかく温かな感情を起こせるとは夢にも思っていなかった。
大江は悪徳の谷底には美しい人情の花と香しい涙の果実が、沢山に摘み集められると考えている。
溝の臭気と蚊の声との中に生活する女たちに親しみを覚えているのだ。
お雪の性質は快活で現在の境遇を深く悲しんではいない。寧ろこの境遇から得た経験で身の振り方を考えようという元気も才智もあるようだ。
お雪は正直で純朴で真面目なところがある。銀座あたりのカフェの女給と比べても、なお愛すべく人情を語ることができる。大江はお雪に江戸の残り香を感じており、玉の井の街路の光景も、銀座や上野とは異なり、浅薄の外観の美を誇らず、不快の念を覚えさせることが少ない。
九月も半ちかくなったころ、お雪にまた会いに行く。
雷門からは円タクを走らせ、やがていつもの路地口。いつもの伏見稲荷。いつもの溝際に、いつもの無花果と、いつもの葡萄が、その葉はすこし薄くなり、秋は知らず知らず夜毎に深くなっていく。
大江はお雪と馴染みになるにつれて、断言できることがある。
お雪の性質の如何に係らず、窓の外の人通りと、窓の内のお雪との間には、互に打ち解けることができる糸に繋がれていることである。
窓の外は大衆であり、即ち世間である。窓の内は一個人である。そしてこの両者の間には、著しく相反目している何物もない。
お雪はまだ年が若く、世間一般の感情を失っていない。
お雪はわたしの力によって境遇を一変させようという心を起している。しかしわたしなどと一緒に所帯を持てば、お雪も怠け者のだらしない女になるのではないか。
お雪がほんとうに幸福な家庭の女になるには、失敗してばかりのわたしではなく、前途に希望の多い男でなければならない。他との交際を嫌い、所帯を嫌うという、わたしの二重人格を、お雪は知らないのだ、悲しませたくはない。
お雪は倦みつかれたわたしの心に、懐かしい幻影を彷彿たらしめたミューズである。
世から見捨てられた一老作家の、最後の作とも思われる草稿を完成させた不可思議な激励者である。
今ならそれほど深い悲しみと失望とをお雪の胸に与えずに済むだろう。こうして大江はお雪と別れることを決意する。
大江はお雪に秋袷の着物代を渡して、馴染みの客が来たのと入れ替わりにそっと外へ出る。
四、五日たつとお雪はどうしたかしらと思い、顔だけでも見たくて堪らない。真の事情を打ち明けてしまいたいと思い、お雪の家の窓に立ち寄った。
お雪は来るはずの人が来たという心持を様子と調子に著したが、新たな親方やおかみさんが一緒にいて、長く居られず説明もできなかった。
四、五日過ると彼岸に入った。十五夜の当夜にお雪が病んで入院していることを知った。十月になると例年よりも寒さが早く来た。
『濹東綺譚』は、ここで終わる。その方が良いと大江は考える。
お互いに本名も住所をも知らず、ただ濹東の裏町、蚊のわめく溝際の家で馴れ親しんだだけ。ひとたび別れれば生涯逢うべき機会も手段もない間柄である。
軽い恋愛の遊戯とは云いながら、再会の望みなき事を初めから知りぬいていた別離の情は、強いて之を語ろうとすれば誇張に陥り、之を軽々に叙し去れば情を尽さぬ憾みがある。
永井荷風:濹東綺譚より
お雪はあの土地の女には似合わしからぬ容色と才智とを持っていた。鶏群の一鶴であった。
わたくしは二十の頃から恋愛の遊戯に耽ったが、この歳に至ってこのような夢物語を語る心持になろうとはと思わなかった。
荷風は老境にあって、若き窓の女、お雪との恋の遊戯に、江戸の残り香が漂う詩情あふれる失恋話を、自身の心の中に創作することができたのであろう。
このうらぶれた色町を背景に、主人公の大江(永井荷風)とお雪のはかない縁と交情が、夕立から始まった夏を超え、秋の彼岸へと向かう季節の移り変わりとともに、始まり、そして終わる。
玉の井を舞台に男と女のラビリンスを描いた儚い物語なのである。