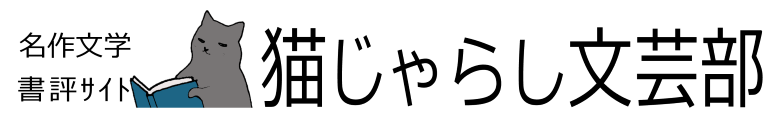神を信じない反キリスト者であることが、西欧キリスト教文明の社会でいかに排除されるか。カミュはこの不条理と向き合い、抵抗する人間を『異邦人』に描く。そしてついにムルソーは自己の真理に到達して死んでいく。それは半年後に発表された随筆『シューシポスの神話』や後の評論『反抗的人間』で不条理に抗う人間の自由を幸せと捉える姿である。偽りの条理に嫌悪し、多数を疑い、法律や宗教に盲信することなく、自らの思考で真理を探究する。ムルソーは決してニヒリズムではない。そこには自分に正直な人間の生き方と疎外する社会への反抗の精神がある。
解説
眩しい太陽(自然) VS 神の教え(従順)
「きょう、ママンが死んだ。もしかすると、昨日かもしれないが、私にはわからない」養老院から電報をもらった。「ハハウエノシヲイタム、マイソウアス」これでは何もわからない。恐らく昨日だったのだろう。
Albert Camus :L’ETRANGERより
主人公のムルソーの下に、一通の電報が届く。有名な書き出しであり、この訃報が、ムルソーの運命を決定づけることになる。
印象的な冒頭に滲む、カミユと実際の母親の関係に触れておくと、カミュはフランスの旧植民地アルジェリアのモンドヴィに生まれる。貧しい暮らしとほとんど耳が聞こえず読み書きが出来ない母、愛してはいたが母子の間には会話が無かったことを後悔していると、カミュは述懐している。このことを象徴しているようだ。
ムルソーは母を施設に預けている、身内はムルソーしかいない。この葬儀の際の無感動な振るまいに、キリスト教への信仰的態度は無い。
ムルソーは知的な青年だが貧困で大学を断念する。海運業の仕事で平凡に暮らすが、母親を扶養できず、三年前に国庫で運営される養老院に入所させている。それは親不孝だが、貧しさゆえに止むを得なかった。そして彼は深く自問することを放棄した。
当時のフランス人は、多くがカトリック教徒だ。当然、主なる神のもとで「汝、父母を敬え」であり、「汝、殺すなかれ」が絶対的戒律である。
ムルソーはフランス人だがアルジェリアに生まれ暮らす。そこは 太陽の光と海だけが永遠のように存在する。太陽がいつもそばにあり、彼は、太陽に恋する飾らない男であり、神を信じぬ無信仰な人間なのだ。
『異邦人』は、このアルジェの地で、キリスト教徒ではないひとりの青年が、母国フランスの法律で裁かれ、異端審問さながらに、死刑を宣告されギロチンにかけられる。
この悲劇のなかでムルソーは何を思い、何を掴んだかという話である。
不条理への抵抗は、以下の心理変容に表現されます。
①ムルソーは、無口で内向的な男で、物事を深刻に考えることをせず、 日々を思うままに過ごすだけの人間になっていた。
②この事件で、判事は執拗にムルソーを追求し、言葉を捏造し、虚構を仕立て上げる。その背景に、彼が無神論者であることが理由になっている。
③ムルソーは、法廷に理不尽を感じ、同時に、自分は何者なのか考えるようになっていく。獄につながれた不自由のなかで太陽や海の自然を感じながら思索を巡らす。
④死刑が宣告され、恩赦のために司祭の説教を受けるが、ムルソーは神を否定し、 怒りを交え司祭に反駁する言葉を浴びせ続ける。
⑤ムルソーは、神のもとに人間があるのではなく、自由こそがすべてであり、そのために抵抗するという真理に到達し、自分を幸せと感じ刑場に向かう。
葬儀での態度が、判決の根拠となる不条理。
『異邦人』は第一部と第二部に分かれます。
第一部では母の葬儀での態度と、日常に戻りアラブ人の殺害にいたるまで。
第二部では殺人に対する法廷での審議と裁定の模様と、死刑に至るまで。
訃報を受けたムルソーはマランゴの養老院を訪れる。院長はムルソーに、経済的な理由で別居したことを皮肉まじりに同情する。母親は、埋葬はカトリック教の葬式を希望していた。
ムルソーは無神論者ゆえに葬儀の儀礼や慣習を知らない。母の死に顔を見ることもなく、薦められたミルクを飲み、我慢できず煙草に火をつけた。十人ほどの母の友人たちと通夜を過ごすが、暑さと仕事の疲れもあり、夜と花の匂いでうとうとする。
埋葬の日もムルソーは母の顔を確認することを拒む。葬儀屋から母の年齢を聞かれ、正確な年齢を知らないことに気づく。ママンの「許婚」とからかわれる仲の良かったペレーズが、参列を許される。
ムルソーは、友人たちの悲しみや恋人の存在を知り、母の人生を想う。
やがて焼きつける暑さのなか埋葬が行われる。残酷な太陽に支配された葬儀が終わる。この通夜と埋葬での行為。ムルソーは、それを別に不適当と感じていなかったが、後に法廷での証言で不穏当な行為として注目される。
無軌道な日常が、危険思想をもつ人間とされる。
ムルソーは葬儀の疲れを癒すため海水浴場に行く。かつての同僚だったマリイに出逢う。太陽の下、二人は海ではしゃいだ。ムルソーは彼女に、彼女もムルソーに気を寄せていた。
彼女は喜劇映画を観たいと言う。服を着た時、黒いネクタイ姿のムルソーにマリイは気づく。「昨日」ママが死んだと伝えると、マリイは驚いたが何も言わなかった。映画の後、マリイはムルソーの部屋に泊まった。
母親が死んでも家の窓から見る景色は何も変わらない。けだるい一日が過ぎる、いつもと同じ日曜日。ママは埋葬され、ムルソーは明日からまた勤めに出る。アパルトマンの隣室のサラマノ老人と出会う。老人はスパニエル犬を連れて八年間、同じコースを散歩に出るが、お互い仲が悪くて紐を引っぱりあい罵り合っている。それでもムルソーは老人と犬の関係を微笑ましく見ている。
同じ階にレエモンという男がいる。「倉庫係」と名乗っているがやくざ者の女衒で情婦と揉めているようだ。
周囲には好かれていないが、彼の話は面白いと思う。ムルソーは他人の噂では人を判断しない。レエモンは情婦の兄といざこざがあり、喧嘩話をムルソーに聞かせる。情婦を懲らしめるために手紙で呼び出すことを考え、レエモンはムルソーに文章を頼む。
土曜にマリイが来てムルソーの部屋に泊まる。マリイはムルソーに「愛しているか」と尋ねるが、ムルソーは「恐らく愛していないと思う」と答え、マリイは悲しむ。
隣室ではレエモンの呼び出しに訪れた情婦が殴りつけられる。ムルソーは仲裁にも入らず警察も呼ばなかったが、やがて巡査が来てその場は収拾された。
その後、レエモンはムルソーに警察での証言を頼み、警察嫌いのムルソーはレエモンを擁護する発言をする。
サラマノ老人の犬がいなくなり途方に暮れ涙すると、ムルソーは優しく同情する。
太陽のシンバルとナイフの刃、それは偶然の出来事。
ムルソーはレエモンから次の日曜日、友人マソンの浜辺の別荘に誘われる。
出発の日、レエモンと諍いを起こしているアラブ人の一団を目にする。やがてムルソーたち一行は別荘地に到着する。
マソン夫妻は、三人をもてなし、楽しく時を過ごす。ムルソー、マリイとマソンの三人が浜辺に向かう。ムルソーとマリイは沖で泳ぎ、浜辺で心地良いまどろみを感じる。
食事を終えて、今度は、マソン、レエモンとムルソーの男三人で浜辺に行く。
太陽の光は垂直に砂の上に降りそそぎ、海面は煌めいていた。
そこに二人のアラブ人が現れ、こちらに向かって歩いてくる。彼らはレエモンたちを追いかけてきたのだ。
三人も歩み続け近づいていく。双方ともやる気になっている。レエモンと大男のマソンは二人を殴りつけたが、レエモンがナイフを持った例のアラブ人に腕をえぐられ、口を切られた。血が噴き出している。
別荘に戻り医者に診てもらった後、レエモンが再び、浜に出たがるので、ムルソーはレエモンに付き添う。レエモンはピストルを携えていた。
太陽は圧倒的で、砂の上に、海の上に、光はこなごなに砕けていた。
再び、冷たい泉のある大きな岩陰に潜んでいるアラブ人たちと出会う。
血気(にはやるレエモンをなだめ素手で闘うことを促し、ムルソーはレエモンのピストルを預かる。このときはアラブ人が逃げて何も起こらなかった。
二人は一緒に別荘まで戻ったが、ムルソーは暑さで頭ががんがんしていて、女たちの会話もうるさく感じて、レエモンを残して一人で浜へと引き返す。
太陽は容赦なく攻撃する。砂や白い貝殻やガラスの破片から、光の刃が閃く。
ムルソーは岩陰の涼しい泉を求める。すると例のアラブ人がまた来ていた。ムルソーと一触即発の状況である。太陽から逃れようとムルソーは泉に近づく。激しい陽光に攻められ、額に痛みを感じる。それは「ママンを埋葬した日と同じ太陽」だった。血管が皮膚の下で脈打つ。
アラブ人はナイフを抜き構える。額の上の太陽のシンバルと、ナイフからの光の刃を感じる。
切っ先は煌き、長い刃となりムルソーの視力を奪い、アラブ人の顔が全く見えなくなった。「空は端から端まで裂けて、火の雨を降らす」かと思われ、ムルソーは引き金を引く。
それは真昼の均衡と浜辺の静寂を破壊する。さらに身動きしない体に四たび撃ち込む。海と太陽だけ。それは偶然が起こした出来事だった。