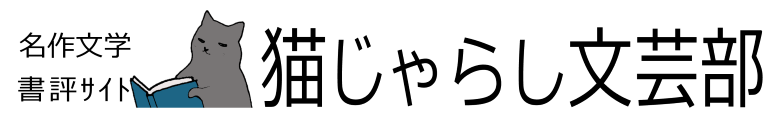「人情」対決
①「人情」に耽る画工
3章 就寝前に画工は「竹影階払塵不動」の額を読みました。上演の合図です。
芝居合、人情対決、画工編が始まります。真夜中に目を覚ました彼は、歌っているような女の小声を聴きます。その細く低い声に、耳を澄ませると「あきづけば、をばなが上に、おく露の、けぬべくもわは、おもほゆるかも」という文句を何度も何度も繰り返しています。昼間に茶店の婆さんから聞いた「長良の乙女」が詠んだ和歌です。しばらくは布団の中で我慢してこの声を聞いていた画工ですが、遂に布団をすり抜けて障子を開けて、中庭を確認しました。声が聞こえる方を見ると、月光の下すらりとした女の影が、彼の部屋とつながった向かいの棟に消えました。
影の正体は、那美さんです。これが彼女の最初の奇行であり、画工編「人情」の芝居です。彼女が演じているのは、もちろん「長良の乙女」。画工編「人情」として、彼が出してきた物語は「長良の乙女」なのです。「長良の乙女」の情報を、念のためもう一度貼ります。
- この村の伝説で、「長良の乙女」と呼ばれる、美しい長者の娘。
- 二人の男が一度に娘を好きになり、娘は思い煩った挙句、淵川へ身を投げて自死。
- 死に際に「あきづけば をばなが上に置く露の けぬべくもわは おもほゆるかも」という和歌を残した。
二人の男に懸想された長良の乙女、どちらか一方を選べば、傷つけたり、争いになったりすると考えたのでしょうか。それより自分が消えることを選び、淵川へ身を投げました。儚く消えた彼女ですが、美しい和歌を残しました。
秋づけば 尾花が上に 置く露の 消ぬべくも吾は 思ほゆるかも
本当は万葉集の和歌ですが、「長良の乙女」の気持ちになって意味を考えると、
(秋になって すすきの穂にかかる露が 儚く消えるように 私も消えてしまおうと思うのです)という感じでしょうか。
「長良の乙女」のように、二人の男に求婚されて女が命を落とす物語は、
「大和物語」等にもある、典型的なものです。「人情」の板挟みで死んでしまった可哀想な女の物語だけど、「人情」を存分に表現した日本の和歌、和歌を中心に構成された歌物語って「あはれ」でしょう、というのが、画工の意図です。
画工編「人情」は、和歌が栄えた平安時代の空気に半分浸っています。画工と那美さんの出会いの場面も、その影響を受けました。
真夜中に那美さんの影だけを見た画工は、その姿を俳句に詠みます。うとうとと眠りかけたところへ部屋に忍び込む女の幻に、妖しい気分になります。那美さんが画工の寝た頃を見計らって、こっそり自分の着物を取りに来たのでしょう。ついでに、画工の枕元に置いてあった写生帖をそっと持ち出したはずです。翌朝、彼が風呂に入っている5分間の間に、またこっそり部屋に戻しておきました。そして風呂上り真っ裸の画工の前に、いきなり現れて、後ろから着物を着せかけてくれました。
この時初めて、二人はお互いの顔を見たのです。画工は、生まれたままの姿を見られてしまいました。部屋に戻った彼が写生帖を見ると、昨夜作った俳句に対して、添削のような返句のような句が書いてあるのを発見します。
二人の出会い方、まるで・・・顔も見ないまま歌を贈り合い、暗闇の中で契り、翌朝ようやく相手の正体を見る平安王朝の恋人たち、みたいでしょう?和歌という文芸を花開かせた、宮廷貴族の恋の形式を真似てみたのです。
明るい光の下、 画工は那美さんの顔をじっくりと観察します。2章で茶店の婆さんの顔をものすごく褒めていたのに、那美さんに対しては、とても手厳しいのです。しかしここで、彼自身の弱点も露見しました。那美さんの顔をけなすついでに、こんな事を言ってしまいました。
このゆえに動と名のつくものは必ず卑しい。運慶の仁王も、北斎の漫画も全くこの動の一字で失敗している。
『草枕』3章
この見解は、画家として偏りすぎですね。那美さんを見習って『遠羅天釜』を読んだほうが良いでしょう。「静」と「動」両方の大切さが書いてありますから。
それでも画工の観察の目は確かです。那美さんの表情に、複雑な心境が表れていることは間違いありません。まだ20代半ばの那美さんですが、当時の女性としては「出戻り」という苦しい立場です。
『この女の顔に統一の感じのないのは、心に統一のない証拠で、心に統一がないのは、この女の世界に統一がなかったのだろう。不幸に圧しつけられながら、その不幸に打ち勝とうとしている顔だ。不仕合な女に違いない。』と断定します。
ただ表面的に見れば、彼女はなかなかの美人、粋でお洒落で、気の利いた会話ができる魅力的な大人の女性です。3章の終わり、画工は那美さんの後ろ姿をじっと見つめます。
「ほほほほ御部屋は掃除がしてあります。往って御覧なさい。いずれ後ほど」 と云うや否や、ひらりと、腰をひねって、廊下を軽気に馳けて行った。頭は銀杏返に結っている。白い襟がたぼの下から見える。帯の黒繻子は片側だけだろう。
『草枕』3章
那美さんの髪型は、漱石作品では定番の銀杏返し、着物については「不断着の銘仙さえしなやかに着こなした」と12章に記述があります。銘仙というのは、着物の格としては木綿の次に低く、実直でカジュアル、レトロモダンな雰囲気の大胆な柄のものが多いです。上の引用文に、帯の描写があります。「帯の黒繻子は片側だけだろう。」これはおそらく裏側に黒いサテン地を使ったリバーシブルの半幅帯を斜めに折って、左右非対称に裏の黒を見せて結んでいます。粋で気取りのない着こなしの彼女の帯の結び方は、色っぽい“片流し”でしょうか。画工はその後ろ姿を見つめながら、(あの帯は簡単に解けるのではないかしら)と誘惑を感じたに違いありません。この時の気持ちを正直に詠んだ句を13章で披露しています。
春風に 空解け繻子の 銘は何 ―『草枕』13章
(やわらかな春風に 自然と解けてしまいそうな繻子帯の あの粋な女は何者だろうか。)
4章 「画工の人情・余韻」の4章ですから、「非人情」を気取る画工もずいぶんと「人情」に立ち寄ってしまいます。昼食を運んできた小女郎に、那美さんについて詮索する質問をしつこく浴びせます。昼食後も部屋でごろごろしながら、(もしあの銀杏返しに懸想したら・・・・)と英詩を思い浮かべたり、本当に恋をしてしまったらどんなに苦しいだろう、と想像します。 そんな彼の気持ちを察してか、那美さんがお茶と羊羹を持って、部屋に来てくれました。二人は色々と話をします。なかなか手応えのある反応をする那美さんです。画工が長良の乙女の詠んだ和歌を「あの歌は憐れな歌ですね。」と言いますが、彼女は同意してくれませんでした。
「どうれで、むずかしい事を知ってると思った。――しかしあの歌は憐れな歌ですね」
『草枕』4章
「憐れでしょうか。私ならあんな歌は咏みませんね。第一、淵川へ身を投げるなんて、つまらないじゃありませんか」
「なるほどつまらないですね。あなたならどうしますか」
「どうするって、訳ないじゃありませんか。ささだ男もささべ男も、男妾にするばかりですわ」
「両方ともですか」
「ええ」
「えらいな」
「えらかあない、当り前ですわ」
この会話の後、鶯が「ほーう、ほけきょーう。」と囀ります。すると那美さんが「あれが本当の歌です」と言ってのけました。例の和歌を夜中に繰り返していましたが、これは画工の頭の中を読み取って演技をしていただけであって、彼女自身は「長良の乙女」にまったく共感できない様子です。勝気な那美さんは、男二人に挟まれて、進んで犠牲になる女を美しいとするような物語には感動できない。鶯の鳴き声のような自然の美こそ本物の美なのだ!と言いたいわけです。
次は、10章 那美編の「人情」で彼女の主張を見ていくのですが、その前に「休憩の9章」で起きる重要な出来事について考えます。