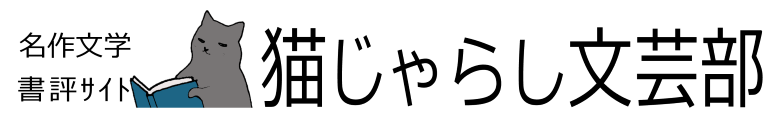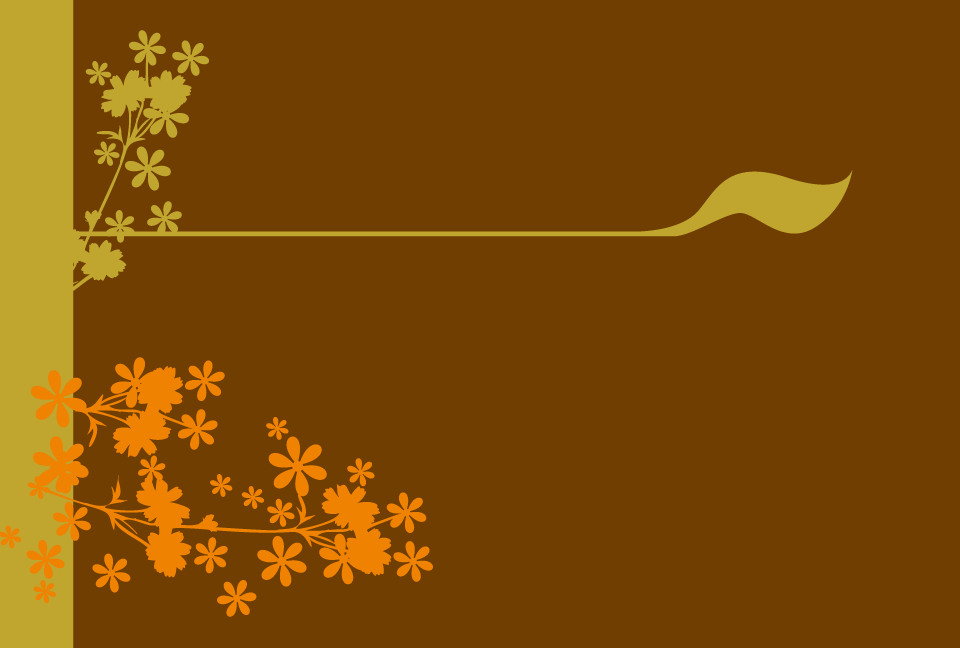酒に入り浸る詩人の大谷は、自身をヴィヨンになぞらえて芸術の苦悩を理由に、今宵も飲み歩いている。そして行きつけの料理屋で金を奪い盗人を働く。それでも自分は、神におびえるエピキュリアンとうそぶく。妻の幸子は夫の飲み代を料理屋で働いて返そうと考える。戦後の混乱の中、社会が倫理を見失い、悪徳が栄えまかり通る。そんな時代には生のみを肯定する強さこそが求められる。神を信じない逞しくなっていく妻が夫を支える物語。
登場人物
私
大谷の妻、夫の借金の返済に椿屋で働くことで自身の考えが変わっていく。
大谷
破天荒で無頼な詩人、いつも酒に酔って違う女性を連れている放蕩な夫。
動画もあります!こちらからどうぞ↓
解説
タイトル『ヴィヨンの妻』のヴィヨンは、フランソワ・ヴィヨンという15世紀フランスの人で、中世最大の詩人とも最初の近代詩人とも呼ばれるほどの名を残します。
パリに生まれパリ大学に入学しますが、在学時から売春婦やならず者といった輩と行動を共にし、乱闘騒ぎでついに司祭を殺してしまいパリから追放される。
それからも窃盗団に加わったり淫売宿で傷害事件を起こしたりと投獄と出獄を繰り返し、無頼・放浪の日々を送り、波乱万丈の人生だった人です。
この作品は、放蕩三昧の詩人と内縁の女性の話ですが、悲嘆にくれたり、家を出ていったりするのではなく、そんな夫を逞しく支える妻の姿を、太宰お得意の女性の独白で描いています。
夫の浅慮な行動に、呆れ果て笑いだす妻。
昭和二十一年の暮れのことです。いつもと同じように、その日も夫は、泥酔して深夜に慌ただしく玄関をあけて帰ってきました。ただ珍しく「坊やはどうですか」と気遣う。子供は栄養不足で発育も遅く、体も弱い。しかし医者に見せようにも、我が家にはお金がない。
どうもこの夫はきちんとお金を家には入れず、飲み歩いているようです。
突然、玄関から男女の叫ぶ声が聞こえる。大谷が何かしでかした様子だ。夫と男は、もみ合いになり夫はナイフをちらつかせ「放せ!刺すぞ」とかわして外に逃げていった。
男女は夫婦で、中野で「椿屋」という料理屋を営んでいるという。二十年前に東京に出てきて苦労して店を持ち、今は闇酒を仕入れて売っている。大谷との出会いは、昭和十九年の春、新宿のバーにいた秋ちゃんという女性に連れられて初めてやってきたという。
椿屋とバーはお互い客を紹介しあう関係で、大谷もその一人だったという。
それが魔物と会った初めての日だった。
その時は女性が勘定を払ったが、一か月後、大谷が一人で入ってきて、いきなり百円紙幣を出して酒を飲んだ。
いやその頃はまだ百円と言えば大金でした、いまの二、三千円にも、それ以上にも当る大金でした、それを無理矢理、私の手に握らせて、たのむ、と言って、気弱そうに笑うのです。
ここでは、戦中の統制経済から、戦後のインフレで通貨価値が大きく変化しているのがわかります。つまり、約三年で通貨価値は三十倍、この後インフレは、さらに加速していくことになります。無頼気取りの大谷は、原稿料か何かをまるごと主人に渡したのでしょうね。話を元に戻します。
大谷は酒に強く、大酒飲みだった。後にも先にもお金を払ったのはこれきりで、以降は現在まで一銭も払わずに店の酒をひとりで飲みほすほどに飲んだ。
話を聞くと、幸子は、思わず噴き出してしまいます。するとおかみさんもご亭主もつられて笑いだす。
まぁ、何というか、大谷の性格にほとほと呆れている感じでしょうか。
じゃ、大谷という男はどんな人物かということになる訳ですが・・・
この椿屋の夫婦だけではなく、秋ちゃんも大谷に見込まれてしまい、お金も着物も無くし今では貧乏な長屋住まいだが、知り合った頃は、のぼせていて、
だいいち、ご身分が凄い。四国の或る殿様の別家の、大谷男爵の次男で、いまは不身持のため勘当せられているが、いまに父の男爵が死ねば、長男と二人で、財産をわける事になっている。頭がよくて、天才、というものだ。二十一で本を書いて、それが石川啄木という大天才の書いた本よりも、もっと上手で、それからまた十何冊だかの本を書いて、としは若いけれども、日本一の詩人、という事になっている。おまけに大学者で、学習院から一高、帝大とすすんで、ドイツ語フランス語、いやもう、おっそろしい、何が何だか秋ちゃんに言わせるとまるで神様みたいな人。
そして椿屋のおかみさんまで熱を上げていた。
しかし大谷は、自身の出自や学識を偉ぶることなく、言葉少なに静かに酒を飲む。そんな佇まいが、まさか悪い人ではあるまいとなるわけです。だけど実は、たいへんな男だった。
どこか嫌いになれない魅力はあるけれど、見込まれてしまうと、大変なことになると云うのです。だから魔物だっていうんでしょう。
そしてご亭主は不満げに、言う。
いまはもう、華族もへったくれも無くなったようですが、終戦前までは、女を口説くには、とにかくこの華族の勘当息子という手に限るようでした。へんに女が、くわっとなるらしいんです。やっぱりこれは、その、いまはやりの言葉で言えば奴隷根性というものなんでしょうね。
こんなやりとりのなかにも、戦後の華族令の廃止とそれ以前の比較があり、以前は一応、四民平等ですが華族だけは特権でした。さらにはGHQ統治下における日本人の意識、つまりは隷属意識を感じさせられる。
大谷は、家柄も良く教育もあり慎ましくどこか浮世離れした哲学者のような感じで、不思議な人間として描かれます。ただし大酒のみで金を払わず女に寄生している。
稀代の詐欺師か天才かのどちらかだというのでしょう。
大谷はお金を払わず、代わりに年増女の秋ちゃんや別のお金持ちそうな奥さんが払うこともあったが、とにかく大酒のみなので十分な額ではなかった。やがて大空襲の連続となる。
つまり昭和二十年三月から始まった東京大空襲を指していて、ここでは多くの死者が出ています。
そんな時も大谷は店に来て酒を飲む。終戦になると闇の酒や食料をふるまえるようになり、今度は新聞記者たちと来るようになるが、ここでも金を払わず酒を飲む。
終戦後は一段と酒量もふえて、人相がけわしくなり、これまで口にした事の無かったひどく下品な冗談などを口走り、そして椿屋の若い女給にも手を出していた。
そして、大谷はついに “どろぼう” をはたらく。
亭主が仕入れ用にと年末に集金した五千円を、店に来た大谷がわしづかみにして出ていったとのこと。
またもや私は、わけのわからぬ可笑しさがこみ上げ、声をあげて笑い、涙が出て、大谷の詩の中にある「文明の果ての大笑い」のことを考えた。
私は、警察沙汰のするのは一日、待ってくださいとお願いし、お金の返済を約束して、夫婦にその夜はひきとってもらった。
ヴィヨンの題に涙し、途方に暮れる妻。
ついに泥棒までしてしまった夫の恥ずかしい行為、何とかお金を弁償しなければならない。さりとて妻の幸子に金の貯えはなかった。
そもそも大谷との馴れ初めは、父のおでん屋を私が手伝っているとき、客だった大谷と付き合い始め、そして子どもが出来た。籍にも入っていない。私は内縁の妻であり、子供は父無し子だ。
大谷はいつも外で飲み歩き、どこで何をしているか分からない。たまに帰ってきても、私の体を抱きしめて
「ああ、いかん。こわいんだ。こわいんだよ、僕は。こわい!たすけてくれ!」
とがたがた震えたりする。
大谷は繊細で情緒が不安定なようですね・・・・。
私は坊やを背負って、とにかく行動を、と電車に乗って井の頭公園に行く。お金の返済に途方に暮れる幸子。車中の雑誌広告に目をやると、
夫が「フランソワ・ヴィヨン」の論文を発表しているのを見つける。私はその<フランソワ・ヴィヨン>という題と<夫の名前>を見つめているうちに、辛く涙をこぼしてしまいます。
が・・・ここで覚悟するのです。
返済のあてなどどこにもない「私」は、とにかく中野にある夫婦の店に行き、金の手立てはついたとその場を繕います。
ご亭主は不在だったがおかみさんがいて、とっさに
「あの、おばさん、お金は私が綺麗におかえし出来そうですの。今晩か、でなければ、あした、とにかく、はっきり見込みがついたのですから、もうご心配なさらないで」
と言い
「確実にここに持ってきてくれる人があるので、それまで人質になって、ここにいることになっている。」
と続け、そして店を手伝うと言ってしまった。
帰ってきた店のご亭主にも同じことを伝える。ご亭主は、
「へえ? しかし、奥さん、お金ってものは、自分の手に、握ってみないうちは、あてにならないものですよ」
と教えさとすような口調で言う。そうこうするうちに客が入ってきた。
賑わいの中で、新しい自分を発見する妻。
とっさに、幸子は店の手伝いをする。客の下卑たひやかしにも、何なく下卑てこたえる。
その日は、クリスマスの前夜祭で店は賑わう。私は、羽衣一枚をまとって舞うように身軽に立ち働き、自惚れかもしれないが、店は異様に活気づき私は店の人気者だった。
奇蹟はやはり、この世の中にも、ときたま、あらわれるものらしゅうございます。
九時過ぎにクリスマスのお祭りの紙の三角帽で顔の半分を仮面で隠した男と、三四.五歳の綺麗な奥さんが入ってきた。私はすぐにそれが “どろぼうの夫” だと解った。
私は、
「クリスマスおめでとうって言うの? なんていうの? もう一升くらいは飲めそうね」
と夫に挨拶をする。
奥さんは、ご亭主に話があると言う。私はご亭主を呼ぶと、
ご亭主は
「いよいよ、来ましたね」
と言った。
そして三人で店を出ていった。私は「万事が解決したのだ」と信じられてうれしかった。
そして、
「飲みましょうよ、ね、飲みましょう。クリスマスですもの」
三十分もせずにご亭主が帰ってきて
「奥さん、ありがとうございました。お金はかえして戴きました」
しかし亭主は、大谷にはまだ二万円ほどの借金が残っていると言う。幸子は、ここで働いて返すことを願い出て了承される。
ほんとうに奇跡が起こり、京橋のマダムが難を救ってくれたと幸せになると同時に、幸子は何故、これまで椿屋で働くという名案を考えつかなかったのだろうと後悔する。
聞けば、夫は昨夜どこかで泊まり、けさ早く綺麗な奥さんの営む京橋のバーを襲い、朝からウィスキーを飲み店で働く五人の女の子にクリスマスのプレゼントといって金を振る舞い、デコレーションケーキや七面鳥を買い、知り合いを呼び大宴会を開いたようだ。
いつも金の無い大谷を不審がったバーのマダムが聞くとあの五千円の話だった。警察沙汰を心配しマダムがお金を立替えてくれたのだった。
ご亭主が「よくそこまでお見通しでしたね」と聞くので、私は「ええ、そりゃもう」と答えておいた。この返済に充てられたお金だって、大谷とマダムとの個人的な関係、つまり大谷はマダムのヒモのような存在なのです。
辛さを楽しさに変え、逞しく夫を支える妻。
幸子一人の力で返す方法は唯一 “椿屋で働く” しかない。ここで恥や屈辱を顧みず女給となって働くことを決心したのです・・・
が、思わず、これが楽しい。
夫にも会えるし、おでん屋の経験もあり客あしらいもうまくできる。
それからの私の生活はまるで変わり、浮々した楽しいものになった。店に出るために髪を手入れし化粧品も揃え着物を縫い直したりした。朝起きて坊やと二人でご飯を食べて、坊やを背負い中野へご出勤となった。
お店での名前は “さっちゃん” で、椿屋のさっちゃんは、大みそか、お正月と毎日、目の廻るような忙しさで二日に一度は夫も店に顔を出し、一緒に楽しく帰ることもあった。
「なぜ、はじめからこうしなかったのでしょうね。とっても私は幸福よ」
と夫に言うと、
「女には、幸福も不幸も無いものです」
と言う。
「そうなの? そう言われると、そんな気もして来るけど、それじゃ、男の人は、どうなの?」
と訊ねると、
「男には、不幸だけがあるんです。いつも恐怖と、戦ってばかりいるのです」
と言う。
幸子は、大谷が椿屋のおかみさんもかすめたことを問い質す。
すると大谷は、
「僕はね、キザのようですけど、死にたくて、仕様が無いんです。生れた時から、死ぬ事ばかり考えていたんだ。皆のためにも、死んだほうがいいんです。それはもう、たしかなんだ。それでいて、なかなか死ねない。へんな、こわい神様みたいなものが、僕の死ぬのを引きとめるのです」
と言う。
そして
「おそろしいのはね、この世の中の、どこかに神がいる、という事なんです。いるんでしょうね?」
と確認するように言う。
自分が悪いのは分かっているが、そんな自分の性格を自分で恐れているようです。まぁ、これって都合の良い言い訳ですよね。
そして十日、二十日と店にかよっているうちに、お客さんがひとり残らず犯罪人ばかりだという事に、気がついてくる。路を歩いている人みなが、何か必ずうしろ暗い罪をかくしているように思われてくる。
そして悲惨なことが起こります。
神がいるなら、出てきてください! 私は、お正月の末に、お店のお客にけがされました。
それは初めて見たお客さんでした。人を疑うことを知らなかった幸子は、どしゃ降りで終電がないなか、頼まれて家の玄関口に泊めた男の手にいれられました。好意のつもりが、騙されてしまたのです。
それでも何もなかったかのように、うわべは同じ様にお店に勤めにでかけました。
幸子は、神なんかはいないと確信し、信じないことに決めたのでしょう。
そして、以前にも増して強くなります。
お店では土間で、夫が酒を飲み新聞を読んでいます。私は家を引き払って、これからは椿屋に住み込もうと思うと話し、夫も同意します。
大谷は、自分のことを “エピキュリアンのにせ貴族” と書いている新聞に対して “神におびえるエピキュリアン” だと訂正します。さらに “人非人” と形容されていることに、「今だから言うけれど “あの五千円” は、さっちゃんと坊やにいいお正月を過ごさせたかったからだ」と嘯きます。
ほんとうに、大谷ってひどい夫ですよねぇ・・・・。
私は格別うれしくもなく、
「人非人でもいいじゃないの。私たちは生きていさえすればいいのよ。」
と言うのでした。
本作品のメッセージと感想
「フランソワ・ヴィヨン」の論文とは何だったのか?
電車のなかの雑誌の広告を見て、「私」は、なぜか悲しく涙がにじみます。
論文を書くのですから、大谷は有名な詩人であり評論家でもあるのでしょう。幸子は、ヴィヨンのことなど知らないでしょう。当然、論文の中身も知らないわけです。
涙が出るのは、酒浸りの夫と無力な自分という我が身の惨めさからでしょうか。あるいは、自身の運命というかめぐり逢わせへの戸惑いでしょうか。
夫は、ついにどろぼうまで働いたのです。返すあてのないお金の返済について頭がいっぱいでしょう。
しかし幸子は、ここで何故か、これまでの “諦観”から“生きる逞しさ”へと変身するのです。
夫の放蕩三昧や貧乏暮らしを、泣き笑いでは解決できないことを知ります。“椿屋” で働くことを「私」は決心します。そしてはじめて目に映る風景、幸子は世間を知るのです。
見渡せば、戦後の荒廃の中で、酷い行為が横行し、後ろ暗い罪を隠して生きている人々ばかりです。そこには、道徳や倫理などの奇麗ごとは通用しません。
「夫などはまだ優しい方だ」と思うようになります。
借金の返済のため、身を落とす覚悟の料理屋の手伝いだったのですが、思いのほか “生” を感じる「私」は 、ここで夫の借金返済、つまり尻拭いの “覚悟” を決めます。
思いもよらぬ客の一人に汚された不幸な一夜が起こります。そして自分も夫への隠し事をひとつ持ちます。でも挫けません。
荒すさんだ時代を生き抜くうえで、些細な出来事と思うようにします、神などいないのです、信じても頼っても救ってくれたりはしないのです。
大谷は、男には不幸しかないと言うが、芸術を信じながら、無頼を装うだけの気の弱い男です。大谷は、生まれながらの自分の自堕落な性癖に対して神を畏れます。
しかし幸子は神を畏れません。逞しい妻に変わりました。
「フランソワ・ヴィヨン」の論文とは何か? これは推測ですが、
ヴィヨンの放蕩で波乱万丈の人生のなかでこそ生まれた素晴らしい詩作を大いに評価すると同時に、自分はまだまだ足元にも及ばないが、素晴らしい伴侶を得なかったことが悔やまれる・・・。
なんて書いていたかもですね。
そこで作品のタイトル『ヴィヨンの妻』は、幸子への感謝ということになるのです。
太宰晩年の作品、自身の業を夫婦の人間ドラマに描く。
作品は昭和二十一年(1946年)の年末から翌年の一月中旬にかけて執筆されています。物語もクリスマスや新年を挟んでいます。太宰、三十七歳。自殺の一年前です。
終戦の詔書、玉音放送の翌年にあたります。物語では、時間軸に沿うように戦中・戦後の社会の様子が描写されていきます。
昭和二十年八月十四日を境に、天皇を元首とした体制が変わり、主権は国民となります。
まさにこれまでの価値が崩壊します。新しい時代を期待する人と同時に、信じるものを失い不信感に包まれる人も多かったのではないでしょうか。
主人公の大谷は、生そのものの意味を失い自堕落な無頼が加速する。
日本人は天皇という絶対の権威を失い、誰もが平等となり、GHQに統治される。物資のないなかで、倫理観を失い、生きるために多くの人々が闇屋をはじめ何らかの悪事を働き、食べる ことを優先します。
それでも大谷はどこかに神の姿を見ている。自身を“神におびえるエピキュリアン”と称し、妻の幸子は、「とにかく生きていればよいと」いう。
男は観念的で弱いが、女は現実的で強いということだ。
戦後の混迷期、道徳は無くなり、悪は栄え、誰もが生きることに懸命な時代だったのでしょう。
『ヴィヨンの妻』は、ヴィヨンのように生きたい大谷という放蕩な詩人と、幸子という無頼派気取りの弱虫な夫を支え愛する妻がいるというお話なのです。
自分はヴィヨンになりたいから、君はヴィヨンの妻になってくれ。そして人非人の僕を受け入れておくれ!というお話です。
太宰が大谷と幸子を演じる一人二役の物語ですね。
実生活における太宰は、酒と薬物に苦しみ自殺未遂を何度も繰り返しましたが、恩師、井伏鱒二の紹介で昭和十四年に再婚し、その時の「結婚誓約書」には、これまでの乱れた生活を反省、家庭を守る決意をして「再び破婚を繰り返した時には私を完全の狂人として棄てて下さい」と書いてあったといいます。
結婚して妻を得て、子ができて家庭を持ち、そして作家という人生を太宰は演じているのです。
いつもながらの自己中な太宰ですが、晩年の太宰は芸術に生きながら、家族といる現実に、不自由さや罪悪感もあったのかなと思えてしまいます。
しかし戦争が終わり、疎開していた津軽から東京の三鷹に戻り作家として忙しくなっていくと同時に、またその性癖は繰り返されることになります。 そして作品の翌年、愛人と入水自殺をしてしまいます
※太宰治のおすすめ!
太宰治『人間失格』解説|ただいっさいは、過ぎて行くということ。
太宰治『道化の華』解説|人と繋がるための道化と、弱者への慈悲。
太宰治『斜陽』あらすじ|恋と革命に生きる、新しい女性の姿。
太宰治『走れメロス』解説|愚かでもいい、ヒロイックに生きる。
太宰治『水仙』解説|芸術家は自分の才能を信じ、世評を気にせず。
太宰治『きりぎりす』解説|お別れします、妻から夫への告白。
太宰治『ヴィヨンの妻』解説|神を信じぬ逞しさと、神におびえるエピキュリアン。
太宰治『桜桃』あらすじ|子育てと家事を横目に、創作の苦労を描く。
太宰治『グッド・バイ』あらすじ|人生即別離、さよならだけが人生だ。
作品の背景
太宰晩年の作品にあたります。1946(昭和21)年1月に再び戦後活躍の幕があがります。4月には戦後初の衆議院総選挙が行われ長兄の文治が当選。11月には疎開していた津軽から帰京します。東京の三鷹に住む太宰は、この小説の中で中野、吉祥寺、小金井と周囲の町が舞台にします。GHQの統制にありながらも積極的に創作活動を行います。
発表時期
1947(昭和22)年「展望」3月号に発表。後、8月に筑摩書房から刊行。太宰治は当時37歳。この年の春に「斜陽」のモデルとなる太田静子を訪ねます。また山崎富栄ともこの時期に知り合います。3月には、次女が生まれています。