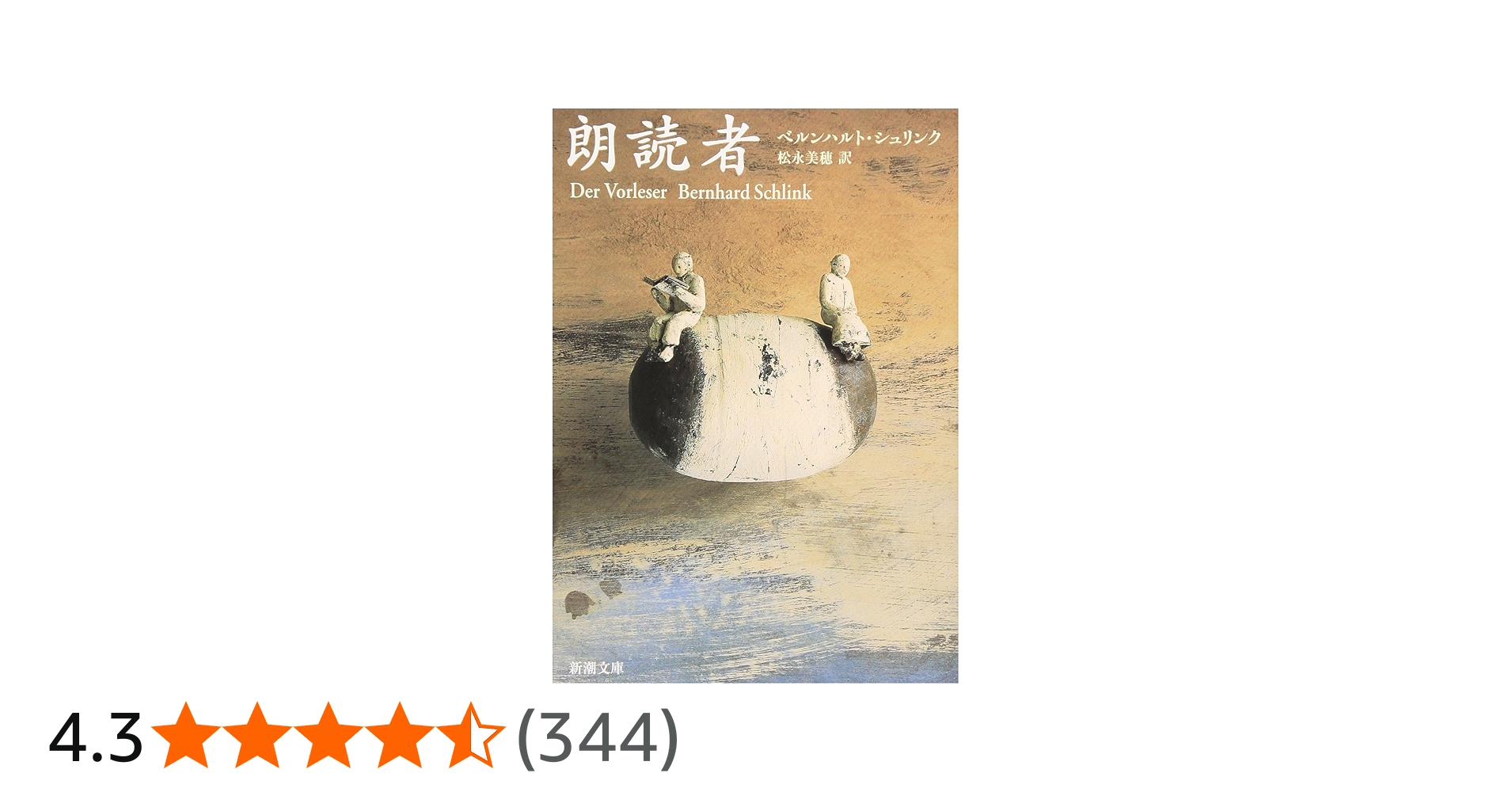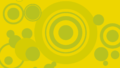文盲だったハンナは、自身の尊厳のために罪を一人被った。
読み書きができない恥ずかしさがほんとうに裁判や収容所での態度の原因なのだろうか?字が読めないことを隠すために犯罪者であることを自白し、文盲の露顕を恐れ、犯罪を犯したのだろうか?
彼女の人生では、出発は大きな後退を、勝利は密かな敗北を意味していた。
ミヒャエルが行動できることは、裁判長のところへ行き、ハンナが文盲であることを話し、他の被告人たちがでっち上げようとする主犯ではないこと。有罪かもしれないが、見かけほど重罪でないこと、を告げることだった。
しかし彼女はそれを望んでいなかった。
ハンナは、文盲であるという事実を秘密として隠して生きてきた。それはナチス親衛隊としての犯罪を引き受けること以上に、認めてはならないことだった。そしてロマの民族も、ヨーロッパにおいて迫害を強いられているもう一つの悲劇でした。それは、ヨーロッパの秘密性でありロマへの民族差別でした。嘘をつくことと、秘密を持つことは本質的に違います。
この物語は、秘密を隠し守りながら生きていかねばならない人間や、人間がつくった価値や差別と同時に、そこで苦しめられる人々の運命を感じさせます。
裁かれるべき法の精神を超えて、ハンナには守りたい秘密があったのです。
ミヒャエルは父と話そうと決心した。道徳的問題に関わったカントやへーゲルについて著書を著した哲学者との会話だった。
父は、それは「幸福」についてではなく、「自由と尊厳」の話だと言った。
裁判所の人々は二週間、イスラエルに飛んだ。事情聴取には何日もかからなかった。裁判官と検事たちは法的な仕事と観光を結びつけていた。
ミヒャエルはアウシュヴィッツ収容所で命令する看守のハンナと、出会ったときの恋に落ちたハンナを空想した。それはハンナについてのミヒャエルの記憶を解体し、頭の中の収容所の世界と結びついた。
しかし知っていることは、アウシュヴィッツに関しても、ビルケナウに関しても、ベルゲン・ベルゼンに関しても多くはなかった。世間の人々の頭に固定されている収容所の共通のイメージだった。
ミヒャエルは一番近いシュトルートホーフの強制収容所に出かけてみることにした。行き先を告げると、ヒッチハイクで乗せてくれたトラックの運転手が言った。
「人間がどうしてそんな恐ろしいことをすることができたのか、理解したいというんだね。」
人が情熱によって人を殺す、愛のため、憎しみのため、名誉や復讐のために人を殺す。金持ちに、あるいは権力者になるために人を殺すこともあるし、戦争や革命の際に人殺しをすることもある。
死刑執行人だって自分が処刑する人を憎んでいるわけではなく、それでも刑の執行はする。それは命令や服従からではなく、自分の仕事をしただけだ。
運転手はロシアでのユダヤ人処刑の写真を見たことがあると言い、そのときの将校の様子を話した。ミヒャエルは「あなたがその将校だったんですか?」と尋ねた。彼は車を止めて真っ青になって「降りろ!」と言った。
この会話が真実だとすれば、ロシアでもユダヤの迫害があったということである。そして社会に組み込まれてそれぞれの過去を持つ人々が生きている。ナチス・ドイツの親衛隊としてホロコーストに加担した人々も、あるいは他国の人々も複雑な思いに苛まれながら戦後から現在までを生きているのである。
ユダヤのホロコーストに隠された、ロマの人々の悲しい運命。
判決が下った。ハンナは無期懲役になった。他の被告たちはもっと期間の短い懲役刑だった。
ハンナは黒いスーツに、白いブラウスという服装だったが、それは親衛隊で働いていた制服のように思えた。親衛隊のために働いていた女性、ハンナは告発されたような犯罪をすべてやってのけた女性という感じだった。
判決理由が読み上げられ、裁判が終わり、被告が連れて行かれるときハンナが見てくれるのではと期待したが、彼女はまっすぐに前を向き、突き抜けるような目をしていた。高慢な、傷ついた、敗北し、疲れた眼差し。誰も見ようとしない目だった。
ここでハンナには殺人罪が言い渡され、他の五人は共犯と幇助の罪となります。ハンナは<未必の故意>によって裁かれたのです。殺人罪として終身懲役に処せられます。他の被告に比べれば、途方もなく大きな刑量の差であるにも関わらず、ハンナにとって事実を明かすことは、何よりも「恥ずかしい」ことなのです。
ミヒャエルが大学を卒業し、司法修習生になったとき、学生運動の夏がやってきた。
ナチズムの過去との対決は学生運動の本当の理由ではなく、世帯間の葛藤の表現だった。親世代は第三帝国あるいは崩壊後において、誤った行動をとったということで片づけられてしまった。
ナチの犯罪に手を染めた者、傍観していた者、目をそらしていた者。あるいは戦争犯罪を追及しないどころか、戦犯を受け入れてしまった者。その子供たちにとっては、自分自身の問題だった。
ミヒャエルは、自分がハンナを愛することによる苦しみが、運命であり、ドイツの運命を象徴していていることが、この世代に属しているという感覚で心地よいものだった。
ミヒャエルは修習生のときに結婚をした。その後、子供も授かった。
しかしいつまでもハンナと過ごしたことが忘れられない。何かが違うと感じる。ハンナのさわり方、感じ方、匂い、味、すべてが間違っていると思った。そして娘が五歳のころ離婚する。
朗読テープを送り続け、ハンナは読み書きができるようになる。
修習期間が終わり、仕事を選ばねばならなかったが、ハンナに対する裁判の記憶があり決断は難しかった。告発という仕事は弁護と同じくらいグロテスクな単純化に思え、裁くことは一番のグロテスクな行為だった。
ミヒャエルは法吏学者となった。研究分野は第三帝国の法律だった。啓蒙主義時代の法律や法案を研究しているときは人間中心の考え方で幸福な気分になった。
やがてミヒャエルは朗読をしたものをテープに吹き込み始めた。全体として市民的教養のある人には馴染みのものばかりだった。そしてハンナに送った。
ハンナはミヒャエルにとって、すべての力、創作力、批判的想像力を束ねる存在だった。彼女の服役八年後から十八年目まで続いた。十八年目に恩赦が認められた。
接触の四年目に挨拶が届いた。「坊や、この前のお話は特によかった。ありがとう。ハンナ」
「彼女は書ける、書けるようになったんだ」ミヒャエルは驚き感動する。
文盲であるということは、市民として成熟に達することができない。ハンナが読み書きを習う勇気を持ってくれたことは啓蒙への一歩だった。しかし同時に、その努力が遅すぎたことや、彼女の人生が失われたことを悲しくもあった。
そして一定の間隔で手紙が届くようになる。
刑務所で気づいたことや自然に感じたことが書かれ、手紙には季節を感じた。文学については、ハンナは驚くほど正確に作家の個性を言い当てた。
ミヒャエルからハンナへ手紙はなかったが、朗読テープは送り続けられる。朗読が彼の流儀であり、話しかけ、ともに話をする方法だった。
自身の文盲の理由を、誰に確かめることもなく生きるしかない人生。
そして再び恩赦願いによりハンナは十八年の服役生活に終止符をうって出所することになる。その際のささやかな世話を依頼された。
ミヒャエルは、出所後のアパートや仕事の手配を済ませていたが、彼女と会うことは伸ばしていた。ハンナとは自由な関係で、お互い近くて遠い存在だったから、彼女を訪問したくなかった。
朗読テープという挨拶とカセットだけの小さくて軽くて安全な世界は人工的で脆く、実際の近さには耐えられないのではと不安だった。ついにハンナの恩赦の決定が下り、来週出所の予定で、刑務所に出向くよう依頼の電話があった。
次の日曜日、彼女のところへ行った。
ベンチに座っている女性、それがハンナだった。灰色の髪で、額にも頬にも深い縦皺が刻まれていた。「大きくなったわね、坊や」とハンナは言った。
ミヒャエルは、記憶の中の彼女の匂いを思い浮かべたが、目の前のハンナは老人のような外見で、老人のような匂いになっていた。アパートや仕事のことを伝え安心させ元気づける。
ミヒャエルが「裁判で話題になったようなことを裁判前に考えなかったのか?」と訊ねると、
ハンナは「誰にも理解してもらえないし、どうしてこうなってしまったかも、誰も知らない。誰にも理解されないなら、誰に弁明を求められることもない。裁判所も私に弁明を求める権利はない、ただ死者にはそれができる。死者は理解してくれる。その死者たちがたくさん自分に訪れたという。裁判所ではなく死者だけが彼女を責めることができるのだ」と語った。
迫害された死者たちの言葉が、ハンナに語りかけてくる。ここには文盲を克服し言葉を理解でき正しい知識を獲得したハンナが、ミヒャエルへ送っていた手紙以上に、自己を確認していた。ナチスの現実を学んだのである。そしてその表現には自身の冒した罪の意識とともに、自分の出自の運命の謎に深いところで同期し共振している。
ハンナは自身の尊厳のために自死の選択をした。
翌朝、ハンナは死んだ。夜が明けるころに首を吊ったのだった。
刑務所の所長にハンナの独房を案内してもらう。そこはきれいに整頓されていて、棚のところにはナチの犠牲者たちの本と並んで、アイヒマン裁判についてのハンナ・アーレントのレポートや強制収容所についての研究書もあった。
ベッドの上には絵や紙切れがぶらさがり、詩は自然についての喜びやあこがれに満ちていた。絵にもさまざまな自然が描かれていた。
カセットに吹き込まれた本を図書館から借りて字を一語一語、一字一字、たどって学んだ。読み書きができるようになったことを誇りに思ったようだった。ハンナは銀行に入っている七千マルクを教会の火事の際に生き残った親娘に渡してほしいと、ミヒャエル宛てに手紙を残していた。
ハンナにとって刑務所は修道院のような生活の場だったと聞く。他の囚人たちからの人望も厚く、一種の権威のようなものもあった。しかし彼女はそれを投げ出してしまう。もっと孤独な庵へ、誰からも見られない世界へ、そして自分の居場所を正しく定義した。自分にとって正しいやり方で。
ハンナはナチス・ドイツの行ったユダヤ人へのホロコーストの事実を知る。すでに十五年目の収監を迎えたころには、ハンナは自身に気を使わなくなっていく。迫害を呪う自身が加害者となったことの取り返しのつかない自責の念であり、ロマである自分には生きる望みはもう無かったのかもしれない。
ハンナは、その出自を静かに受け入れ、プライドを持って死んでいく。
安置された遺体を見ると、死んだ顔の中に、生き生きとした表情が、老いた顔の中に若いときの顔が表れるように感じた。
秋になってミヒャエルは、ハンナの遺志を実現した。生存した娘をニューヨークに訪ねた。途中の列車でまどろみ、ハンナの夢を見る。出逢った頃よりは年をとっていたが、再会したときより若かった。
生存した娘にハンナの遺志を伝え、お金を有意義に使われることを伝えると、娘は、
「あなたは彼女がお好きなのね?あなたたちはどういう関係でしたの?」と訊ねられ、一瞬ためらいながら「彼女の朗読者で、十五歳で始めて、刑務所のいるときもそれが続いた」ことを話した。
娘は、ミヒャエルの心を見抜く。ミヒャエルの人生が、ハンナと伴にあったことを。十五歳の切ない初恋の思い出を引きづり、大人になっても心を閉ざし、離婚も経験したほどのハンナという女性の存在。
娘は「なんて粗暴な女なのかしら。十五歳でもてあそばれたことに、あなたは耐えられたのですか?」と聞いた。
そして娘は、どんなユダヤ人団体があるか調べて、ふさわしいと納得された団体に寄付することを薦めた、そしてお金の入ったブリキのお茶の缶だけを貰うと言った。
歴史の真実の不確かさの中で、真実の愛を物語として残していく。
いつのまにか、あれから十年が経ってしまっていた。
ハンナが死んで間もない頃は、昔の疑問がミヒャエルを苦しめた。ハンナを裏切ったのか、借りがあるのか、彼女を愛したことで罪ある者となったのか、彼女の思い出と離れるべきか、そしてときおり、死の責任も自分にあるのかと考えた。
死んだ後に物語を書こうと思った。なんて悲しい物語だろうと考えていたが、いまではそれが幸福というよりも真実の物語なんだと思った。
歴史の真実の不確かさと人間の営みの中にある真実、愛はその最も意味あるもので悲しみや幸せを超え、真実を伝えてくれる。
傷ついているときは傷心の思い出、自責の念にかられるときは罪悪感、あこがれやなつかしさに浸るときは憧憬や郷愁、人生は何層にも重なっている。
ハンナのお金は、彼女の名前でユダヤ人識字連盟に振り込んだ。連盟からはハンナ・シュミッツさんの寄付に感謝しますという手紙が届いた。
ミヒャエルはそれをもってハンナの墓へ行った。マイケルはハンナの命を救えなかったが、尊厳を守り通した。
アウシュヴィッツの大量のユダヤ人に対するホロコーストと同時に、ロマ族もナチスだけでなくヨーロッパの歴史において迫害された民族でした。そこで定住が難しく移動の生活となり、就学の機会を失くします。少数民族に生まれ虐げられたロマの出自。文盲となり、さらなる不幸な罪へ向かう悲しさ、その中でただひとつ、ハンナにはマイケルへの感謝が残りました。朗読によって救われた愛を表現した物語です。