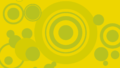解説
ドイツは過去の戦争の過ちの反省にもとづき基本法の第一条で人権に関して規定し「人間の尊厳は不可侵である」と謳っている。
この作品『朗読者』には、ナチの迫害を受けた人々は当然のことながら、ヨーロッパの深い歴史に根差した迫害もテーマであり、プリズムのようにハンナの角度やミヒャエルの角度からその苦悩と尊厳の輝きを反射させ照らしている。
作者のベルトハルト・シュリンクは伝統あるフンボルト大学の教授で、専門はミヒャエルと同じ法律学だ。ナチス・ドイツの罪をまさに物語を通して、過去の歴史の再検討を行い、啓蒙的・告発的使命を確信しようとする。
先の戦争で日本も戦争責任を東京裁判で裁かれるが、ナチスのホロコーストについてはヨーロッパの民族の歴史や文化など様々に複雑な背景もあり、我々、日本人には理解が深く及ばない。また当事国であるドイツにおいても永遠に語り継がれていくことだと思う。
ドイツの置かれた人道の立場と日本のそれは異なる部分もあるが、戦争の正しい認識がないなかで、過去を負の遺産としてだけ背負わされるのは、日本人もある意味で同じである。
風化しそうな歴史を「あなたの愛した人が戦争犯罪者で、戦犯として裁かれたら」という視点を加えることで、さらにロマという民族を暗示しながら、奥深いヨーロッパの歴史や迫害の事実に触れている。
映画ではオデッセイアの一部が紹介されていた。引用すると
西洋文学の核となるのは “秘密性” だ。登場人物がどういう人間か、作者は、ある時は意地悪く、ある時は深い目的のために、情報を明かさない。読者は行間を読み取って登場人物をイメージせねばならない。
そして
何も怖くない、何も。苦しみが増せば、愛も増す。危険は愛を一層強め、感覚を研ぎ、人を寛容にする。私はあなたの天使、生の時より美しくこの世を去り、天国はあなたを見て言うだろう。人間を完全にするもの、それこそが “愛” だと。
人間には他者に明かせない秘密があるが、その秘密が「戦争犯罪」のような倫理的、道徳的に関わるもので、その戦争犯罪の責任の問題と個別の問題が重なることでさらに複雑化する。
少数の迫害されたアウトカーストにとって社会はいかに酷く生きにくいものかーそこに自身の尊厳を守りぬいて自死を選んだハンナがいたー。今に生きる人間は、歴史の教科書的な受動的知識だけでなく、それが歪められたり、何かが隠されていたりする可能性を考え、自ら能動的に積極的に歴史と向き合い更新していくことが必要なことを教えられる。
十五歳のミヒャエルと三十五歳のハンナ。思春期の強い衝撃としてミヒャエルに残る初恋の記憶、そしてミヒャエルが人道的かつ啓蒙的に正義を求める法科を目指した優秀な学生であったことが、結果として真実を究明する行為に及んだ。そして朗読がハンナの精神を救った。
『朗読者』は、歴史に翻弄されたハンナに唯一、生きる幸せを与えた文学の力でもある。
作品の背景
作者のベルンハルト・シュリンクは一九四四年生まれ、フンボルト大学の教授で、専門は法律学です。本作品はナチスの犯罪を如何に捉えるかという重い問題を孕んでいますが、同時に愛した女性が戦犯として裁かれるなか、他の被告とは違うハンナの態度からそこに隠された真実を何とか究明しようと試みる。
そして真相を掴んだときに、それはナチスの人類上の大きな過ちのなかで、さらに以前に階級から外れ迫害され続けた少数民族の現実が湧き上がり、そして晒され、深いヨーロッパの闇の中へ引きこまれていく。
それは敗戦後の民主主義を受けて育ったベルンハルトの世代に共通の親世代への糾弾に対して、形式上のものではなく、もっと本質をみようとする姿勢である。戦後の連合国によって裁かれたニュンベルグ裁判ではなく、ドイツ人の手で過去の犯罪を如何に裁くかという「アウシュヴィッツ裁判」が行われた一九六三年から六五年の動きにも呼応している。
ナチスの迫害のなかに、もうひとつのヨーロッパの民族の記憶がある。なぜハンナは文盲だったのか?なぜハンナは何も知らなかったのか?そしてなぜハンナはナチの親衛隊に協力してしまったのか?
ミヒャエルのハンナへの愛を通して、現実の深層を知ることで物語の厚みをもってヨーロッパの深く複雑に絡み合う民族の歴史の遠い彼方へ誘ってくれる。
発表時期
1995(平成7)年に出版。発売後5年間で20以上の言語に翻訳、アメリカでは200万部を超えるミリオンセラーとなる。尚、映画も2008年に『愛を読むひと』のタイトルで公開され、ハンナを演じたケイト・ウィンスレットは第81回 アカデミー賞 主演女優賞をはじめゴールデングローブ賞助演女優賞、英国アカデミー賞主演女優賞を受賞している。