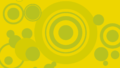なぜハンナは突然、ミヒャエルの前から姿を消したのか? なぜハンナは不利な証言をしたのか? 隠し通さねばならないもうひとつのナチスの迫害の記憶。ハンナはひとり罪を背負い、死を選ぶ。映画では、ケイト・ウィンスレッドが生の逞しさで美しくイノセントなハンナ役を演じ『愛を読むひと』としてアカデミー賞の主演女優賞に輝いた。その真実を知る『朗読者』。原作の中にヨーロッパの深い謎を訪ねて行く。
あらすじ
彼女の名はハンナ。過去は不要、未来は無用、今だけを生きる
物語は、長い歳月を経ての主人公ミヒャエル・ベルグ(映画の邦訳ではマイケル)の回想のかたちをとりながら進んでいく。
十五歳のマイケルは学校からの帰り道、途中で気分が悪くなり吐いてしまう。そのとき、一人の女性が乱暴なほどてきぱきと面倒を見てくれ、家まで送ってくれた。医者から黄疸と診断された。少し回復したミヒャエルは女性のアパートへお礼に行く。
一緒に外へ出ようとする彼女は、気にすることもなく着替えを始めた。彼女は逞しいと同時に女らしい体つきだった。三十歳過ぎくらいに思えた。マイケルは目のやり場に困り、慌てて外に飛び出す。
思春期のマイケルにとって、彼女は流れるように優雅で魅惑的に映る。乳房や尻や足の誘惑ではなく、体の中で世界を忘れさせるようで、それは思春期の男の子が成熟した女性に抱擁されるような最初の感情だった。
それからマイケルは病床で悶々とする。彼女にもう一度、会うべきか否か。思考と決断を行き来しながら、結局、行動に移すことにした。
もう一度、訪れて、身につけた制服から女性が路面電車の車掌ということが分かった。
地下室からコークスを運び上げるのを手伝い、黒い埃だらけのミヒャエルを彼女は風呂に入れる。そして彼は、彼女と肉体関係を持つ。それは初めての経験で二十ほども違う母親のような女性に恋に落ちた。それから毎日のように共に過ごすようになる。 ミヒャエルは名前を訊ねる。
名前を告げることを少しためらい、女性は答える。名前は「ハンナ」。
病気で何カ月も学校を休み落第しそうで「自分をバカだ」と言うと、ハンナは突然、切符切りの仕事の真似をして「バカとはこういうことよ」と怒った。それは、学がないから仕方なく行っているのが切符切りの仕事という意味だ。
ミヒャエルが懸命に勉強をすることを条件に、ハンナは会い続けてくれた。ミヒャエルは、残された数週間で進級試験に合格し、ハンナと愛しあった。
ハンナは自分自身だけを頼りにして生きていた。
彼女は、ジーベンビュルゲンで育ち、十七歳でベルリンに出て、ジーメンスという会社の労働者となり、二十二歳で軍隊に勤めたという。
二.三年前から市電の車掌になる。家族はいなく、年は三十六歳。ハンナはそんなことをあたかも自分の人生ではないような、自分と関係ない人の人生のように話して聞かせた。
ジーベンビュルゲンは、現在のルーマニアであり、現在にいたるまで一人で、しかしミヒャエルとの愛の表現は、激しく情熱的。家族も身寄りも無いというハンナには、過去の記憶は不要で、未来の夢も無用で、奔放な野生を型に抑え込み、人知れず静かに目立たないように生きているようである。人生を無関心に振る舞う様子にはある秘密を暗示している。
ハンナは物語を愛し、ミヒャエルは彼女にたくさんの本を朗読する。
ハンナは語学の勉強に興味を持つ。ミヒャエルはギリシア語やラテン語で『オデュッセイア』や『カティリナへの演説』の一節をハンナに読んで聞かせる。
「坊や!あなたはとてもいい声をしている」と言う。そして朗読をさせる。
注意深い聴き手となり、笑い声や、軽蔑したように鼻を鳴らす音、怒りや同意を示す叫び声を出します。ミヒャエルとハンナは朗読を通じてお互いの思いを深めていきます。
復活祭の休暇の初日に、ハンナを驚かそうとミヒャエルは、彼女が乗務する電車に乗り気を引こうとしますが、結果、その行為はハンナを侮辱することになります。
次の週には、四日間の自転車旅行に出かけます。二人はサイクリングを深緑の中で楽しみます。ハンナは泊まる宿も、宿帳の記帳もレストランでメニューを読み料理を決めるのもミヒャエルに委ねます。
一度だけ、喧嘩をした。朝早く起きたミヒャエルは一輪のバラと朝食を持参しようと部屋を出た。メモにはその内容を残した。帰ってくるとハンナは怒ってベルトでミヒャエルの顔を殴った。
落ち着いたときに、ハンナは「なぜ黙って出て行ったのか」と理由を訊ね、ミヒャエルは「メモを残しておいた」と答えたが、テーブルの上にメモは無かった。
「何か朗読してよ、坊や!」そして仲直りして「朗読をはじめた」。
ハンナの涙に対して、これまで以上にミヒャエルは内面的に深くなることができた。それ以降、二人はお互いを優しくいたわり合うようにひとつになっていった。
ハンナにとって辛すぎるほどの自身の人生への憤りである。その気持ちをミヒャエルにぶつけている。そこにはどうすることもできない理由があり強い怒りに満ちている。ここでの違和感が<ハンナは文字が読めない>。つまりは文盲の可能性が読者には伝わる。しかし物語では、まだその事実は判明せず、後の衝撃的な場で知ることになる。
ハンナは突然、姿を消した、そしてミヒャエルは裁判の法廷で再会する。
ハンナは、ミヒャエルの前から姿を消した。
それは務めていた市電の会社にも伝えられていた。役所の住民課でハンブルグへの転出届を出していることが分かった。何も告げずに、理由も分からず、突然、一人残されたミヒャエルは途方にくれる。
やがて彼の家も別の場所に引っ越すことになり思い出は遠のいて行った。
大学に入ったミヒャエルは法学を専攻した。そして法廷でハンナと再会する。
それは、ナチス時代とその関連する裁判を研究する教授が、事件をゼミで取り上げたのだった。過去の行為を遡って罰することを禁止すべきかどうか討論することだった。
収容所の看守や獄卒が裁かれる根拠となっている条項が
・犯罪行為が行われた当時すでに刑法に記載されていることで充分なのか
・その条項で犯罪が起こされた時点で、いかに解釈され適用されていたことが重要か
・当時は収容所職員の行動が刑法に照らされることがなかった点を重視すべきか
ということだった。さらに、そもそも法律とは、法律書に載っていることが法なのか?社会で実際に行われ、遵守されていることが法なのか?本に載っていようといまいと、正しいことが行われる場合に実施され遵守されることが法なのか?教授は知識だけではなく、実際に被告人たちを見て判断することを学生に薦めた。
歴史の再検討、社会が悲惨な過去の上に積もらせた埃を、巻き上げてくれる。学生たちは、啓蒙的・告発的使命を確信するようになっていた。
ハンナはただ役割として、ナチス親衛隊の任務を全うしただけだった。
ミヒャエルはゼミの研究としてナチス戦犯の裁判、フランクフルト・アウシュビッツ裁判を傍聴する。
そして、その被告席に、ハンナの姿を見つける。
ハンナ・シュミッツ一九二二年十月二十一日、ヘルマンシュタット生まれ。四十三歳。一九四三年の秋にナチス親衛隊に入隊。
陪席判事の「なぜ親衛隊に行ったのか?」の質問に対して、ハンナは「看守の仕事をする女性の募集があったから」と答える。
裁判長は、ハンナが一九四四年初頭までアウシュヴィッツで、一九四四から一九四五にかけてクタクフ近郊の収容所で、さらに西へ移動し終戦当時はカッセルにいて、そこで生活をしていたことを確認し、彼女はそれを認める。
ミヒャエルは、ハンナの拘留を当然で正しいと見做していた。そのことで過去の思い出であり続けられると考えた。釈放されれば会う覚悟をしなければならないし、会いたいのか、会うべきなのかをきちんとしなければならない。
ミヒャエルは、一日も休まず公判に通った。たった一度だけ、ハンナは傍聴席を見上げ、彼の方も見たが、それ以外は高慢な印象を与えた。
ミヒャエルは考える。
後から来た世代の人間は、ユダヤ人絶滅計画にまつわる恐ろしい情報を前に、実際何をはじめるべきなのか?
「理解不可能なことを理解できると考えるべきでない。比較不可能なことを比較すべきでもない」と主張する人がいるが、我々はただ驚愕と恥と罪のなかで沈黙すべきだろうか。
ゼミに参加する際に感じた、過去の再検討と啓蒙活動への情熱が公判で失われたわけではなかったが、何人かの人々が判決を受け、刑に服し、押し黙った。
<選別の手続き>のハンナの合理的な説明は、積極的な関与と見做された。
ハンナは正しく振舞おうとした。自分の不正が加えられていると思われる箇所では反論し、正しい主張や告発がなされていると思う箇所では罪状を認めた。反論の仕方は頑固だが、罪を認めるのにも積極的だった。しかしハンナは自分が裁判長を怒らせていることに気づかなかった。
社会を動かしているのは道徳ではなく“法” である。アウシュヴィッツで働いたというだけは罪にならない。アウシュヴィッツでは数千人が働き、有罪判決を受けたものは数十人、そのうち殺人罪は数人。殺人罪は意図を実証しなければならない。
法廷では、アウシュヴィッツ収容所の元囚人の生存者の娘が書いた本が紹介される。その本には<選別の手続き>のことが記されている。それは毎月六十人の囚人が選別されてアウシュヴィッツに送られたのだった。
<選別の手続き>について、ハンナは「六つの規模のグループで十人ずつ合計六十人の囚人を届け出ることになっていた」と述べた。
裁判長は「囚人たちを死なせることになるとはわからなかったのか?」と問うと、ハンナは「わかっていましたが、新しい囚人が送られてきて、古い囚人は新しい囚人のために場所を空けなければならなかった」と答えます。
そしてハンナは、逆に裁判長へ「あなただったらどうしますか?」と問うた。裁判長の答えは「この世には関わり合いになってはいけない事柄があり、命の危険がない限り、遠ざけておくべき事柄もあるのです」と返したが、聴衆は裁判長の答えに失望の溜息を洩らした。
さらに傍聴席に座っていた生存者の娘が「ハンナが若くて弱くて華奢な女の子を選んで、その子が働かなくていいように、いいベッドを与え、世話を焼き、いい食事を与え、毎晩、本を朗読させた」と証言を加えた。
収容所における看守としての任務の遵守が、未必の故意となる。
<死の行進>の話に移る。四十四年の冬に収容所が閉鎖され西へ向かって歩き出す、一週間後、女たちの半数が雪の中で死んだ。
ある日、教会で泊まることになるが、夜中に空襲があって教会が被爆。教会が燃えはじめ、皆は、叫びながら外へ向かったが、外から鍵が掛けられ中にいた者は、生存者の母娘以外は全員、焼け死んだ。
裁判長は被告人一人一人に「どうして鍵を開けてやらなかったか」と同じ質問をした。他の五人は同じような返答をした。いかにも教会の火事のことを知らなかったという言い方だった。
「囚人を逃亡させたら、逮捕され、死刑判決を受け、銃殺になると思ったのですか?」と確認する裁判長に、ハンナだけが「囚人をみすみす逃がすことはできませんでした!わたしたちには責任がありました」と答えた。
それは、ハンナにとっては「秩序を守るためであり、村に囚人を放ったらどうなるか」という答えだが、裁判長には「囚人を逃がすよりも殺すほうが良い」と判断したと受け取られる表現だった。殺意があった可能性。そして他の看守五人は鍵を開けないことの判断は、ハンナが一人でやったと口を揃える。皆、少しでも心象を良くしようと罪をハンナひとりに被せようとしていた。
報告書は皆で書いたというハンナに対して、他の被告たちは「報告書はハンナひとりが書いた」と口を揃えて言い立てる。裁判官は、筆跡鑑定を求めます。
するとハンナは、報告書は自分が書いたことを認めます。
ミヒャエルは気づきます。ハンナは読むことも書くこともできないことを。
だから人に朗読させたんだ。自転車旅行のときも、書いたり読んだりするのをさせたんだ。ホテルでの朝、メモがあるのを見て文盲がばれるのを恐れ、夢中になって怒ったんだ。市電の会社で出世のチャンスを棒に振ったのもそのためで、だからジーメンスの昇進を断り看守になったのだ。