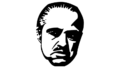愛と恩を忘れず養父母を救う、おぎんの閃き。
芥川はキリスト教に興味を持ち切支丹物という作品を残している。その代表作『おぎん』を解説してみる。江戸時代初期のキリシタン弾圧と棄教がテーマである。一読すると、おぎんは実父母への愛から、ぱらいそに行くことを断念し、いんへるのへ落ちる孝道物語で<人倫の道>がテーマかと思う。
解説
禁教令下の長崎でキリシタンが弾圧され、聖人と天使、悪魔が入り乱れる。
しかし人間観察の鋭い芥川の筆致を丁寧になぞっていくと、厳格なローマカトリックやイエズス会の権威、キリスト教の教義に怜悧に距離を置き、随所にシニックなユーモアを配置し、天真爛漫な「おぎん」のとっさの閃きのなかに、<生の逞しさ>すら感じさせる。
この物語は、おぎんの妙案で、恩ある育ての養父母の命を救った御伽話なのである。
「元和か、寛永か、兎に角遠い昔である」と言う一文から始まる。つまり、昔、昔のお話ですよ!と前置きしているのである。
「天主のおん教を奉ずるものは 、その頃でも もう見つかり次第 、火炙りや磔に遇わされていた」という時代背景である。
続いて「しかし迫害が激しいだけに、「万事にかない給うおん主」も、その頃は一層この国の宗徒に、あらたかな御加護を加えられたらしい」として、「村々には、天使や聖徒の見舞うことがあった」とする。そしてついに、洗礼者ヨハネが宗徒 みげる弥兵衛 の水車小屋に、姿を現したと伝えられる。
悪魔のほうも堕落(棄教)させようと負けてはいない。宗徒の精進を妨げるために、見慣れぬ黒人に扮したり、舶来の草花に化けたりして村々に出没する。牢に捕らわれた弥兵衛を苦しめた鼠も、実は悪魔の変化だったというのである。そして弥兵衛は元和八年の秋、十一人の宗徒と火炙りになった。―と紹介している。
こうしてキリシタンが、また一人、火炙りのなか棄教せず、りっぱに殉教したのである。
西暦の年代で見ると元和が(一六一五~二四年)で寛永が(一六二四~四四年)である。元和から寛永に入ると、弾圧がより一層、厳しくなる。迫害による反乱の中心は長崎である。
寛永六年に踏絵の制度が始まり、寛永十四年の島原の乱の後は、鎖国政策となり宣教師は元よりポルトガル人は追放され、寺請制度や宗門人別改長を整備し、人々は仏教を強制され、奉行は隠れキリシタンをあぶり出す。キリスト教はついえて絶え絶えである。
このキリシタン弾圧下、聖人や天使や悪魔も参戦する中で、いかに天真爛漫な童女の「おぎん」が生き抜き、養父母を守ったか!という風刺まじりのお伽話なのだ。
孤児のおぎんは、孫七の養女となり洗礼を受け まりあ おぎんとなった。
おぎんという童女は一五六歳くらいの設定だろう。両親と共に大阪で暮らしていたが、流浪の末、長崎に辿り着いた。
両親は仏教徒だが、「禅か、法華か、それとも又浄土か、何にせよ釈迦の教である」とある。強い宗教心があったかどうか疑わしい。どこかの宗門に記されたのであろう。ともかくも、おぎんの実母は仏教を信じた。しかし間もなく両親は死ぬ。
これより前の時代にはキリシタンが隆盛だった。長崎にはキリシタン大名さえいた。キリスト教にとって仏教は邪教である。イエズス会の修道士ジャン・クラッセの著<日本教会史>によれば・・・
「天性奸智に富んだ釈迦は、支那各地を遊歴しながら、阿弥陀と称する仏の道を説いた(P151)」とし、その教えは、「我々人間の霊魂は、その罪の軽重深浅に従い、或いは小鳥となり、或いは牛となり、或いは樹木となる(P151)」とある。
輪廻のことを指しているが、これは釈迦の教えの荒誕、つまりでたらめであるとする。さらに釈迦の母、マーヤが出産七日後に「死ぬ」が、これが「殺した」となり、「釈迦は生まれる時、彼の母を殺した(P151)」として大悪とする。
おぎんの実母は、そんなことも知らず、釈迦の教えを信じ、墓原の松かげに、末は「いんへるの」へ墜ちるのも知らず、はかない極楽を夢見ている。
両親を失くし孤児となったおぎんは、浦上の山里村の隠れキリシタンである農民で憐れみ深いじょあん孫七に引き取られる。孫七は、ばぷちずも の水を注ぎ、「まりあ」と云う名を与えていた。おぎんの洗礼名は「まりあ おぎん」である。聖母マリアに因んだのである。
禁教令下の厳しい弾圧の長崎で、童女おぎんは自分の意思とは全く預かり知らぬところで、孫七の独断で洗礼を受け、キリシタンとなった訳である。
おぎんは釈迦が天と地を指して「天上天下唯我独尊」と大演説をぶったことなど信じていない。最初から仏教を信心したことはないのだから。
代わりに「深く御柔軟、深く御哀憐、勝れて甘しくまします童女さんた・まりあ様」と、寛容、仁慈、甘美な聖母マリア様より処女懐胎したことを信じている。そしてキリストが十字架に懸り死に給い、大地に埋められたが、三日後に復活したことを信じている。さらに罪深い人間の魂を審判し、善人は天上の快楽を受け、又悪人は悪魔と共に、地獄に墜ちることを信じている。
おぎんの心は「素朴な野薔薇の花を交えた、実り豊かな麦畠である」こうして孫七の養女となった。
孫七の妻、じょあんな おすみも心の優しい女である。おぎんは「夫婦と一緒に、牛を追ったり麦を刈ったり、幸福にその日を送っていた(P152)」とある。牛を追う?麦を刈る? これはほんとうに、当時の農民の生活風景なのだろうか。貧窮で年貢に苦しんでいたはずだが・・・
そして断食や祈祷も励行する。祈りは簡単だが、以下のようなものである。
「憐みのおん母、おん身におん礼をなし奉る。流人となれるえわの子供、おん身に叫びをなし奉る。あわれこの涙の谷に、柔軟のおん眼をめぐらせ給え。あんめい」
この “流人となれるえわの子供” は意味深だ。楽園を追い出され流人(罪人)となったイブの子供=すべての人間となる。これは後半に重要なメッセージとなる。
悪魔は何人かの役人と一緒に、孫七、おすみ、おぎんを捕らえるが・・・
こうしてキリシタンの教義を守り幸せに暮らしていたが、或年のなたらの夜に、悪魔が何人かの役人と一緒に孫七の家に入ってきた。
この日だけは普段とは異なり、暖炉の火で語らい、壁には十字架が祭られ、ぜすす様の産湯のために、桶に水がたたえられている。役人は隠れキリシタンと認め縄をかけた。
しかし三人ともに、全く悪びれることなくあにまの救いのためならば、如何なる責苦も覚悟の上。おん主は必ず我等の為に、ご加護を賜わるに違いないとする。
悪魔は彼らが捕らわれるのを見て「手を拍って喜び笑った」が、彼らの健気なさまに腹を立て、唾を吐く。そして「大きい石臼」になって「ごろごろ転がりながら闇の中に消え失せて」しまった。何とも悪魔らしい悪戯っぽさである。
孫七、おすみ、おぎんは土の牢に投げ込まれ、キリストの教えを棄てるように、水責めや火責めの拷問に遭わされるが、彼等の決心は動かなかった。たとえ、皮肉は爛れても、はらいその門へはいるのは、もう一息の辛抱である。尊い天使や聖徒も慰めにやってくる。
おぎんには特に、あの洗礼者ヨハネが現れ、「大きい両手の手ひらに蝗を沢山掬い上げながら、食へ」と云う。さらに「大天使がぶりえるが、白い翼を畳んだ儘、美しい金色の杯に、水をくれる所を見た」と云う。
おぎんは、幸福な空想にふけることのできる、天真爛漫な楽天主義者のようだ。
取り締まる代官のほうは「天主のおん教は勿論、釈迦の教も知らなかったから、彼等が剛情を張る理由が、さっぱり理解できなかった(P154)」とある。
そんなことはあり得ないのだ!キリシタン禁止令が発布され、鎖国となり、農民は全員仏教徒として寺請制度や宗門人別改長で監視されるのである。中枢の職である代官がキリスト教や仏教の教えを知らない訳がない。
芥川には日本の昔話を、風刺をこめて創作した『猿蟹合戦』や『桃太郎』があり、実はこの『おぎん』もキリスト奇譚のお伽話として読むと分かりやすい。
そして拷問に屈せず一向に転ばない 孫七、おすみ、おぎんたちを、代官は「大蛇とか一角獣とか、兎に角人倫には縁のない動物のような気がした(P154)」とある。
聖書では、イブは蛇に騙されて禁断の知恵の木の果実を食べてしまい楽園を追われる、一角獣は、最強の動物だが、処女(聖母マリア)に懐く。
その大蛇(=狡猾)と一角獣(=勇敢)ということになる。先ほどの話に戻せば、大蛇はともかく、代官が “一角獣” なる西洋の伝説上の生き物を知っているだろうか?