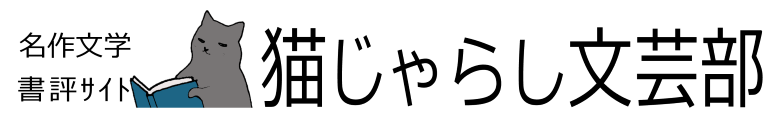この作品は芥川の「芸術至上主義」を表すと言われることがあります。その意味は、芸術は純粋に美を目的としたものであり、そのためには他のことを厭わないとする表現者の態度ということでしょうか。十二年の作家人生のなかで、この作品は初期のもので『鼻』で漱石に褒められた僅か二年後です。得意とする平安時代の「王朝物」を題材にしていますが、芥川独自の創作のなかに、これから作家として生きる覚悟を示した、その魂の証と捉えることができます。
あらすじと解説
物語は、御家の宝物となっている荘厳な「地獄変の屏風絵」の完成までの経緯が、第三者の言葉で回想の形で進んでいきます。そこには、天下を掌握した「権力」に生きる者と、美を極めたい「芸術」に生きる者との違い。あるいは闘いがあります。「権力」に抗う「芸術」の在り方という芥川の姿勢として読み進んでみます。
権力の象徴が「堀川の殿様」、芸術の象徴が「絵師の良秀」。この二人の対決です。
権力が追求する俗物的な欲と芸術が追求する創造的な美の対象として「良秀の娘」がいて、娘に懐き、身を案じる不思議な猿がいるという構図です。
まずは、この語り手の立場を確認しておきます。
二十年来、大殿のお傍に仕えている男です。きっと腹心でしょう。主君に忠実で絶対服従のはずです。決して悪く言うことなどないでしょう。どこまでが本当のところかはわからない。その分、所謂、信頼のおけない語り手でもあるわけです。
語り手は、まずは人物評をしています。
大殿様の天下人としての人物像
堀川の殿様は、この世に二人といない人物で「大威徳明王の御姿が母君の夢枕に立った」という。大威徳明王とは五大明王の一つ。西方を守護し、悪を征伐し、衆生を救済するとされています。さらに、始皇帝や煬帝のような我が身だけの栄耀栄華を求めるのではなく下々の事まで考えている。
大殿様は、度量の大きな御方で、壮大で豪放で徳があり、世の人々から尊ばれる人物である。
そんな人物ゆえ妖怪に遭っても何事もなく、幽霊も叱りとばすほどの威光があり、洛中の老若男女は、大殿様を権現の再来のように尊ぶ、と評します。いやはや、大絶賛ですね。
語り手の大殿の描写は、独裁者だが、大衆に尊崇され、絶対の権力を誇る支配者の姿です。容姿の描写がないのは無礼だからでしょうか。
しかし繰り返しますが、信頼のおけない語り手の評価であることは忘れてはいけません。
天才絵師としての良秀の人物像
語り手は、続いて良秀の話に及びます。
絵筆をとると、良秀の右に出るものはいないと云われるほど、高名な絵師。
と前置きして、こちらは、細かに容姿や性格の描写が始まります。
年は五十の坂、背の低い、骨と皮ばかりに痩せた、意地の悪そうな老人、人柄は卑しく、年に似ず唇が赤く獣めいている。立居振舞が猿のようで、猿秀・・と云う渾名までつき、大殿様の邸の者には嘲笑されていた。
さらに悪い癖をあげ連ねる。吝嗇で、人情味がなく、恥知らずで怠けもので強欲、とりわけ横柄で高慢で、いつも天下一の絵師と偉そうである。そして、世間の習慣とか慣例を莫迦にしている。
つまりは、絵の才をのぞけば、最悪の性質で社会不適合者だと言っています。
語り手は、二人の人物について、大殿様は立派な為政者で皆から尊敬され世間の評判だが、良秀は天下一の絵師ではあるが、傲慢で世間の不評判と紹介しています。
溺愛される娘と不思議な猿
良秀には十五になる一人娘がいて、大殿の邸に小女房として上がっています。小女房とは使用人(女官)のこと。
この娘は、生みの親には似つかぬほど美しく、愛嬌があり、母と早く別れ、 思いやり深く、利巧で、気がつき、正室はじめ外の女官からも可愛がられた。
丹波から一匹の猿が大殿様に献上される。悪戯盛りの若殿様が良秀という渾名をつけ、皆がこの猿を笑い、いじめた。或日の事、この小猿の良秀が「柑子盗み」をして、若殿に追いかけられているところを、良秀の娘が「父が折檻を受けているようでいたたまれません」とお許しを請う。
以来、小猿がなつき、良秀の娘と仲良くなり、御姫様から頂戴した黄金の鈴を、美しい深紅の紐に下げて、猿の頭に懸けてやる。小猿は、逆に可愛がられるようになり、良秀の娘は「孝行な奴じゃ」と大殿様から褒められ、紅の内着を褒美に頂く。
この内着を猿が押頂き、大殿様の機嫌はさらによくなり、良秀の娘を可愛がり、そして小猿も可愛がられた。
このくだりは、権力に仕える姿であり、大殿の覚え目でたき出来事だろう。あくまで力が背景ではあるが、平和で微笑ましいひとときでもある。予め、良秀の立居振舞が猿のようだと描写されており、邸にやってきた良秀と渾名される猿が、娘を見守る監視的な役割となっている。
良秀の化身である猿が、親代わりの愛情で繋がるという不思議な味わいをそえる。
地獄変の中心に、愛と死を描く
当時の名匠は、優美な評判が立ったが、良秀は奇妙な評判しかたたない。その理由は良秀が気味の悪い絵ばかり描くからである。
あるとき大殿様が「その方は醜いものが好きと見える」と仰ったとき、良秀は「さようでござりまする」と答え、
凡庸な絵師には醜いものの美しさは分からないと、横柄に高言を吐く。
良秀は、梅の花や、月の夜毎の匂い、大宮人の笛吹く姿など、優美なものを芸術とは認めていない。
芸術は苦悩のなかにあり、苦悩を描くことが、良秀にとっての画道なのだ。
そんな良秀だが、一人娘を途轍もなく可愛がっている。それゆえ、娘が大殿様の御声がかりで小女房に上がったのが何より大不服である。子煩悩で、始終、娘の下がることを祈っていた。大殿様の邸の務めから父親の元へ娘を返して欲しいのである。
ある時、大殿様言いつけの稚児文珠を描き、ご寵愛の童(わらべ)の顔を見事に完成させ、大殿様も満足で「褒美には望みの物を取らせるぞ」とありがたいことを言われる、すると良秀は「私の娘を御下げ下さいまするように」と申し上げ、大殿様は機嫌を損じ「それはならぬ」と云う。
このようなことが四.五遍あった。良秀のこのような発言は、大殿様の前では許されることではなく、決してあってはならないことなのです。
大殿様の良秀を見る目は冷ややかになった。そうすると娘も心配になり涙する。
語り手は、ここで付け足すように「地獄変の屏風絵」の由来について、大殿様が娘を恋慕したが、娘が大殿様に従わなかったからという噂が立ったことがあることを話しだし。
大殿様がお下げにならなかったのは、娘の身の上を哀れに思し召し、頑なな良秀よりも御邸において何不自由なく自由に暮らさせてやろうとのお考えからで、大殿様が色を好んだなどと言うのは、道理に合わない嘘だと、その噂を否定する。
その良秀の再三の娘のお暇こいの申し出で、大殿様の御覚えが、かなり悪くなってきたときだった。
それは大殿様の機嫌を損ねた果ての出来事であり、そこには計画的な思惑があったのかもしれない。それは分からない。
大殿様は「地獄変の屏風絵」を描くように良秀に云いつける。
「地獄変」とは、地獄の世界を描いたものである。
ここで、予め、語り手による良秀の屏風絵が紹介される。
それは構図からして独特で、一帖ほどの屏風の片隅に、十王を始め眷属の姿を描き、一面に紅蓮大紅蓮の猛火が剣山刀樹も爛る渦を巻き、火焔の色で卍のように黒煙と金粉を煽った火の粉が舞う。
特徴的なのは、業火に焼かれて上は月経雲鶴(殿上人のこと)から下は乞食非人に至るまで、あらゆる身分の人間が描かれているー殿上人、青女房、念仏僧、侍学生、女の童、陰陽師―が火と煙りが逆巻くなかを牛頭馬頭の獄卒に虐まれ四方八方に逃げ惑う様である。
この世界に生きる者はすべてが罪人であるというような芥川の考えかもしれない。
ひと際、目立って凄まじく見えるのは、中空から落ちてくる一輌の牛車。車の簾の中には、綺麗やかに装った女房が、黒髪をなびかせて、白い頸(うなじ)を反らせながら、悶え苦しんでいる。
この一人の女房に、良秀の渾身の力がこめられ、すさまじい叫喚の声が伝わるほどの入神の出来映えである。
娘を犠牲に、芸術を完成させる
「云わば、この絵の地獄は、良秀が、自分で何時か堕ちていく地獄だった。」と語り手はしみじみ回想します。
「何時か堕ちていく地獄」つまり、絵師良秀の生き方の行く末として必然であったというわけです。
あれ程の子煩悩が絵を描くという段になると娘の顔を見る気もなくなる。ここに良秀の芸術は日常から離れていくことを証明している。まるで、狐が憑いたようになる。特に地獄変の屏風絵を描くときの夢中になり様は甚(はなは)だしかった。
良秀は悪夢を見る。
「なに、己に来いと云うのだな。―どこへ―どこへ来いと?ー奈落へ来い。炎熱地獄へ来い。―誰だ。そう云う貴様は。―貴様は誰だー誰だと思ったら」
弟子が師匠の顔を覗くと、皺だらけな顔が白くなり大粒の汗を滲ませ、脣の渇いた、歯のまばらな口を喘ぐように大きく開いている。
「誰だと思ったらーうん、貴様だな。己も貴様だろうと思っていた。なに、迎えに来たと?だから来い。奈落へ来い。奈落にはー奈落には己の娘が待っている」
「待っているから、この車に乗って来いーこの車に乗って、奈落へ来いー」
良秀は、うなされながら何かが見えている。悪夢のなかで娘が現れているのだ。良秀は絵師として自分が見たものしか描けないこと、そして娘が大殿の恋情を拒んだことで、その後に起こることが夢に現れる。
良秀は、屏風絵の創作のために、弟子を鎖で縛り上げ、皮膚の色が赤み走るのを描いたり、蛇に弟子を噛ませようとしたり、耳木兎(が両脚の爪を張り弟子の頭をとびかかる有様を描いたり狂人さながらである。
しかし、良秀は納得できない。
或日、良秀が人のいないところで泣いている。そして又一方、良秀の娘は憂鬱になって涙を堪えている様子が目立ってきた。と描写される。この別空間での二人の心情を、あの猿が繋いでいるかのようである。
「地獄変」の屏風絵の中心・・がない。画竜点睛(がりょうてんせい)を欠いている状態なのだ。
ここで殿様の残酷な姿が現れる。
或夜、小猿の良秀が、語り手の袴の裾をひっぱり、けたたましく啼き立てる。唯事ではないと思い、一太刀あびせることも辞さぬ思いで猿の引っぱる方へ行くと、どこかの部屋から争いらしい気配がある。
部屋から出てきたのは良秀の娘だった。目を輝かし頬も赤く燃え、乱れた袴や袿が艶めかしい。誰の仕業か?と尋ねると、娘は脣を噛みしめながら、黙って首を振る。そして睫毛(まつげ)の先に涙をいっぱい浮かべている。すると、
あの猿の良秀が人間のように両手をついて、黄金色の鈴を鳴らしながら、何度となく丁寧に頭を下げている。
この意味は何なのでしょう?
猿は、娘の安否を気遣う絵師の父親、良秀の化身です。啼き立て騒ぎ立て、語り手の助けをかりて、大殿から言い寄られる娘を救うことができた。それで頭を下げ感謝しているのです。
大殿と娘の関係が最悪となる。娘が拒んだことで、支配者である大殿を怒らせます。理不尽だろうと権力に逆らうことは死を意味します。時を同じくして、良秀は地獄変の屏風絵の中心に夢で見た牛車の構図が必要と考えている。 ここで大殿は権力の赴くままに残酷な企みを思いつくのである。
芸術は勝り、死をもって道徳を贖う
その晩の出来事があって、半月ばかり後、良秀は大殿様に御目通りして、地獄変の屏風絵の作業状況を申し出る。精を尽くして筆を執った甲斐があり、あらましは出来上がったが、唯一つ、描けぬ場所がある。
良秀は「見たものでなければ描けぬ」と云う。大殿様は「地獄を見なければなるまいな」と嘲るように微笑む。
良秀は「屏風の唯中に、檳榔毛の車が一輌空から落ちて来る所を描こうと思っておりまする」「その車の中には、一人のあでやかな上﨟(高級女官のこと)が、猛火の中に黒髪を乱しながら、悶え苦しんでいるのでございます」それがどうしても描けません。
大殿様は、妙に悦ばしそうな御気色となる。良秀は突然、噛みつくような勢いで「どうか檳榔毛(びろうげ)の車を一輌、私の見ている前で、火をかけて頂きとうございまする、そうしてもし出来まするならば・・・」
そうしてもし出来まするならば・・・
この言葉で、大殿は自分に逆らった者を生贄にする妙案が浮かびます。
大殿様は「檳榔毛の車にも火をかけよう。又その中にはあでやかな女を一人、上﨟の装いをさせて乗せて遣わそう。炎と黒煙に攻められて、車の中の女が、悶え死にする。それを描こうとするのは流石に天下第一の絵師じゃ」と云う。
ここで、大殿は自分に恥をかかせた娘に、いかなる罰を与えようかと思案中だったが、良秀の生きた人間をひとり犠牲にしてほしいとの願いで、一致してしまう。
あるいは良秀には悪夢に見た牛車の中の女が己の娘になることは予感したのかもしれません。良秀の化身である猿が、大殿と良秀の意中を繋いで見せているようで、そこには、やがて殿様から死を申し付けられるくらいならば、愛する娘を芸術の最高の場所に据えることを是とすることを自分に言い聞かせたのかもしれません。
権力者の残酷さ、芸術家の残酷さ、ともに人間の常識や道徳心を越えてしまいます。
こうして洛外の山荘で車の焼ける所を見せる。
御庭に檳榔毛の車が、牛はつけずに黒い轅を斜に榻をかけ、金物の黄金を星のように光らせている。
大殿様は云う。
「その内には罪人の女房が一人、縛めた儘、乗せてある。されば車に火をかけたら、必定その女めは肉を焼き骨を焦して、四苦八苦の最期を遂げるだろう。その方が屏風を仕上げるには、又とないよい手本じゃ。雪のような肌が燃え爛れるのを見のがすな。黒髪が火の粉になって、舞い上がるさまもよう見て置け」
それそれ、簾(みす)を揚げて、良秀に中の娘を見せて遣わさぬか。
中にいたのは、きらびやかな縫いのある桜の唐衣に黒髪が艶やかに垂れて、黄金の釵子も美しく輝いた、身なりこそ違え、良秀の娘でした。
「火をかけい」大殿の言葉で松明の火を浴びて炎々と燃えあがり、見る見るうちに、車蓋(やかた)をつつんだ火の粉が雨のように舞い上る。
良秀の顔つきは、満身に浴びた火の光で、皺だらけの醜い顔が見え、大きく見開いた眼、引き歪めた脣の辺り、絶えず引き攣っている頬の肉の震え、心に交々に往来する恐れと悲しみと驚きは、歴々と顔に描かれた。
何と云う惨(むご)たらしい景色。地獄の業苦を目のあたりに写し出したものでした。
すると良秀の渾名のある小猿が、どこからか現れて炎のなかに飛び込み娘の肩に縋る。
このとき、猿に化身した良秀の親としての愛も、娘とともに火にかかり炎に燃やされます。そして絵師としての良秀だけが強く現れます。
一輌の火の車が凄まじい音を立てながら燃え沸る。
火の柱が、星空を衝いて煮え返る。
さっきまで「地獄の責苦」に悩んでいた良秀は、今は云いようのない「恍惚のような法悦の輝き」を、皺だらけの満面に浮かべながら佇む。
それは、唯、美しい火焔の色が、心を悦ばせる。炎熱地獄に苦しむ女人に見入り、絵を完成させようとする。
芸術が権力に勝るとき
語り手は、この恐ろしい光景を以下のように伝えます。
不思議なのは、あの男が一人娘の断末魔を嬉しそうに眺め、その時の良秀は人間とは思われない、獅子王の怒りに似た、怪しげな厳かさがあった。男の頭上に、円光のように懸っている不可思議な威厳が見えたのです。
私たちは、まるで開眼の仏でも見るように、目も離さず、良秀を見つめた。
物語の冒頭では、大殿様を権現の再来と称賛していましたが、「開眼の仏」・・・つまりは仏像に魂が宿るような心持で、見物人たちは良秀を見ているのです。空一面に鳴り渡る車の火、魂を奪われて、立ちすくむ良秀ー何という荘厳、何という歓喜。
その中でたった一人、大殿様だけが御顔の色も青ざめて、口元に泡をおためになり、喉の渇いた獣のように喘ぎ続けていた。一方で、大殿様の恐怖に怯えるかのような憐れな姿を見てしまいます。
世間では、「なぜ大殿様が良秀の娘を御焼き殺しなすったかーそれはかなわぬ恋の恨みから」という噂がもっとも多かった。
語り手は、「人を殺してまでも屏風を描こうとする絵師根性の曲なのを懲らしめるおつもりだったのに相違ございません」と言う。「画の為には、親子の情愛も忘れてしまう人面獣心の曲者」つまりは冷酷でしたたか者と言うものもいたという。
僧都様(そうずさま/位の高い僧)も「如何に一芸一能に秀でようとも、人として五常(儒教で説く五つの徳目-仁・義・礼・智・信を指す)を弁えねば、地獄に墜ちる外ない」と仰った。大殿様の行為を弁護し、僧都様の意見を人倫として紹介する。
その後一か月たって、いよいよ「地獄変」の屏風絵が出来上がり、恭しく大殿様にご覧に供えると、僧都様が「出かしおった」と仰り、大殿様が苦笑いなさいました。
それ以来あの男を悪く云うものは、少なくとも邸のなかには一人もいなくなりました。
あの屏風を見るものは、不思議に厳かな心持ちに打たれる、それは炎熱地獄の大苦艱を如実に感じたからでしょう。
つまりは愛する娘を炎のなかに失う、良秀の苦しみが描かれているのです。 これほどの地獄はないでしょう。良秀の芸術―地獄変の屏風-が、すべてに勝(まさ)った瞬間でした。
良秀は屏風の出来上がった次の夜に、自分の梁(はり)へ縄をかけて、縊れました。柱に首を吊ったのです。一人娘を失った良秀は、絶望のなかで死んでしまいます。