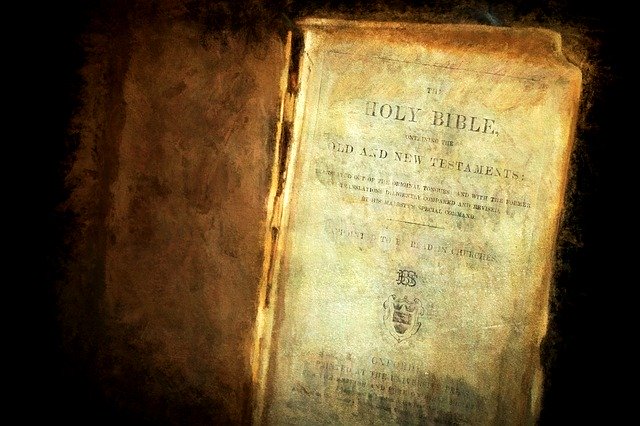●目次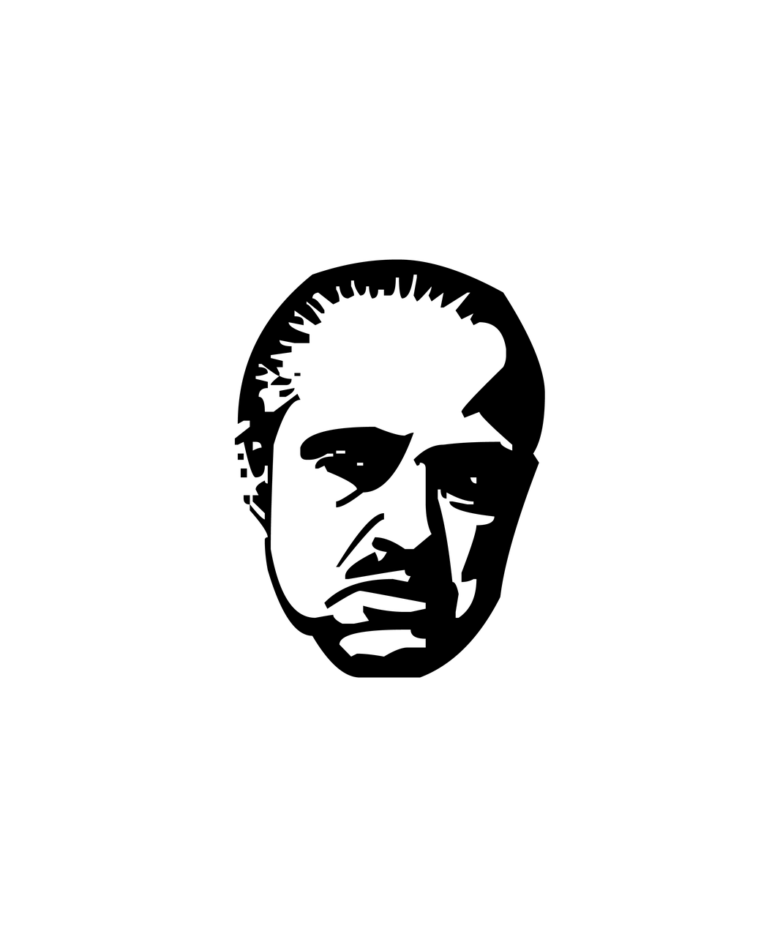
- 『ゴッドファーザー』|あらすじと主要登場人物について
- 『ゴッドファーザー』|家族の名誉をかけた荘厳なオデッセイ|原作の解説その1
- 『ゴッドファーザー』|原作の解説その2
- 『ゴッドファーザー』|原作の解説その3
- 『ゴッドファーザー』|原作の解説その4
- 『ゴッドファーザー』|愛するということ、女たちのサイドストーリー
愛するということ、三人の女たちのサイドストーリー
マフィアの抗争を描いた『ゴッドファーザー』は、イタリア、シシリーを起源とする秘密結社を描き世界中でベストセラーとなったが、同時に、この小説の大きなテーマは<愛>である。人間社会において、愛する感情が結実した夫婦の関係は、最も小さな単位ながら、最も大きな生きる熱源である。
『ゴッドファーザー』の物語の基底をなす<愛>について、ママ・コルレオーネ、ケイ・アダムス、アポロニアの三人の女性を中心に原作と映画の世界も含めて最後に解説します。
都会人にとって、失われた故郷だったママ・コルレオーネの存在
ママ・コルレオーネは、ドンとの長い生活から知らないでいる方が賢明なことを学んでいた。男たちの苦しみを分ちあわないことに甘んじていた。いったい男たちは、女の苦しみを分ちあってくれるのだろうか?彼女の経験では、食事こそが苦しみを和らげるものだった。
この引用文は、ソニーが敵の罠に嵌り蜂の巣になり殺された報が、トムにもたらされる。ヴィトーは病院から自宅治療に移ったばかりで安静の身。その中で家中が慌ただしくなる。そこでのママ・コルレオーネの描写である。
ママ・コルレオーネはシシリー出身で、ニューヨークで十六歳で結婚をしている。ヴィトーは当時十八歳。二十五歳の時に、ヴィトーはファヌッチを殺害し、定めと知り悪の道を選ぶ。夫の不穏な動きを気づいたかもしれない。犯罪に手を染めていく中で、ヴィトーは、四十歳を越えた頃にも抗争で胸に銃弾を受けたことがある。老境にさしかかる今、また数発の弾を受けて九死に一生で生還したのである。
ヴィトーと連れ添う人生のなかで、「知らないでいる方」が賢明であると知ったのだ。そして「食事こそ」が、苦しみを和らげると考えている。
Mangiare , Cantare , Amare ― 映画(PARTⅠ.Ⅱ.Ⅲ)の冒頭は必ず、宴で始まり、“食べること” “歌うこと” “愛すること” が描かれる。そこには人間の生きる本能の営みが象徴される。
映画では、ママ・コルレオーネはヴィトーに従順な妻だが、原作では、「男たちの苦しみを分ちあわないこと」に甘んじている。彼女の寡黙な態度が、夫であるヴィトーの生き様を支える形となっている。
ソッロッツォとマクルスキー警部を殺害し、シシリーに身を隠すマイケル。クリスマスの前にデートをした日を境に、マイケルはケイの前から姿を消す。
ママ・コルレオーネはケイとの対話の変遷に、「女の苦しみを分ちあって」いる様子がみえる。
ケイはマイケルの消息を尋ねるためロングビーチのコルレオーネ邸へ訪れる。トム・ハーゲンは頑なにマイケルについて口を閉ざす。そこに偶然、現われたママ・コルレオーネは、ケイを充分に素晴らしい女性だと敬意を表した上で、
「マイキーのことは忘れなさい。あの子はもう、あなたにふさわしい人間じゃないんです」
と語る。トムはママ・コルレオーネにマイケルの不在をうまく説明しているつもりだ。しかし、彼女は事実を知っている。そして、ケイもママ・コルレオーネの言葉で、マイケルが殺人者であることが、半信半疑から確信に変わる。
それから二年余の月日が流れ、ケイが二十四歳の時に久しぶりにコルレオーネ邸に電話を入れると、ママ・コルネオーネが受話器に出て
「マイケルは半年前から戻って来ている、今すぐに会いにおいで」
と言います。ケイは驚きますが、ママにうながされてタクシーを走らせる。物語では、「ボッキッキオ一族」の一人を真犯人に仕立てて、マイケルの無実を証明し、アメリカに帰国させています。マイケルの嫌疑は残るものの、法律上は無実となっています。
手紙も言伝もなく音信不通だったマイケルが、半年前に戻っていたことでケイのプライドは傷つけられ会うのを躊躇しますが、ママ・コルレオーネは「私に会いに来たと言えばいいじゃないの」とアドバイスする。
ママ・コルレオーネはケイの気持ちを察している。「ケイの苦しみを分ちあって」いるのです、そして茶目っ気たっぷりにケイの背中を押している。
そしてケイは自己の生き方に悩みながらも愛ゆえにマイケルと結婚し、子供をもうけます。ヴィトーは半ば隠居し、野菜いじりをしている。ケイは、義母が毎朝、教会に行く理由を問う。するとママ・コルレオーネは、
「主人の魂があそこに昇れるように毎日祈りを唱えているんですよ」
と言います。教会の天井の方を指し、「夫がそうなる見込みはない」と言うかのように、悪戯っぽい微笑みを浮かべて言ってのけるのです。どこか楽天的な覚悟が伝わります。
ヴィトーは「家族を大切にする」という厳格で保守的な父権意識の強い男です。それはシシリーを追われて、生き死にを経験する中で、妻を得て、家族を得て、家名を尊んだ誇れる男としての生き方です。
同時にママ・コルレオーネは、銃後の守りとして、妻として、母として、ヴィトーを支え、子供たちを育てる役割です。映画のなかでは、ママ・コルレオーネとケイとの接点はほとんどありませんが、原作の中ではママの存在は、ケイの心理変化の大きな支えとなっています。
それは女性には社会が不要ということではなく、女性にとって社会よりも必要なものは夫や家族であり、まるで本能のように夫の味方につく状態です。このママ・コルレオーネの無口な<愛>は、サイドストーリーとしてヴィトーとは対極の母性の包容力を持っています。
ニューイングランドの入植者の子孫、自由で自尊心の強いケイ・アダムス
ヴィトーの三男、マイケルが運命に翻弄された人生ならば、マイケルの妻となることを決意したケイ・アダムスはリベラルなアメリカ女性の象徴です。
まず前提に、マイケルはヴィトーのファミリーのビジネスを嫌い、自らの名前も変えるつもりでいました。つまりマイケルはケイとの結婚を契機に、家族との縁を絶とうとしていたのです。
そんなマイケルに対して、固定観念に動じない進歩的なケイとの恋愛が進行します。そして二人は相思相愛で、結婚届をクリスマスに市役所に出そうとしていたのです。
しかし狙撃事件が起こり、マイケルが父親を見舞いに行った日から、マイケルはケイの前から姿を消してしまったのです。何も告げず、以後の消息も知らせずです。
冒頭のコニー・コルレオーネの結婚式の宴で、マイケルと二人連れで現れたケイ・アダムスの人物評は、痩せすぎで、肌も白く、知的すぎる顔立ちと描写されます。これはイタリア人女性とは正反対であることを意味します。
出身は、ニューイングランド。二百年前に移住してきた家柄と紹介され、イギリスからの最初の入植者を想起させます。WASPで正統なアメリカ人、父親は教授であると同時に宗教家でもあります。プロテスタントとして最も大きなパブテスト教会の家系です。
自我を主張し、自由を大切にする女性。さらに開けっぴろげな態度、つまり率直で飾らず、物おじせずに、知的で良識ある女性なのでしょう。代々の保守的な家柄ながら、ケイには新しい時代のリベラルな気風が漲っています。
マイケルがシシリーからアメリカに戻った後で、ケイはマイケルに再会します。
原作と映画の違いは、映画(PARTⅠ)では、マイケルが教師となっているケイの前に車で現れますが、原作では、ケイがママ・コルレオーネに背中を押される形でコルレオーネ邸を訪れ、そのままマイケルの別宅に向かい、体を重ね、愛を確かめ合います。
マイケルは、殺人を起こす決心をした時点で、ケイと生きることを諦めました。そしてこの再会の時点ではすでに、シシリーでアポロニアの死を経験しています。
「あんなことが起こった後で、君が待っているとはまったく思えなかったからだ」
とソッロッツォの一件を匂わせながらも、「今までのことは話せない」と言います。それは「危険が及ぶから」との理由からです。「妻となっても人生を共有することはない」と言い、「同等の仲間になることはできない」とします。これで、夫婦と言えるのでしょうか。二人は、最初から大きな矛盾を孕んでいます。
きっとそれまでのマイケルとケイの関係は、「ともに語り」「ともに知り」「ともに理解し合う」というお互いの考えを共有し合う関係だったのでしょう。ここで、ケイはマイケルが「マフィアであること」を理解します。そして、
「あなたのお母さんのように、子どもと家の世話をするだけのイタリア人の主婦のようになるの?」
と訊ねています。「イタリア人の主婦」とケイは表現しています。恐らくこの時点のケイには、納得できない生き方、少なくともこれまでのマイケルと描いていた世界とは異なる生き方だったはずです。マイケルはそれでも求愛します。
「君は僕が愛情を感じる、ぼくが気にかけているただ一人の人間なんだ」
翻訳文の引用ですが、愛を感じないぎこちない表現です。
「すべてがうまくいけば、コルネオーネ・ファミリーは五年ぐらいのうちに、完全に合法的な組織になるだろう。そしてそれを可能にするために陰険な手段を用いなくてはならない」
と「五年ぐらいのうち」という期限を約束します。さらに、マイケルは続けます。
「僕には君が必要だし、家族がほしい。ぼくは子どもがほしい(中略)僕はファミリーのために戦わなくてはならなかった。僕の子どもには僕に感化されず、君の感化を受けてもらいたい」
このマイケルとケイの会話の応酬のなかで、ケイはマイケルがマフィアの人生を選んだことを理解しています。そして二人が当初、考えていたような愛が存在しないことに苦悩します。それでも愛ゆえに、マイケルを選びます。
ケイの考え方は、マイケルの育った家柄は問題ではありません。むしろマイケルの方がケイの両親を気にしています。ケイはマイケルを愛することで、現実を過少に考えようとします。そしてケイはマイケルの言う「五年後」を信じたのです。
原作では、形の上では、コルネオーネ・ファミリーはニューヨークを捨ててネバダで移動して合法的な法人として変わっていきます。
楽園のようなシシリーの原風景の中、無垢なアポロニアとの出逢いと別れ。
富を持ち、尊敬を集め、成功した父、ヴィトーの生まれたシシリーにマイケルは隠れます。そこは足を踏み入れたことはなくても、マイケルにとっての心の中の風景でした。
イギリスはじめヨーロッパの各地、プロテスタントからカソリックの宗派の人々、さらにアジアや南米から多くの人々がアメリカへ移住します。マイケルは人種の坩堝であるニューヨーク、ヘルズ・キッチンで生まれます。
ファミリーの仕事を嫌い、愛国心を抱き軍隊に入り敵と戦った経験も持つ。しかし父親が襲撃され、尚、命を狙われる危険の中で勇気と決断で敵を殺し逃れてきた。
匿われたシシリー。そこは知れば知るほどに、貴族、カソリック教会、警察までもが従順な人々を弾圧する歴史があった。貧困で弱き者がいわれなき弾圧を受ける。それは、ニューヨークでも同じでした。支配者と支配される者の関係を知り、父ヴィトーの生き様を理解する。
そして自分は何処から来た何者なのかをシシリーの丘陵を歩きながら思索する。
その自然の描写が美しい。それは地上にはない楽園のよう。そこで村の娘、アポロニアと出逢い、その美しさにマイケルはこの地方の言い伝えである「稲妻に打たれた」状態になる。
彼女は「皮膚はココア色で、目は大きく、瞳は濃い紫か茶色。唇は甘く豊かで深紅に染められている。信じがたいほどの愛らしさだった」と描写される。ケイとは全く対照的に描かれている。それは全く別世界に生きている、そしてマイケルの遺伝子に組み込まれたシシリーの女性なのです。
アポロニアは、ママ・コルレオーネが結婚したときと同じ年齢、きっと十六歳くらい。厳格な父親と妹を思う兄弟に、マイケルは礼を尽くし、アポロニアに求婚する。親兄弟、血縁や村人に祝福された、つつましくも自然と神々に讃えられた結婚式。
そしてアポロニアの処女の情熱がマイケルの結婚したての欲望と重なり合い二人はいつまでも愛しあった。しかし敵はいつも愛する者を奪っていく。アポロニアは、敵に内通したボディガードが車に仕掛けた爆弾で死んでしまう。
アポロニアは、自然と調和する美しい楽園の精として登場する。それは理性ではなく直観の愛である。
言葉を超えた、野生の存在である。体の中に刻みこまれたDNAとしてのシシリーの熱情が、マイケルに甦った瞬間であり、マイケルの本能的な恋情が、アポロニアを通して表出したのです。
この夢のような幸せなひとときは、映画(PARTⅢ)において、印象的に回想される。
人々の団欒の場でマイケルの息子アンソニーがギターの引き語りでマイケルが好きなコルレオーネ村に伝わる古いシシリーの歌を捧げる。
哀切のメロディのなかに、カメラは、深い年輪を刻むような穏やかな表情のドン・トマシーノ(原作ではトッマジノ)の顔から回り込んで、マイケルの顔を捉える。時間の流れが、ファミリーの物語を、そしてマイケルの人生を巡ります。
それは、歴史の中で貧しく虐げられ続けても、幸せを信じるシシリーの人々への敬愛、自分の身代わりなった若く美しいアポロニアの面影。さらに許されぬ恋をするヴィンセントとマイケルの娘メアリーをカメラは映し、そしてもう一度、マイケルに戻る。
美しく、せつなく、はかない、恋する心と人生の苦悩を捉えている。やはりマイケルには、ケイには理解できないシシリーの血が流れているのです。
走馬灯のようにめぐるマイケルのアポロニアとの愛の記憶。マイケルと子供たち兄妹が散策する場面で「こんな美しい村に、そんな悲惨な出来事があったなんて」とアンソニーがしみじみ語る。
マイケルの魂を神に祈ることで、告解と愛を信じ生きようとするケイ
マイケルは五大ファミリーの血の粛清を決行し勝利します。しかしその代償は、家族の絆を大きく棄損します。妹コニーの夫カルロをソニー殺しの手引きをしたとして殺害し、コニーは半狂乱になります。そしてケイの疑念が高まっていきます。
ケイはマイケルに真偽の確認のために問い質します。
「マイケル、あれは本当じゃないわね、お願い、本当じゃないと言って」
マイケルは答える。
「もちろん本当じゃないさ。ぼくを信じるんだ。あれは絶対に本当じゃない」
その口調はかってないほど強く、ケイの目をじっと見つめます。そして扉が半開きになり、「ドン・マイケル」と部下から臣従の礼を受けるマイケルに、ケイは呆然とします。
その瞬間、ケイはコニーの言葉がすべて真実であることを悟ります。
マイケルの嘘は、二人の信頼の全てと互いの愛情を故意に利用した、つまり最も忌み嫌うことでした。
ケイは失望しマイケルのもとを去ります。しかしそれから一週間後、マイケルの命をうけてトム・ハーゲンがやって来て、言葉巧みに連れもどされます。(ここからは映画と原作では異なります)
ケイ・アダムス・コルレオーネは、カトリックの教えを信奉するようになり、家族の者を大喜びさせます。マイケルは「子どもたちはプロテスタントになる方が良い」と考えます。
コルネオーネ・ファミリーはニューヨークを捨ててネバダへ移動し、ケイはネバダの暮らしが気に入ります。マイケルは、建設会社を経営し、実業家クラブや市の委員会の会員となり地方政治にも関心を持ちます。
ケイは毎朝、教会へ行き、やがて聖体拝領の儀式を受ける日を迎えます。ケイはママ・コルレオーネを伴います。聖水を指先につけ、軽く乾いた唇につけてから、十字を切る。
マイケルがマフィアのドンである事実を知ったケイは、苦悩の果てにマイケルと生きることを決意したのです。そしてケイが選んだのはママと同じように「祈る」ことでした。
ケイは罪をすべて洗い流し、恩寵を受けた祈願者として頭を垂れ、祭壇の手すりの上で指を組み合わせます。彼女は、マイケル・コルレオーネの魂のために祈りを唱えます。