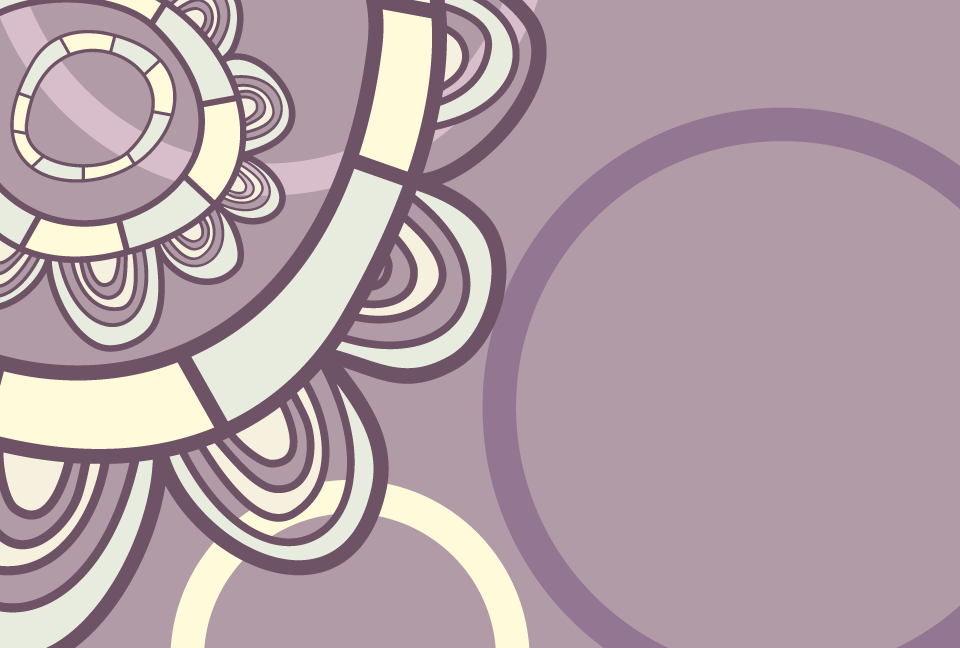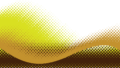恋の妄想を赤裸々に!
あれこれと想像する、その先に空想の翼を広げてみる。それは外側からは見えぬ、あくまで内側の心情です。そして時に楽しいものです。少年や少女であれば感受性を育むことになります。
しかしこれが度を越すと、妄想になり病的になってくる。この物語の主人公は、人生の倦怠期を迎えた妻子ある大人の作家です。相手は自分を慕って弟子になった若く美しい女性。
中年の男が若い女性に恋の妄想を膨らませます。やがて恋人が現れ、別れの時が来て、残していった夜具の匂いを嗅ぐ。性に惑溺していく内面の変化を描写します。現実には起こり得ない、誤った確信を抱いていきます。対象が恋ゆえにキモイのですが、それは真実を描き、美化を否定し心の思いをありのままに赤裸々に表現する手法でした。
田山花袋は美文家でもあり読みやすく分かりやすい文章です。傍目には分からぬ、恋の妄想を描いた『蒲団』。赤裸々な心の動きを、ぜひお楽しみください。
あらすじ
竹中時雄は生活に疲れた中年作家。彼は三年の月日が経った今、終わった出来事を名残り惜しく回想します。
三十六にもなって子供も三人いて、よくもまぁ、あんなことを考えたかと思うと、馬鹿々々しくなる。しかしあれだけの愛情を注いだのは恋ではなかったのか・・・としんみりと振り返る。
時雄は十九歳の横山芳子から弟子入りを乞う手紙をもらう。女が熱心なので師弟の関係を結んだ。
神戸の女学院でハイカラな生活を送り、美しいこと、理想を養うこと、虚栄心の高いこと、こういう明治の女学校の長所と短所を遺憾なく備えていた。
時雄の家に仮寓する。華やかな声、艶やかな姿、今までの孤独で淋しい彼の生活は一変。しかし女弟子を家に置くのはまずいとなり、細君の姉の家に寄寓させ其処から某女塾に通学させることにした。
芳子は時雄を慕い、それは基督教の教訓より自由で、権威があるように考えられた。芳子と時雄の関係は、単に師弟の間柄としては余りに親密であった。
四月末に帰郷、九月に上京。そして今回の事件が起こった。
芳子は恋人を得た。上京の途中、恋人と京都嵯峨に遊んだ。関係を問いただすと、神聖なる恋愛で二人は罪を犯してはおらぬが、将来は恋遂げたいとの切なる願望。
時雄は芳子の師として、この恋の証人として仲立ちの役目を余儀なくされた。芳子の恋人は同志社の学生、神戸教会の秀才、田中秀夫 年二十一。
時雄は悶えた。愛するものを奪われ心を暗くした。もともと芳子を自分の恋人にする考えはない。しかし、淋しい生活に色彩を添え、限りなき力をくれた芳子を突然、奪われることに耐えられなかった。
夕食の膳の酒量は夥しい量となり、泥鴨のように酔って寝た。
彼は三日間、苦悶と戦った。性格として惑溺できぬ一種の力をもっており、そのためにいつも圏外に立たされ苦しい味を嘗めさせられるが、世間からは正しい人、信頼するに足る人と信じられている。
「これからは師としての責任を尽くし、愛する女の幸福のためを考えるばかりだ、つらい、つらいがこれが人生だ!」と思った。
芳子から手紙が来た。
田中が上京してくる。目的は「今回の件で芳子が郷里に伴れて帰られると申し訳ないと、先生に打明け、お詫びし、情にすがり、円満に解決したい」と云う。
芳子が田中に「先生のお情け深い言葉、我ら二人の神聖な真面目な恋の証人とも保護者ともなって下さることを伝え、折を見て打ち明ける方が良い」と書いたとある。
さまざまな感情が時雄の胸を火のように燃えて通った。
芳子が田中を迎えに行った、何をしたか解らん。手を握ったかもしれぬ、胸と胸が触れたろう。旅籠屋の二階、何をしているか解らぬ。
「監督者の責任にも関する!」と腹の中で絶叫した。「保護しなければ」と思った。
そして酒をあおり、芳子を監督するために姉の家からもう一度、自分の家に置くために迎えに行った。
芳子の美しい姿、流行りの庇髪、派手なネイルにオリーブ色の夏帯、斜に座った艶やかさ。時雄は今までの煩悶と苦痛を半ば忘れて、有力な敵があっても占領すれば心が安まると考えた。
時雄は安心も満足もした。細君も芳子に恋人があるのを知って、危険の念、不安の念は全く去った。
芳子は師を信頼し、時期が来て父母にこの恋を告げる時、旧思想と新思想と衝突することがあっても、この恵み深い師の承認を得ることが出来ればと思った。
時雄は監督という口実で手紙を読んだ。手紙の中に接吻の痕、性慾の痕が、どこかに顕れていないか。神聖なる恋以上に進歩していないかと探すが、それは解らなかった。
一か月は過ぎた。
時雄は恋人が芳子に宛てた一通の端書をみて、平和は一時にして破れた。
そこには、
東京で文学をやるという。芳子は大学は卒業してくれと止めたが、田中は独断で決め、既に東京に向かっているとのこと。
平和は再び攪乱されることとなった。時雄は芳子の留守に思い切って恋人の下宿を訪問した。
田中という中背の、少し肥えた、色の白い男が祈祷をするような眼色で、同情を求めるように話した。時雄は「君が東京にいるなら、芳子を国に帰すか、この関係を父母に打明けて許可を乞うか、どちらかだ」と云った。
田中は東京に居たいというが、時雄は帰郷を勧めた。田中は秀麗でもなく天才肌とも見えず、基督教に養われた取澄ました、老成な厭な不愉快な態度だった。
時雄は考えた。寧ろ国に知らせて遣ろうかと。それをどういう態度でやればよいかを考えた。
翌日の夜、芳子が時雄の書斎に来て希望を述べた。
「如何に説いても男は帰らぬ。国へ知らせれば父母は許さぬ、二人の間は、決して汚れた行為などはなく惑溺することも誓って無い。暫くこのまま東京においてくれ」と頼み、時雄も京都嵯峨における女の行為に、その節操を疑いながらも弁解を信じ、そんなこともあるまいと思った。
それからお互いを行き来し、時雄はいつの間にか、二人の「温情の保護者」として認められていった。
時雄は苛々していた。二人の恋の温かさを見るたびに、罪もない細君に当たり散らして酒を飲んだ。
若い二人の恋が愈々人目に余るようになった。時雄は見るに見かねて故郷の父母に知らせた。
この恋に関しての長い手紙を芳子の父に寄せた。
芳子と田中との関係は、更に惑溺の度を加えた様子。余りに頻繁に二人が往来する。
時雄は芳子から来た封書を開く。
そこには「田中に従おうと思う。私等は二人で生きてみようと思う。先生にご心配をかけること、監督上、ご心配なさるのも御尤もながら、父母があまりに無慈悲ゆえ勘当されても仕方ない。堕落というがそんなに不真面目でもなく、家の門地というが父母の都合で致すような旧式の女でないことは先生もお許し下さるでしょう。二人して一生懸命に働けば飢えることもないでしょう。私の決心をお許しください」とある。
時雄は「温情の保護者」の態度を変えた。父母への手紙にはこの恋を許して貰わねばという主旨にした。想像通り父母は勘当すると言ってきた。二人は受けるべき恋の報酬を受けた。
彼は真面目に芳子の恋とその一生を考えた。一たび男子に身を任せて後の女子の境遇を憐れんだ。真面目な解決をせねばならぬという気になった。
時雄は父母に手紙を書いた。父たる貴下と師たる小生と当事者たる二人、相対してこの問題を真面目に議論すべき時節到来せり。貴下は父としての主張、芳子は芳子としての自由あるべく、小生は師としての意見を語り合うというものだった。
時雄の宅を訪問した父親の言い分は、
・女学生を上京の途中で泊まらせ、年来の神戸教会の恩人を捨て去ったりする男なので話にならぬ。
・宗教が厭になり文学が好きになったというのもおかしいし、東京に居るなども訳がありそうだ。
・結婚の約束は大きく、身分を調べ釣り合いも考えねばならないし、血統も知らべなければならない。
・神戸では多少秀才らしい男のようだが、説教や祈祷など大人も及ばぬ巧いことを遣りおったそうだ。
・なるたけは連れた帰りたくない、私も妻も村の慈善事業や名誉職などをやっており困る場合もある。
・貴方の仰しゃるとおりに、男を京都に帰して、此処一二年、貴方にお世話になりたいと思っている。
という内容だった。「それが好いですな」と時雄は言った。
時雄は京都嵯峨の事情その以後の経過を話し、二人は神聖の霊の恋のみで汚い関係はないだろうと言った。父親は頷きながらも疑いは消えず、娘についての悔恨の情が多かった。
一時間後には田中も来ていた。父親は軽蔑の念と憎悪の念を胸に漲らした。田中は服従という態度よりも反抗という態度が歴々としていた。恋する二人、殊に男にはこの分離は甚だ辛いらしかった。
時雄は「お父さんの言葉が解らんですか、君の罪も問わず、破廉恥も問わず、将来、縁があれば恋愛を承諾せぬではない。ともに修行中の身、一緒には置かれぬ。どちらかが東京を去るとなれば、追いかけてきた君になるのでは」と云った。
田中は「一緒に東京にいることは出来ないか」と云い、時雄は「監督上出来ん、二人の将来の為にも出来ん」と云うと、芳子が「私が帰ります」と涙を震わせていった。
京都嵯峨行きを弁解させるべく、身の潔白を証するための手紙を見せるように芳子に迫った。芳子は手紙は焼いたといって顔が赤くなった。
時雄は激さざるを得なかった。事実は恐ろしい力で彼の胸を刺した。欺かれたという念が烈しく心頭をついて起こった。
時雄のその夜の煩悶は非常であった。欺かれたと思うと、業が煮えて為方がない。芳子の霊と肉、その全部を一書生に奪われながら、その恋について真面目に尽くしたかと思うと腹が立つ。
あの男に身を任せていたくらいなら、その処女の貞操を尊ぶには当たらなかった。自分も大胆に手を出して、性慾の満足を買えば好かった。
芳子は時雄宛の手紙を書く。
「私は堕落女学生です。先生の厚意を利用して欺きました。どうかお憐みください。新しい明治の女子としての務めを行っておりませんでした。私は田中に相談して、このことは人に打明けますまい。過ぎたことは仕方がないが、これからは清浄な恋を続けようと約束したのです。けれど先生の御煩悶が私の至らない為と思いますとじっとしていられません。憐れなる女をお憐み下さいまし。先生にお縋り申すより、道がないのでございます」
時雄は、地の底にこの身を沈められるかと思った。
時雄は芳子に「こうなっては、あなたが国に帰るのが至当だ。今夜、これから父様のところへ行き一部始終を話し、国に帰った方がよい」と言い、芳子を父親に預けて帰宅した。
翌、父親は芳子を伴って来た。今夜六時の神戸急行で帰国するという。
時雄は以前より軽快であった。もうその美しい表情を見ることが出来なくなると思うと侘しさを感じるが、恋せる女を父親の手に移したことは愉快であった。
三年前、青春の希望湧くがごとく東京に出てきた時と比べて何という悲惨、何という暗黒であろう。
午後三時、車が三台来た。行李、支那鞄、信玄袋を車夫は運んだ。時雄は芳子の将来のことを思った。
妻が無ければ、無論自分は芳子を貰ったに相違ない。芳子もまた喜んで自分の妻になったであろう。理想の生活、文学的な生活、堪え難き創作の煩悶を慰めてくれただろう。一度、節操を破ったということが、却って年多く子供のある自分の妻たることを容易にする条件となる。
汽車は動き出した。
さびしい生活、荒涼たる生活は再び時雄の家に訪れた。生活は三年前の旧の轍にかえったのである。
五日目に、芳子から手紙が来た。時雄は田舎町を思いやった。
別れた後そのままにしておいた二階に上がった。懐かしさ、恋しさの余り、微かに残ったその人の面影を偲ぼうと思った。机、本箱、罎、紅皿、依然としてもとのままで、恋しい人はいつものように学校に行っているのではないかと思われる。
襖をあけてみた。芳子が用いていた蒲団―萌黄唐草の敷布団と、線の厚く入った同じ模様の夜着とが重ねられていた。
時雄はそれを引き出した。女のなつかしい油の匂いと汗のにおいとが言いも知らず時雄の胸をときめかした。
夜着の襟の天鵞絨の際立って汚れているに顔を押附けて、心ゆくばかりなつかしい女の匂いを嗅いだ。
性慾と悲哀と絶望とが時雄の胸を襲った。時雄はその布団を敷き、夜着をかけ、冷たい汚れた天鵞絨の襟に顔を埋めて泣いた。
薄暗い一室、戸外には風が吹暴れていた。
動画もあります、こちらからどうぞ↓