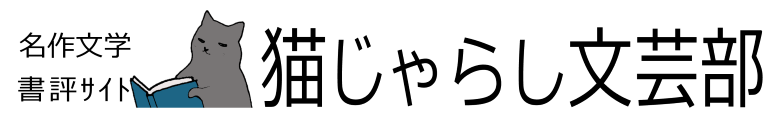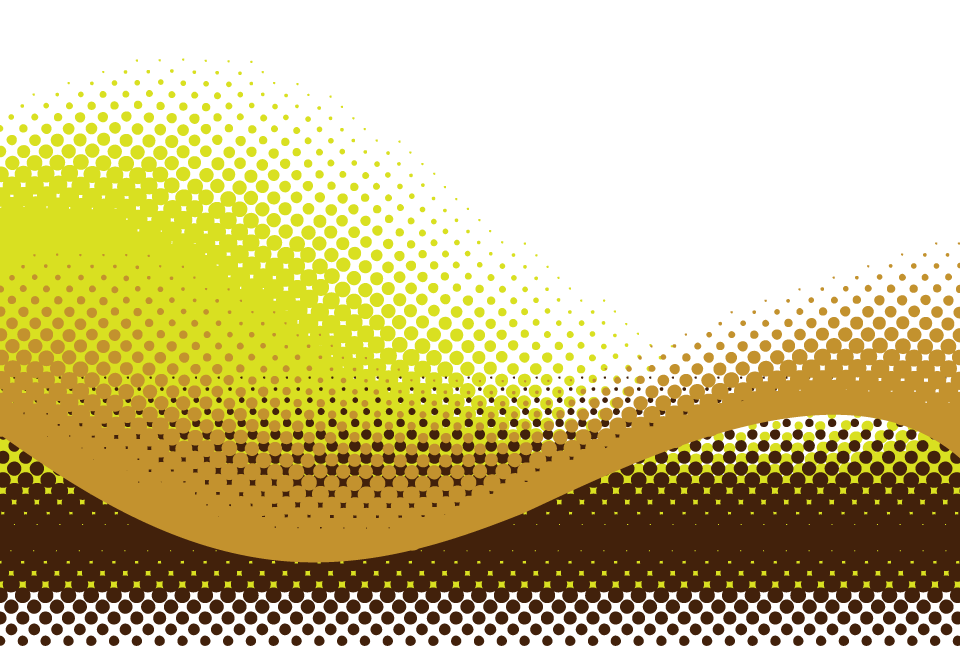不条理な日常から逃れるために砂丘を訪れた一人の男が、海辺の村落で砂穴に埋もれゆく一軒家に閉じ込められる。そこには一人の女が住み、女は男をひきとめようとする。逃れたい男と、巣ごもりする女。やがて男は、流動する砂の閉塞のなかで、砂を掻くだけの徒労のなかに新たな生きがいを見つける。複雑に構造化された現代から飛び立ちたいと願う自由と、巣ごもって誰からも邪魔されまいと願う自由の関係を描き近代社会の憂鬱から脱出の回路へと導く。
動画もあります!こちらからどうぞ↓
解説
八月のある日、男が一人、行方不明になった。休暇を利用して、汽車で半日ばかりの海岸に出掛けたきり、消息をたってしまったのだ。捜索願も、新聞広告もすべて 無駄に終わった。(1章)
七年たち、民法第三十条によって、けっきょく死亡の認定を受けることになったのである。(1章)
いったい、この男の身に何が起こったのか?男は何処で何をしているのか?倒叙ミステリーのような冒頭から、男の心情を巻き戻しながらその経緯を明らかにしていきます。
自己肯定感の強い、仁木順平という男。
いつか地面は砂地に変わり、男は砂丘に立っています。潮の香りがたちこめ、突然、視界がひらけ小さな部落があらわれた。そこは砂の斜面が家の屋根よりも高くなり、家並みが砂の窪の中に沈んでいる不思議な地形だった。
男の名前は、仁木順平。中学教師。教師という仕事に失望している。子供たちを流れる川の水に例え、教師を川底に沈殿する土に例える。そんな我が身を思えば、人生によりどころがあるなどと 子供に希望を持たせる教育の仕方に仁木は否定的だ。
教師の世界は灰色だと感じている。教師くらい妬みの虫にとりつかれた存在も珍しい。彼等は自分をぼろ屑のように感じ、孤独な自虐趣味に陥るか、他人の無軌道を告発しつづける。
妻はいるが、うまくいっていない。情熱を失ったというよりも情熱を理想化したあげくに、凍りつかせたと考えている。男は妻のことを「あいつ」と呼びすてる。常に意見は対立し、心が通わず、関係も冷めている。そしておふざけに、妻あてに、「しばらく一人旅に出る」と書いた手紙を、部屋に残したままこの旅に出てきてしまっている。
不自由で息苦しく呼吸困難になりそうな仕事と家庭、こんな日常から逃れて夢を追いかける。
そんな自分探しが昆虫採集である。あわよくば、新種のニワハンミョウを発見して、長いラテン語の学名と自分の名前がイタリック活字で、昆虫大図鑑に記載され半永久的に保存されて、人々の記憶にとどまることを考えている。 男は自己実現と強い承認の欲求を持っている。
砂の流動性こそが、自由の象徴である。
男はハンミョウを存在させる砂にも関心を持っていた。流動化する砂のイメージは、男に衝撃と興奮を与える。
しがみつくことを強要する現実のうっとうしさと比べ、何という自由だろう。砂は生存には適さないが、しかし、定着が生存にとって絶対に不可欠かどうか。定着に固執するから煩わしい競争もあると考え、男は砂に魅了される。
海と反対側の斜面を下りると大地があり、崖になっていた。見下ろすと幅二十メートルの楕円形をした穴になっていて向こう側は緩やかに、こちら側は垂直に近く感じられた。覗きこむと穴の底に小さな家が一軒、ひっそりと沈んでいた。
村の長らしい老人が話しかけてきた。もう帰りのバスはないという。泊まる家を世話してもらい案内された家は、別の穴の中の一つだった。
老人は「おい、婆さんよぉ!」と大声で叫んだ。「ここ、ここ・・・俵のわきに、梯子があるから・・・」と闇の中からランプの灯がゆらいで、答えがあった。
砂の崖は屋根の高さの三倍はあり、梯子を使わねばならなかった。「気がねはいらんから、ゆっくり休んで下さい・・・」老人はそう言って引き返した。
こうして、男はこの家に泊まることになる。後でわかるのですが、あたりはいくつもの家々が穴に沈み込んでいて、この海辺の集落自体が砂に覆われようとしており、それを防ぐために、男はこの家へ労働力としてあてがわれたのでした。
つまり男は、この村に迷い込み、捕われ、閉じ込められたのです。
砂を掻く一人の女、それは不当で奇怪で徒労。
穴の中の一軒家には女が一人で住み、砂を掻いて暮らしていた。三十前後の人が好さそうな小柄の女で、浜の女にしては色白だった。喜びを隠しきれない歓迎ぶりが有難く思われた。
つまり「女」は「男」を必要としていたのです。男は働き手として、子孫を残す種として待望されていたのです。
家は壁がはげ落ち、襖のかわりにムシロがかかり、柱はゆがみ、窓にはすべて板が打ちつけられ、畳はほとんど腐る一歩手前で、歩くと濡れたスポンジを踏むような音を立て、その上、焼けた砂の蒸れるような異臭がいちめんに漂っていた。
いまにも砂に圧し潰されそうな酷い状態ながら、男はこれもまた面白い経験だと思い一泊させてもらうことにする。
「まず、風呂にしたいんだけれど」と言うと、「明後日にして下さい」と言われ、「明後日?ぼくはいませんよ」と男は大声で笑った。「そうですか?」女は顔をそむけ、ひきつったような表情をうかべた。
ここでは水が非常に貴重であることが伏線となっています。
女が食事を運んできた。魚の煮つけに貝の吸い物だった。女が番傘をさしかけてくれた。こうしないと天井から砂が降ってくるという。女は一人住まいで、亭主と娘は去年の台風で砂に埋まって亡くなったという。
しばらくして、上からもう一人分のカンカラとスコップが降りて来た。それは “私の分” ということだった。
男は日常からの束の間の逃避のつもりが、囚われの身となり労働力として使われようとしていることを気付くことになるが、まだ事の成り行きをよく理解できていない。
外に出てみると、女が器用にスコップを使って石油罐の中に砂を掬すくいこんでいた。砂につぶされないように、日々、砂を掻きながら女は暮らしている。砂が湿る夜の時間に砂掻きをして、砂が崩れるのを防いでいるという。夜は砂が露を吸って糊のように固まるが、午後になって乾くとどかっと落ちて来て、ひとたまりもないという。 村では夜中に砂掻きをする決まりになっていて、昼よりも夜は賑やかだ。
男は、女の話す砂の説明と行動に愕然とする。男が砂に抱いてきたイメージとは大きく異なっていたのだ。さらに掻いた砂と引き換えに水が配給されているらしい。
砂掻きは村の絶対の規則であり、この砂掻きによって集落全体の存続が成り立っているということを知るのである。
穴の上では、俵にロープをあてがい、モッコの上げ下ろしをする。モッコ作業の若者は4人で2.3組あり6回の上げ下ろしで、砂の山が平らになった。
「大変だね、あの連中も」と男が言うと、「うちの部落じゃ、愛郷精神がゆきとどいていますからねぇ」と女は言った。
女が発した愛郷精神という言葉には、文字通り皆が村を愛しており一致団結して砂から集落を守っている共同体の絆があることを意味している。この部落を維持するための過酷な労働、日々の砂掻きを一軒でも怠れば、部落全体が砂に埋ってしまうのだ。
この作業を夜を通して朝までやるという。男が「まるで砂掻きをするだけのために生きているようだ」と言うと、女は「だって、夜逃げするわけにもいきませんしねぇ」と言う。男は、あまりにも不当で、あまりにも奇怪で、そして徒労だと思った。
自由を求める、不条理からの脱出。
目を覚ます。顔からも、頭からも、胸からも、つもった砂が、さらさらと流れ落ちた。唇と鼻のまわりには汗で固まった砂がこびりついていた。
女はイロリの向こうで素裸で寝ていた。手拭いを顔にあて、眼と呼吸器は砂から守っていたが、顔以外の全身をむきだしていた。男は、女が自分を誘っているようにも感じる。
こんな理不尽な方法で自由を奪われてはたまらないと、男は憤慨する。
出発の身支度をして外に出た。すると信じがたいことに昨夜、俵のところにあった縄梯子が消えていた。男は、表の世界へは戻れない、砂の穴に閉じ込められたのだ。
よじ登れそうなところを探した。海に面した北側がいちばん短いが、家の屋根から十メートル以上はあり急だった。西側は比較的、傾斜がゆるく四十五度前後だが、一歩進むと半歩ずり落ちた。やけになってもがくと穴の底にころげ落ちた。
縄梯子が外されたのは、女の承認であり、裸体は生贄の姿勢にちがいない。まんまと策略にかかったのだ。蟻地獄の中に閉じ込められたのだと男は気づいた。
男はこの砂の穴の中に住む女と暮らすことを、村の共同体から命じられているのだ。
男は、突然、狂ったように、叫びだす。一体どういうことなんだ!
ちゃんとした戸籍を持ち、職業につき、税金もおさめていれば、医療保険証も持っている、一人前の人間を、まるで鼠か昆虫みたいに、わなにかけて捕らえるなどいうことが、許されていいものだろうか。信じられない。(7章)
男はこれは何かの誤解に違いないと 思おうとつとめた。しかしまた、
ここはもう、砂に浸蝕されて、日常の約束事など通用しなくなった、特別の世界かもしれない。(7章)
そう思うと、この村に迷い込んでからのすべての辻褄が合うような感じがした。
女は、「もうお分かりでしょう」と言い、「本当に女手一人ではここの生活は無理で、これからは北風の季節で砂嵐の心配もあります」と言う。
男は「自分だけでなく女も被害者であり、誰もあなたをここ閉じ込める権利など無い」と説明する。
そして木の梯子をつくることや、砂の傾斜を緩やかにすることで脱出を考える。男は、スコップで掘り続ける。しかしいくら掘っても崩れるのは掘った真上のほんの僅かな部分だった。確かめてみると、勾配は依然として元のままである。
日常の義務やわずらわしさから逃れるために、しばし訪れた憧れの砂丘のはずが、 砂の穴に落ち、その一軒家での生存を強いられ、予想もしない不条理のなかにある。
日常から逃避し自由を求めた男は、非日常の不自由に閉じこめられてしまうのだ。これまでの自由は消えようとしている、男は、何としても抜け出そうとする。
しかし砂穴に住む女も集落の人々も男の脱出を拒んでいる。
欠けて困るものなど、何ひとつない。
男は長時間、直接日光に晒され、馴れない労働を続けたため気を失ってしまう。高熱と執拗な嘔吐に悩まされた。四五日目には回復したが、彼は仮病を装った。
三日間の休暇はとうに過ぎ、一週間。そろそろ捜索願いが出されていてもいい頃である。
《姓名、仁木順平。三十一歳。一メートル五十八、五十四キロ。髪はやや薄く、オールバック、・・・肌はや浅黒く、面長。・・・血液型はAB型。内向的で、頑固だが、人づきあいはとくに悪いというほうでない》(11章)
彼は久しぶりに新聞を読んでみたいと頼んでみた。尋ね人の広告が出ているかもしれない。素早く社会面と地方欄に目を通すが、失踪記事も尋ね人の広告も見当たらなかった。
新聞記事はさまざまだった。しかし・・・
欠けて困るものなど、何一つありはしない。(13章)
幻の煉瓦を隙間だらけにつみあげた、幻の塔だ。もっとも、欠けて困るようなものばかりだったら、現実は、うっかり手もふれられない、あぶなっかしいガラス細工になってしまう・・・要するに、日常とは、そんなものなのだ・・・だから誰もが、無意味を承知で、わが家にコンパスの中心をすえるのである。(13章)
利便性は高いが、不条理な都市定住のなかの不自由な思いと、砂を掻き暮らしていく不自由な日々への従属を比較してみる。
それでも脱出を諦めてはいない、男は作戦に出た。女を黙らせてさるぐつわをした。モッコ搬びの声が近づき、ロープが降ろされると、男はロープに指をからませる。
ロープは途中まで引き上げられたが、そこで連中はロープの手を離した。男は半回転して落ちて行き、首の付け根から下に砂の上に投げだされた。
やがて “男手があるところへ” ということで、酒とタバコの配給があった。
財産持ちも貧乏人も働きがいのあるものは部落から出て行くという。人手が不足しこれまでに同じように絵葉書屋のセールスマンがいたが亡くなり、帰郷運動の学生は三軒おいた隣に今もいるという。
逃げた人は誰もいないし、一か所でも崩れると堤防にひびが入り危ないと女が言う。
都市化は過疎化をもたらす。地方から流出していく働き手世代。若者は田舎を捨てて都会へ出て行き、地方は過疎化する。やがて窮屈な都会から逃避し、自由に憧れ、砂丘を訪れる夢見る人々。そして、まんまと蟻地獄に誘い込む構造なのか。
これもまた砂に埋もれゆく海辺の村の生存をかけた欠くことのできない循環でもある。
極限の喉の渇きと、安堵による順応性。
男は許可なしにスコップを持たないことを条件に、女の縄を解いてやる。
ストライキを続行し、男はスコップで板壁を壊し梯子の材料をつくろうとした。 女は止めようとして組み合いになり、重なり、そのまま肉体関係を持ってしまった。
水、水、水。喉が渇いてどうにもたまらない。やかんにも水甕の底にも水は全くなかった。水の配給を得るためには砂掻きの労働が必要だった。男は仕方なくスコップを持った。女の声がした。崖の上に向かって呼びかけ、例の老人がロープの先に水が入ったバケツをたぐり降ろした。
バケツの中に男は顔を突っ込んで水を貪るように飲み、女が続いた。
男は老人と交渉を試みた。この砂掻きの重要性の理解や、自分は砂の専門家であること、この場所を観光地にしたり農産物を開発したり砂防工事をしてはどうかなどと話すが、老人は今のやり方がいっとう安上がりと言い、男の話を聞き流すだけだった。
そして「わしらに出来るだけのお世話はいたしますから」といって消え去った。
男の説得は通じなかった。口先だけの都会人の提案など、信じることはできないのだろう。自然と向き合っている集落は、砂のことを一番、良く知っているのだ。
砂と闘い、村の生活を守り、村を存続させえる方法は、村を愛する人々しか見いだせないのだ。
連中は渇きの恐怖を知っている・・・。男は女と一緒にスコップを掘り進んだ。
やがて砂の山ができ、石油罐に入れて広い場所に運び出す。移し終えると、また先に掘り進む。一週間が経ち、もう思ったほどの抵抗は感じなかった。男は女と肉体関係を持ち、砂を掻く作業を受け入れる自分に気づく。
男は考えが少しずつ変化する。この変化の原因はいったい何だったのだろう。水を絶たれる恐怖のせいだろうか、女に対する負い目だろうか、それとも労働自身の性質、つまり労働そのものがどこか充実した気持ちにしてくれるのか。
そう言えば、男は何か講演を思い出した。
労働を越える道は、労働を通じて以外にはありません。労働自体に価値があるのではなく、労働によって、労働をのりこえる・・・その自己否定のエネルギーこそ、真の労働の価値なのです。(22章)
モッコが降ろされ予定量の砂が無事に搬はこび上げられると、ほっと緊張がゆるむ。
脱出に失敗する、そして死の恐怖の後に。
それでも男は砂穴の蟻地獄からの脱出に執念を燃やした。家のなかのこまごまとしたものでロープをつくり端に錆びた鋏を挟み固定した。穴の上の地形や地図は女から大まかに聞くことができた。
女が眼を覚ます直前にここを出て、日が沈むのを待って行動をすることに決めた。
火の見櫓からの監視が心配だったが、靄がたちこめて視界が遮さえぎられる時間を選び、実行は土曜の夜を選んだ。
屋根に上がり、縄梯子を固定する俵めがけて何度か繰り返し、十何度目かでうまくロープがかかり、抜け出すことができた。
その四十六日目の自由は、激しい風に、吹きまくられていた。(24章)
やがて部落の外れに出たらしく、道が砂丘の稜線に重なり視界がひらけ左手に海が見えた。男は部落から遠ざかろうとした。しかし同じところをぐるぐる歩いていた。
何だ、これは!男はうろたえた。いきなり部落の全景が目の前にあった。
部落に接した砂丘の峰に向かって直角に歩いてきたらしい。視界がひらけた途端に部落の中に入り込んでしまった。
男は走った。半鐘が鳴りだし、犬が吠え続け、子供たちが泣いている。
懐中電灯が彼を包囲し距離をつめてきた。一見、不器用そうに見えた彼らの追跡は、実は海の方へ追いつめる計画的なものだった。知らずに彼は誘導されていたのだった。
急に走りづらくなり、足がぬかるみはじめた。底なし沼のような砂地で溺れ死にそうになる。
たのむ、助けてくれ!・・・どんなことでも約束する!・・・おねがいだから助けてくれよ!・・・おねがいだ!」(26章)
ついに男は、泣き出してしまった。嗚咽から号泣に変わり観念した。脱出失敗、立ちはだかる自然に無様に敗北する。
村の人々に助けられた。そして再び、穴の中に吊り下ろされた。
男は女に「失敗したよ」と言うと、女は男に「でも巧うまくいった人なんて、いないんですよ、まだいっぺんも・・・」と言った。
女のいたわりの言葉を、男はかえって惨めに感じる。
十月、陽が沈めば肌寒く感じられた。
男は《希望》と名付けた鴉(からす)を捕らえる罠をしかけてみた。捕まえて、足に手紙をつけて放ち、誰かが発見してくれることを妄想してみた。
男はいきがいを見つけ、新たな生き方を知る。
女はラジオの頭金のために糸にビーズ玉をとおす内職をはじめた。
男も単調な仕事に精を出すことにした。天井裏の砂はらいや米をふるいにかける仕事、洗濯などを日課とした。脱出に失敗してから慎重になり穴の中の生活に順応し部落の警戒を解くことに専念した。
睡眠中にかぶる小型天幕の公案や、焼いた砂のなかに魚をうめて蒸し焼きにする工夫などもした、新聞も読まなくなった。男は繰り返される砂との闘いや、日課になった手仕事にささやかな充足を感じた。
女はここの砂は売り買いを組合がしていて自分たちに不公平なくしてくれると明かす。
塩気の多い砂をセメントに混ぜて密売していると言う。男がたしなめると、女ははじめて声を荒げた。
かまいやしないじゃないですか、そんな、他人のことなんか、どうだって!(29章)
部落の側からすれば、見捨てられているのはむしろ自分たちで、外の世界に義理立てするいわれは何もないという。女を通して部落の顔が見えた。
生き延びるためには、奇麗ごとの都会人の道徳や倫理は役に立たない。他者を騙しても、生き残ることが優先されるのだ。
男は一日に一度、三十分でいいから海を眺めることを老人に相談すると、老人は「あんたたち、二人して、表で、みんなして見物している前で、雌と雄がつがいになっての、あれをみせてくれたら」と言う。モッコ運びの連中がどっと気違いじみた笑い声をたてた。
「どうしようか」と男が女に訊ねる。「あんた、気が変になったんじゃないの?気がふれてしまったんだよ、そんなこと容赦しやしないからね、色気違いじゃあるまいし!」と女が答える。
男は女の気配に狙いをさだめ、いきなり体ごとぶつかっていった。穴の三方の光が夜祭のかがり火のようだ。男は女に下腹を突き上げられ、拳がめり込み、鼻から血が吹きだして失敗した。
男はこれまでこの女と集落を見下していたが、自分の望みのためには恥も顧みない利己的な態度をとっており、今度は、砂の女が男をたしなめている。
この男と男の生きてきた社会と、砂の女とこの集落の人々の関係が逆転した。
原始的と近代的、動物的と理性的の逆転でもある。
さらに言えば、男が村に順応した瞬間かもしれない、薄っぺらな自意識がなくなったのである。そしてこのシーンは、野卑だがどこか祝祭的な記憶として、残ってしまう。
こうして変わりばえのしない、砂と夜の数週間が過ぎ去った。ある日、男は《希望》の蓋を開けてみて水が溜まっていたことに驚いた。砂の毛管現象である。表面の蒸発が地下の水分を引き上げるポンプの作用をしているためだった。
男は研究次第では高能率の貯水装置だって出来ると考えた。砂の中から水を掘りあてたのだ。水がある限り部落の連中にびくともしなくていいのだ。
男は興奮した。そして、
どうやら、これまで彼が見ていたものは、砂ではなく、単なる砂の粒子だったのかもしれない(31章)
彼は、砂の中から、水といっしょに、もう一人の自分をひろい出してきたのかもしれなかった。(31章)
いつしか男は砂穴の生活が居心地の好いものに変わり、溜水装置の研究に情熱を持ちはじめる。
正確な資料を作るにはラジオで天気の予報や概況を確かめる必要があった。ラジオは二人の共通の目標となった。冬が過ぎ、春になった。三月のうちにラジオが手に入り女は幸せそうに驚嘆の声をくりかえす。その月の終わりに女が妊娠した。
二か月後、女は子宮外妊娠で町の病院に入院させることになった。女がロープで連れ去られ、縄梯子はそのままになっていた。男は、待ちに待った縄梯子を海の見えるところまで登ってみる。穴の底を見ると、溜水装置の水が溜まっていた。家の中ではラジオが何やら歌っている。
「べつにあわてて逃げる必要もないのだ」男はそう思った。
男は溜水装置の開発のことを誰かに話したい欲望ではちきれそうになっていた。話すとすれば、ここの部落のもの以上の聞き手はあるまい。逃げる手立ては、また考えればいいと思った。
男の失踪に関する届け出から七年が経ち、妻(仁木しの)の申し立てで、家庭裁判所の審判により仁木順平は失踪者と審判された。