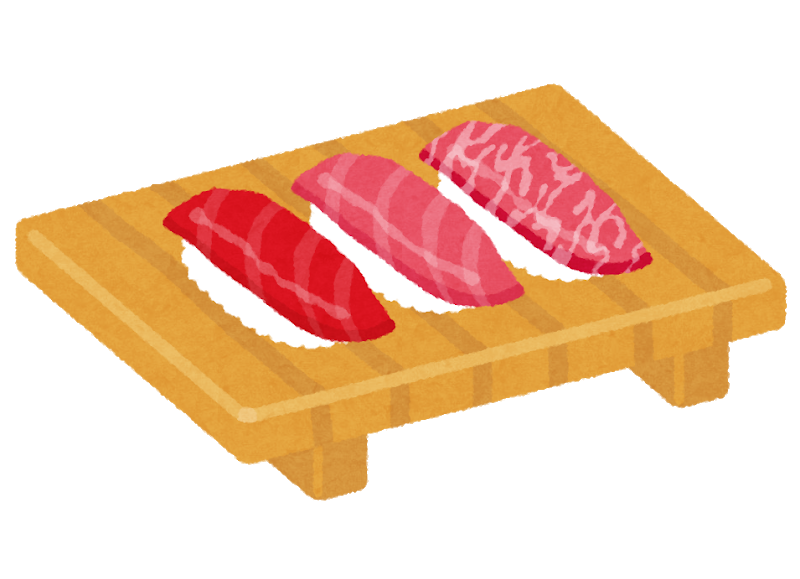解説
小僧の境遇と心の中にある、大人への好奇心や背伸びと現実世界。
上方言葉の「丁稚」に対して江戸言葉では「小僧」となる。小僧は、一〇歳前後で商家に住み込み使い走りや雑役をする。客や外の人からは「小僧さん」と呼ばれる。仕事は多岐にわたり力仕事も多い。
一〇年くらい経て「手代」、そして「番頭」となるのが三〇歳前後である。もちろん奉公なので給与など無い。給与は手代より上からである。物語の仙吉は、一三、四であるから「手代」になるまでにあと六、七年はかかりそうだ。
それまでは辛抱である、鮨屋の話を楽しそうにしている「番頭」になるには、さらにその先となる。
仙吉の言葉を順に連ねていくと「ああ鮨屋の話だな」→「色々そう云う名代の店があるものだな」→「然し旨いと云うと全体どう云う具合に旨いのだろう」→「一つでもいいから食べたいものだ」→「四銭あれば一つは食えるが、一つ下さいとも云われないし・・・」と続く。
ここまでは、仙吉は番頭たちの話を聞きながら鮨のことを思い、早く気軽に入れるような身分(番頭)になりたいなぁと思いながら、唾を飲み込んでいる。苦しい毎日だろうが、未来を思えば、微笑ましくもある。
そして小僧は、大人への背伸びや好奇心で鮨屋の暖簾をくぐるという冒険をする。
使いの往復の片道分を浮かした四銭で鮨屋に入る。そして「海苔巻きはありませんか」と変に大人びるが、あいにく海苔巻きは無く、成り行き任せで、憧れの鮪の脂身に手を伸ばすが、「六銭だよ」と言われ、持った手を放し何も言わず一寸動けなくなるが、なんとか勇気を振るい起して店を出る。
この描写は、貧しさというよりも、寧ろ、小僧の大人への冒険心を感じさせる。寿司への憧れと、食べることの叶わなかった気持ちが、少年の無念さとして読者に細やかに伝わってくる。
心優しいAの試みの実行とその後の淋しさ、小僧にとっての神様。
芥川龍之介は、文芸評論『文芸的な、余りに文芸的な』の中で、「最も純粋な」小説の名手として、志賀直哉をあげている。そして人生を清潔に生きている作家として、道徳的なテーマとそこに潜む苦痛と人間愛が底流にあると評する。
大正という時代であり、その時代の商売人の風景であり、番頭‐手代‐小僧という使用人たちの日常の会話があり、そこから偶然、起こった小僧にとって不思議な体験だ。
志賀直哉の人物評からこの作品を素直に読むと、裕福な貴族議員のAは、たまたま居合わせた鮨屋で、小僧の所作の一部始終を見てしまい、可哀そうだなぁと思う。
偶然、秤屋でその小僧と再会したことで、鮨屋の出来事を気にかけていた心優しいAは一計を講じる。まだまだ長い小僧の奉公の修行、けなげな少年に対して、鮨を腹いっぱい食べさせてあげたい。
そこでAは、<秤屋で購入した体重計を運ぶお礼>との名目で鮨を食べさせようと案じる。ここで、お腹いっぱいに三皿を平らげた小僧だが、後で、あの時の四銭で訪れた鮨屋に居合わせた人なんだなと考える、でもどうして番頭さんの話に出た鮨屋の店まで知ったのだろうと不思議がる。
一方のAは、自分のした行為が、小さな悪事の後味の悪さのように感じる。自分のような気の小さい人間のすることではなかったと後悔する。
それでも小僧は、神様がいるような気持がして、苦しいときにはそのことを思いながら仕事に励む。
作者の意図は偽善の話ではない。その証拠にAは自分の成したことに随分と悩んでいる。せめて荷を運ぶ代償ということにしています。そして、最後に作者は、記した住所には「お稲荷の祠があった」という部分は小僧に残酷なので割愛したと書いています。
まだ「お天道様が見ている」ような世間が、この日本にあった倫理観に満ちた時代の物語なのです。

※白樺派のおすすめ!
志賀直哉『正義派』解説|真実を告げる勇気と、揺れ動く感情。
志賀直哉『清兵衛と瓢箪』解説|大人の無理解に屈せず、飄々と才能を磨く少年。
志賀直哉『范の犯罪』解説|妻への殺人は、故意か?過失か?
志賀直哉『城の崎にて』解説|生から死を見つめる、静かなる思索。
志賀直哉『流行感冒』解説|パンデミックの時にこそ、寛容の大切さ学ぶ。
志賀直哉『小僧の神様』解説|少年の冒険心と、大人の思いやり。
武者小路実篤『友情』解説|恋愛と友情の葛藤に、辿り着いた結末は。
作品の背景
志賀直哉の中期の作品である。大正3年に武者小路実篤の従妹と31歳で結婚。この結婚は父の反対を押し切って行われ、長い父との不和はこのとき極限となり、自ら除籍し別の一家を創設します。さらに師とする漱石に朝日新聞の執筆をすすめられるも約束を果たせず、大正3年から5年までは空白期となり、漱石没後、解放感もあり動から静へ、反抗から和解へと転回します。
そして「佐々木の場合」「城の崎にて」などに続く「小僧の神様」で、志賀直哉は『小説の神様』と呼ばれました。この作品は、偽善を戒めるような内容ではなく、寧ろ人間愛や道徳観を大切に思いながらも、その純粋さを疑い苦渋しています。この貴族議員Aやその妻の会話の中には、清々しさがあり、最終的には人間賛歌で結んでいます。
発表時期
1920年(大正9年)1月、『白樺』にて発表。志賀直哉は当時37歳。この作品で「小説の神様」とよばれるほど知名度を上げます。代表作に「暗夜行路」「和解」「小僧の神様」「城の崎にて」などがあり、白樺派を代表する小説家の一人。
白樺派は、親友でもあった武者小路実篤と志賀直哉が中心となり学習院の十数人で発刊。大正デモクラシーと自由な空気を背景に人間の生命を謳い、理想主義や人道主義的な人間肯定を指向します。