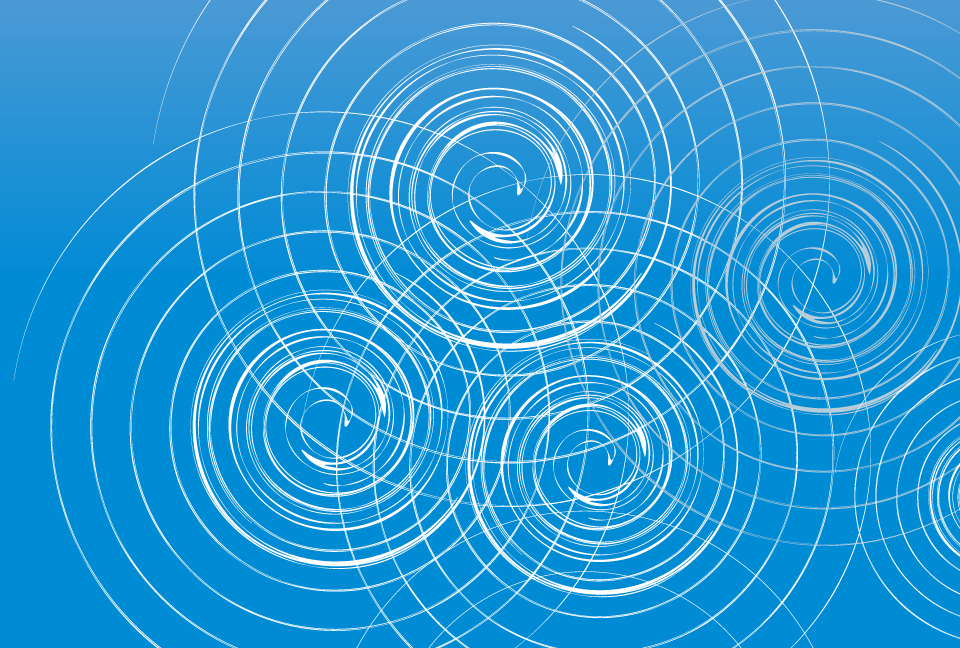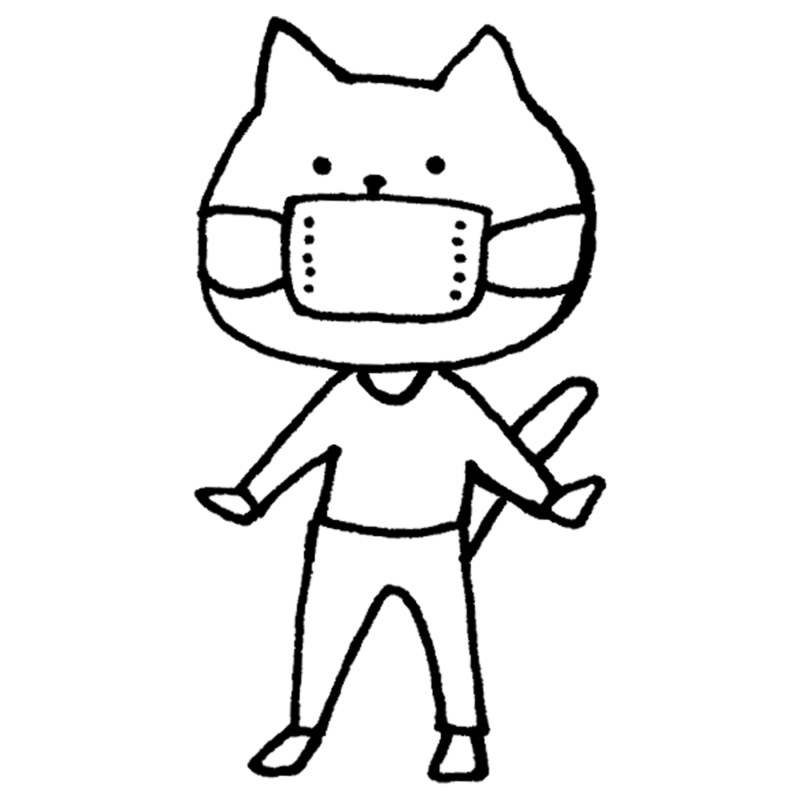
今からおよそ100年前、日本にもスペイン風邪の猛威が襲います。多くの日本人が感染し、致死率は新型コロナウィルスよりも高いものでした。このパンデミックのもとで暮らす人々の日常を、志賀直哉は自身と家族、女中たちとその親元、そして地域のなかで描いています。情動的な行動に対する誤解や短慮による人間関係や共同体の絆の結び目の危うさ。現在のコロナ禍の私たちと照らし合わせながら、古の文豪の思いを訪ねる興味深い作品です。
登場人物
私(主人公)
千葉の我孫子に住み長女が夭逝し、流行感冒の中で幼い次女佐枝子を過保護に扱う。
妻(春子)
私の伴侶として従い尽くしながら、同時に佐枝子を育て女中や村の人々と向き合う。
佐枝子
私と妻のあいだに産まれた次女。長女は夭折し、石にあやされることを喜んでいる。
石
私たち夫婦が雇っている女中で、佐枝子の守や家事をするが禁じた夜芝居を見に行く。
きみ
雇っているもうひとりの女中で、石と同じく佐枝子の守や家事の手伝いをしている。
動画もあります、こちらからどうぞ↓
あらすじ
過酷なパンデミックのなか、人間への信頼と不信が交錯する。
作品名の『流行感冒』とは流行性の感冒のことで、当時、世界的に流行したスペイン風邪と呼ばれた
<A型インフルエンザ(H1N1亜型)>のことです。
長女が夭折(ようせつ)し、大正6年に次女が産まれた志賀直哉ですが、愛娘(まなむすめ)への感染を心配する父親と妻、そして二人の女中たちの日々を描きます。家族の移り住んでいた千葉の我孫子と東京の暮らしぶりの違いなどもうかがえる作品です。
都会と比べ、田舎の開放的な子供たちや無防備な共同体のあり方に、私は、そもそも不安で心配なのです。そこに流行り病が襲います。
1919(大正8)年に発表されたこの作品の原題は『流行感冒と石』でした。実はこの物語は、流行り病のなかでの石という女中の人物評を語っているわけです。
「石」を通しての人間観察のなかで、「私」に起こる心情であり、心理や態度の変化であり、石から学ぶことのできた寛容の眼差しの大切さを、私が知るに至るまでの淡々とした時間の連続の物語です。
愛娘への過保護が過ぎて暴君となる私に対して自分がこうと思うことには周囲を省みない石との間で、人間の感情が曝け出され、摩擦が起こりますが、やがて真意を悟り、相手を思いやる心の大切さを教えられる内容になっています。
女中の石の性格と言動が、家長の私の理解を超え暴君と化す。
ついに流行性の感冒が我孫子の町にも流行ってきた。
私は注意して運動会に行くことを止め、女中にも町へ出て店先で長話をしないように厳しく云う。毎年十月中旬に町の青年会の催しで夜芝居があるが、今年は女中たちが行くことを禁じた。
女中の石は「こんな日に芝居でも見に行ったら、誰でもきっと風邪ひくわねえ」ともう一人の女中のきみに云っていた。それでも村人たちは無防備で無警戒な様子である。
幼い佐枝子の健康を思いたとえ暴君と思われようと、石やきみの行動を細やかに注意し、多くの人々が集まる芝居興行は特に厳禁とした。
或る夜、石がいないことが分かる。もう一人の女中のきみが言うには「元右衛門のところへ薪を頼みに行った」とか。私はそれを聞いて心配になり不機嫌になる。夜十二時近くになっても帰ってこない石に妻も憎らしく思う。
翌朝、妻が確認すると「芝居には行っていない。元右衛門のおかみさんが風邪で寝ていて、そこに石の兄さんが来て話し込んだ」と石は云う。
私が石に「芝居には行かなかったのか?」と訊ねると、「芝居には参りません」と明瞭した口調で答え「元右衛門のおかみさんは風邪をひいていない」と云う。
私は信じられなかったが、答え方が明瞭しており、疚しいところがなかった。だが附に落ちなかった。話も食い違っている。そして私は石のことを「嫌いだ」と妻に云った。
そうして私は妻に「なるべく佐枝子を抱かさないようにしろよ」と云っていたが、石はもう平常通りの元気な顔をして佐枝子をあやしていた。
私は妻の無神経に腹を立て、妻と石に「馬鹿。石に佐枝子を抱かせちゃ、いけないじゃないか。二三日はお前佐枝子を抱いちゃ、いけない」と不機嫌を露骨に出して云う。
妻も石も嫌な顔をした。石は少しぼんやりした顔をしていたが、妻に佐枝子を渡すと小走りに引き返し振り返りもせずうつむいて駆けて行ってしまった。
私は不愉快になり如何にも自分が暴君のように思えた。
石もきみも出て行った。私は「誤解や曲解から悲劇を起こすのは何よりばかげている」と思う方で、できるだけ信じたいが、実は石を全疑しており、自身の気持ちの不統一が、かなり不愉快だった。
石が沼向こうの家に帰って両親や兄に訴えている様子が浮かぶ、私は解らず屋の主人であり暴君である。妻から執拗いと言われ「黙れ」と癇癪を起してしまう。
話が全て噓だとわかり、厳格な私は石を嫌いになる。
女中が二人共にいなくなって不便になり、二人の世話人のところへ行った。
ところがやっぱり石は芝居を見に行っていた。隣のおかみさんに誘われて、きみと三人で行ったということが分かった。
私は石に、もう暇をとって帰すことにした。石と石の母親が挨拶に訪れる。
母親は不愉快な感じを隠し切れない。嘘をついたぐらいで何もそんなに騒ぐことはないと思っているようだった。却ってそれを云い立てて娘を非難する主人の方が遥かに性の悪い人間に見えたに違いない。石は赤い眼をして工合悪そうに只お辞儀をした。
妻が私を呼んで狭い土地だから失策で暇を出されたとなると、後まで何か云われて可哀想だからもう少し置いておけませんかと哀願するので、「・・・・そんなら、よろしい」と云った。
妻は「旦那様はそりゃ可恐い方で、上手に嘘をついても心の中をお見透しなんだから」と石に云い、石がびっくりしたような顔をして、はあ、はあと云っていたのを笑い、私が「馬鹿」と云うと、そのくらいの方がいいと妻は真面目な顔をした。
ところが石は、実は一人で行ったのであった。
きみまで同類にして知らん顔をしていた。妻の御愛嬌な嚇しは石には効いてはいなかった。私は石が嫌いになり不愛想な顔をした。
守りと家事の献身的なふるまい、保身ではない石の情動を知る。
三週間経って流行感冒は下火になった。ところが私が植木屋から感染し四十度近い熱が出て、腰や足がだるくて閉口し一日苦しんだが良くなった。
すると今度は妻に伝染し間もなくきみが変になりとうとう肺炎になった。さらに東京から呼んだ看護婦に伝染り、しまいには佐枝子にも伝染ってしまい、健康なのは済ましている村の看護婦と、石だけになった。
石はまだ伝染る前の佐枝子をおぶって寝かせつける。しかし佐枝子はすぐに眼を覚まして暴れ出す。仕方なく又おぶる。石は座ったまま目をつぶって体を揺すっている。昼間も普段の倍以上に働き、夜は疲れ切った体でこうして横にならずにいる。
このときの石は無垢に只一生懸命に働いた。自分の失策に対する不名誉を挽回しようとか、よく思われようとかの打算は無く、もっと直接な気持ちらしかった。
「私たちが困っている、だから石は出来るだけ働いた」と「長いこと楽しみにしていた芝居がある、どうしてもそれが見たい、嘘をついて出掛けた」。
この二つは石にとって同じ気持ちから起こるものだった。
このとき私は自身の狭い了見を恥じ、人を疑い人間性を決めつけることを悔い改めることを思った。
石の良いところを分かり好きになり、幸せになることを願う。
私は五年ぶりに東京住いをすることになって準備をする。
石に結婚の話があった。相手先は今度が八度目だと妻が誰からか聞いてきた。石は余り行きたくないということだったが、石の父親が乗り気で「とにかく行って、その上で気に入らなかったら帰って来い」と云う。行く前に充分に調べて「行った以上は何があっても帰ってくるな」というのが普通なので、順番が逆で変だと思った。
その後、石の姉が来て八人の妻を更えたという男とは違うことがわかり、石は少しも嫌ではないということだった。ただ写真を見るとか見合いをするとかいうことも無く、田舎の結婚には驚くほどに暢気なものがある。
ここでは人々の無責任で無根拠な様子が挿入されています。神経質で用心深い私とは異なり、田舎の人々は口々に噂話が伝わりどこかいい加減でのんびりしています。
お嫁入りの準備をするので暇をくれと云っていたが、私達が東京に行くことを知ると、羨ましくなり一緒に行くと云いだし、二月一杯で返してくれと石と一緒に来た母親が言う。
東京では佐枝子が麻疹にかかり、ここでも石もきみも良く働いてくれた。石が帰る日が近づき二人を近所の芝居見物にやった。
いよいよ別れるとき、石は少し涙ぐんだが甚く不愛想になっていた。別れの挨拶一つ云わずプラットフォームを行く石は、此方を振り向かない。それは石らしい自然の別れの気持ちを表していた。
「人間は関係が充分でないと、いい人同士でもお互いに悪く思うし、それが充分だと、いい加減悪い人でも憎めなくなる」
「石も、欠点だけを見ると欠点だらけだけれど、いいほうを見るとなかなか捨てられないところがある」と妻が云う。
ある日、石が来ていた。妻がお嫁入までに東京に出ることがあれば是非おいでと葉書を送り、早速、飛んできたという。「今月一杯いられる」という。「家に戻ってもお嬢様のことばかり考えてぼんやりしていた」と云われたという。
もうすぐ結婚する。良人がいい人で、石が仕合せな女になる事を私たちは望んでいる。