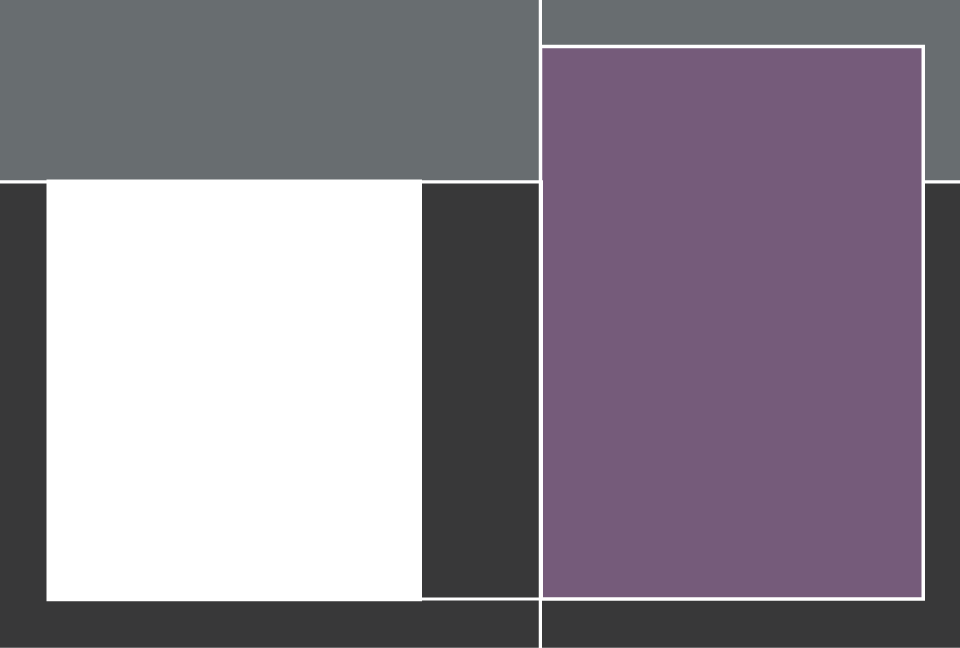范という名前の支那の奇術師が、衆人の見守るなかナイフ投げの演芸で妻を殺してしまう。故意の仕業か?過ちの出来事か? 裁判官が関係者を問い質す。そこには「本統の生活」を求める范の懊悩があった。抑圧から解放され自己に忠実な生き方を選ぶ、范の深い思索の軌跡と不意の殺人を描く。
登場人物
范
支那の奇術師。ナイフ投げで妻を殺してしまい、そこに至る心の葛藤を語る。
座長
范の行ったナイフ投げの演芸について、しくじる可能性の説明を裁判官にする。
助手の支那人
范の助手で裁判官に聴取され、范の身近にいる者として夫婦仲の悪さを語る。
裁判官
妻の殺人について座長、助手、范の話を聴き故意か過失かを見極め判決を下す。
あらすじ
ナイフ投げのモチーフが、殺人にいたる逡巡と結果を象徴する。
死の場面となっている、奇術師が行うナイフ上げの演芸。そこでの惨劇という仕立てです。大きな戸板くらいの板の前に妻であり、相棒である女性を立たせ、二間つまり3.6m離れたところから、体の輪郭をとるように、何本もナイフを打ちこんでいく芸です。
当然、観衆は熟練技の安心と同時に、もし手許が狂ったら女性を刺してしまうのでは・・・・って思います。このナイフ投げのモチーフが、「故意」か?「過失」か?の謎について読者を参加させることに成功しています。
そして、精神的な疾患だったという結論に、到達することはできても、「故意」か?「過失」か?は、謎のままとなります。
ナイフ投げの演芸で、范のナイフが妻の頸動脈を切断し、その場で死亡する。
物語は、悲惨な出来事から始まり、「故意」か?「過失」か?が大きな焦点となります。
范という若い支那人の奇術師が、出刃包丁程のナイフ投げの演芸で誤って妻を刺してしまいます。
若い妻はその場で死に、范はすぐに捕らえられる。現場には、座長も、助手も、口上云いも、そして三百人余りの観客も見ており、巡査すら一人いた。
ところがこれ程大勢の視線の中で、起きながら「故意の業」か「過失の出来事」か、全く解りません。
「故意」なのか?「過失」なのか? の判断を下すために、裁判官は座長、助手、范の順番で訊問を行い真実に迫ります。
裁判官は女の殺人を関係者に問い質し、ある事実に辿り着く。
座長は裁判官に「あの演芸は難しいものなのか?」と問われ、「いつも健全な、そして緊張した気分を持っていれば、難しいものではない」と答え、では「故意か?」と問われると、座長は「熟練と直感的な能力を利用する芸」ですが機械とは違い必ず正確に行くとも断言できず「分かりません」と答えます。
この答えは、一般の人々が、理解ができる説明ですね。しかし明らかに、「健全な気分」ではない、何かがあったことを当然ながら、読者も共有しています。
次に范の助手の支那人が裁判官の質問を受ける。素行について訊ねられると「范も妻も素行は正しい方だ」と云う。「二人共、他人には柔和で親切で怒るようなこともない」と答え、ところが「二人だけになると驚く程、お互いに残酷になる」と付け加えます。
それは「二年程前、赤児が早産で生まれて三日で死んで」からだと云う。時々、烈しい口論をしているが、范は自分の方で黙って了い、キリスト教を信じているせいか手荒な行いはなく、抑えきれない怒りが凄く露れていることがあるという。
裁判官の尋ねる素行については、人間関係や、そのなかには浮気のようなニュアンスも含んでいるのでしょう。その質問の流れで、二年ほど前に、早産で生まれた赤児がなくなり、そのあたりから何かが起こっていることを知ります。
助手の私が「別れたらどうだ」と云うと、妻のほうには離婚を要求される理由があるが、范のほうには無く、自分の我儘だが「どうしても妻を愛することが出来ない」と云う。そしてバイブルや説教集を読んで、心を直そうとしていた。
妻も可哀想な女で范と一緒に彼方此方と廻り歩いているが、故郷の兄は放蕩者で家はもう潰れて無い。別れて帰っても旅芸人の女と結婚する男など居らず「不和でも范と一緒にいるしかなかった」と云い、助手の支那人は考えれば考える程「過失か故意かは解らない」と答える。
夫婦の問題は、妻のほうにあり、范には責任がないと、范は考えている。それでも宗教の力を借りて、なんとかうまくやろうとしたが、それでもやはり妻を許せないと言います。しかし范は、もし離婚したら、その後の妻の行く末を思うと、慈悲の心はないが、憐れに思い、不和で一緒にいるしかなかった、と考えていたことを知ります。
では「出来事のあった瞬間は何方と思ったか?」と問われ「殺したな」と思った。ところが出来事のあった瞬間を共に見ていた口上云いの男は「失策った」と思ったと付け加える。
つまり、夫婦の問題を知っているかどうかで、解釈が分かれます。物語の構成上は、読者を真実の場所に連れていくことになります。
その瞬間、范は「あっ」と声を出し、興奮から「どうしてこんな過ちをしたろう」と云い、跪いて長い事 黙禱をしていた。
裁判官は最後に范に質問する、はじめに妻との生活のことを聞く。
范は「結婚した日から赤児を産む時までは心から妻を愛していた」ところが、「妻の生んだ赤児が自分の児ではない」事を知ってから不和になった。「相手は想像するに妻の従兄で、自分も親しかった友人で、その男から勧められて結婚をした」と云う。
「結婚して八ヶ月目に赤児が生まれ」そして直ぐ死んだ。助手の支那人が早産と云ったのは、范がそう云って聞かせた。死んだのは「乳房で息を止められた」からで、故意ではなく「過ちから」だと妻は云っている。
妻は従兄との関係について范に打ち明けなかったし、范も訊こうとはしなかった。「赤児の死が総ての償いのように思われて、寛大にならねば」と思った。
裁判官はここで范と妻の関係において、赤児の産を通して范に強い嫉妬と辛い悩みがあったことを確認している。これが原因である。
范が巡らせた深い思索の順路から「殺人」が不意に起こった。
しかし赤児の死だけでは償いきれない感情が残り「妻のそのからだを見ていると、急に圧さえきれない不快を感ずる」と范は云う。
裁判官は「離婚しようとは思わなかったのか?」と訊ねると、范は嘗てそれを口に出したことはなく、その理由は「私が弱かったから」と答え、「妻はもし私から離婚されれば、生きてはいない」と云う。
妻が離婚しないのは、范を愛しているからではなく「生きていく必要」からで、「実家は潰れて無いし、旅芸人の妻であった女を貰う男などいないと知っているからだ」と云う。そして「肉体関係も普通の夫婦と同じ」と答える。そして「妻は私の生活が段々と壊されて行くのを残酷な眼つきで見ていた」と話す。
范が自分を救おうとして「本統の生活に入ろうともがき苦しんでいる」のを冷然と脇から眺めている、というのだ。
ここでは、結婚前に付き合った、別の男と間に生まれた赤児という真実が原因であると判明する。と、同時に、范の潔癖さ、正直な感情、そして憐れに思う心と、妻の不貞か否かの疑問ある行為の中で、妻の眼つきが、残酷に映り、憔悴と猜疑のなかで、范自身のの精神が壊れていくさまが描かれる。この状態は、出口のない状況である。
妻の死を願う中での范の憔悴と懊悩、出口を探そうともがく思索の逡巡。
「本統の生活」に辿り着くために、范は「妻が死ねば良いと思いました」と答えた。離婚もせず、逃げることもせず、妻が自ら死ぬことを願ったのである。
裁判官が「では法律が許したら妻を殺したかもしれないな」と質問すると、范は法律をおそれたのではなく「私が只弱かった」からで、「弱い癖に本統の生活に生きたいという欲望が強かった」と答える。
そして「前晩から明け方にかけて殺そうと考えていた」と云う。
妻への殺意を始めて抱いた真夜中、「私は近頃自分に本統の生活がないという事を堪らなく苛々していた」ときで、床に入っても眠れず興奮して色々な考えが浮かぶ。
范は「右顧左顧」し、「欲する事を思い切って欲し得ず」「いやでいやでならないものを思い切って撥退けて了へない、中ぶらりんな、うじうじとしたこの生活」が、「総て妻との関係から来るものだ」という気がしてきた。
自分は不快と苦しみで「今中毒しようとしている」「中毒しきった時には自分は死んで了う」「生きながら死人になる」。一方で「妻が死んでくれればいい」そんなきたないいやな考えを繰り返している。
つまり范は「本統の生活」のためには「妻を殺さなければならない」と思ったのである。
范は、自身が望む「本統の生活」の入り口を掴むことが出来た。
眠れず疲れきると思いつめた気持ちはなくなり、悪夢に襲われたような淋しい気持ちになった。そして夜が明けた。自分が妻を殺すことなどあり得ないと演芸の当日に思った。ただその日は何となく上ずった興奮と疲労からくる神経の鋭さを感じた。
范はナイフ投げの演芸を選んだことは、心の平衡を保つことが出来た理由からだとしている。しかし妻と向き合い二人が目を見合わせた時に、この演芸を選んだ危険を感じた。
そしてナイフ投げが始まり頭上に一本、左右の腋の下へ一本ずつ打ち込む。そして頸の左側に一本、次に右側に打とうとすると「妻が急に不思議な表情をした」と云う。
そして妻の「恐怖の烈しい表情」が「自分の心にも同じ強さで反射したもの」を感じ、「殆ど暗闇を眼がけるように的もなく手のナイフを打ち込んで」しまった。
物語としてのクライマックスです。范の、そして妻の、目が合い感じあったことでの、不思議な高揚感のようなものが描かれます。瞬間の范の殺意ともとれますし、妻のシグナルによって、范の冷静さが失われ、手許が狂った、ともとれます。
そして范は「故意の仕業」のような気が不意にして、狡い手段から祈るふりを装った。そしてすぐ「過失と見せかけることが出来る」と思った。
その晩、范は「自分は無罪でなければならぬ」と「決心」した。何ひとつ客観的な証拠がなく証拠不十分になるのが心丈夫だった。さらに范はよく考えると前晩に殺すことを考えたというだけで「何故、あれが故意だと自分で思ったのか?」と疑問が生じる。そしてついに「興奮」と「愉快」を覚える。
裁判官が「お前は自分で過失と思えるようになったのか?」と質問すると、范は「只全く自分でも何方か解らなくなった」と繰り返す。范は「何もかも正直に云って、無罪になれると思った」と云う。
私にとっては無罪になる事が総てで、その目的の為には自分を欺き、過失と我を張るよりは、「自分に正直でいられることの方が遥かに強い」と考えた。
この瞬間、范は「本統の生活」の入り口をやっと手にしたことになる。
そして裁判官は最後に「お前には妻の死を悲しむ心は少しもないか?」と質問すると、范は「全くありません。私はこれまでに妻に対してどんな烈しい憎しみを感じた場合にも、これ程、快活な心持ちで妻の死を話し得る自分を想像したことはありません」と答えた。
動画もあります、こちらからどうぞ↓