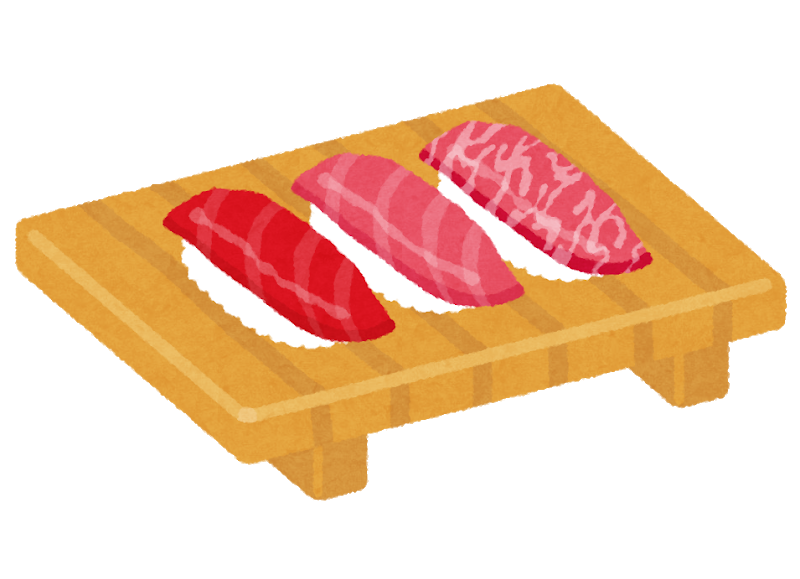
きっと神様からのご褒美なんだ!
秤屋の小僧の仙吉は、鮨が食べれずに意気消沈しているところを粋な客に腹いっぱいの鮨を食べさせてもらう。なぜ自分の気持ちだけでなく、行きたい鮨屋まで分かったのか不思議に思いながら、きっと自分には神様が見てくれているのだと思う。
登場人物
仙吉
神田の秤屋に奉公する一三、四の小僧で、番頭たちの鮨の話を羨ましがる。
番頭
仙吉の奉公する秤屋の番頭たち、鮪の脂身を食べに行く相談をしている。
貴族議員A
妻がいて、娘の体重計を買いにいった秤屋で鮨の屋台にいた小僧と会う。
貴族議員B
同僚のA議員に、通の鮨の食べ方について自慢げに伝授してみせる。
細君
Aの細君で、娘がいる。体重計を喜びAの小僧の話を聞き考えを述べる。
作者
小僧に残酷なので筆を止め、書くつもりだった文章を読者に紹介する。
あらすじ
番頭たちの話を聞きながら、仙吉は鮨を腹いっぱい食べてみたいと思う。
仙吉は、神田の秤屋の店に奉公をしている。
店には客がおらず、帳場格子に座る番頭が、若い番頭に「そろそろ鮪の脂身が食べられるころだから、今日あたり店が終わったら行かないか」と誘い、神田から電車で十五分くらいだと話している。番頭は「あの店で食ったら、このへんのは食えないな」と言い、若い番頭も「そうですね」とうなづく。
仙吉は「ああ鮨屋の話だな」と思って聞いている。そして、「早く自分も番頭になって、そんな店の暖簾をくぐりたいもんだ」と思う。
番頭たちは、他の店のことも話していて「与兵衛やその息子が今川橋の松屋のところにも店を出して、そっちも評判だ」と言い、仙吉は「色々と美味しい店があるのだな」と思い、「旨いというが、どのくらいに旨いのだろう」と口の中に唾がたまりながら想像をする。
使いの帰り道、噂の鮨屋に入るもお金が足らず、仙吉は多いに恥をかく。
それから二、三日後、京橋まで使いを仰せつかり貰った往復の電車賃のうち片道分、四銭を浮かせて鍜治橋で降りて、番頭たちが話していた鮨屋を見ながら通り過ぎた。
使いの用事を済ませて、帰り道で同じ名前を付けた屋台の鮨屋をみつけそちらに歩いて行った。
一方、若い貴族議員のAは、議員仲間のBから、「鮨は手掴みで食う屋台の鮨が通だ」と説かれ、「では立ち食いしてみよう」と、屋台で旨いという鮨屋に銀座の方から京橋を渡ってその店に行った。
既に三人ばかりが立っていてAは割り込まずに後ろに立っていた。そこに小僧が割り込んできて「海苔巻きはありませんか」と訊ね、無いと言われると、勢い良く手を伸ばし鮪の鮨を摘まんだが「一つ六銭だよ」と言われて、その鮨を返した。そして何も云わず一寸動けなくなるが、勇気を振るって店から出ていった。
Aは友人のBにそのことを話すと、Bから「ご馳走してやればいいのに」と言われたが、「そんな勇気は無いよ」とAは言い返した。
貴族議員のAは配達のお礼に、 仙吉にお腹いっぱい鮨を食べさせる。
Aは、幼稚園に通う子供の発育を測りたくて体重計を買いに、偶然、仙吉のいる神田の秤屋に入った。
仙吉はAのことを気づかなかった。Aは小さな体重計を買い、番頭に住所を確認されたが、後で知られるとまずいので出鱈目な住所を書いて渡した。小僧に車宿まで手車で運んでもらうことにした。Aは、慰労の名目でどこかで鮨を小僧にご馳走してやろうと考えた。
そうして体重計を車宿に持っていった後、Aは仙吉に「何か御礼をしたい」と言って、「一緒においで」と、小僧を連れ蕎麦屋や鮨屋や鳥屋を通り過ぎていく。そして神田橋駅の高架の下を潜って、松屋の横を出て電車通りを越して、ある鮨屋の前に来た。そしてAは店に勘定を先に払い、小僧に食べさせるように言いつけて出てきた。
言いつけを受けた店の女将は「小僧さん、お入りなさい」と言い、Aは「私は先に帰るから、十分食べておくれ」と言っていなくなった。
仙吉は、三人前の鮨を平らげて、「もっと召し上がれませんか?」と女将に言われたが、恥ずかしくて顔が赤くなり帰り支度を始めた。
Aは自分のしたことに淋しく嫌な気持ちになり、偽善のように思えた。
Aは、小僧と別れて逃げるような気持ですぐにBの家に行った。Aは変に淋しい気持ちになった、先日の小僧の気の毒な様子を見て、偶然、今日のことを遂行できたのだが、小僧も満足して、自分も満足して、良い気持ちなはずなのに淋しく嫌な気持ちになっている。
まるでこっそり悪いことをした後の気持ちに似ていると思った。
それは、自分のしたことが善行だと考える意識があり、それを本当の心から批判され、嘲られているからこんな淋しい気持ちになるのかと思った。
その後、Bと一緒にY夫人の音楽会を聴いたりしてその気持ちも収まっていた。
家に帰ると細君は、体重計を大いに喜んでいた。小僧のことを話すと「貴方がそんな気持ちになるのは不思議ね」と言った後、「その気持ちわかるわ。でも小僧さんも喜んだことでしょう」と言った。
仙吉はすべてお見通しの「あの客」は、神様に違いないと信じた。
仙吉は、空車を挽いて帰った。今日のことを考え、先日の屋台の鮨屋で恥をかいたことと関係している事に気づいた、あの場にいたのだと思った。しかし自分のいるところをどうして知ったのだろう、そして今日の鮨屋は、番頭たちが話していた鮨屋なのをどうして知っていたのだろうと不思議に思った。
仙吉は、番頭たちと同じようにAやBも美味しい鮨屋の噂話をすることなど想像できなった。すると仙吉は「自分が番頭たちの話を聞いていて、それも知っていて、自分をあの店に連れて行ってくれた」と思い込んだ。
仙吉は、自分が屋台の鮨屋で恥をかいたこと、番頭たちの話していた噂の鮨屋、そして自分が鮨を食べたくてたまらない気持ちだったこと、そして充分に、ご馳走してくれたことをいろいろと思う。
「こんなことは人間業ではない、きっと神様だ。神様でなければ仙人か、お稲荷様かも」と考えた。
お稲荷様と考えたのは、仙吉の叔母で、お稲荷信仰の人がいて乗り移ると体を震わして予言をしたり、遠いところで起こった出来事を言い当てたりする。仙吉はそれを見たことがあったので、超自然なものだという気が段々と強くなっていった。
仙吉は辛いときに「あの客」を思い、いつか自分に恵みをくれると思った。
Aの淋しく変な気持ちは跡形なく消えていったが、彼は、神田の秤屋にも、あの鮨屋にも足が遠のいた。自分のような気の小さい人間は、軽々しくあんなもことをするもんじゃないと思った。
仙吉は「あの客」がますます忘れられなくなり、ただただありがたかった。仙吉もあの鮨屋には再び、ご馳走になることはなかった。そうつけあがるのが恐ろしかった。
仙吉は、悲しいとき、苦しいときに必ず「あの客」を想った。思うだけで慰めになった。いつかまた思わぬ恵みをもって、自分の前に現れてくれることを信じていた。
作者はここで筆をおくことにする。
仙吉が「あの客」が何者かを知りたい要求から番頭に住所を確認して、そこへ尋ねてみるとその番地には人は無くて、小さい稲荷の祠があった。そして小僧はびっくりした。
・・・というふうに書こう思ったが、そう書くことは小僧に対して残酷な気がした。それで、作者はその前で筆をおいた。
★動画もあります、こちらからどうぞ↓


