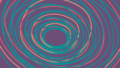人気作家であり、エッセイストとしての評価も高かった安吾は、昭和21年の『堕落論』の翌年に『特攻隊に捧ぐ』という短い随筆を書く。終戦の翌々年だ。
天皇陛下万歳と唱えた戦時下の皇国史観から、戦後の国民主権へと180度の転回を迫られる。GHQから戦争を賛美する人とモノは排除させられ、新たな民主制と平和憲法を強要される。政治家もマスコミも掌を返すような言説に変わっていく。
解説
随筆の冒頭には、数百万の血を捧げたこの戦争に、我々の心を真に高めてくれる本当の美談のないことを嘆く。明らかになっていく軍部の指導方針や積悪が、兵隊を非人道的な死に追いやったことを安吾は厳しく批判する。
特攻隊についても、戦争中は「勇躍護国の花と散った」とされたのに、戦後は「死にたくない」特攻隊員で、殉国という魂などは流行らないという風潮となる。
ただ何もかもが悪いと、一方的に流れるのは、日本国民が自ら自国民を愚弄することゆえ決して健全ではなく、深く熟考することを安吾は促す。
現代人の我々は特攻隊と聞けば、ゼロ戦(=零式艦上戦闘機)に搭乗した神風特別攻撃隊を思い、特攻の記録映像を見ることで昭和の歴史を偲ぶ。
命を賭して戦った英雄が、終戦を境に無駄死にとなる。戦中と戦後の正邪の逆転である。
しかし安吾は、戦争という運命のなか起こったことに対して、一瞬で表と裏をひっくり返す思考を戒め、特攻隊の偉業を誇ることを随筆で試みる。
時節柄、そこには並々ならぬ覚悟が込められている、なにせGHQの統制下なのだ。
現代でも、「特攻隊」は愛国の殉死か、犬死か、という議論に分かれるのだろう。
九段北にある靖国神社の「遊就館」で人間魚雷「回天」等と共に展示されている復元された「ゼロ戦」は重量感の無い構造で、片道のみの燃料と爆弾を搭載し大空を縦横無尽に羽ばたき、砲撃のなか一点、敵空母を目がけて精緻に急降下していった。
隊員たちの決死は何だったのか、死と向き合いながらの精神力と集中力は人間の行為とは信じ難い。
父祖の歴史に繋がることで現代の日本に暮らす私達。平和ボケの中で戦争や戦争による死を、実感できない。愛国心という言葉で、思考の中でのみ死の恐怖を否定することは出来ても、それは実際の行為ではなく、あくまで勇ましい空想にすぎない。
必ず死ぬ、と決まった時にそれが実行できる人は常人ではない。まして、それが、一時の激した心ではなく、冷静に、一貫した信念によって為された時は、偉大なる人である。
その死は、後に続くと信じた日本の国体や悠久の歴史のための殉国の死である。
安吾は、若者の胸に殉国の情熱が存在し、死にたくない本能と格闘しつつ、至情に散った尊厳を敬い、愛す心を忘れてはならないという。
さらに、戦法としての特攻は日本としては上乗という。ケタ違いの工業力で戦う日本軍の作戦の幼稚さは言語同断だと喝破する。そして工業力と作戦が結びついていないなか、最も独創的な新兵器といえば、それが特攻隊であったとする。
ゼロ戦、その超軽量の機体の構造は、軽く薄く、上昇力や急転回など格闘性能と航続時間を誇る世界でも最高の戦闘機であった。そして特攻とは十死零生の明らかに非人道的な攻撃方法だ。
サイパンはじめマリアナ諸島の守備隊が玉砕、日本本土への空襲が可能となる。そしてフィリピン諸島の陸上戦の敗退とレイテ沖海戦での戦艦大和など連合艦隊の壊滅。このとき本土防衛のために作戦として特攻が本格化する。
敵空母の被害は甚大で、一時期、神風特攻隊は大戦果を収めアメリカ軍を震撼させた。それは破滅的であり、軍部には甘美な結果をもたらす。そして終戦間際まで続けられ2,500名以上の若者が戦死した。
安吾は、特攻隊はともかく可憐な花であったという。
戦争は呪うべし、憎むべし。再び犯すべからず。という安吾の立場だが、それでも 特攻隊員の心情だけは、疑わぬ方がいいと思っているという。
必死必中の信念で、彼らは自ら爆弾となって敵艦にぶつかり、大部分が途中に射ち落されただろうけれど、敵艦に突入したその何機かを含めて彼等全部の栄誉ある姿と見てやりたいという。
誰も死にたくなどない、死にたい兵隊などいない。戦争は抜きさしならない歴史の運命だが、我々は戦争の正体を見破り自省と明日の建設の足場としなければならない、つまり総括と共に未来を築こうということである。
そのためにも、戦争の中から真実の花をさがして、ひそかに我が部屋をかざり、明日の日により美しい花をもとめ、花咲かせる努力と希望を失ってはならないという。
彼等は、基地では酒飲みで、ゴロツキで、バクチ打ちで、女たらしだったかも知れぬが、死へ向って歩むのだから、聖人ならぬ二十前後の若者が、酒を飲まずにいられようか。せめても女と時のまの火を遊ばずにいられようか。
ゴロツキで、バクチ打ちで、死を怖れ、生に恋々とし、世の誰よりも恋々とし、けれども彼等は愛国の詩人であったとする。
いのちを人にささげる者を詩人という。迷わずにいのちをささげ得る筈はない。そんな化物はあり得ない。その迷う姿をあばいて何になるのかと、戦後の日本人の言説を疑う。
我々愚かな人間も、時にはかかる至高の姿に達し得ること、それを必死に愛し、守ろうではないか。
軍部の偽懣とカラクリに操られた人形の姿であったとしても、死と必死に戦い、国にいのちをささげた苦悩と完結はなんで人形であるものか。
戦争は凡人を駈って至極簡単に奇蹟を行わせた。
安吾は、特攻隊員たちが、国のために命を捨てることを強要された事実を知っている。至高の行為などより、人はむしろ平凡を愛する。小さな家庭の小さな平和を愛する。このような人々を軍部は強要して体当たりをさせたのだ。当時の指導者たちの愚劣と腐敗のなかで若者が特攻に飛び立つ。大部分の兵隊が戦争を呪ったはずだ。
しかしその強要のなかで、次に始まったのは、個人の凄絶な死との格闘があり、燃焼した結果だとしている。それは強要と切り離して、それ自体として見ることも可能だという考えである。
否、むしろ切り離して、それ自体として見ることが正当で、格闘のあげくの殉国の情熱を最大の讃美を以て敬愛したいという。
凡人も亦かかる崇高な偉業を成就しうるということは、大きな希望ではないかと続ける。
平和な時代に於て、特攻隊の至高の苦悩と情熱が花咲きうるという希望は、日本を世界を明るくする。美しいものの真実の発芽は必死に守り育てねばならない。
私は戦争を最も呪う。だが、特攻隊を永遠に讃美する。
人間の懊悩、苦悶と、かくて国のため人のために捧げられた命に対して。
そして安吾は青年諸君に向けて、最後に語っている。
この戦争は馬鹿げた茶番にすぎず、そして戦争は永遠に呪うべきものだが、かつて諸氏の胸に宿った「愛国殉国の情熱」が決して間違ったものではないことに最大の自信を持って欲しい。
要求せられた「殉国の情熱」を、自発的な、人間自らの生き方の中に見出すことが不可能であろうか。それを思う私が間違っているだろうか、と結ぶ。
安吾らしい、深い思索の果てに辿り着いた結論であり、戦後日本人への問いかけなのである。
※坂口安吾のおすすめ!
坂口安吾『白痴』あらすじ|墜ちることで、人間は救われる。
坂口安吾『桜の森の満開の下』解説|桜の下に覆われる、虚無な静寂。
坂口安吾『夜長姫と耳男』あらすじ|好きなものは、呪うか殺すか争うか。
坂口安吾『堕落論』解説|生きよ堕ちよ、正しくまっしぐらに!
坂口安吾『続堕落論』解説|無頼とは、自己の荒野を生きること。
坂口安吾『文学のふるさと』解説|絶対の孤独を、生き抜くために。
坂口安吾『日本文化私観』解説|人間のいる芸術だけが、前進する。
坂口安吾『特攻隊に捧ぐ』解説|殉国の情熱と、至情に散る尊厳。