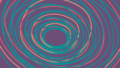作品の背景
終戦後に平和憲法を受け入れ新たな民主制に転換した日本。戦争の当初は、軍部だけでなく、マスコミも煽り、国民も狂騒したはずである。一転、一億総懺悔の変節である。日本の戦争行為は悪だったとの世論のなか、またGHQの占領下、かくも覚悟あるエッセイを発表した安吾の心中を思えば、感慨ひとしおである。
坂口安吾は、太宰治らと共に無頼派と呼ばれる。他にも友人である壇一雄や石川淳、織田作之助、田中英光なども含まれる。無頼派とはどういう意味なのか?
自分中心で、自己本位で生きるということ。世間の規則や約束事には頓着せず、酒ならば果てしなく飲み、創作という名目で薬を乱用する。確かにそのような破天荒な生き方を安吾は送ったようだが、それだけではない。無法者とは違うのだ。
この随筆『特攻隊に捧ぐ』は、散華した特攻隊の若者たちに心を砕き、たとえなんと言われようとも、安吾には彼らの尊厳を守り抜く信念がある。戦争をいかに捉え、生とは何か、死とは何かと考えぬき、思索を尽くし搾りだされた言葉で表される。
安吾の「無頼」とは、「頼るべきところのないこと」。先入観や贋物の言説に惑わされることなく、常に求道的であり、実存的である。そしてロマンチストなのだ。
安吾は、寧ろ求道の念が強く、破滅しそうなほどの弱い心を奮い起こす。そのときに真摯に堕ちていくことを薦める。その果てに自身にとっての真実の信仰や価値に辿り着くと信じる、だから恐れずに、正しく堕ちきってしまえと『堕落論』のなかで言う。
裕福な家に生まれ、やがて不良となり、代用教員として子供を見つめ、東洋大学の印度哲学の倫理学を学ぶ、その意味では安吾は、真面目で正直な落伍者であった。
戦中と戦後。8月15日を境に一瞬で正邪の価値が逆転した日本の混沌の中で、当時の人々は如何に考え、そして坂口安吾はいかに捉えたのか。安吾の作品は小説であり随筆であり、また思想でもあり、哲学でもある。戦争と平和という激動の日本と日本人を知る上でも、多いに読まれるべきだろう。
発表時期
1947(昭和22)年2月1日発行の実業之日本社『ホープ第2巻第2号』に掲載予定だったが、GHQの検閲により発禁・削除され未発表となる。当時の事情を鑑みれば、当然だろうが、それでもあえて発表しようとした安吾には特攻隊に対して真の日本人としての尊崇の念がある。坂口安吾は当時41歳。
検閲資料をもとに1983(昭和58)年、雄松堂のマイクロフィルム資料「占領軍検閲雑誌」に収録。その後、「坂口安吾全集 16」筑摩書房にて2000(平成12)年4月25日初出。同6月1日「堕落論」新潮社文庫から刊行、収録されている。