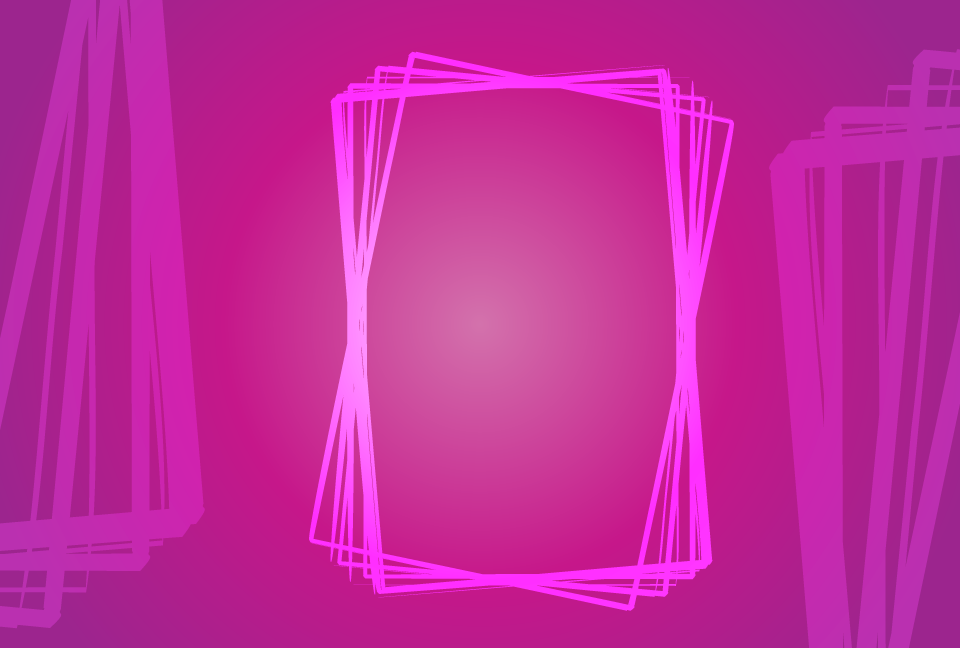安吾は『日本文化私観』というエッセイを発表している。1.「日本的」ということ 2.俗悪について3.家に就いて 4.美に就いての項目からなる。明治維新以来、西洋に学び近代日本を目指し突き進み、ついに米英を相手に太平洋を舞台に未曽有の歴史の運命に呑み込まれていったこの時期に、日本の伝統とは何か、日本人とは何かについての私的な省察である。
★動画もあります、こちらからどうぞ↓
解説
1.「日本的」ということ
冒頭、ブルーノ・タウトを引いてエッセイは始まる。タウトはドイツの世界的建築家であり1933年から4年弱、日本に滞在し精力的に活動をする。
西洋を超えるものが日本の建築を支える精神にはあるとして、日本の美の極致を伊勢神宮とし、また桂離宮の素晴らしさを世界に知らせる。それはヨーロッパ人のタウトの眼から見た「日本の美」の発見である。
しかし安吾は、「僕は日本の古代文化に就て殆んど知識を持っていない」と切り出す。そして日本人ながら、タウトが絶讃する桂離宮を見たことがないと突き放す。
1939年(昭和14年)に出版されたタウトの「日本美の再発見」は評判となる。それは日本の伝統美と精神性を賞賛するもので、当時の国威発揚にもつながる。
安吾の『日本文化私観』は、このタウトの観た日本のカウンターとして始まる。
さらにタウトが日本で最も俗悪な都市と評した新潟が、安吾の出身であることもあり、日本の伝統や精神を礼賛するタウトに対して、安吾は「ネオン・サインを僕は愛す」と卑俗さを告白しながら、日本とは何か?の鋭い省察の扉を開く。
日本人が日本の古代文化の伝統を見失ったという理由で、貧困だとは考えていない。
安吾の論理の展開には、逆説に立つものが多い。パラドックスによって通念から背理する方法で、読者をぐいぐいと引き込んでいく。その意味で、タウトの「日本文化私観」に対して、安吾の「日本文化私観」が、逆説として提起される。
タウトはある富豪に招かれ、一幅の掛け軸を愛でて楽しむ。その後、茶の湯と礼儀正しい食膳に供されたという。風流人の嗜みというところだ。
ところが安吾は、そんな生活が、「古代文化の伝統を見失わない」ための内面的に豊富な生活なら、内面とはいったい何なのかと問いかける。
日本人が、和服を着なくなり伝統を忘れ、欧米化に汲々としているというジャン・コクトーの歎きを引いてきて、フランス人はモノを通して伝統の遺産を受継いできたというが、伝統を生むのは、人間自身に外ならぬことを全然知らないと痛烈だ。
伝統とは何か? 国民性とは何か? 日本人が永遠に和服を着なければならない決定的な理由でもあるのかと、安吾はコクトーの的を外した日本人論を否定する。
キモノとは何ぞや? 安吾の考えは、洋服との交流が千年ばかり遅かっただけだ。その間、別の手法がなかっただけ。日本人の貧弱な体躯が特にキモノを生みだしたのではく、同時に日本人にはキモノのみが美しいわけでもない。つまり殊更、取るに足らない指摘だといっているのだ。
キモノ文化を大切と思う日本人も多いので異論もあろうが、安吾の立論には一定の合理があると思われる。いやもっとそれ以上に、日本の伝統や国民性はどこから来ているのであろうかと深く問い質していく。
さらに小学校の頃の記憶から、幅広い信濃川にかかる木橋が壊されて、川幅が狭くなり鉄橋になり、誇りを失ったようで悲しい思いをしていたが、今では、極めて当然だと考えているという。
故郷の古い姿が破壊されて、欧米風な建物が出現するたびに、悲しみよりも、むしろ喜びを感じる。きっとより安全で快適になったからだろうと、気持ちの変化を分析してみせる。
伝統の美だの日本本来の姿などよりも、より便利な生活が必要なのである。
新しい交通機関も必要だし、エレベーターも必要だ。安吾の視点には、不便なものは便利なものに、実用的なものに変わっていくことの合理性を認めている。
京都の寺や奈良の仏像が全滅しても困らないが、電車が動かなくては困る。
大切なのは「生活の必要」で、日本の古代文化が全滅しても、生活自体が亡びない限り、我々の独自性は健康なのである。なぜなら、我々自体の必要と、必要に応じた欲求を失わないからである。ここには人間の健全なる営みの大切さが優先される。
安吾の考えの前提には、人間の生活がある。日本人の生活がある限り、日本は無くならないという考え方なのである。つまり日本の文化もなくならないのである。これは実存ともいえるのではないか。
桂離宮も見たことがなく、竹田も玉泉も鉄斎も知らず、茶の湯も知らず、小堀遠州は何者だと思い、ネオン・サインの陰を酔い、電髪嬢を肴にしてインチキなウィスキーを煽る、呆れ果てた奴だと日本の文化人(つまり安吾自身)を自虐的に笑ってみせる。
タウトが日本を発見し、その伝統美を発見したことと、我々が日本の伝統を見失いながら、しかも現に日本人であることとの間には、タウトが思いもよらぬ距りがあるという。
タウトは日本を発見しなければならなかったが、我々は日本を発見するまでもなく、現に日本人なのだ。
キモノを着なくなったとか、洋服は日本人には不似合いなどは本質とは無関係である。
我々は古代文化を見失っているかも知れぬが、日本を見失う筈はない。
日本精神とは何ぞや、そういうことを我々自身が論じる必要はないと安吾は言う。
説明づけられた精神から日本が生れる筈もなく、又、日本精神というものが説明づけられる筈もない。日本人の生活が健康であれば、日本そのものが健康だ。
安吾は、不易とされる形式論を疑り、皮相な様式美による芸術論を否定する、同時に、いくら西洋化されても、日本文化の破壊などとは何も結びつかず無関係だとしている。
日本文化は、日本人の健康な生活に根差している。安吾は、日本人で在ることの現実の精神風景の大切さを論じている。
このエッセイが発表されたのは、戦時中で、日中戦争の泥沼からついに真珠湾を攻撃した翌年です。
1937年7月7日に盧溝橋事件が起こる。近衛内閣は「挙国一致」「尽忠報国」「堅忍持久」をスローガンとする。10月13日には国民精神総動員強調週間がはじまり、戦意高揚のために「欲しがりません勝つまでは」「ぜいたくは敵だ!」と自己を犠牲にして尽くす国民の精神(滅私奉公)の運動が加速していく。
政治や軍部による迷走が加速して無益な戦争への深入り、報道に扇動され沸き立つ国民、統制される経済と暮らし、西欧に恭順し自らも帝国主義化した歴史のなか、ヨーロッパ人のタウトの意見にも、伝統美を日本の国威に利用する風潮にも、レジストしたい安吾の精神は旺盛です。
そして安吾は、日本人が、わざわざ日本を「発見」する必要はないと結論づけます。
2. 俗悪に就て(人間は人間を)
エッセイが書かれた頃の安吾は、『吹雪物語』の執筆のために一人、京都で思索の時を過ごします。
京都の思い出として、始めて舞子に触れます。最初、馬鹿らしい存在だと感じた。特別の教養があるでもなく、無邪気な色気があるでもなく、つまらないと思った。ところが東山のダンスホールで踊りだすと群集を圧し、堂々と光彩を放って目立つ。
座敷とは異なり、舞子の独特のキモノ、だらりの帯が、洋服の男も、夜会服の踊子も、西洋人にも圧倒していて、伝統には独自の威力があると感服したと驚いてみせる。安吾にとって、伝統の威力が現実を具体的に圧倒した瞬間 に映る。
さらに日本の相撲とアメリカの野球を比べて、相撲の様式美ー呼出、行司の名乗り、力士が一礼して、四股をふみ、水をつけ、塩を撒き散らし、仕切りにかかり、また仕切り直して、暫く睨み合い、悠々と塩をつかんでくる。
この土俵の上の力士たちは国技館を圧倒し、見物人も、大建築も小さく見えるという。
野球は、9人の選手がグランドの広さに圧倒され、追いまくられ、数万の観衆に比べて無力に見える。プレーというよりも、息せききって追いまくられている感じだとする。
意見の分かれるとこだろうが、どこか面白い解釈である。
これを安吾は、伝統の貫禄という。ただ同時に、長い年月を経ただけという伝統の貫禄だけではだめで、貫禄を維持するだけの実質がなければ舞妓も力士も亡びるとし、問題は、伝統や貫禄ではなく、実質だと言う。
京都の寺々はつまらないと感想を述べた後で、車折神社という、学者を祀りながら、非常に露骨な金儲けの神様があり、小石に姓名と金額を書いて祈願するという。俗っぽいが記憶に残ると安吾は言う。
それに比して、嵯峨や嵐山の寺々の空虚な冷たさで不快で、記憶に残らないというのだ。
龍安寺の石庭が何を表現しようとしているか。如何なる観念を結びつけようとしているか。
タウトは修学院離宮の書院の黒白の壁紙を絶讃し、滝の音の表現していると言うが、こういう苦しい説明までして観賞のツジツマを合せなければならないのは、情けない。
「仏とは何ぞや」という。答えて「糞カキベラだ」という。庭に一つの石を置いて、これは糞カキベラでもあるが、又、仏でもある、という。禅問答だ。
ここでも安吾は、仏かも知れないという風に見てくれればいいけれども、糞カキベラは糞カキベラだと見られたら、おしまいである。実際に、糞カキベラは糞カキベラでしかないという当然さには、禅的な約束以上の説得力があるからである。
そこまで言っては身も蓋(ふた)もないということになるのだが、安吾は実質こそが大切で、そこから真の美が生まれると考える。
龍安寺の石庭がどのような深い孤独やサビを表現し、深遠な禅の修行に通じていても構わない、石の配置が如何なる観念や思想に結びつくかも問題ではない。
我々が、石庭の与える感動が涯しない海の郷愁や砂漠の落日に及ばない時には、石庭を黙殺すればいいのである。つまり実質として真の美を生まないものは不要なのだとする。つまりわからないことを、わかったふうに装うなということだろう。
安吾は、禅問答にも、日本の仏教の悟りのひらきかたにも疑問を抱いている。
芭蕉は、人工的なものを不要として大自然のなかに庭を見、又、つくった。彼の人生が旅を愛しただけでなく、彼の俳句自体が、大自然に庭をつくった。
その庭には、ただ一本の椎の木しかなく、ただ夏草のみが萌えていたり、岩と、浸み入る蝉の声しかなかった。そこには意味を持たせた石だの曲りくねった松の木などなく、それ自体が直接な風景であるし、同時に、直接な観念なのである。
それが、特に日本の実質的な精神生活者には愛用された。
大雅堂は画室を持たなかったし、良寛には寺すらも必要ではなかった。画室や寺が無意味ではなく、その絶対が有り得ないとの立場から、中途半端を排撃し、無い方がむしろ良いという清潔を選んだ。
そして安吾は、人力の限りを尽くした豪奢、俗悪なるものの極点を開花させようとするのも自然だとして秀吉の例を引き称える。
秀吉は、芸術に就て、理解や観賞力があったのか疑わしい。しかし彼の命じた芸術には、一貫した性格がある。それは人工の極致、最大の豪奢であり、そこには清濁合せ呑むの概がある。まさに俗悪の闊達自在さが特徴だという。
城を築けば、途方もない大きな石を持ってくる。三十三間堂の塀は巨大な太閤掘であるし、智積院の屏風は、坐った秀吉が花の中の小猿のように見えただろう。芸術も糞もない。一つの最も俗悪なる意志の表れだが、否定することの出来ない落着きがある。安定感があるという。
事実に於て、「天下者」の精神を持ったものは秀吉のみだ。金閣寺も銀閣寺も、凡そ天下者の精神からは縁の遠い所産である。いわば、金持の風流人の道楽である。
秀吉には、風流も、道楽もない。彼の為す一切合財が全て天下一でなければ納らない。不逞な安定感というものが、天下者のスケールに於て、彼の残した多くのものに一貫して開花している。
タウトの好む簡素なる茶室も、タウトの嫌う日光の東照宮も、共に「有」の所産であり、詮ずれば同じ穴の狢である。
この精神から眺めれば、桂離宮が高尚で、東照宮が俗悪だという区別はない。どちらも共に饒舌であり、「精神の貴族」の永遠の観賞には堪えられぬ普請なのである。
本質とは何か、俗であり、小であるなかに、「精神の貴族」を見いだすことである。
俗なる人は俗に、小なる人は小に、俗なるまま小なるままの各々の悲願を、まっとうに生きる姿がなつかしい。芸術も亦そうである。まっとうでなければならぬという。
我々に仏教が必要ならば、それは坊主が必要なので、寺が必要なのではない。
京都や奈良の寺々は大同小異、深く記憶に残らない、古い寺がみんな焼けても、日本の伝統は微動もしない。しかし尚、車折神社の石の冷めたさ、伏見稲荷の俗悪極まる赤い鳥居を忘れることが出来ない。
これは、「無きに如かざる」ものではなく、その在り方が卑小俗悪でも、「なければならぬ」ものであった。
安吾は、美しさのためだけの美しさは「有」の所産であり、そのための建築美や様式美を肯定しない。そこにはきっと人間がいない空虚なものと考えているのだ。
逆に、見るからに醜悪で、てんで美しくはないのだが、人の悲願と結びつくとき、まっとうに胸を打つものがあるのである。そこには人間がいるのだ。
人間は、ただ、人間をのみ恋す。人間のない芸術など、有る筈がない。
そして、古いもの、退屈なものは、亡びるか、生れ変るのが当然だという。安吾らしい主張である。
3. 家に就て
安吾は、家というものはたった一人で住んでいても、いつも悔いがつきまとうという。
「帰る」ということは、不思議な魔物だという。「帰る」ことで悔いや悲しみが在り、「帰ら」なければ、悔いも悲しさも無いという。
「帰る」以上、どうしても悔いと悲しさから逃げることが出来ないのだ。帰るということの中には、必ず、ふりかえる魔物がいる。
ここでの「帰る」という行為の辿り着いた所は、安吾のいう「絶対の孤独」である。
人は孤独で、誰に気がねのいらぬ生活の中でも、決して自由ではない。精神の内面深くに求める。「文学は、こういう所から生れてくるのだ」と安吾は信じている。
この部分は、安吾のエッセイ『文学のふるさと』に通じている。
文学は万能だという。なぜなら、文学というものは、叱る母がなく、怒る女房がいなくとも、帰ってくると叱られる。そういう所から出発しているからである。だから、文学を信用することが出来なくなったら、人間を信用することが出来ないという考えである。
現代の我々は、どのくらい文学と向き合っているだろうか。
4. 美に就て
安吾は、美しいものとして3つを挙げている。それは小菅の刑務所、佃島のドライアイスの工場、帝国の軍艦だという。
この頃の安吾は、京都を引き上げて茨木県南部の取手に住み、1ヵ月に2回、東京へ出ていた。利根川、江戸川、荒川という三つの大きな川を越え、ひとつの川岸に小菅刑務所があった。
高いコンクリートの塀がそびえ、獄舎は堂々と翼を張って十字の形にひろがり十字の中心交叉点に大工場の煙突よりも高々とデコボコの見張の塔が突立っている。
この大建築物には美的装飾はなく、どこから見ても刑務所然としており、刑務所以外の何物でも有り得ない構えだが、不思議に心を惹かれる眺めだと、安吾はいう。
威圧的とは違い、むしろ、懐しいような気持である。どこかしら、その美しさが心を惹くという。
これに似た経験として、銀座から築地へ歩き、渡船に乗り、佃島へ渡ると、突然遠い旅に来たような気持になる。聖路加病院の近所にドライアイスの工場がある。
このドライアイスの工場が、奇妙に心を惹くという。
ここにも一切の美的考慮がなく、ただ必要に応じた設備だけで一つの建築が成立っている。いかつくて異観であったが、然し、頭抜けて美しいことが分る。
聖路加病院の堂々たる大建築。それに較べれば余り小さく、貧困な構えだが、この工場の緊密な質量感に較べれば、聖路加病院は子供達の細工のようで、この工場は僕の胸に食い入り、遥か郷愁に続く大らかな美しさがあったという。
小菅刑務所とドライアイスの工場。どちらにも、郷愁を揺り動かす逞しい美感があり、法隆寺だの平等院の美しさとは全然違う。
法隆寺や平等院は、古代とか歴史を念頭に入れ、納得しなければならぬような美しさである。安吾からすれば、きっと押しつけられた美しさであり、飾られた美しさなのだろう。直接心に突当り、はらわたに食込んでくるものではないという。
小菅刑務所とドライアイスの工場は、もっと直接突当り、補う何物もなく、心をすぐ郷愁へ導いて行く力があった。
ある春先、半島の尖端の港町の小さな入江の中に、わが帝国の無敵駆逐艦が休んでいた。それは小さな、何か謙虚な感じをさせる軍艦で一見したばかりで、その美しさは魂を揺り動かしたという。
ここには、美しくするために加工された美しさが、一切ない。ただ必要なもののみが、必要な場所に置かれた。そうして、不要なる物はすべて除かれ、必要のみが要求する独自の形が出来上っている。
それは実質の問題で、美しさのための美しさは素直ではなく、空虚なのだ。
武蔵野の静かな落日はなくなり、バラックの屋根に夕陽が落ち、月夜の景観に代わってネオン・サインが光っている。ここに我々の実際の生活が魂を下ろす限り、これこそが美しいとする。
我々の実際の生活が魂を下している限り、これが美しくなくて、何であろうか。
我々の生活が健康である限り、我々の文化も伝統も健康だという。
必要ならば、法隆寺をとりこわして停車場をつくるがいい。我が民族の光輝ある文化や伝統は、そのことによって決して亡びはしない。
それは虚飾を廃した機能美でもあるが、それ以上に安吾の精神の風景なのである。その風景とは、安吾の眼から見た、戦争の時代の心象風景でもあるのだろう。
※坂口安吾のおすすめ!
坂口安吾『白痴』あらすじ|墜ちることで、人間は救われる。
坂口安吾『桜の森の満開の下』解説|桜の下に覆われる、虚無な静寂。
坂口安吾『夜長姫と耳男』あらすじ|好きなものは、呪うか殺すか争うか。
坂口安吾『堕落論』解説|生きよ堕ちよ、正しくまっしぐらに!
坂口安吾『続堕落論』解説|無頼とは、自己の荒野を生きること。
坂口安吾『文学のふるさと』解説|絶対の孤独を、生き抜くために。
坂口安吾『日本文化私観』解説|人間のいる芸術だけが、前進する。
坂口安吾『特攻隊に捧ぐ』解説|殉国の情熱と、至情に散る尊厳。