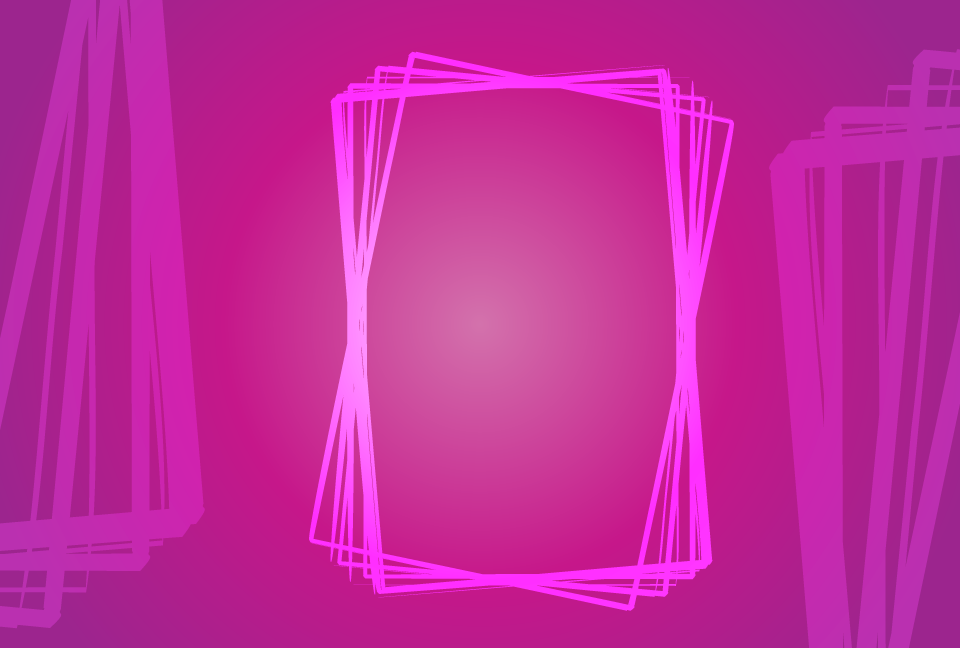作品の背景
このエッセイは、ブルーノ・タウトの「日本の伝統美」における日本礼讃に対する、安吾のカウンター的な視点で書かれている。日本は戦時下だが、このような西洋からの日本文化観を国威発揚へ活用する風潮もあった。
前年のエッセイ『文学のふるさと』では、アモラル(倫理を超えたもの)のなかにモラル(倫理)を見いだすという逆説的な立場をとることが安吾の文学の原点になっていると論じている。必要なことは現実に根ざした生活の中にあるという。

次に発表されたのが『日本文化私観』である。安吾は、求道的である。主体としての我々日本人が内省的に本質に迫る必要を説いている。日本の伝統とは何か、日本人とは何か、家とは何か、美とは何か、と次々に問いかけ、紐解き、自己省察の持説を展開している。
深く丁寧に鋭く本質に迫っていく、真理をどこまでも訪ねていく求道家の姿がある。
戦後のエッセイ『堕落論』や小説『白痴』において、一気に時代の寵児となる安吾だが、堕落や淪落のなかで、正しく堕ちて行くことが、生きることであると叫ぶが、これも戦中からの思索の連続であることが分かる
安吾の思考には印度哲学仏教の倫理の観念が影響している。それは決して日本仏教の解脱や悟りでは到達しえない。
戦中と戦後の日本の大きな転換のなか、安吾は、日本と日本人を見つめてきた。それは同時に自身を見つめ、世相を懐疑し、経験主義的に真理を求めて生き抜くために孤独と自由を糧としながら、創作を精力的に続けてきた人生だった。
安吾にとっての日本文化は、日本人の生活のなかに実質として根づいているものなのだ。
人間は、ただ、人間をのみ恋す。人間のない芸術など、有る筈がない。
そこに生まれるものは聖であれ俗であれ、大であれ小であれ、かけがえのない日本文化であり、この約束事以外の装飾的で実用性が無く、人間の臭いのしないものは、不要なのだ。
因みに日本本土の初空襲は1942(昭和17)年4月18日のドーリットル空襲である。1944(昭和19)年中頃からは本格的な戦略爆撃となり、大規模な無差別爆撃が実施された。京都は戦火を免れるが、東京を始め日本の主要都市のほとんどは焼け野原となる。
次々に灰燼に帰していく日本の風景。この歴史的な背景を鑑みると、日本文化、あるいは日本の美の根底に、安吾は日本人の暮らしを信じ、日本を愛している姿がうかがえる。
発表時期
1942(昭和17)年2月、『現代文学(第5巻第3号)』に発表。坂口安吾は、当時36歳。真珠湾攻撃の翌年である。単行本は1943(昭和18)年12月、文体社から刊行。