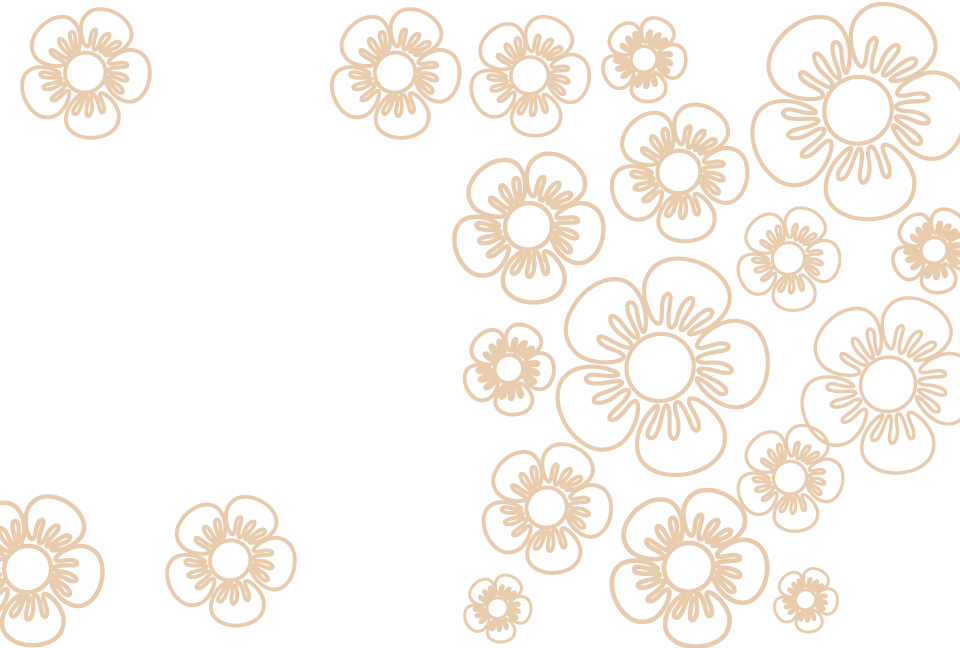一族は肺病で死んでいく。かよわい彼女は死を見つめ艶めかしく、ひとときの時間の連続も信じない。肺療院に送られ二人の男に愛される。医者に身体を治され、そして小説家に心を癒される。しかし彼女は二人を避け、一人孤独に死を思う。真に求められれば、肉体と魂を捧げるのにと彼女は思うのだった。
登場人物
彼女
血族結婚で一族が肺病でだんだんと死に絶え、いつも自分は死に向き合って生きている。
従兄
肺病となり死ぬ運命を静かに受容れるが、彼女と接吻できなかったことだけを後悔する。
若い医者
療院で彼女を特別に介護して、医者として彼女を治しひとりの男として好意を伝える。
若い小説家
彼女と同じ療養院を退院し二人は旅に出て、彼は美しい彼女の魂を小説の言葉にする。
あらすじ
肺病で死に絶える一族の運命を受け入れ、彼女は人生の海を漂流する。
血族結婚が代々重なっており、彼女の一族は肺病で死に絶えて行く。彼女もとても小さい肩をしていて、体が弱そうである。
親切な女が「結婚に気をつけるように、胸の病にだけは縁のない男を選ぶように」と彼女に忠言する。弱い身体は免疫力が低いので、感染の可能性が高くなる。
しかし彼女は自分の肋骨が折れるほど、強い男の腕に抱かれたいと思っている。そして澄み通る顔をしながらも、どこか捨鉢のように人生の海に身を浮かべ、流れに任せるような素振りをする。これが彼女を艶めかしくする。
従兄から手紙が来た。ついに自分も肺をやられたと綴られていたが、運命が来たと静かに受け入れているという。
ただひとつ口惜しいことは、達者でいる間になぜあなたに接吻することをお願いしなかったのかと書いてある。
そして「あなたの脣だけは肺病菌に汚されずにあれ!」と締めくくられる。
彼女は従兄のところへ飛んでいき、そして間もなく肺療院へ送られた。
死に向かう白い花に、一瞬の桃色の生を燃やしたい。
彼女は肺療院で医者と小説家と、二人の男に好意を抱かれる。
若い医師は彼女を特別に看護した。寝椅子を毎日岬の鼻に運び、海をともに見つめた。彼女を抱き上げ、医者は彼女に告白をする。その言葉は甘く優しい。
回復した彼女を新たに昇った陽に喩え、「海の舟が桃色の帆を掲げてくれないのか」と言う。医師としての自分と、彼女を好きな自分がいたことを告げ、「今、治ったあなたに一人の男として好意を抱いている」と言う。
彼女は医師を見上げ、眼を沖にそらして待ったが何も起こらなかった。
きっと接吻を期待した彼女は、自分に貞操がないことに驚く。彼女は幼いころから自分の死を見ている。だから時を信じないし、時の連続を信じない。してみれば貞操があろうはずがない。
しかし彼女は、医師に「あなたのからだは実験室」だと言われ、厭になった。
若い小説家が彼女に言った。彼は同じ療養院にいた。同じ日の退院を祝い、門から二人は一つの自動車で松林を走った。小説家は彼女の肩に腕をそっと置きそうな風をして、彼女は男に凭れかかった。
二人は旅に出た。「人生の桃色の曙だ」と言い、二つの朝が同時にあることを不思議がった。
そして小説を書こうと言い、「二人が死んでも小説のなかで生き続ける」と彼女の美しさを春の野の匂う花に喩えた。
彼女は歓びに満ちて小説家を見上げた。
しかし彼女は、小説家に「こんな美しい材料」だと言われ、厭になった。
彼女は自分一人の部屋に座っている。従兄は前に死んだ。
透き通ってくる白い肌を覗きながら、「桃色」と言う言葉を思い出して笑っている。
解説
胸の病とは結核のこと。当時は不治の病と呼ばれていました。身内に罹患した者がいれば感染を恐れて隔離します。これが肺療院です。血族結婚が代々重なり彼女の一族はだんだん死に絶えて行った。とあり、遺伝や免疫力低下による罹患が多かったものと考えられます。そこに身体のひ弱な主人公の女性がいる設定となっています。
従兄の手紙に綴られた求愛に、生の哀しみに応える彼女。
従兄は結核に罹患し血族の血筋から運命を静かに受け入れます。ただひとつの後悔は、従兄が彼女を好きだったことを告白しますが、血族ゆえに感染の恐怖で付き合うことができなかったことです。
死を静かに受け入れる従兄ですが、そこには生の哀しみがあります。
彼女自身も身体が弱く、周囲から「肺を患った男は気をつけるように」と念を押されますが、壊れそうな小さな肩を、強い男に抱きしめられたいほどに生を感じたい女性です。
そしてどこか捨鉢になる代々の死の運命への諦観が、彼女を艶めかしくしています。
果たして彼女は従兄のもとへ飛んでいきます。そして罹患してしまいます。
桃色の熱き血潮こそが、彼女にとっての生であり死である。
肺療院で二人の男が彼女に近づきます。若い医者と若い小説家。二人とも甘味な言葉で彼女に思いを伝えます。しかし医者にとって彼女は「美しい実験室」であり、小説家にとっては「美しい材料」であることに気づきます。二人は彼女の唇に触れようとはしません。
彼女は、医者と小説家の空虚な言葉を見透かします。
ただ医者の言葉を感謝の眼で見たときに、自分が貞操がないことに驚きます。それは幼い頃から自分が死と向き合っている。いつ死ぬか分からない自分には、ひとときの時間の連続も無く信じてはいない。つまり結婚は自分には出来ない、だから貞操があろうはずがないと考えます。
従兄は既に死んでしまいました。医者と小説家は「桃色」という言葉で、生の活力を表していました。しかし彼女にとっては「桃色」は血の色なのです。
彼女は近づいてくる死を感じながら、「桃色」と言う言葉を思い出し笑います。
きっと彼女には生も死も、熱い血潮の果てにあるものなのでしょう。
誰か男が一言、自分を求めれば、こくりとうなずこうと思って笑っています。
※掌の小説をもっと読む!
『骨拾い』あらすじ|冷徹な眼が、虚無を見る。
『白い花』あらすじ|死を見つめる、桃色の生。
『笑わぬ男』あらすじ|妻の微笑みは、仮面の微笑みか。
『バッタと鈴虫』解説||少年の智慧と、青年の感傷。
『雨傘』解説|傘が結ぶ、初恋の思い出。
『日向』解説|初恋と祖父の思い出。
『化粧』解説|窓から見る、女の魔性。
『有難う』解説|悲しみの往路と、幸せの復路。
作品の背景
川端は「大半は二十代に書かれている。多くの文学者が若い頃に詩を書くが、私は詩の代わりに掌の小説を書いたのだろう、若い日の詩精神はかなり生きていると思う」と述べています。大正末期に超短編の流行があったが永続はせず、川端のみが洗練された技法を必要とするこの形式によって、奇術師と呼ばれるほどの才能を花開かせます。
大正十二年から昭和四、五年に至る新感覚派時代で作品の大半はこの時期に書かれています。内容は、自伝的な作品で老祖父と初恋の少女をテーマにしたもの、伊豆をテーマにしたもの、浅草をテーマにしたもの、新感覚派としての作品、写生風の作品、さらに夢や幻想の中の作品など幅広い。
発表時期
1971年(昭和46年)、『新潮文庫』より刊行される。「掌の小説」(たなごころのしょうせつ)あるいは(てのひらのしょうせつ)とルビがふられる場合もある。川端が20代のころから40年余りに亘って書き続けてきた掌編小説を収録した作品集。短いもので2ページ程度、長いもので10ページに満たないものが111編収録される。改版され全総数は127編になる。