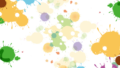脚本家の私は、撮影の立会いで京都に来ている。脳病院の現実を描いた映画で、終わりまで暗かったので最後は空想で美しい仮面で包んでやった。その能面をひとつをもって東京に帰り、入院している妻を見舞う。子供たちにせがまれて仮面を被った妻が、能面を外すとみじめな人生の顔が現れた。私は芸術がいけないのだと思った。
登場人物
私
東京に住んでいるが映画の脚本家として撮影で京都を訪れ、最後の場面で幸せな結末を考える。
妻
東京で入院しており夫や子供の見舞いで疲れているが、子供に良人が持参した面を被ってやる。
あらすじ
仮面を被ることで、美しい微笑みで包もうとする映画芸術の世界。
脚本家の私は徹夜明けの撮影宿屋に帰るが、京都の青磁色が濃くなったような空や寝床の中から鴨川の水が朝の色に染まり行くのを眺めながら、あらたな美しい空想が生まれそうな気持だった。
まず四条通の景色が浮かび、昼食をとった西洋料理店の三階の窓から東山の新緑に木々が見えた、そして骨董店で見た芸術性の高い能面のような笑い面が浮かんできた。
ラスト・シーンは空想で終わろうと考える。今回の映画脚本は脳病院を書いたもので、毎日、痛ましい狂人達の生活が写されるのを見るのが辛かった。明るい結末にしなければ救われない気持だった。狂人たち一人ひとりに柔和な笑いの仮面を被せて、画面いっぱいに浮かび出る。暗い物語の終わりを美しい笑いの仮面で包もうとした。
お能のような面はなかなか見つからなかったが、なんとか古楽の面が五枚集まった。非常に高くて買えないから借物ということだった。
当初、私が考えた二三十枚ではなかったが、五枚の面の柔和な笑いが漂っており、高い芸術性に触れると気持ちが安らいだ。
そのうちの一枚、頬に黄色の絵の具をつけてしまったものを私は買い取った。
仮面を被りそして外すことで現れた、妻のみじめな人生の顔。
東京に戻ると私は真直ぐに妻の病院へ行った。子供たちは仮面を被ってにぎやかに笑った。私はなんとなく満足だった。
「お父さん被って見せて」と言われ、「厭だ」と断ると、次男が私の顔に面を押しつけようとした。
その時、妻が「母さんが被ってみましょうね」といい、私は蒼ざめて「これ、病人が何をするんだ」と言った。
病床に笑いの面が寝ているということは、何という恐ろしさだ。
面を取りのけた瞬間に、妻の表情は何と醜く見えたことか。初めて妻の表情を発見した驚きだ。美しい仮面に隠れたから、その後でみじめな人生の顔が現れたのだ。
美しい面が恐ろしくかった。その恐ろしさが「これまで私の傍で絶えずやさしい微笑みをしていた妻の顔は仮面ではなかったろうか。女の微笑みはこの面のような芸術ではなかろうか」という風な疑いを起こさせた。
面がいけないのだ。芸術がいけないのだ。
メンノトコロヲキリステヨと、京都の撮影所へ電報を書いた。
解説
芸術と日常の乖離である。表現者だけに備わっている創造性に、仕事の世界では自身で満足するが、日常の世界に安易に持ち込んだことで、おぞましいものを発見してしまいます。作者(私)の芸術と日常のあいだで内面の心象を捉えている幻想的な作品となっています。
芸術のように美しく調和できない、現実のやつれた世界。
仕事の世界では、脚本家の私は役者の都合で一週間の徹夜仕事に疲れています。そして映画のなかの脳病院の狂人達の生活をテーマにした暗さにやり切れません。
撮影場所の京都の青磁色の空や鴨川の朝の光の染まる水、四条通の景色や東山の新緑の木々という優雅な自然に接するうちに、表現のアイデアが研ぎ澄まされます。ラスト・カットだけは微笑む能面を映すことでハッピーエンドに出来たらと考えます。
作品は柔和な笑いを漂わせて終わるという、芸術性の高い感じに仕上がります。
私は 世界が美しく調和した未来では、人間はみんなその面のような柔和な同一の顔をお揃いで持ちそうと空想します。自身の表現力への充実した満足な気持ちです。
その能面が気に入って、ひとつ買って東京に戻ります。
日常の世界では、妻が入院しています、長患いをしている様子です。
夫は一週間も東京を空けた訳ですから、その間、病気の妻は子供たちの面倒もみて大変でした。病院では子供たちが仮面を被ってはしゃぎその姿に救われますが、子供たちから「被ってくれ」と言われ断ると、「母さん被って見ましょうね」と言って、代わりに妻が被ります。
そして仮面を取りのけた瞬間に、妻のやつれた顔が改めて強調されました。そこにはみじめな人生の顔が現れたのでした。
妻の微笑みも仮面で、その下には別の素顔があるのではと考える。
私は美しい面が恐ろしくなります。
芸術としての美しい仮面は、日常では被って取りのけると真実の姿が見えてしまうのです。
ここでの面は芸術性のある能面で、幻想のなかに吸い込まれていくようです。美しい面を被ることが、かえって外すときに現実の苦悩を浮き彫りにしてしまい恐ろしくなります。
すると、私は考えます。
これまでわたしに、やさしい微笑みをしていた妻の顔は実は仮面ではないか。と思われてきます。
病気で体が衰弱していても、子供たちにせがまれて面を被る母親の描写があります。どんなときも優しい微笑みを絶やさない妻であり母のようです。
徹夜続きと長患いの妻の看病は、表現者の感性のなかに この微笑みの下には別の素顔があるのではないか と疑いを起こさせます。
今回の脚本では、微笑む能面の下には脳病院の狂人達がいて暗い世界がありました。
そう思うと男は、面を代わるがわる次々と被る妻や子どもたちが、笑いあうような気持と同じようにはならず、とても笑えない。
日常の世界に面など持ち込んだのがいけなかった、芸術がいけないと思う。そう作者は感じてしまいます。日本の美や骨董に造詣の深い川端らしい幻想とシニカルな作品です。
※掌の小説をもっと読む!
『骨拾い』あらすじ|冷徹な眼が、虚無を見る。
『白い花』あらすじ|死を見つめる、桃色の生。
『笑わぬ男』あらすじ|妻の微笑みは、仮面の微笑みか。
『バッタと鈴虫』解説||少年の智慧と、青年の感傷。
『雨傘』解説|傘が結ぶ、初恋の思い出。
『日向』解説|初恋と祖父の思い出。
『化粧』解説|窓から見る、女の魔性。
『有難う』解説|悲しみの往路と、幸せの復路。
作品の背景
川端は「大半は二十代に書かれている。多くの文学者が若い頃に詩を書くが、私は詩の代わりに掌の小説を書いたのだろう、若い日の詩精神はかなり生きていると思う」と述べています。大正末期に超短編の流行があったが永続はせず、川端のみが洗練された技法を必要とするこの形式によって、奇術師と呼ばれるほどの才能を花開かせます。
大正十二年から昭和四、五年に至る新感覚派時代で作品の大半はこの時期に書かれています。内容は、自伝的な作品で老祖父と初恋の少女をテーマにしたもの、伊豆をテーマにしたもの、浅草をテーマにしたもの、新感覚派としての作品、写生風の作品、さらに夢や幻想の中の作品など幅広い。
発表時期
1971年(昭和46年)、『新潮文庫』より刊行される。「掌の小説」(たなごころのしょうせつ)あるいは(てのひらのしょうせつ)とルビがふられる場合もある。川端が20代のころから40年余りに亘って書き続けてきた掌編小説を収録した作品集。短いもので2ページ程度、長いもので10ページに満たないものが111編収録される。改版され全総数は127編になる。