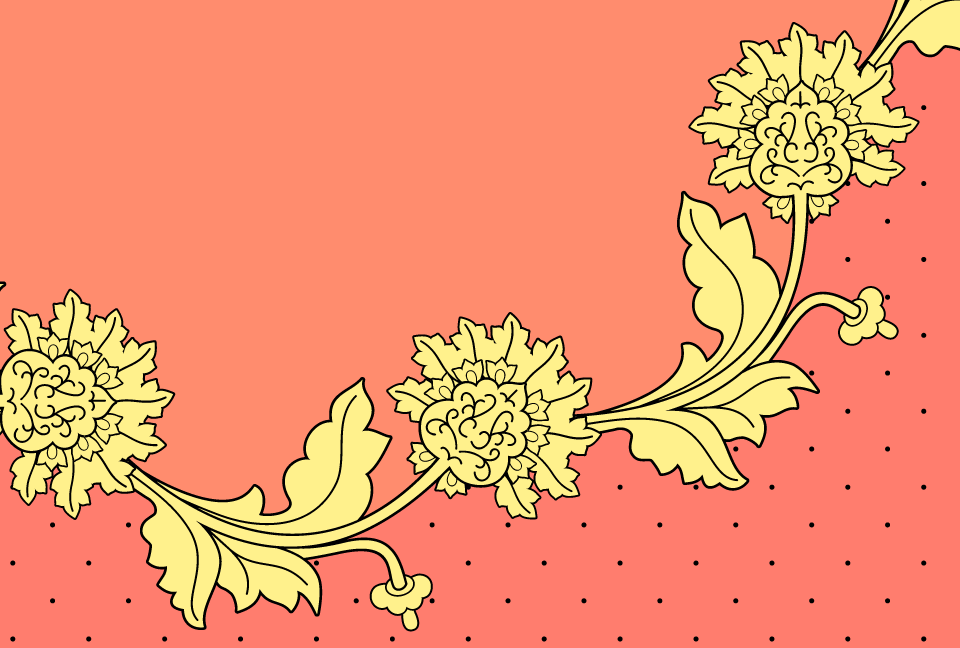斎場の厠と向きあう、我が家の厠の窓から女性の化粧する姿が見える。死者を弔い終え、厠の鏡で平然と化粧をする喪服の若い女たち。それは屍を舐める血の唇の印象を与える。そこに肩をふるわせ涙しながら十七、八歳の少女がやって来るが、さらに不可解な出来事を目撃する。
登場人物
語り手「私」
斎場の厠の窓と向き合う、自分の家の厠の窓から見える女性の化粧のことを思う。
あらすじ
捨てられた供花に、白菊の薫りや紅薔薇や桔梗の萎れ腐っていく命をみる。
家の厠の窓が、谷中(東京台東区)の斎場の厠と向かい合っている。二つの厠の間の空き地は斎場のゴミ捨て場となっている。ここに葬式の供花や花輪が捨てられる。
九月の半ば、面白いことがあると妻とその妹とを連れていく。手洗い場の窓から、いっぱいに白菊の花が捨てられている。二十ばかりの白菊の花輪が並んでいる。こんなにたくさんの菊の花を一度に見るのは何年振りだろうと妻が言う。
度々、厠へ立つ私は、夜、幾度となく菊の匂いを嗅ぎ徹夜の疲れがその薫りに消えていくように感じた。放鳥のカナリアがとまっているのを見つけるときもあった。
これなどは美しいと言えよう。
しかし、私はまた弔いの花々が腐っていく日々を見なければならない。三月初めは、花輪に咲いた紅薔薇と桔梗が萎れるにつれ、どんな風に色変わりするのか四五日の間つぶさに見てみた。
死を弔った喪服の女達の化粧する姿に身を縮め、少女の謎の笑いに戸惑う。
斎場の厠のなかでは若い女が多い。男は入ることが少なく、老婆は斎場の厠で長いこと鏡を見るには、もう女ではないのであろう。
若い女のたいていは、鏡に立ち止まって化粧をする。
葬式場の厠で化粧をする喪服の女性たちは皆、落ちつきはらっている。誰にも見られていないと信じながら、しかも隠れて悪いことをしているという罪の思いを体に現わしている。
濃い口紅を引いているところを見て、屍を舐める血の唇を見たようにぎょっと身を縮める。
街頭や客間の女性たちの化粧に同じものを浮かべると、女性に対して良い印象などをわざわざ抱かなくて済むと思う。
昨日、白いハンカチでしきりに涙を拭いている一七、八の少女を見た。肩を震わせしゃくりあげて、最後は頬を拭く力もなく涙を流れるままにする女性を見たときに、彼女は隠れて化粧に来たのではなく、人目をはばかり泣きに厠に来たのだと思った。
私は女への悪意が少女によってきれいに拭い取られていくのを感じた。
その時、思いがけなくも彼女は小さい鏡を出し、鏡に「にいっ」と一つ笑うと出て行ってしまった。
私には謎の笑いである。
動画もあります、こちらからどうぞ↓
解説
濃い紅色の口紅を引く若い女性に、生への貪欲さを見て嫌悪する。
語り手は、九月の半ばに美しい白菊の花を見る。次に、三月初めに紅薔薇や桔梗が萎れ色変わりがしていくのを見る。
それは自然の移ろいであり、美しさと萎れゆく姿に、生命の宿命的な時間の流れを感じる。
そこに若い女性が、 葬儀場の厠で濃い紅色の口紅を引くところを見る。血の唇を見る感じで、化粧が奇怪なものに見える。
死者への悼みを終えた後の、若い女性たちの生への貪欲さを感じる。
弔いの清浄な場所と化粧との不均衡もあり、女たちが魔女に見え、美しく化粧をしている街で見かける女性や、私のところへ客としてやって来る女性も、皆、同様だと考えて付き合うべしと自分に納得させることが、自分のためだと思う。
語り手である「私」は、紅い口紅を引く女性たちが、屍を舐める魔女に見えてしまう。
十七、八歳の女性の中に、既に棲んでいる不可解な笑いに戸惑う。
語り手である、川端にとって女性の処女性は大きな意味を持っている。
十七、八歳という年齢は、その境界線にいる存在なのか。このあたりの年齢を基準に大人の女性の位置づけがあるのかもしれない。
それは「伊豆の踊子」では、旅芸人の踊子の薫を一七歳の娘盛りと勘違いして、夜の酒宴の後、客相手に汚されることを心配するが、翌朝、共同湯で無邪気に裸体で手を振るのを見て十四、五歳で、まだ子供なんだと、ことこと笑うシーンがある。
この「まだ子供なんだ」との気づきは、初恋の女性、十三歳の伊藤初代の出会いでも、同じように起こりる。
『化粧』では、九月の半ば、三月最初と、観察する語り手の「私」は、昨日、見た出来事に驚く。
白いハンカチで涙を拭く十七、八歳の少女。涙をいっぱいにして泣く少女に、彼女だけは隠れて化粧をしに来たのではなく、隠れて泣きに来たのだと信じている。
少女のおかげで、それまでに植えつけられた若い女性たちへの悪意がなくなる。
ところが全く思いがけなく、少女は小さい鏡を持ち出し、鏡に「にいっ」と一つ笑って出ていく。
もうすでに、少女も魔女の入り口に来ているのだろうか。時がもう少し経てば、少女も生への貪欲さを持ち始めるのでしょう。女性を謎な存在として受け止め、当惑する川端の姿が描かれています。
※掌の小説をもっと読む!
『骨拾い』あらすじ|冷徹な眼が、虚無を見る。
『白い花』あらすじ|死を見つめる、桃色の生。
『笑わぬ男』あらすじ|妻の微笑みは、仮面の微笑みか。
『バッタと鈴虫』解説|少年の智慧と、青年の感傷。
『雨傘』解説|傘が結ぶ、初恋の思い出。
『日向』解説|初恋と祖父の思い出。
『化粧』解説|窓から見る、女の魔性。
『有難う』解説|悲しみの往路と、幸せの復路。
作品の背景
川端は「大半は二十代に書かれている。多くの文学者が若い頃に詩を書くが、私は詩の代わりに掌の小説を書いたのだろう、若い日の詩精神はかなり生きていると思う」と述べています。大正末期に超短編の流行があったが永続はせず、川端のみが洗練された技法を必要とするこの形式によって、奇術師と呼ばれるほどの才能を花開かせます。
大正十二年から昭和四、五年に至る新感覚派時代で作品の大半はこの時期に書かれています。内容は、自伝的な作品で老祖父と初恋の少女をテーマにしたもの、伊豆をテーマにしたもの、浅草をテーマにしたもの、新感覚派としての作品、写生風の作品、さらに夢や幻想の中の作品など幅広い。
発表時期
1971年(昭和46年)、『新潮文庫』より刊行される。「掌の小説」(たなごころのしょうせつ)あるいは(てのひらのしょうせつ)とルビがふられる場合もある。川端が20代のころから40年余りに亘って書き続けてきた掌編小説を収録した作品集。短いもので2ページ程度、長いもので10ページに満たないものが111編収録される。改版され全総数は127編になる。