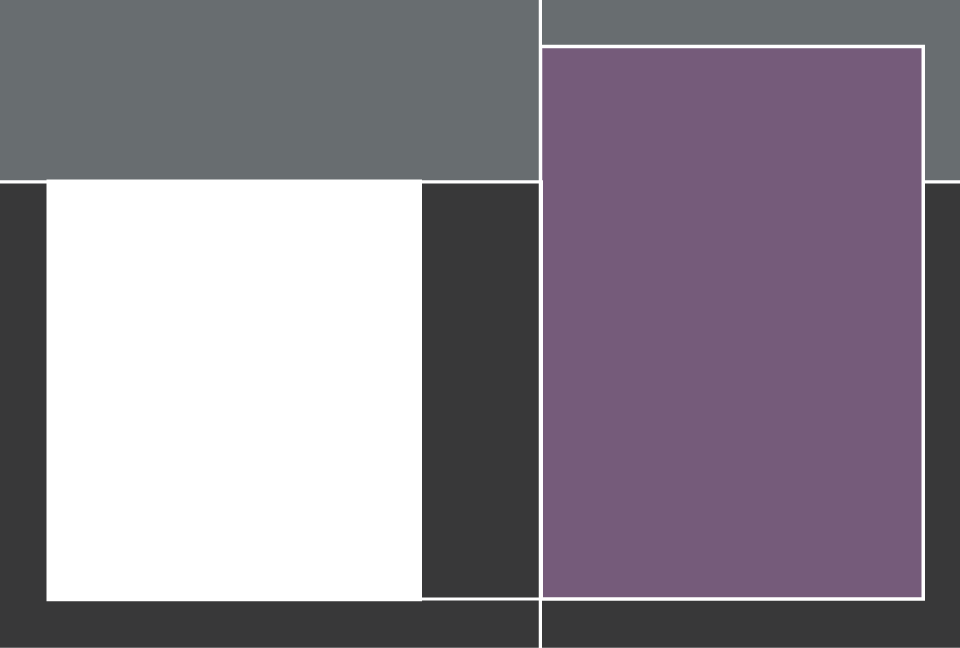解説
無罪と書く前に、裁判官に湧き上がった「興奮」とは何だったのか。
范は「本統の生活」をしたいとずっと考え思索し続けている。その「本統の生活」とは何なのか、それは「自分らしい自由な生活」です。「自分らしい」とは何か、それは范の考える正義を貫くことです。
范は物語のなかでこう云います。
その位なら、何故殺して了わないのだ。殺した結果がどうなろうとそれは今の問題ではない。牢屋に入れられるかも知れない。しかも牢屋の生活は今の生活よりどの位いいか知れはしない。その時はその時だ。その時に起ることはその時にどうにでも破って了へばいいのだ。
破つても破っても破りきれないかも知れない。然し死ぬまで破ろうとすればそれが俺の本統の生活といふものになるのだ。まさに抑圧から自己を開放するために「何故殺して了わないのだ」と自分の正義を強く貫くことを求めている言葉です。
范は妻に対して嫉妬し、懊悩し、長い時間をかけて思索を巡らせます。
范のなかには、順序だてられた道理があり正義があり、それは決して突発的ではなく、赤児が従兄と妻との子であることが発覚してからはじまり、この日のナイフ投げで「不意の殺人」として帰結します。それは過失として処理される必要があります。
范にとっては思索の到達点が、定まらぬナイフ投げでの殺人になってしまったのです。然し范は過失と我を張るのではなく、何方か分からないと考えます。
范自身が何方か分からないとなれば、殺意の有無は誰にも分らないことになり、裁判官は「故意」とは判定できません。と同時に、正直でいられることの方が遥かに強いと范は考えます。
范の思いは「殺した結果がどうなろうとそれは今の問題ではない」と考え「然し死ぬまで破ろうとすればそれが俺の本統の生活といふものになるのだ」で結ばれます。
范は本統の生活の入り口に立つことを決めたのです。范の考える正義の結果得られる「本統の生活」の始まりです。そして憂うことなく前へ進もうとさらなる強固な意志を持とうとしています。
それは強い自我であり自己への忠誠です。頑なに守られる自己中心主義です。
范の証言は客観的な証拠とは見做されず、そして、范は神経症的で責任能力を問えない精神疾患の状態です。裁判官が過失だと判断し「無罪」とするのは当然と思われます。
裁判官は何かしれぬ興奮の自身に湧き上がるのを感じた。
とあります。この裁判官の「何か知れぬ興奮」とは何なのでしょうか。
范の長い時間、深く熟考された思索にもとづいた主張や、考え方、生き方。妻を殺して了うことで法の裁きの結果を気にせず、拘泥する嫉妬と生理的な嫌悪に対して、圧迫された抑圧を跳ね返す自我の開放という范の自己中心主義です。
その范の強い自我の人間性と、「故意」なのか?「過失」なのか? とのどちらかの判断を下すことのできない、人間の思索の複雑さ、心情とその結果を知ることで裁判官は興奮を覚えたのでしょう。
対決から調和へ、この作品を経て変わっていく直哉の心境。
范の話を聴取し直ぐにペンを取り上げ、 裁判官はその場で「無罪」と書きます。
范の思索の軌跡を読者に提示しながら、裁判官の 「何か知れぬ興奮」 という人間心理が浮かび上ってきます。読者は裁判官と同じ眼を持ちます。と同時に、読者は范の精緻な思索の果ての行為という情動の背景を理解します。そして判決を迫られます。
范は志賀直哉であり、裁判官もまた志賀直哉であり、自問自答の行為でもあります。
ここに志賀直哉の激しい自我が強く確認されます。それは范が唱える文中の「本統の生き方」とは何かに明確に表れています。
裁判の「無罪」判決は自己の正当化です。そんな直哉の心情が、緊迫した范の心理描写に描かれます。しかしこの作品をピークに直哉の自我の高揚は沈静化していきます。
四年後の大正六年に発表された『城の崎にて』の作品の中に、以下の一文があります。
范という支那人が過去の出来事だった結婚前の妻と自分の友達だった男との関係に対する嫉妬から、そして自身の生理的圧迫もそれを助長し、その妻を殺すことを書いた。
とあります。結果を省みない強い自我の肯定です。ここは直哉と父親との不仲から関係を断ってしまうことを意味しています。自己への忠誠であり自我の開放です。そして文章は続きます。
それは范の気持ちを主にして書いたが、しかし今は范の妻の気持ちを主にし、仕舞に殺されて墓の下にいる、その静かさを自分は書きたいと思った。(引用:志賀直哉 城の崎にて )
と『城の崎にて』の作品の中で、『范の犯罪』について記しています。山手線の電車事故の後に、療養で訪れた城崎温泉で静かに思ったことは直哉のこれまでの考え方とこの後の考え方を大きく動から静へと変えたものでした。
その文末に「しかし今は范の妻の気持ちを主にし、仕舞に殺されて墓の下にいる、その静かさを自分は書きたいと思った」とありますが、結局、この作品は書かれませんでしたが、この一文から直哉の自我が沈静された感情が伝わってきます。
この後は、これまでの父子の対立から、調和へと向かう心境に変わっていきます。

※白樺派のおすすめ!
志賀直哉『正義派』解説|真実を告げる勇気と、揺れ動く感情。
志賀直哉『清兵衛と瓢箪』解説|大人の無理解に屈せず、飄々と才能を磨く少年。
志賀直哉『范の犯罪』解説|妻への殺人は、故意か?過失か?
志賀直哉『城の崎にて』解説|生から死を見つめる、静かなる思索。
志賀直哉『流行感冒』解説|パンデミックの時にこそ、寛容の大切さ学ぶ。
志賀直哉『小僧の神様』解説|少年の冒険心と、大人の思いやり。
武者小路実篤『友情』解説|恋愛と友情の葛藤に、辿り着いた結末は。。
作品の背景
『范の犯罪』の裏話が「創作餘談」に書かれています。支那人のナイフ投げの奇術を見ていて、もし殺害が起こった場合に「過失」か「故意」か分からないと思い、小説の題材にと考えていた。
そんな折に直哉の従弟の一人が夫婦関係のもつれから自殺するという事件が起こります。「直哉の従弟をAとすると、Aの親友の男であるBは、Bの従妹と関係し子どもが出来た事を知らずに、BはAに交際をすすめ二人は結婚した。子が早く生まれAは自分の子ではないと煩悶した。そして神経を病み自殺した。このことを知らされた直哉は、善良なAを歯痒く思い、自分がAならば妻を殺す方がましだと考えた」とあります。
この話と組み合わされ、8月7日に「従弟の死」と題され、次に9月初旬に「支那人の殺人」とされ、そして父との不仲な関係のなかに投影されたかたちで9月24日に『范の犯罪』となり完成しました。
発表時期
1913年(大正2年)10月、『白樺』に発表された。志賀直哉は当時30歳。父親との不仲で大正元年から尾道に転居し、一旦、東京に戻り8月15日には山手線にはねられて重傷を負い東京病院に入院する。この事故の前に書かれた「従弟の死」「支那人の殺人」と、事故の後に脱稿した『范の犯罪』は、死を身近に体験し死生観に対する思いを含め複雑な思索の往還を経た作品になっています。