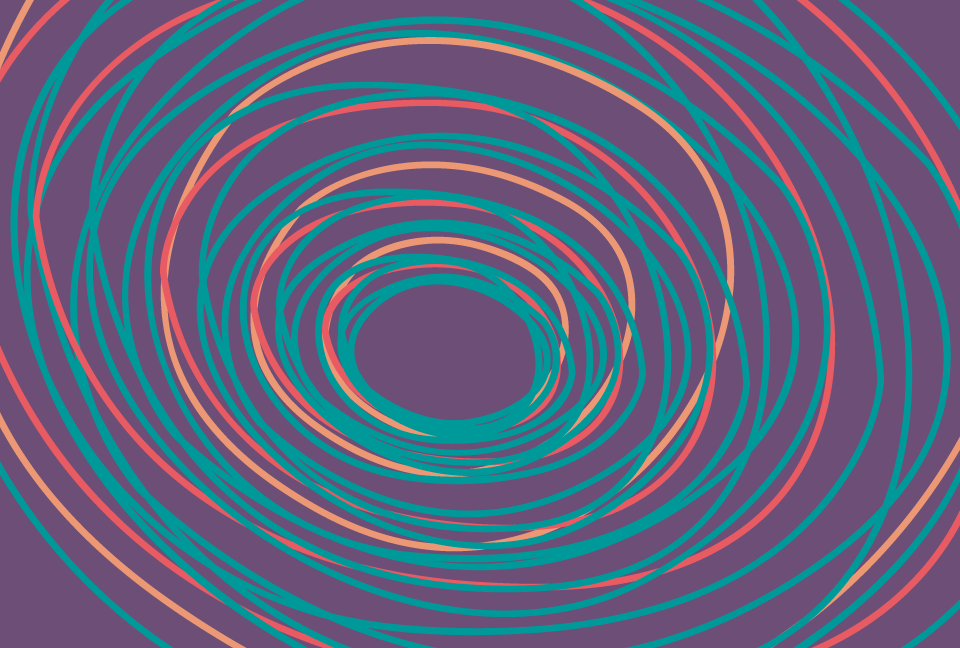作品の背景
明治の上流階級の子弟であった荷風は、厳格な家の雰囲気に反抗、みずから落ちこぼれる。早くから欧米に遊学し、物質文明ではなく古い歴史臭に興味を持つ。それに比べて日本の浅薄な西洋崇拝とその模倣の風潮を嫌い、江戸情緒を愛した。
そして大正6年9月16日から昭和34年4月29日の死ぬ間際まで『断腸亭日乗』として自身の独居、隠棲、散策の記録を残す。この日記は今では時代の風俗を伝える資料として貴重なものとなっている。
荷風の強いエリート意識と貴族主義は生涯、貫かれたが、反面、文壇やアカデミズムの付きあいを嫌った。さらに軍国主義からも背を向け町をよく歩いた。散策好きである。古き良き時代の下町、裏町、横町、路地を愛した。路地の裏にこそ人生の哀歌があると考えた。
そして東京を舞台にした作品を出し続ける。向島と今戸を『すみだ川』に、新橋を『腕くらべ』に、白山と富士見町を『おかめの笹』に、銀座を『つゆのあとさき』に。
山の手で生まれた荷風は、浅草を中心とした下町に、表通りよりも裏通りに惹かれた。戦後の浅草通いから、さらに奥の墨田区の東の私娼の町、玉の井を見つける。ここで、失われつつある江戸情緒のなかに男女の恋愛を描いた作品が『濹東奇譚』となる。
どぶの臭い、うるさい蚊の羽音、洗浄薬と屎尿の臭い、そんな場末の色まちを、戦争の時運から逃れた静かな別世界として、荷風は透明で詩情漂う異界の迷宮に見立てている。その象徴がお雪さんである。頽廃のなかにも、善良で単純で、可愛らしさが溢れている。
軍国主義の高まりの中、還暦が近い58歳の荷風にとっては、身を隠すに心地良い江戸の風情を残し、安らぎを感じるラビリンス(迷宮)の里だったのだろう。
物語の結末は、お雪が大江におかみさんにしてくれと云いだしたところで、別れる理由となす。それは二度の結婚に失敗(意図的に離別)し、独身主義を貫いた荷風ならではの結末である。
それは他人と自分の間に境界線を引く個人主義でもあり、それゆえに、いとおしく思う余韻を残しながら別れて行く姿でもある。
発表時期
1937(昭和12)年、4月に朝日新聞夕刊に掲載、好評を博す。永井荷風は当時58歳。 『濹東奇譚』 は叙情小説の名作とされる。
荷風は昭和11年3月末から玉の井に頻繁に足を運ぶようになる。2月には2・26事件が起こっている。5月には「玉の井見物の記」を書く。そして9月21日から『濹東奇譚』の執筆を始め、10月25日に脱稿する。同時に新聞連載が決定していたが当時は日支の関連記事や時局を鑑みて連載が遅延した。
翌12年、私家版として少部数出版し、4月16日から6月15日の35回の連載で完結した。8月、岩波書店から単行本として刊行。この間、7月7日に盧溝橋で日支が武力衝突、ここに日中戦争が始まる。その後、玉の井の町は昭和20年3月10日の東京大空襲によって焼失した。今はもうその面影はない。
荷風は戦争に無関心で執筆活動を続ける。終戦直後は作品が一挙に発表され荷風ブームを起こす。『濹東奇譚』は1946(昭和21)年に川端康成らが作った鎌倉文庫から出版される。1959(昭和34)年、80歳で死去。