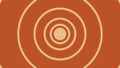四十歳になる人間嫌いの彼は、幾数種の鳥の番の仲睦まじさを観察したり、飼育する犬の出産を助け純血主義を美しく思う。彼は、犬の顔に心中未遂した千花子の顔を重ね合わせる。それは、生きかつ死へと向かうときの生命の明かりと、虚無の世界であった。
登場人物
彼
四十歳で独身、音楽や舞踊が好きで人間嫌い、複数種の鳥や犬などを飼っている。
千花子
元娼婦で十年前に彼と心中未遂し、その後、踊子となり満州で伴奏弾きと結婚し離婚。
女中
彼の家の女中、主人に仕え、鳥や犬などたくさんの愛玩動物の世話をしている。
小鳥屋
菊戴をはじめ何か新しい鳥が入ると、黙って番いで彼のもとに持ってくる。
犬屋
腎臓病の持病があり、金に困って野良犬にかかったドーベルマンを客に売る。
あらすじ
小鳥の鳴声に彼の白昼夢は破れ、家に置いたままの死んだ菊戴を思う。
千花子の踊りを観に行くために、タクシーで日比谷公会堂に向かう彼は、途中、葬いの車列の間へ乗り入った。道端に「史蹟太宰春吉墓」と石標のある禅寺の前だった。
放鳥のため大きな鳥籠を乗せたトラックからの小鳥の声で、白昼夢から醒めた彼は、「途中で葬式に会うなんて、なんて縁起が悪いんだろう」と言うと、運転手は「縁起がいいんですよ。これほどいいことは、ないっていうんですよ」という。
「逆なんだね」と笑いながら、人間がそんな風に考えるようになったのは、当然だと思った。
彼は、動物の死骸を置きっぱなしにしていることの方が、よほど縁起が悪いと思った。彼の家には、 死んでもう一週間になる 菊戴の番が押入に放り込まれたままだった。
菊戴は、黄菊の花弁をひとひら戴いたように見え、円い目におどけた愛嬌があり可憐でありながら、高雅な気品がある。番は、それぞれの首を相手の体の羽毛のなかに突っ込み合い、一つの毛糸の鞠のように円くなる。人間でも幼い恋人であれば、こんなきれいな感じで眠っているのが、どこかの国に一組くらいはいてくれるだろうかと思う。
四十近い独身者の彼は、客に会うのにも鳥や犬などの愛玩動物を放したことはなかった。彼は、男と会うのが嫌で、女でも薄情そうな方が良く結婚も気が進まない。鳥屋は、なにか新しい鳥が手に入ると、黙って彼のところに持ってくる。彼の書斎の鳥は三十種になることもある。籠の鳥となっても、小さい者達は生きる喜びをいっぱいに見せていた。
小柄で活発な菊戴夫妻は、殊にそうであった。ところがひと月して、女中が一羽を逃がしてしまった。残ったのは雌だった。彼は小鳥屋に雄を催促したが、小鳥屋は一番を取り寄せるので、雄だけだと雌が残ってしまうという。仕方なく三羽を籠に入れると、騒ぎだし、数日後、一羽が死んでいた。
予期とは逆に、生き残ったのは古い雌のほうだった。
ボストンテリアの雑種の出産で、幼い娼婦の千花子の顔を思い出した。
小鳥屋も飼い主も、鳴かない雌は棄ててしまう。動物を愛するといっても、やがてはその優れたものを求めるようになるのは当然で、この冷酷は避けがたい。
だから人間は嫌なんだと、孤独な彼は勝手な考えをする。
と同時に、良種へ良種へと狂奔する動物虐待的な愛護者たちを人間の悲劇的な象徴として、冷淡を浴びせながらも彼は許している。そして彼もまたそうであった。
去年、犬屋がやってきて言うには、売りもののドーベルマンを公園でちょっと目を放した隙に野良犬がかかり、結局、買い手の家で妊娠したが子は死産し、さらに母犬が子犬を喰っているのを見て、飼い主は驚き大いに憤慨されたという。彼が買い手を紹介したので、犬屋の不徳義に彼も腹を立てた。
それでも彼は雌犬だけを飼う、それは犬の出産と育児が何より楽しいからであった。
彼の飼っていたボストンテリアが、ある日、紐を噛み切って外へ出歩き雑種を孕んだ。彼は、道徳的な呵責を感じたが、鋏と脱脂綿を女中に用意させた。この犬は今度が初潮で分娩というものの実感が分からないようだった。
彼は、十年前の千花子を思い出した。その頃、彼女は彼に自分を売る時に、ちょうどこの犬のような顔をしたのだ。彼女は幼い娼婦だった。
犬は、直ぐに袋児を産んだ。彼は鋏で袋を裂いて、臍の緒を切った。次の袋は二つの胎児が死の色に見えた。続いて三頭産まれた。七番目は袋のなかでしなびていた。
どこかへ捨てておいてくれと女中に言った、一頭の子を自分が殺したことなど忘れていた。それよりも、新しい命の誕生にみずみずしい喜びが胸にあふれた。
ところが或る朝、子犬が一頭死に、二三日後にまた一頭死んだ。母犬が子犬を圧死させたのだった。人間の愚かな母親と同じである。三頭目も死んだ。子供を殺したのも知らぬ顔で、公園で駆け廻るボストンテリアを見ると、ふいとまた千花子を思い出した。
結婚し妊娠し退廃していく千花子が、ボストンテリアの幻覚と重なる。
千花子は十九の時、投機師に連れられてハルビンへ行き、三年ほど白系ロシア人に舞踊を習った。その後、満州巡業の音楽団に入り、そして東京に落ち着くと投機師と別れて満州から同行した伴奏弾きと結婚した。そして自分の舞踊会を催すようになった。
その頃、彼は或る音楽雑誌に月々金を出し音楽会に通っていた。千花子の舞踊も見た。彼女の肉体の野蛮な退廃に惹かれた。しかし第四回の舞踊会の時、彼女の肉体はげっそり鈍って見えた。彼女は妊娠していた。
「子供を持って一芸に生きられるものか」と彼は言ったが、その後の噂では、生まれた子供も彼女の傍には見られなくなり、夫婦生活も暗く荒んでいるらしかった。
犬の子にしても、彼が助けようと思えば助けられたのであるが、生かさねばならないとも思わなかった。それほど冷淡だったのは雑種だったからだ。
彼は世の中の家族たちを蔑みながらも、自らの孤独も嘲るのである。
健やかだった菊戴の二羽が、水浴びをさせすぎて死んでしまった。冷え切った体を長火鉢に焙ったり、水籠の底に手拭いを敷き、小鳥を載せて火にかざしたりした。番茶に浸したり口の中で温めたりしたが、六日目の朝、菊戴夫婦は仲良く死骸となっていた。
その後、鳥屋がもってきた菊戴も、注意していたにもかかわらず、また同じ水浴の結果、弱らせてしまった。今度は介抱せずに、死なせたほうがいいと女中に言われてそうしてしまった。菊戴は小柄なだけに、弱くて落鳥しやすい。
二度も水浴で殺してしまい、彼は「菊戴とはもう縁切りだよ」と女中に言った。
十六歳で死んだ少女の遺稿集に、純血の素晴らしさを感じ虚無に浸る。
その夜の舞踊会は、千花子の舞台を二年振りに見るのだが踊りの堕落に目をそむけた。踊りの基礎の形も、彼女の肉体の張りと共に、すっかり崩れてしまっていた。
楽屋に行くと千花子は、若い男に化粧をさせていた。静かに目を閉じ、じっと動かない真白な顔は、脣や眉や瞼が描けていないので、命のない人形のように見え、まるで死に顔のように見えた。
十年近く前に、千花子と心中しようとしたことがあった。その頃、彼は死にたいと口癖にしていたほどだから、独身で動物と暮らすような生活の泡沫の花に似た想いに過ぎなかった。そして死の相手に千花子が良いとも感じられた。
すると千花子は、死の相手としてたわいなくうなずいた。彼女は彼に背を向けて寝ると、無心に目を閉じ、少し首を伸ばした。それから合掌した。彼は虚無のありがたさに打たれた。
彼は、勿論、殺す気も死ぬ気もなかった。千花子は本気だったか、戯れ心であったか分からぬ。真夏の午後であった。あれから後、彼は自殺を夢にも思わず、たとえどのようなことがあろうと、この女をありがたく思い続けねばならないと思った。踊りの化粧を若い男にさせている千花子が、その昔の合掌の顔を彼に思い出させた。
さっきの自動車での白昼夢もこれであった。夜でも千花子を思い出すたびに真夏の白日の眩しさに包まれる錯覚を感じる。
彼は楽屋の廊下で、千花子の亭主の伴奏弾きに会った。伴奏弾きは「こうして大勢躍らせると、やっぱり千花子のいいのがはっきりしますね」という。去年の暮れに離婚したという。それでも「千花子の踊りは抜群ですね。いいですなぁ」と言う。
彼は自分も何か甘いものを見つけなければと胸苦しくあわて、一つの文句が浮かんだ。それは彼が好んで読んでいた十六で死んだ少女の遺稿集で、死に化粧をしてやった母親が、娘の日記の終わりに書いていた。
その文句は「生まれて初めて化粧したる顔、花嫁の如し」