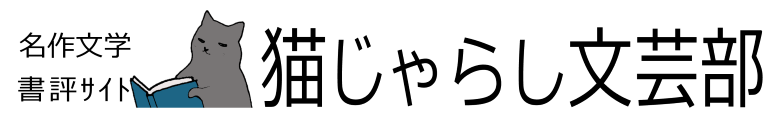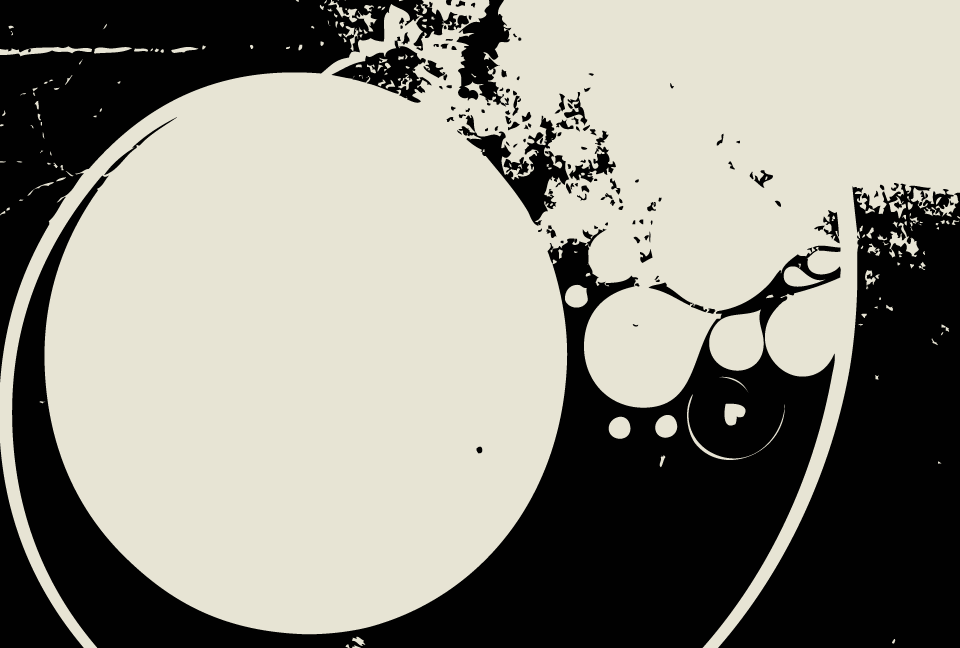作品の背景
坂口安吾は、1906年に新潟の裕福な旧家に生まれ、13人兄弟の12番目で、母の愛情を受けず、繊細な内面性と破天荒な性格で小学校の頃にはガキ大将となり、中学では落第する。その後、東京の中学に編入し17歳の頃から宗教への関心を持つ。
中学のころ「余は偉大なる落伍者となっていつの日か歴史の中によみがへるであろう」と学校の机の蓋の裏側 (*実際は柔道場の板戸) に彫ったことを『いずこへ』に記しているが、乱暴さと神経の細やかさという両面を持ち、20歳を超えたあたりからは、哲学を通じて倫理と向き合う求道家であった。
19歳で小学校の代用教員となる。後の『風と光と二十の私と』で不良少年を見守る安吾の眼は優しい。ここで「本当の美しい魂は悪い子供がもっているので、あたたかい思いや郷愁をもっている」という。
仏教を勉強するために東洋大学の印度哲学倫理学科に入学、悟りをひらくための修業をはじめる。さらに大学在学中のままアテネ・フランセに学び、24歳で『木枯の酒倉から』を発表。やがて初めての純愛を経験し、後に32歳で『吹雪物語』として発表。
前後してバーのマダムと同棲に入りデカダンな生活を送る。この頃、日中戦争から大東亜戦争へ突入していく。終戦後、日本は大きく変わる。これまでの正しいものが邪悪に変わり、米主導の自由や民主主義や平和憲法を押しつけられ、戦時の体制を皆が口々に批判し、変節の逃げ道とします。
混迷と荒廃と虚無。この世相に対して、安吾は決して高見からではなく渦中に入って真実を見つめる実存の姿勢を貫いていく。東京大空襲のなか起居していた蒲田区の家の周辺は工業地帯であり、爆撃の対象であったが安吾はそこを離れず、そこから生まれたエッセイ『堕落論』と小説『白痴』で一躍、時代の寵児となり、戦後文学の代表的作家となる。

安吾は戦中・戦後の人間を見つめている。『模範少年に疑義あり』や『焼夷弾のふりしきる頃』などのエッセイにも、運命はあったが堕落はなく、無心であったが、充満していたことが語られている。
翌年には『続堕落論』を発表している。そこでは、さらに天皇と日本人を深堀する。

人間は堕ちるところまで正しく堕ち、そこから真の自己や真の天皇を発見しなければならないとする。
発表時期
1946(昭和21)年4月1日、雑誌『新潮』(第43巻第4号)に掲載される。翌47(昭和22)年『銀座出版社』より単行本「堕落論」を刊行。坂口安吾は当時39歳。
太宰治、織田作之助、石川淳、壇一雄らと、無頼派・新戯作派と呼ばれた。41歳の時に17歳の年の離れた美千代夫人と結婚。1955(昭和30)年2月17日、桐生市の自宅で脳出血を起こし急逝。享年48歳。