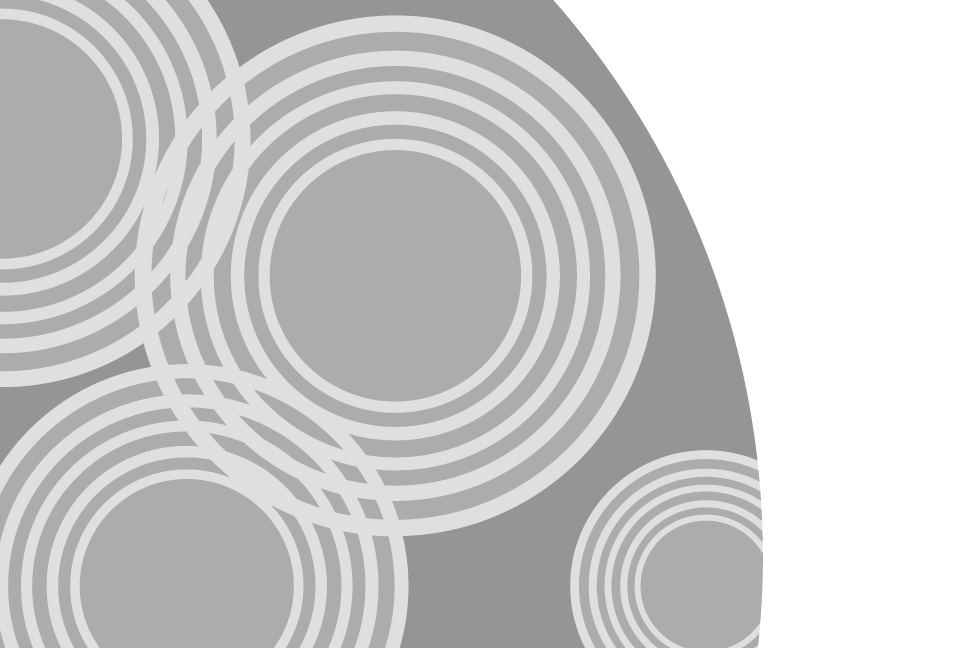行男の急変に、駒子の冷たい薄情と熱い愛情を感じて雪国を去る。
それから泊まることがあっても、駒子は夜明け前に帰ろうとはしなかった。
東京に帰る前の月の冴えた夜に、島村は駒子をもう一度呼ぶと、彼女は散歩をしようと聞かなかった。島村を無理やり連れだした。月はまるで青い氷のなかの刃のように澄み出した。道は凍り村は寒気に寝静まっていた。
部屋に戻り「つらいわ。ねぇ、あんたもう東京へ帰りなさい。つらいわ」と言う。つらいとは旅の人に深くはまっていきそうな心細さであろうか、それともこらえるやるせなさか。
島村が「どうもできないので明日帰ろう」と言うと、駒子は「あんたそれがいけないのよ」と言う。それから潤んだ目を開くと「ほんとうに明日帰りなさいね」と静かに言った。
次の日、駒子はコートに白い襟巻をして島村を駅まで見送った。
その時、葉子が駆けてきて「ああっ、駒ちゃん、行男さんが変よ。早く帰って、様子が変よ、早く」と急変を知らせるが、駒子はかぶりを振る。駒子はもう二度と来ないかもしれない島村を送ると言う。葉子が島村の手を握って帰すように頼み、島村が駒子に「早く帰れよ、馬鹿」って言うと「あんた、何を言うことあって」と葉子の手を島村から押しのける。
島村は「あの車で、今帰しますから先に行ったらよい」と葉子に言い、葉子は走り出す。
島村は「君たち三人にどういう事情があるかは知らないが、死にそうな息子さんが会いたがっている、素直に帰ってやれ。でないと一生後悔する。君が東京へ売られていく時に、ただ一人見送ってくれた人じゃないか。いちばん古い日記の一番初めに書いてある、その人の最後を見送らなくてよいはずはない。その人の命の一番終わりのページに、君を書きに行くんだ」と言った。
駒子は「いや、人の死ぬの見るなんか」と言い、それは冷たい薄情とも余りに熱い愛情とも聞こえた。
汽車は国境の山から登って長いトンネルを通り抜ける。島村は何か非現実的なものに乗って時間や空間の思いも消え、虚しく体を運ばれて行くような放心状態に陥ると、単調な車輪の響きが女の声に聞こえ始めた。
行男の墓を見舞い、駒子と葉子の死者への思いの違いを知る。
翌々年、国境の山々が夕日を受けて秋に色づくころ、島村は温泉町にやってくる。
部屋に到着すると、少し遅れてやってきた駒子は「あんた、なにしに来た。こんなところへなんしに来た」となじる。二月の十四日に鳥追いの祭りがあり、島村はこの祭りを見に来ると約束していたのだ。行男は島村と駒子が駅で別れてから間もなくして亡くなっていた。また踊りのお師匠も肺炎で亡くなっていた。
駒子は二十一歳になっていた。お師匠さんが死んで屋根裏の前の家から置屋に住まいをかえていた。
「一年に一度でいいからいらっしゃいね。私のここにいる間は、一年に一度、きっといらっしゃいね」と駒子は言い、年期は四年だと言った。
島村は三年足らずの間に三度来たが、その度毎に駒子の境遇も変わっていた。
内湯から上がって来ると、駒子は安心しきった静かな声で身の上話を始めた。「私のようなのは子どもが出来ないのかしらね」と真面目に尋ねた。一人の人とつきあっていれば夫婦と同じではないかと言うのだった。駒子にそういう人のあるのを島村は初めて知った。
十七の年から五年続いているという。親切な人だが生き身を許す気になれないという。また年期は四年だが、既に半年過ぎ、元金も半分以上を返したと語った。
翌朝、駒子は早く起き、窓際の鏡台には紅葉の山が写り、秋の日ざしが明るかった。
葉子は墓参りばかりしているようだった。駒子が帰ってから島村も村へ散歩に行ってみた。道端の日向に藁むしろを敷いて小豆を打っている葉子がいた。乾いた豆がらから小豆が小粒の光のように躍り出る。葉子はあの悲しいほど澄み通って木魂しそうな声で歌っていた。
翌朝、目をあくと駒子が座って本を読んでいた。駒子は杉林のところから掻き登ってきたという。湯から上がった島村を裏庭へ誘い出した。畑沿いに水温の方へ下りていくと川岸は深い崖になっていた。
島村は駒子の許婚の墓に行ってみようと言うと、駒子は「あんた私を馬鹿にしてんのね。なんの因縁があって、あんた墓を見物するのよ」と言う。許婚でないことは駒子から聞いてはいたが、島村にはその “行男” という男が心に残っていた。
「ねえ、あんた素直な人ね。なにか悲しいんでしょう。今に命まで散らすわよ。墓を見に行きましょうか」と言い、「駒子は一度も参ったことがないことを、そしてお師匠さんも一緒に埋まっていて、お師匠さんにはすまないと思うけれど、今更参れやしない。そんなことしらじらしい」と言い、「生きた相手だと思うようにはっきり出来ないから、せめて死んだ人にははっきりしとくのよ」と言う。
墓場に行くと葉子がいた。真剣な顔をして燃える目でこちらを見た。
駒子は「私ね行男さんのお墓参りはしないことよ」と言い、葉子はうなずいて墓の前にしゃがんで手を合わせた。
夜中の三時。障子を押し飛ばすようにあける音で島村が目を覚ますと、胸の上へばったり駒子が長く倒れた。駒子は元結を切ってもらおうとやってきた。島村は駒子の髪を掻き分け元結を切った。朝の七時と夜中の三時と一日に二度も異常な時間に暇を盗み来たのかと思うと島村はただならぬものを感じた。
葉子は駒子を「憎い」と言い、駒子は葉子を「気ちがいになる」と言う。
紅葉を門松のように門口に飾りつけていた。島村は帳場のほうを見ると葉子が炉端に座っていた。
島村は駒子の愛情が美しい徒労であるかのように思う彼自身の虚しさがあり、かえって駒子を哀れみながら自らを哀れんだ。そのありさまを無心に刺し透す光に似た目が葉子にはありそうな気がして、島村はこの女にも惹かれるのであった。
島村が呼ばなくても駒子はやって来た。彼女は宿へ呼ばれさえすれば島村の部屋を寄らぬことはなかった。「悪い評判が立てば、狭い土地はおしまいね」と言いながら駒子は「ほんとうに人を好きになるのはもう女だけなんですから」と言う。
葉子もお銚子を運ぶのを手伝っているようで「駒ちゃんが、これよこしました」と、駒子の結び文を持ってくる。島村は葉子に話しかける。
葉子は「駒ちゃんはいいんですけれども、可哀想なんですから、よくして上げて下さい」と言い、島村が「何もしてあげれないので、早く東京に帰ったほうがいいかもしれないんだけど」と言うと、葉子は危険な輝きが迫ってくるように「私も東京に連れて行ってください。駒ちゃんは憎い」と言う。
葉子は、以前、東京では看護婦になりたいと思っていたが、それは行男を看るためで行男以外の病人を世話することも墓に参ることももう無いという。
葉子は涙を流しながら「駒ちゃんは、私が気ちがいになると言うんです」と言って、部屋を出て行ってしまった。
島田は駒子にこのことを話すと「あなたみたいな人の手にかかったら、あの子は気ちがいにならずにすむかもしれないわ」そして「私はこの山の中で身を持ち崩すの。しいんといい気持ち」と言う。
島田は駒子からその後、部屋を見せてもらった。送っていくという駒子は、そのまま島村と一緒に宿に入り冷酒をついでくる。
島村がぽつりと「君はいい子だね」と言った。「どうして?どこがいいの」「いい子だよ」一人の女の生きる感じが温かく島村に伝わってきた。「君はいい女だね」「どういいの」「おかしなひと」
ところが何と思ったか。「それどういう意味?ねえ、なんのこと?」そう言って不意に部屋を出て行った。島村は十分に心やましいものがあった。
しかしすぐに戻ってきてお湯にいき、体が温まる頃から痛々しいほどにはしゃぎだした。紅葉のさび色が日毎に暗くなっていた遠い山は、初雪であざやかに生きかえった。
島田はもう雪国に来ないと思い、虚無に天の河が落ちてくる幻影を見る。
雪のなかで、糸をつくり、織り、水に洗い、晒す。雪ありて縮あり。島村はこの雪国の縮を好んだ。島村が着る古着の縮のうちにも明治の初めから江戸の末の娘が織ったものがあるかもしれなかった。島村は今でも自分の縮を「雪晒し」に出す。
縮の産地はこの温泉場に近い。妻子のうちへ帰るのも忘れたような長逗留だった。駒子のすべてが島村に通じて来るのに、島村の何も駒子に通じていそうにない。駒子が虚しい壁に突きあたる木霊に似た音を、島村は自分の胸の底に雪が降りつむように聞いた。
島村はこんど帰ったらこの温泉には来れないだろうという気がした。
縮の産地へ行ってみようと思った。この温泉地から離れるはずみをつけるつもりだった。島村は寂しそうな駅に下りた、そして家々の庇を長く張り出して積雪でも通行できるようにこしらえた雁木を見た。
大屋根から道の堤へ投げられた雪をくりぬきトンネルにして、そこをくぐって向こう側に行くことを “胎内くぐり” とこの地方では呼ぶらしい。島村も試してみたりした。そうして、ぶらぶらと温泉場に戻った。
小料理屋の菊村で駒子が見えた。駒子は車の扉の外の足場に身をかがめて、扉の取っ手につかまって、どうして連れて行かなかったのと言った。
その時、突然、擦半鐘が鳴り出した。火の手が下の村の真中にあがっていた。黒い煙の巻きのぼるなかに炎の舌が見えかくれした。火は横に這って軒を舐め廻っていた。場所は繭倉で、今晩は映画館になっていてフィルムから火がでていた。島村も駒子も走り出す。
「天の河。きれいねえ」駒子はそうつぶやくと、その空を見上げたまま、また走り出した。
島村も振り仰いだとたんに、天の河のなかへ体がふうっと浮き上がってゆくようだった。
裸の天の河は、夜の大地を素肌で巻こうとすぐそこに降りてきている。恐ろしい艶めかしさだ。
「ねぇ、あんた、私をいい女だって言ったわね。行っちゃう人が、なぜそんなこと言って、教えとくの?」島田は駒子がかんざしを畳に突き刺していたのを思い出した。
天の河は二人が走ってきた後ろから前へ流れおりて駒子の顔は天の河の中で照らされるように見えた。見上げていると天の河はこの大地を抱こうとして下りてくる。
「あんたが行ったら、私は真面目に暮らすの」駒子の姿は街道の人家でかくれた。
火の子は天の河のなかにひろがり散って、島村は天の河へ掬い上げられてゆくようだった。煙が天の河を流れるのと逆に、天の河がさあっと流れ下りてきた。島村は別離が迫っているように感じた。
あっと人垣が息をのんで女の体が落ちるのを見た。人形じみた不思議な落ち方だった。
女の体は空中で水平だった。非現実的な世界の幻影のようだった。生も死も休止したような姿だった。駒子が鋭く叫んで両の眼をおさえた。島村は瞬きもせず見ていた。
落ちたのは葉子だった。葉子は仰向けに落ちた。島村は死は感じなかったが葉子の内生命が変形する、その移り目のようなものを感じた。
幾年か前、島村が駒子に会いに来る汽車のなかで、葉子の顔のただなかに野山のともし火がともった時のさまをはっと思いだした。一瞬に駒子との年月が照らし出されたようだった。せつない苦痛と悲哀もここにあった。
駒子は自分の犠牲か刑罰かを抱いているように見えた。「どいて、どいて頂戴。この子、気がちがうわ。気がちがうわ」
さあと音を立てて天の河が島村のなかへ流れ落ちるようであった。