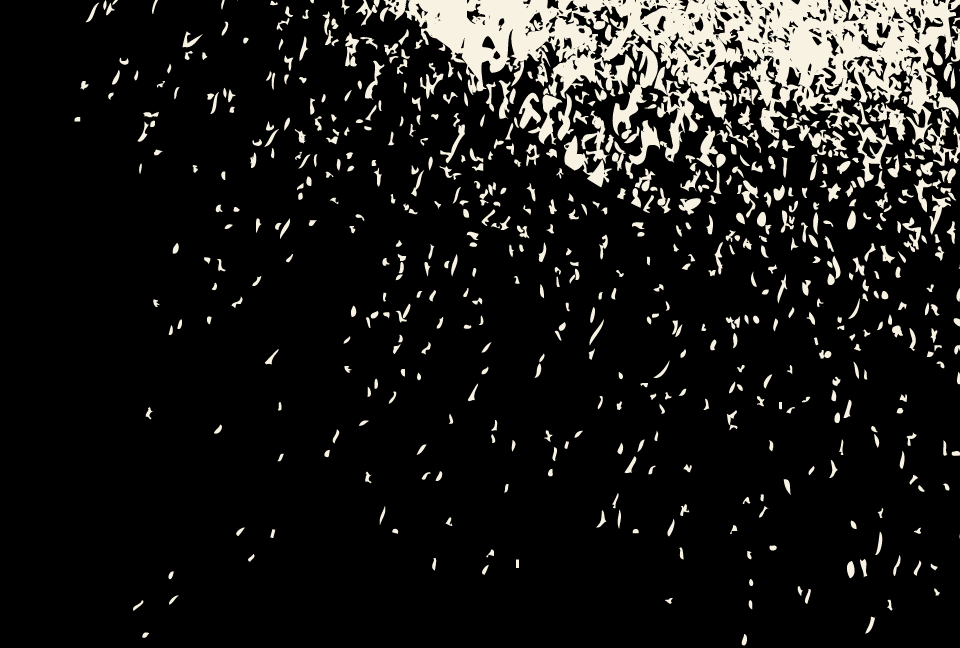天皇に殉じた青年の魂の復権を目指し、天皇批判の問題作として物議をまきおこす。三島自身が11歳のときに起こった2・26事件。そして神風を起こさんと命を捧げた特別攻撃隊。精神のなかの何かが、時空を超えて現れる。青年将校や特攻隊員の激烈な歎きを、その純潔の死を、神語りを通じて蘇らせる。
登場人物
私
木村先生の主催する「帰神の会」に参会し、神霊の聲を聞き感銘を受け忠実に記録し伝える。
木村先生
審神者として幽斎の本義に則り、石笛で厳かで重々しく静かな「帰神の会」の神事を催す。
川崎重男
神主を勤める二十三歳の青年、十八歳の時に両眼を失明し、以来、霊眼が開かれ神語りとなる。
あらすじ
三月初旬、浅春の夜「帰神の会」が催される。
私は木村先生の主催する「帰神の会」に参席し、終生忘れられない感銘を受け、筆にすることは憚られるが、忠実にその記録を伝えることが自分の務めである、として物語は始まる。
「帰神の法」は、通常の神殿宮社で祝詞供銭の神祇をおこなう「顕斎の法」ではなく、霊を以って霊に対する法で、またの名を「幽斎の法」と呼ばれている。
顕の帰神とは、神がかりのことで本人はもとよりまわりの者にも明瞭に見てとれる。
神意を伝える審神者がいて、霊媒たる神主がいて、正式には神霊の来格を乞うための琴師がいる。木村先生の厳父天快翁は、琴師を廃されて石笛を自ら吹き鳴らされる法を興された。
神主は、川崎重男君が勤め、二十三歳の盲目の青年である。
「帰神の会」は仰々しいおどろおどろしいものではなく、神霊が新しい霊であれば古事記や日本書紀のような古語で神語られるのではなく、現代の言葉で語られる。
その夜は、浅春三月初旬に似合わぬ暖かい南風が雨を含んで吹きめぐり、雨戸も鳴り窓を叩き、やがて嵐になっていく。
木村先生の石笛の最初の一声が吹き鳴らされ、私は自分の魂が呼び起こされるように感じる。
われらは裏切られた者たちの霊だ、蹶起将校が現れ歌いはじめる。
神が憑られた川崎君の上体はかすかに左右に揺れ、突然、諸手で手拍子を打って、歌いはじめた。
かくまくもあやにかしこき / すめらみことに伏して奏さく / 今、四海必ずしも波穏やかならねど / 日の本のやまとの国は・・・ /
その歌声は、一人の声ではなく、大勢の唱和する声が遠くから聞こえるようである。
それは「荘厳な神の声というよりは、青年たちの群衆が、怒りと嘲笑を含んで声を合わせて歌っている」ようにしか聞こえなかった。
そして声は続く。
今、四海必ずしも波穏やかならねど / 日の本のやまとの国は / 鼓腹撃壌の世をば現じ / 御仁徳の下、平和は世にみちみち / 人ら奉平のゆるき微笑みに顔見交わし
しかし次第に、あやしくなっていく。
利害は錯綜し、敵味方も相結び、/ 外国の金銭は人らを走らせ / もはや戦いを欲せざる者は卑劣をも愛し、/ 邪まなる戦のみ陰にはびこり / 夫婦朋友も信ずる能わず / いつわりの人間主義をたつきの種とし / 偽善の団欒は世をおおい力は貶せられ、肉は蔑され、/ 若人らは咽喉元をしめつけられつつ / 怠惰と麻薬と闘争に / かつまた望みなき小志の道に / 羊のごとく歩みを揃え、/ 快楽もその実を失い、信義もその力を喪い、/ 魂は悉く腐蝕せられ / 年老いたる者は卑しき自己肯定と保全をば、/ 道徳の名の下に天下にひろげ / 真実はおおいかくされ、真情は病み、/ 道ゆく人の足は希望に躍ることかつてなく / なべてに痴呆の笑いは浸潤し / 魂の死は行人の額に透かし見られ、/ よろこびも悲しみも須臾にして去り/清純は商われ、浮蕩は衰え、/ ただ金よ金よと思いめぐらせば / 人の値打は金より卑しくなりゆき、/ 世に背く者は背く者の流派に、/ 生かしこげの安住の宿りを営み、/ 世に時めく者は自己満足の / いぎたなき鼻孔をふくらませ、/ ふたたび衰えたる美は天下を風靡し / 陋劣なる真実のみ真実と呼ばれ、/ 車は繁殖し、愚かしき速度は魂を寸断し、/ 大ビルは建てども大義は崩壊し / その窓々は欲求不満の蛍光灯に輝き渡り、/ 朝な朝な昇る日はスモッグに曇り / 感情は鈍磨し、鋭角は摩滅し、/ 烈しきもの、雄々しき魂は地を払う。/ 血潮はことごとく汚れて平和に澱み / ほとばしる清き血潮は涸れ果てぬ。/ 天翔けるものは翼を折られ / 不朽の栄光をば白蟻どもは嘲笑う。
かかる日に、などてすめろぎは人間となりたまいし
声は弾んで朗々と。いいしれぬ怒りと歎きを含んで歌います。
神々は、月の照る、はるかなる海上に数多く集っておられる。
木村先生が「いかなる神にましますか、答えたまえ」と言われると、これに答える川崎君の声は、ますらおの声で「われらは裏切られた者たちの霊だ」と言った。
「何者が裏切ったのか」と問うと、「それを今言うには憚りがある。」と言い、物語をきけば自ずと明らかになるという。そして志を同じくする者が今宵は海の上に数多く集まっているという。
心は怨みと憤りと、耐えがたく嘆かわしい思いに引き裂かれている。なぜならわれわれは裏切られた霊だからだという。
「海上の神遊びのみこころをおきかせ下さい」と問われると、「神遊び」かと嘲るような響きを込めて、日本をめぐる海は、なお血が経めぐっている。若者の流した血が海の潮の核心をなしている。
徒に流された血が、黒潮を血の色に変え、唸り、喚び、猛き獣のごとく彷徨う。悲しげに吼える姿を見ることが神遊びなのだ。
真姿を顕現しようとした国体は踏みにじられ、国体なき日本は浮標のように心もとなげに浮かんでいるという。
「三十年前に義軍を起こし、叛乱の汚名を蒙って殺された者」
二・二六事件で処刑された青年将校たちの霊だったのである。
恋のはげしさと至純を語り、取り巻く君側の奸に歎く。
われらは恋について語る。
「朕は汝等軍人の大元帥であり、股肱と頼み、汝等は朕を頭首と仰ぎてぞ、その親しみは殊に深かかるべき。」
大演習の黄塵のかなた、天皇旗のひらめく下に、白馬に跨られた大元帥陛下の御姿は、遠く小さく、そのために死すべき現人神のおん形として、心に焼きつけられた。
神は、遠く、小さく、美しく、清らかに光っていた。われらの心は恋に燃え、仰ぎ見ることはおそれ憚りながら、忠良の兵士の若い輝く目は、至高のお姿をえがいていた。大元帥にして慈母、勇武にして慈悲のお方。
無双の勇武と無双の慈悲の化現であらせられるそのおん方。
君臣一体のわが国体は成立し、すめろぎは神にましますのだ。
恋して、恋して、恋して、恋狂いに恋し奉ればよいのだ。至純、熱度にいつわりなければ、必ず陛下は御嘉納あらせられる。かくもおん憐れみ深く、かくも情け深く、かくもたおやかにましますからだ。それこそはすめろぎの神にまします所以だ。
陛下が御年三十五におわしましたとき、奸臣倭臣、保身の者、臆病者、陰謀家、野心家が取り囲み奉っていた。我らの目には醜き怪獣どもに幽閉されたおわします清らかにも囚われの御身に映った。
そこで陛下をお救いだし申しあげたいと切に念じ、そうすることで民は塗炭の苦しみから救われ、兵は後顧の憂いなく、勇んで国の護りに就くことができると考えた。
義兵を挙げるもかなわず、義軍を反乱軍として死なしむる。
そして義兵を挙げた。
瑞穂の国は荒蕪の地と化し、民は飢えに泣き、女児は売られ、大君のしろしめす王土は死に充ちていた。そのとき歴史のもっとも清らかなるものは、遍満する腐敗、老朽と欺瞞を打ちやぶり、純血と熱血のみ、若さのみ、青春のみをとおして、陛下と対晤せんと望んだのだ。
そしてふたつの絵図を見る。
一つの絵図は、君側の奸を斬り、泰然として、陛下の御命令を待つもの。
『御苦労である、心配をかけた。今よりのちは朕親ら政務をとり国の安泰を計るであろう』というもの。そして位や地位を断り、御親政の実りと後顧の憂いを無からしめて下さることで、この上なき褒章とすること。
一つの絵図は、我らの志が大御心にはげしい焔を移しまいらせたのを知る。
『今日よりは朕の親政によって民草を安らかしめ、必ずその方たちの赤心を生かすであろう。心安く死ね』といわれるもの。我らの志を理解下さり、誠忠をうれしく思われる。
そして奸臣の血と至純の血がまじわり、同じ天皇の赤子の血として御馬の前に浄化される。
しかし陛下は、二月二十六日のその日、「今回のことは精神の如何を問わず、甚だ不本意なり、国体の精華を傷つくるものと認む」と仰せられた。
国体を明らかにせんための義軍をば、叛乱軍と呼ばせて死なしむる、その大御心に御慈悲はつゆほどになかりしか。
次に弟神の特別攻撃隊の勇士の英霊が憑る。
神霊の一団が、月光に透かされ佇む。いずれも飛行服を召し、日本刀を携え、胸もとの白いマフラーが血に染まっている。
彼らは「戦の敗れんとするときに、神州最後の神風を起こさんとして、命を君国に献じたものだ。」と答える。
ある日、二〇一空飛行長は、総員集合を命じて、こう言った。
『陛下は神風特別攻撃隊の奮戦を聞こし召されて、次の言葉を賜わった<そのようにまでせねばならなかったのか。しかしよくやった>』
そして飛行長は、「我々はまだ宸襟をなやましており、ますます奮励して、大御心を安んじ奉らねばならぬ」と言った。
われらは神秘を信じず、自ら神風となり、自ら神秘となる。人をしてわれらの中に、何ものかを祈念させ、何ものかを信じさせることだ。その具現がわれわれの死だ。
われら自身が神秘であり、われら自身が生ける神であれば、陛下こそが神であらねばならぬ。神としての陛下が輝いていて下さることで、われわれの不滅の根源があり、死の栄光の根元があり、歴史をつなぐ唯一条の糸がある。
神のみが、このような非合理な死、青春の壮麗な屠殺によって悲劇を成就させてくれる。そうでなければ、われわれの死は愚かな死になる。神の死ではなく、奴隷の死を死ぬことになる。
そしてわれらは進発した。目標は一点のみ。敵空母のリフトだけだ。眦を決して、ただ見ることだ。
人間宣言によって、われらの死の不滅は瀆された。
2・26事件の兄神たちは、その死によって天皇の軍隊の滅亡と軍人精神の死を体現し、神風特攻隊の弟神たちは、日本の滅亡と日本の精神の死を体現した。
栄光の代わりに、われらは一つの終末として記憶された。われらこそ暁、われらこそ曙光、われらこそ端緒であることを切望したのに。
われらはどうして、この若さを以って、この至純を以って、不吉な終末の神になったのか。暁光でありたいと願いながら、夕日の最後の残光になったのか。
昭和二十年の晩秋、幣原首相は、民主主義日本の天皇たるには、神格化を是正せなばならぬと暗示された。さらに総司令部から宮内省に対して『もし天皇が神でない、というような表明を為されたら、天皇のお立場はよくなるのではないか』との示唆があった。
『然れども朕は爾等国民と共に在り、常に利害を同じふし休戚を分かたんと欲す。朕と爾等国民との間の紐帯は、終始相互の信頼と敬愛とに依りて結ばれ、単なる神話と伝統とに依りて生ぜるものに非ず。天皇を以て現御神とし、且日本国民を以て他の民族に優越せる民族にして、延て世界を支配すべき運命を有すとの架空なる観念に基づくものに非ず』
この『人間宣言』には、明らかに天皇御自身の御意志が含まれていた。
忠勇なる将兵が、神の下された開戦の詔勅によって死に、神の下された終戦の詔勅で、一瞬にして静まった半年あとに、陛下は、『実は朕は人間であった』と仰せ出された。
だが、昭和の歴史においてただ二度だけ、陛下は神であらせられるべきだった。人間としての義務において、神であらせられるべきだった。
一度は兄神たちの蹶起の時。一度はわれらの死のあと、国の敗れたあとの時である。
この二度のとき、陛下は人間であらせられることにより、「一度は軍の魂を失わせ玉い、二度目は国の魂を失わせ玉うた。」
そして「われらの死の不滅は瀆された。」という。
などてすめろぎは人間となりたまいし
川崎君の声は慄えて途切れたが、次には肉体があちこち小突きまわされ怖ろしい情景であった。立ちつ居つ叫びながら身を撚る姿を見守った。顔は蒼ざめて死人のようであった。室内の置物は震動し、床の間の掛軸の風鎮は壁にあたって白く弾いた。嵐は絶頂に達した叫喚を挙げ、雨戸も窓も鳴り続けた。
綸言汗のごとしとは、いずこの言葉か。神なれば勅により死に、勅により軍を納める。その力は天皇おん個人のお力にあらず、皇祖皇宗のお力であります。
などてすめろぎは人間となりたまし
幾度もこの句がくりかえされる。川崎君は仰向けに倒れ、動かなくなった。そしてついに、神々の荒魂は上りましたと確信した。
木村先生が川崎君をゆり起こそうとするが、盲目の青年は死んでいた。
その死顔は、川崎君の顔ではない、何者とも知れぬと云おうか、何者かのあいまいな顔に変容しているのを見て、慄然とする。