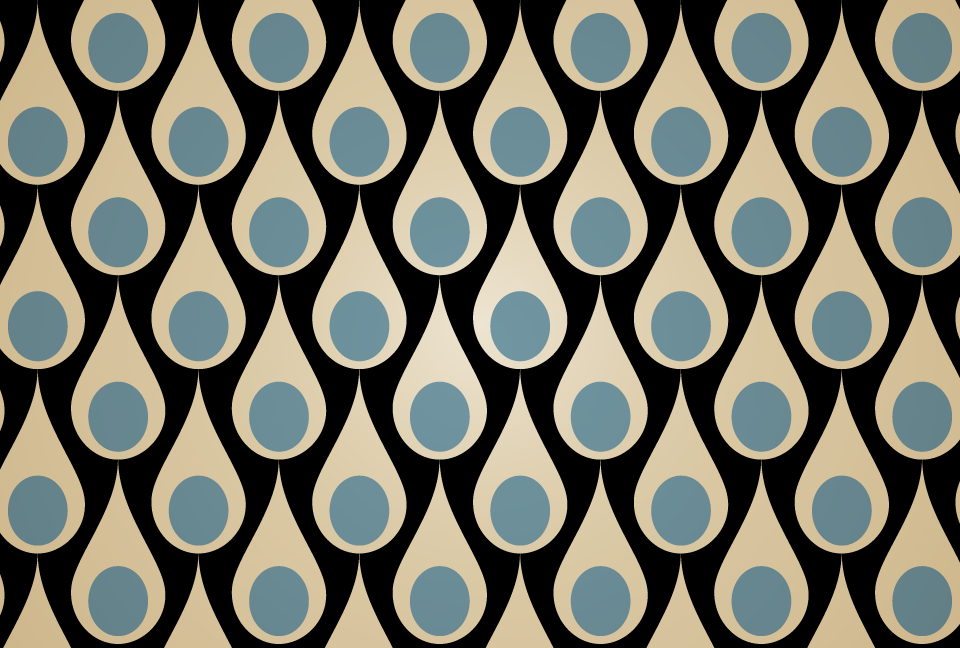そこには肉体の死と美しさというエロティシズムの萌芽があった。昭和の元号と共に生きたひとりの男、平岡公威が青白い病弱な少年時代を経て、二十四歳の本格的なデビュー作で自身を生体解剖してみせた性的倒錯の世界。それは三島由紀夫という仮面の告白の始まりだったのか。そして二十余年後に憂国の烈士としてその益荒男ぶりを戦後の日本に突きつけて自刃した。 その相手は、仮面はおろか素面すらも失くした顔無しの日本だった。
登場人物
私
幼少から人と違う性的な傾向に悩み、大人になり女性に対し不能であることを発見する。
近江
主人公が中学二年生の時に一緒になり、二.三歳上の不良で野蛮な逞しい肉体の男性。
草間
高等学校時代からの信頼のおける友人で、特別幹部生候補として軍隊に入っている。
園子
草間の妹で十八歳の時に会う、私と付き合うが思いが遂げられず他の人と結婚する。
★動画もあります!こちらからどうぞ↓
解説
「私は無益で精巧な一個の逆説だ。この小説はその生理学的証明である」— 三島由紀夫『仮面の告白』ノート
と記し、自身の生体解剖をしようと試みたという。
少年期から青年期にかけての特異な性的目覚めを扱った『仮面の告白』。
その題名の解釈について・・・。告白の意味は分かる。心のなかの秘め事を、勇気をもって打ち明ける感じですよね。しかし「仮面の告白」なので、仮面で顔を覆っている人間のつく嘘である可能性がある。それとも仮面を被ることで、素顔は見せられないが真実を告白しているということなのか。
事実かフィクションか・・・。三島の言葉を確認します。
この作品を書くことは私といふ存在の明らかな死であるにもかかはらず、書きながら私は徐々に自分の生を恢復しつゝあるやうな思ひがしてゐる。これは何ごとなのか? この作品を書く前に私が送つてゐた生活は死骸の生活だつた。この告白を書くことによつて私の死が完成する・その瞬間に生が恢復しだした。少くともこれを書き出してから、私にはメランコリーの発作が絶えてゐる。— 三島由紀夫「作者の言葉」
これは告白という行為、つまり性的倒錯の告白によって私の死が完成する、社会的な死を意味するのだろうか、しかし生が回復しつつあるとされている。これは平岡公威から三島由紀夫になることではないか。
そして、「仮面」の「告白」の意味について
肉にまで喰ひ入つた仮面、肉づきの仮面だけが告白することができる。告白の本質は「告白は不可能だ」といふことだ。— 三島由紀夫「『仮面の告白』ノート」
肉づきの仮面、つまりは仮面を脱ぐのは不可能、だから告白は不可能というのです。
ではどうなんだ?と聞きたくなります。
すると、
「仮面の告白」といふ一見矛盾した題名は、私といふ一人物にとつては仮面は肉つきの面であり、さういふ肉つきの仮面の告白にまして真実な告白はありえないといふ逆説からである。人は決して告白をなしうるものではない。ただ稀に、肉に深く喰ひ入つた仮面だけがそれを成就する。— 三島由紀夫「作者の言葉(「仮面の告白」)
と表しています。この作品は、自伝的だが、フィクションということになる。そして自伝的とは平岡公威の素面の正体、フィクションとは三島由紀夫の作家の表現世界ということだろう。
この最後の部分が気になる・・・。
ただ稀に、肉に深く喰ひ入つた仮面だけがそれを成就する
何が成就するのか・・・。この作品の二十年後を知る読者は、三島は未来まで予知しているのかと考えてしまう。この成就とは、結果、自衛隊駐屯地での自刃まで繋がっていく。
作品の背景に貼りついている戦争と敗戦、そして戦後。その時代を生きた人間にしか理解できない感情。日本人の精神と肉体が揺さぶられるなかで、平岡公威と三島由紀夫は、その真ん中を生きた。
この時代の若者は死を当然と考えていました。大きな実存の問題でもあります。殉死であれ非業の死であれ美に昇華せずにはいられなかったでしょう。そして、散るはずだった命を、叶わなかったひとりの男が、作家として生きる覚悟をした。その自身の生体解剖なのです。
自分が生まれた光景を覚えており、幼くして異形の幻影たちに出逢う。
主人公は、自分が生まれたときの光景を覚えていると言い張っています。
私には一箇所だけありありと自分の目で見たとしか思われないところがあった。産湯を使わされた盥のふちのところである。下したての爽やかな木肌の盥で、内がわから見ていると、ふちのところにほんのりと光がさしていた。そこのところだけ木肌がまばゆく、黄金でできているようにみえた。ゆらゆらとそこまで水の舌先が舐めるかとみえて届かなかった。しかしそのふちの下のところの水は、反射のためか、それともそこへ光がさし入っていたのか、なごやかに照り映えて、ちいさな光る波同士がたえず鉢合わせをしているようにみえた。(第一章)
これは、生を受けた瞬間の光景であり、そして「ぎらぎらと凄まじい反射をあげた」という物語の終りに直結しています。
まさに生まれたときに見たと言い張っている自分の光景が、青年となって現実の異形として証明されたのです。
平岡公威は、大正十四年の一月十四日の夜九時に生まれたとされる。翌年に元号が変わるので、彼の、そして三島由紀夫の満年齢は昭和の年号と同じです。生まれてすぐに、祖母は母の手から私を奪い取った。脳神経痛と老いの匂いにむせかえる祖母の病室で、床を並べて私は育てられた。
私は外で遊ぶことや、男の子の玩具も禁じられ、遊び相手は、女中か看護婦、祖母の選んだ女の子だけだった。
五歳の元旦の朝、赤いコーヒーのようなものを吐き、死をさまよった。以降も自律神経の不安定でよく嘔吐をした。私は病気の足音で死に近いか遠いかが聴き分けられるようになった。
幼少から体が弱く病弱だったことが語られます。さらに「死」を意識しています。
その反動から、屈強な肉体に強い憧れを持ちます。
それからの数々の異形の幻影たちの記憶を思い出す。最初は汲穢屋―糞尿汲取り人―であった。糞尿の入った肥桶を前後にかつぎ、血色のよい美しい頬と輝く目をもつ若者を見て、「私が彼になりたい」、「私が彼でありたい」という欲求が、私をしめつけた。
それは下半身を明瞭に輪郭づける紺の股引、そして鋭い悲哀。虚無と活力の混合を感じる「非劇的なもの」だった。
次は、絵本で見たジャンヌ・ダルク。
身に着けた美しい白銀の鎧、美しい顔に剣を青空に振りかざし「死」へ向かう姿。しかし、「彼」が「女」だと知って落胆する。
そして、練兵から帰る軍隊の兵士たちの汗の匂い。
それは、私を駆り立て、憧れをそそり、支配した。兵士たちの運命、彼らの悲劇性、彼らの死。十一歳の時、二・二六事件は起こります。それは叛乱を雪景色の仮面劇とする描写となっています。
私は「王子」を愛し、「王女」を愛さなかった。殺される王子や殺される若者を凡て愛した。王子たちのタイツをはいた露(あら)わな身なりと、彼らの残酷な死を結びつけることが快かった。 そして私自身も「死」を空想することに喜びをおぼえた。
「セバスチャンの絵」に惹かれ射精し、野蛮で逞しい級友の近江に恋をする。
十三歳の時、グイド・レーニの「聖セバスチャン」の絵に強く惹きつけられた。
美しい青年が裸で木の幹に縛られていた。手を高く交差させ手首を縛めた縄が樹に続いていた。
ただ青春、ただ光、ただ美、ただ逸楽があるだけだった。
この殉教図を見た瞬間、血液は急に激しくなり、最初のejaclatio(射精)を体験する。それが「悪習」の始まりだった。
紀元節の祭日、遊動円木の遊びで、私の右手は落ちまいとして近江の右手にしがみついた。その一瞬、目と目が合った。
私が彼を ―ただ彼をのみ- 愛していることを、近江が読みとったと直感した。近江への片思い、人生で最初の恋だった。
初夏の一日、体育の授業で懸垂をする近江のむき出された腋の下の豊饒な毛が、皆を驚かせ二の腕が固くふくれ上がり肩の肉が盛り上がる。生命力の夥しさが圧倒した。
私はerectio(勃起)し同時に嫉妬した。私の中には、愛する相手に寸分たがわず似たいという熱望があった。
理知に犯されぬ肉体の保有者、与太者、水夫、兵士、漁夫など言葉の通じない蛮地、激烈な夏への憧れが、幼い時から在った。
しかし、鏡のなかの自分は、細い肩、薄い胸のひ弱な裸しか見出せない。
私はこういう「欲望」と私の「人生」との間に重大な関わりがあるとは、夢にも思っていなかった。
こうして私は、自分の性的指向を隠したまま生きていこうとする。
美しい園子への思いは、「罪に先立つ悔恨」として私に意識させた。
昭和十九年、大学に入った。父の強制で専門は法律を選ばされた。しかし遠からず兵隊にとられて戦死すると思うと苦にならなかった。
唯一の友人である草野の家で、下手なピアノの音を聞いた。それは草野の妹で十八歳になる園子だった。夢見がちな自分の美しさを、それと知らない幼さの残った音である。
園子の脚の美しさが私を感動させた。何らの欲求もなく女を愛せるプラトニックの観念を信じていた。
戦争の最後の年が来て、私は二十一歳になった。
私はN飛行機工場へ動員された。近代的な科学技術、経営法、合理的なものが「死」へ捧げられていた。特攻隊用の零式戦闘機の工場はそれ自身が鳴動し、唸り、泣き叫び、怒号している一つの宗教のように思われた。
これは、終戦まじかの零戦の隊員たちの「死」に向かう描写である。
私はその後、招集令状をうけるが、軍医の肺浸潤との誤診で入隊は免れ即日帰郷となった。
再び園子に会う、私は心を動かされるほどの美しさを覚えた。胸が高鳴り清らかな気持ちになった。
園子は「肉の属性」ではなく、悲しみと「罪に先立つ悔恨」だと私に意識された。やがてお互いに好意を持つようになる。
ここでの意識は、プラトニックな恋愛を至高のものとしながらも、自身の同性への性的意識と、異性との肉体の関係への不安を何とか乗り越えようとします。
私は是が非でも彼女を愛さなければならぬと感じた。それが私の、例の奥底の疾(やま)しさよりもさらに奥底によこたわる当為となった。(第3章)
つまり男として異性と普通の人生を生きること、生きなければならないと考えるわけです。それは、人間の当然のことと捉えています。
私は自分が園子を愛しており、園子と一緒に生きない世界は何の価値もないとの観念に圧倒された。
初めての接吻に何の快感もなく、私は逃げねばならないと思った。
学徒動員で海軍工廠にいる私と、疎開した園子との文通は、特別なものになっていた。不在が私を勇気づけ、距離が私に「正常さ」の資格を与えた。
戦争の激化のおかげで錯覚をしていただけなのだが、その時は、園子との結婚や子どもを持つことも極めて重大な幸せかもしれないと考えるようになった。
園子の住む疎開先の軽井沢に招かれた。林を自転車で走り、木立の蔭に来た。
私は彼女の唇を唇で覆った、一秒経った。何の快感もない。二秒経った。同じである。三秒経った。-私には凡てがわかった。(第3章)
逃げなければならぬ。私は、あせり、身が震えた。
このとき私は異性を感じることができないという自身の異常性を知ることになる。
私は本気になって自殺を考えたが、滑稽なことだと思い返した。
私は彼女を愛していればこそ、彼女にふさわしくない私は、彼女から逃げなければならなかった。
その後、正式な結婚の申し込みが来て、私は婉曲な拒絶の手紙を書いた。私はただ生まれ変わりたかった。終戦となった。私の妹は死んで、園子は結婚した。彼女が私を捨てたのではなく、私が彼女を捨てた当然の結果だと虚勢を張った。
広島・長崎への原爆投下、そして十五日の終戦の詔書の玉音放送で戦争が終わった。日常が戻ってくるのだ。
私は自分が生きているとも死んでいるとも感じなかった。あの天然自然の自殺 ―戦争による死― の希(のぞみ)がもはや絶たれてしまったことを忘れていた。
二十三歳の誕生日に、私は友人に誘われて娼家にいくが、やはり不能が確定し絶望した。
その苦しみは私にこう告げる
「お前は人間ではないのだ。お前は人交わりのならない身だ。お前は人間ならぬ何か奇妙な悲しい生き物だ」(第四章)
愛と引き裂かれたもう一種の、おそろしい<不在>を感じた。
春が来ても自堕落な放蕩な生活だった。ある梅雨曇りの午后、麻布の町を散歩していると後ろから名前が呼ばれた。
園子である。二年ぶりだったが、私はすべてを予知しているように感じた。園子は、あの時、なぜ結婚を承知されなかったのかを短刀直入に私に問いただした。私は人妻となっていた園子に、また二人で逢いたいと思った。
私は園子に逢いたいという心持ちは神にかけて本当である。しかしそこに、肉欲がないことも明らかである。ではなぜ、逢いたい欲求が起こるのか。肉の欲望に全く根ざさぬ恋などはあるのだろうか。
しかしまた「人間の情熱があらゆる背理の上に立つ力を持つとすれば、情熱それ自身の背理の上にだって、立つ力はないとは言い切れまい」と思う。
園子は私の正常さへの愛、霊的な愛、永遠なものへの愛の化身のように思われた。
一年経って官吏登用試験に合格し、私は官庁に奉職していた。この一年、私たちは二.三か月おきに逢っていたが、プラトニックな関係だった。
晩夏の一日、避暑地から帰った園子と役所を辞めた私はいつものように会話を続けていた。園子は今のままだと抜き差しならないことになるので洗礼を考えているという、クリスチャンの家に育った彼女の気持ちは揺れ動いていた。
あと三十分で別れの時間が来る。私たちはダンスホールに行った。そこは常連で混雑しており、たまらず私たちは外気を吸いに中庭に出た。コンクリートの床の照り返しが強烈な熱を投げかけていた。私は、粗野な二十二.三の浅黒い整った顔立ちの若者に視線が吸い寄せられた。
露な胸は引締まった筋肉の隆起を示し、脇腹には縄目のような肉の連鎖が、半裸の肩は輝き、腋窩(えきか)からはみ出た叢は金色に縮れて光った。そして腕にある牡丹の刺青を見たときに、私は情欲に襲われた。
あやしい動悸が私の胸の底を走り彼の姿から目を離すことができなかった。
私は彼が与太者と戦い、鋭利な匕首で胴体を突き刺され、血潮で彩られ屍が運ばれるのを想像した。
そのとき「あと五分だわ」園子の高い哀切な声の方へ振り向くと、瞬間、私の中で何かが残酷な力でふたつに引き裂かれた。
私という存在が何か一種おそろしい「不在」に入れ替わる刹那を見たような感じがした。
私は園子から性体験の有無をたずねられ、私は「知っている」と嘘をついた。時刻だった。私は立ち上がるとき、もう一度、若者のいる方を盗み見た。
空っぽの椅子と、卓の上にこぼれている何かの飲物が、
ぎらぎらと凄まじい反射をあげた。