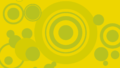父親の転任で離ればなれになる二人は記念写真を撮りに行く。恥ずかしがり屋の少年と素直で活発な少女。霧のような春雨のなか、行きは、恥じらう二人の距離が、帰りは、ひとつになる。少年の優しさを少女が受け入れる、それは雨傘が結んだ淡い初恋の思い出。
せつない思いが、強い絆にかわる
あらすじ
霧のような春雨の日、別れの記念写真を撮りに少年は少女を迎えに。
濡れはしないが肌がしめる、そんな霧のような春雨の日、少年は少女を迎えに行く。
少女が座っている店先を通る、恥ずかしさを隠すため少年は雨傘を開く。少女は片方の肩を傘に入れるが、少年は濡れたままで、少女に身を寄せることができない。少女は片方の手で、少年の握る傘の柄を持ち添えてあげたいと思いながらも、恥じらいでできない。
二人は写真屋へ行った。少年の父親が、遠いところへ転任をすることになった。
少年と少女は離ればなれになってしまうので、お別れをする前に、記念に写真を撮る約束をして二人で写真屋に出かけたのだ。
写真屋は、二人で並ぶよう長椅子を指したが、少年は少女と並び、身を寄せて写ることが恥ずかしい。
少年は少女の後ろに立ち、二人の体がどこかで結ばれていたいために、椅子を握った指を少女の羽織に触れさせた。それが、少女の体に触れた初めてだった。
強い絆を感じながら一生、この写真を手放すことは無いだろうと思う。
少年は少女を裸で抱きしめたような温かさを感じた。一生、この写真を見るたびに彼女の体温を思い出すだろうと思った。
「もう一枚いかがでしょう」と写真屋が言い、「髪は?」と少年は少女に言った。
少女は少年を見上げ、頬を染めると明るい喜びに眼を輝かせて、子供のように素直にぱたぱたと化粧室にいった。少女は店先で少年を見て、髪を直す暇もなく飛び出してきたのだった。
化粧室へ行く少女の明るさは少年をも明るくした。二人はあたりまえのように身を寄せ長椅子に座った。
写真屋を出ようとして少年が雨傘を探すと、先に出た少女が傘を持って表に立っていた。そのとき少女は、少年の傘を持って出たことに気がついた。
そして少女は驚いた、なにごころなく彼女が彼のものだということを感じていることを現したではないか。少年は傘を持とうと言えなかった。少女は傘を少年に手渡すことが出来なかった。
けれど写真屋に来る道とは違って、二人は急に大人になり、夫婦のような気持で帰って行くのだった。
傘についてのこれだけのことで。
★動画もあります、こちらからどうぞ↓
解説
別れの切ない気持ちを、二人を繋ぐ雨傘が強い絆に変えてくれる。
少女は少年に会えた嬉しさに、髪も整えず店を駆け出し、雨が降っているのを知ります。少年は、少女を店先で迎える恥ずかしさで、雨傘を開きます。
少年は少女に優しく傘をさしかけますが、少女の体が触れるのが恥ずかしく、自分は濡れながら傘の柄を握っています。
少女は傘の柄に手を添えてあげたいと思いながらも、恥ずかしくて傘の中から逃げ出したい気持です。二人は、まだ初々しい関係です。
記念の撮影では、少年は少女の後ろに立って二人の体がどこかで結ばれていると思いたく、指を軽く羽織に触れます。指に伝わる体温に、少女を裸で抱きしめたような温かさを感じます。
少年は少女に、髪を直すことさりげなく言い、少女は少年に、気遣いの優しさを感じ、二人はお互いが、身近に感じられ親近感で距離が無くなります。
写真屋を出るときには、自分の傘を少女が持っていることに少年は驚きます。
それは、少年のする行為を少女が代替する。少女は少年と一体であるという関係であり、彼女は彼のものだということを現していることに驚きます。
二人は急に大人になったように、強い絆で結ばれる夫婦のような気持になります。
夫婦を誓う婚約写真、傘を手向ける少年と傘を持ち先に出て待つ少女。
実生活では、川端は本郷で働くカフェの女給、伊藤初代に恋をします。彼女はまだ十三歳でした。
川端は結婚を決意します。川端が二十ニ歳、伊藤初代が十五歳の時に岐阜市の写真館にて婚約写真を撮影します。その後、料理屋を出る際に、下足番から川端の雨傘を受け取る初代に、川端は<温かく寄り添はれた喜び>を感じます。
川端は、その後十六歳になった少女と一緒になれるという奇跡のように美しい夢を持ち、若い恋愛の気持ちでいっぱいです。家族の暖かさを知らずに育った孤独な川端にとって、夫婦となることはこの上ない幸せです。
川端は初代と出会うことで孤独から解き放たれ、幸せな日々を送ります。その当時の思いを綴った瑞々しい作品が『雨傘』です。
この婚約は、結局は破婚となってしまいます。伊藤初代から送られた手紙には<私には、ある非常があるのです>と綴られていました。
婚約破談その後の紆余曲折、その苦しみから抜け出すために、この恋愛の思いと伊豆を旅した思いを結晶して完成した作品が『伊豆の踊子』となります。
※掌の小説をもっと読む!
『骨拾い』あらすじ|冷徹な眼が、虚無を見る。
『白い花』あらすじ|死を見つめる、桃色の生。
『笑わぬ男』あらすじ|妻の微笑みは、仮面の微笑みか。
『バッタと鈴虫』解説|少年の智慧と、青年の感傷。
『雨傘』解説|傘が結ぶ、初恋の思い出。
『日向』解説|初恋と祖父の思い出。
『化粧』解説|窓から見る、女の魔性。
『有難う』解説|悲しみの往路と、幸せの復路。
作品の背景
掌編小説である。川端は「大半は二十代に書かれている。多くの文学者が若い頃に詩を書くが、私は詩の代わりに掌の小説を書いたのだろう、若い日の詩精神はかなり生きていると思う」と述べています。大正末期に超短編の流行が起こりましたが永続はせず、川端のみが洗練された技法を必要とするこの形式によって、奇術師と呼ばれるほどの才能を花開かせます。
大正十二年から昭和四、五年に至る新感覚派時代で、作品の大半はこの時期に書かれています。内容は、自伝的な作品で老祖父と初恋の少女をテーマにしたもの、伊豆をテーマにしたもの、浅草をテーマにしたもの、新感覚派としての作品、写生風の作品、さらに夢や幻想の中の作品など幅広い。
発表時期
1971年(昭和46年)、『新潮文庫』より刊行される。「掌の小説」(たなごころのしょうせつ)あるいは(てのひらのしょうせつ)とルビがふられる場合もある。川端が20代のころから40年余りに亘って書き続けてきた掌編小説を収録した作品集。
短いもので2ページ程度、長いもので10ページに満たないものが111編収録される。改版され全総数は127編になる。若い頃の川端の瑞々しい感受性に触れることのできる掌編集である。