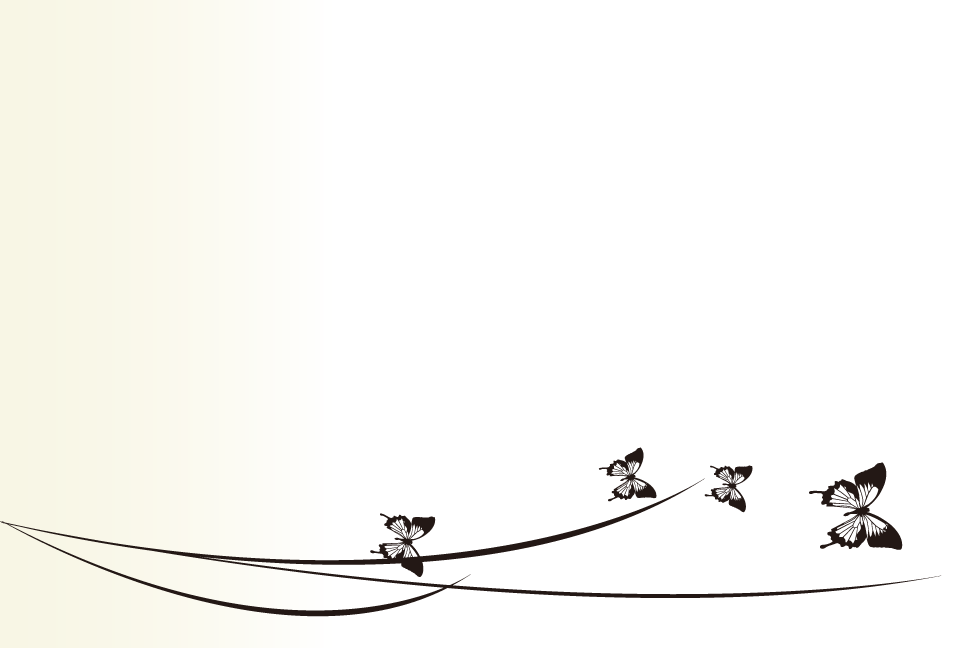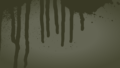高野吾郎の職業は、歌舞伎町にある裏ビデオ屋の雇われ店長。偽装結婚をした中国人女性の突然の訃報に対処するなかで、なぜか湧き上がる憤りとせつなさ。それは、女性がしたためた手紙のせいだった。見知らぬ妻からのラブ・レターに、読者のあなたもきっと涙してしまいます。
★動画もあります、こちらからどうぞ↓
吾郎さん、吾郎さん、吾郎さん。
伝えきれない万感の思いが、「詩」となって胸を裂く。
解説
白蘭が死んだ、それは吾郎が戸籍を貸した出稼ぎの中国人女性。
吾郎はパクられて釈放されたその日、保安係の刑事にかみさんが死んだことを知らされる。独身のつもりの吾郎は、話が呑み込めない様子だが、それは自分が戸籍を貸した出稼ぎの外国人だと気づく。
女の名前は「白蘭」 刑事から病気で死んだ仏さんを引取りにいくようにと告げられる。
女は戸籍上の “妻”。偽装結婚を勧めたのは佐竹という男。新宿を縄張りにする小さな組織の親分で、歌舞伎町で手配師をする佐竹興業の親分だ。
手配師とは人材派遣業のこと。佐竹興業は、外国から日本への出稼ぎ外国人労働者の斡旋をしている。
釈放の挨拶と次の仕事の依頼のため、吾郎は佐竹興業に向かう。こちらにも既に、警察から連絡が入っており、吾郎は佐竹から千葉県の千倉町に行くように言われる。
「一人じゃ心細いだろうから」と佐竹の若い衆で、18歳の若者サトシが一緒について行く。
戸籍の貸し賃は50万円、女の名前は康白蘭。中国語で、“カン・パイ・ラン”。戸籍上の妻の名は、“高野白蘭”。亭主は、新宿でビデオ・ショップを任される “高野吾郎”ということになる。
夫になってくれた吾郎に、死を予感して感謝の手紙を綴る白蘭 。
数日前に、佐竹のところへ吾郎宛てに白蘭から封書が届き、そこには「体調が悪くそう長くないので、死ぬ前に吾郎と中国の家に手紙を書いた」とあり、そこに<結婚への感謝>が綴られていた。
中国から日本に送られ、売春を強いられている白蘭の手紙には、吾郎との結婚のおかげで入管にも心配することなく働ける。ここでは組の人も、お客さんもやさしいし、海も山もきれいだと書いてある。
そして何よりも、自分と結婚してくれた吾郎がいちばんやさしいと綴られていた。
“白蘭は24歳。上海の日本語学校で日本語を学び・・・” 千倉へ向かう車中で、白蘭を外国人労働者として斡旋したサトシから情報を聞くが、吾郎は夫だということがまだぴんと来ない。
何の因果か、初対面が死体。吾郎が初めて会う見知らぬ妻。
吾郎は仏さんを千倉まで引き取りに行く自分の役回りを深く考えもせず、貸した戸籍からの展開に戸惑い煩わしく思う。しかしパスポートの写真を見ると、そこに若く美しい女性の姿があった。
カン・パイ・ランという名前が音楽のように、吾郎に響く。
吾郎は白蘭の写真を見ながら、ほんとうに結婚をしている姿を想像する。
サトシは前借りをさせ日本での稼ぎや手間賃の儲けで成り立つ商売のからくりを吾郎に話し、自由の身にするにはかなりの金がかかることを説明する。
春雨の中、千倉に着く。1年前の夏に、同じように千倉に着いた白蘭の姿を、なぜか吾郎は想像する。そこには、中国から売られ、何も知らずにこの地に辿り着いた、白蘭の人生があった。
吾郎は、白蘭のことを考えると暗鬱な気分になっていきます。
サトシが去年の夏に白蘭たちと泳ぎに行った話を聞いて、吾郎は夏の海辺で波とたわむれ、まぶしく輝く白蘭の姿を想像します。
白蘭は、借金で縛られ医者にもかからずに死んでいった。
千葉の警察署で、吾郎は国民健康保険証を提示し、被保険者の氏名欄に「高野白蘭」と妻の名前があることを改めて気づきます。警察の身元確認は、何の問題もなく簡単に終わります。
あまりのあっけなさを疑問に思う吾郎に、警察は死亡に至る「疑義がない」ことを説明します。
「疑義がない?」・・・吾郎は、自分たちのあこぎな商売が「何で疑いがないんだ」。俺が50万円で戸籍を売り、偽装結婚をして、借金地獄にして売春させ、最後は医者にも見せずに、死んでいった白蘭に対して、そのことに加担している自分もすごく嫌な気分でした。
吾郎は「俺たちのやったことは、管理売春、不法就労、拉致監禁じゃないか」と喚きます。
病院に移動して “死んだ白蘭” と初めて面会した吾郎。美しい白蘭の死に顔を見て慟哭します。見知らぬ外国人女性の死に、吾郎はとめどなく獣のように泣いてしまうのです。
その夜、吾郎は夢をみます。北の故郷 オホーツクの海で漁を営む自分と、白蘭と子どもたちとの幸せな暮らしでした。
親を捨て、故郷を捨て、東京に来た吾郎。吾郎のことをずっと心配しつづけて死んでいった両親。今も漁を続け、弟を優しく迎えてくれる兄。けれど夢の中でも、白蘭は死んでしまうのでした。
幸せな吾郎との暮らしを、いっぱいに感謝しながら・・・。
吾郎さん、心から愛しています。世界中の誰よりも。・・・謝謝
吾郎は、白蘭の骨を抱えて東京に戻ります。
焼き場は、数人の外国人女性が集まっただけの寂しいお別れでした。女たちは店から命じられて来たようです。女たちは気味悪がって骨を拾うとはせず、吾郎は、骨壺を抱えこむようにして薄い骨を残らず拾います。
遺品の中に「高野吾郎さんへ」と、白蘭が最後に綴った手紙がありました。
白蘭は、会ったこともない吾郎のことを、住所、年齢、性格、くせ、好きな食べ物など、佐竹が記したものを毎日読んでいました。写真も毎日、忘れないように見ていました。
白蘭は、借金を返せば吾郎と暮らせると信じていたのです。吾郎は、声を出して泣き、白蘭の口紅で骨壺に「高野白蘭」と書きます。
吾郎は白蘭の遺骨とともに、兄や皆が待ってくれている北海道に帰ることを決意します。
泣きながら笑うと、乾いた骨が膝の上でカタカタと鳴りました。