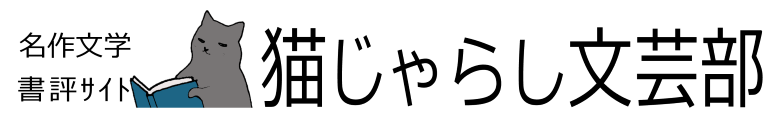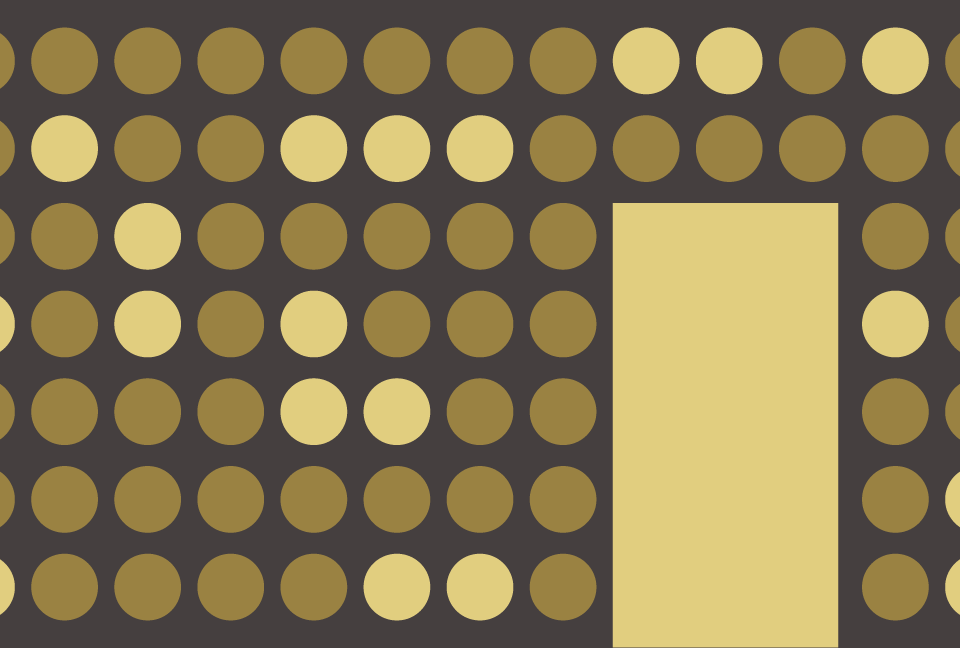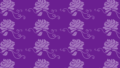最後に感想です
傲慢な都会人への戒め
童話集出版に際して作成された宣伝用のちらしには『糧に乏しい村のこどもらが、都会文明の放恣な階級に対する止むに止まれない反感です』と記されていたとされています。
“放恣”とは、“勝手で、気ままで、だらしがないとか、しまりがないとか”の意味で、まさに都会の文明がそういうものだと賢治は感じているのです。
文明の名のもとに、常識も良識も無くなってしまった都会人、とくに金持ちの人間ほど傲慢で虚栄心のかたまりのようです。 都会は豊かでも、田舎では食べるものにも困っているのに・・・。山に来た紳士二人の行為は、賢治の眼には許されないことのなのです。
ひとりは「何でも構わんから、早くタンタアーンと、やってみたいもんだなあ」と言い、もうひとりは「鹿の黄色い横っ腹に、二、三発お見舞いしたら、ずいぶん痛快だろうね。くるくるまわって、それからどたっと倒れるだろうねぇ」と話します。
自分たちの享楽のためだけ。それは動物たちの命を弄ぶ狩猟であり、動物たちが殺されても何とも思っていないのです。
大正のこの時代は、都会の一部の成金に対して、田舎では、貧しい村の暮らしは一層、厳しくなります。信仰心を持ち、農民と共に生きた賢治はその苦しみや不条理を知っていました。
都会文明に対して、強い反撥があったことでしょう。
賢治の思い
自然の心象をスケッチする賢治にとって、短編「注文の多い料理店」は、人間が化け猫に食べられそうな話になりました。自然の脅威や怒りを童話の世界にして届けます。
子どもたちに、利己ではなく利他を教えるにはどうしたらよいか。相手の立場で考えるためには、このお話では、人間たちが、逆転して動物たちの立場に置かれること。
すごいショック療法ですよね。
だって自分たちが食べられるためのレシピを喜んでいるのですから・・・。
不道徳な狩りの次は、ただ空腹を満たしたい二人。どこまで行っても自己欲求だけ。そこに現れた<山猫軒>。彼らのお好みらしい西洋料理店でしたが、二人は、命を奪われる側の恐怖を味わいます。
イーハトーヴでは、生きものそれぞれが大切な仲間であり、人間もその一部であるという賢治の宗教観であり、自然観であり、宇宙観があります。
仏教の輪廻転生の生まれ変わりを信じていた賢治は、人間の心は過去からの無数の生物の記憶の集積と考えます。農業に従事し、教師として指導し、法華経の信仰を童話によって広げようとした賢治には、全てが幸福でなければ個の幸福などはないと説いています。
自然界の “いのち” は、人間の “いのち” の大切さと同等である。賢治にとっては “ほんとうのたべもの” というのは “きれいにすきとおった風” であり “桃いろのうつくしい朝の日光” なのです。それは物質ではない真理を探す生き方です。
最後にある、
紙くずのようになった二人の顔だけは、もうもとのとおりになおりませんでした。
って、いいですよね。
ここでピタッと物語が恐怖に凍ったように完了します。自然が傲慢な二人を異界に誘惑してこっぴどく懲らしめます。都会人へのお仕置きですよね。
恐怖体験が、いつまでも二人の記憶に残り続けます。烙印みたいですよね。きっと鏡を見るたびに思いだすことでしょう。
ざまぁあみろって感じです! せめて生命だけは助かってよかったと思わないといけないですよね・・・。
傲慢になりそうなときは、謙虚に自分を戒めましょう!
※宮沢賢治のおすすめ!
宮沢賢治『銀河鉄道の夜』あらすじ|ほんとうの幸いのために、生きて死ぬ。
宮沢賢治『注文の多い料理店』あらすじ|動物を食べるなら、人間も食べられる?
宮沢賢治『どんぐりと山猫』あらすじ|「ばか」が、いちばん「えらい」。
作品の背景
宮澤賢治は、1896年(明治29年)、岩手県花巻の裕福な家に生まれています。幼少のころから鉱物、植物、昆虫などに熱中します。この「注文の多い料理店」は、賢治の唯一の童話集です。自然界の “いのち” は、どれもみんな人間の “いのち” の大切さと同等であるという考え方です。
1920年10月、賢治は国柱会に入会、法華文学はその布教の活動のひとつでもあります。国柱会は元日蓮僧侶の田中智学により「我日本の柱とならん」から命名、創設された法華宗系在家仏教団体です。お題目は “南無妙法蓮華経” で、仏教の輪廻転生の生まれ変わりを信じていた賢治は、人間の心は過去からの無数の生物の記憶の集積と考えます。
そこで心に起こる現象を記録すれば、それはあらゆる生物の心の集合体であることの証明で、世界がひとつの心をもつという理想社会に近づけると考えます。それが賢治の童話の根幹にあり“法華文学”でもあります。
有名な「雨ニモマケズ」は、そんな自己犠牲の精神の自身への訓戒でもあります。そして賢治はその自然のテーマを文科ではなく理科の眼で、自然の仕組みの中に、人間も自然科学のなかのひとつとして組み込まれるイーハトヴの世界となっています。
発表時期
1924年(大正14年)12月1日、盛岡市杜陵出版部、東京光原社から童話集『注文の多い料理店』が刊行される。宮沢賢治は当時28歳。初版1000部のうち100部を印税にかえ受け取り、その後、売れ行きが芳しくなくさらに200部を買い取る。初版本の「イーハトヴ童話」の副題がついている。先立って4月には『春と修羅』が刊行されている。前年には、この「イーハトヴ童話」の「序」が書かれている。
尚、「注文の多い料理店」は東京にいた賢治が、妹トシの病気の知らせを受けてトランク一杯の書きためた原稿をもって帰郷したときの25歳の11月に書いている。その生涯を法華経信仰と農民生活に根ざした創作を行う。