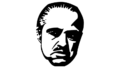●目次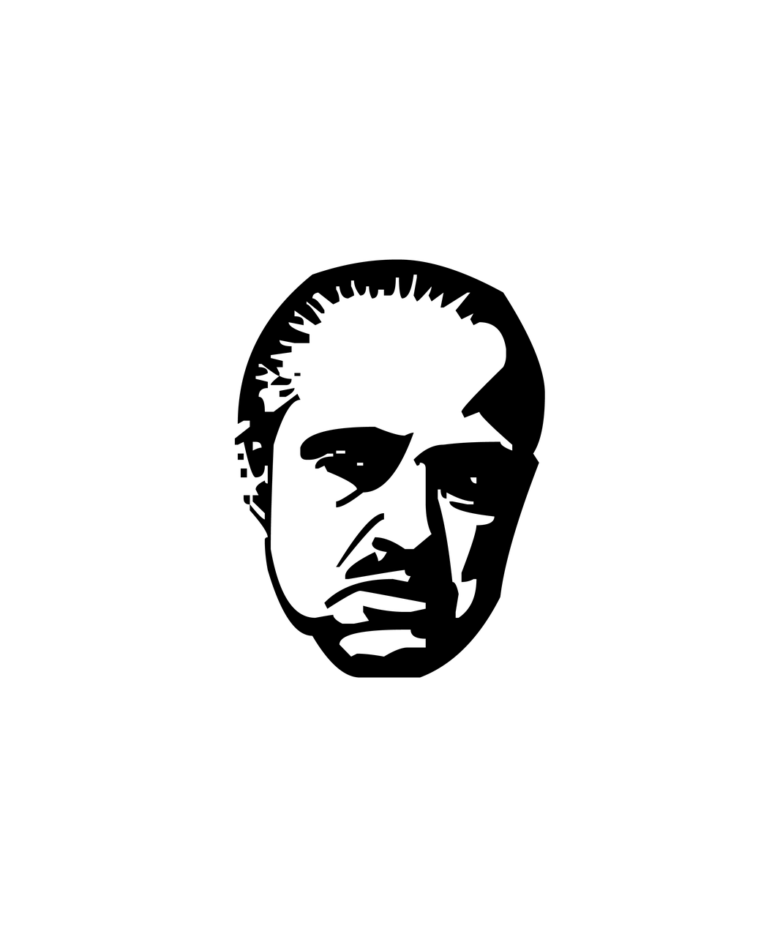
- 『ゴッドファーザー』|あらすじと登場人物
- 『ゴッドファーザー』|家族の名誉をかけた荘厳なオデッセイ|原作の解説その1
- 『ゴッドファーザー』|原作の解説その2
- 『ゴッドファーザー』|原作の解説その3
- 『ゴッドファーザー』|原作の解説その4
- 『ゴッドファーザー』|愛するということ、女たちのサイドストーリー
法律に不満な人々の欲望や復讐心を、友情と忠誠で請け負うヴィトー
法の秩序の下の平等は、民主主義の基盤である。その約束において人々は社会の一員として生活している。しかし賄賂や口利きや忖度が働きすぎると、正しい判断が歪んでしまう。それもまた事実である。民主主義は絶対ではなく、時に脆弱なものだ。
そんな時に人々はいかに処するのか?強い権力者であれば、うまく計らうことはできるだろう。しかし弱き者はどうするのか。泣き寝入りをするのか、それとも法では満たされない欲求を、別の手段に訴えて思いを晴らすのか。
原作の冒頭に登場する主だった三人の相談事とその裁きが、マフィアの存在の原点として紹介される。
葬儀屋を営むアメリゴ・ボナッセラ、ハリウッドの映画俳優で人気歌手でもあるジョニー・フォンテーン、パン屋を営むナゾリーネ。それぞれの話が対照的に描かれる。彼等はすべてイタリア人だ。三人三様の象徴的な相談事だ。
その日は、コニー(コンスタンツィア)・コルネオーネの結婚式。お相手はハンサムな金髪、カルロ・リッツイ。ニューヨーク州南東部に位置するロングアイランドの大邸宅では、盛大な結婚披露のパーティが催されている。
花嫁の父 ヴィトー・コルレオーネは、ニューヨークの五大マフィアのひとつコルネオーネ・ファミリーの領袖、“ゴッドファーザー” だ。
ドンの妻、子どもたち、ファミリーのビジネスに係わる幹部たちやその家族、さらに来客には、ドンの友人や隣人たちが集まり催しを手伝い宴を盛り上げる。動勢を探るFBIが舗道の端に止まって車のナンバーを控える。招かれざる客にいらつく長男のソニーは車の傍に唾を吐きかけた。
故郷イタリア、シシリーの民謡や戯れ歌、陽気な踊りとお酒や食事で二人はお祝いを受ける。コニーへのご祝儀の袋には途方もない現金が集まってくる。
この祝儀袋をポーリー・ガット―が羨ましそうな目で見る場面は暗示的だ。花嫁のコニーの介添え役であるルーシー・マンチニは、ソニーに秋波を送り、二人は二階の部屋で体を激しく合わせる。
シシリーには昔から「娘の結婚式の日には友人の頼みごとを聞き入れなくてはならない」との習慣があり、ヴィトーは三人の相談事を聞き、裁きを下すのである。
社会には個の自由があり、問題が発生した場合は、法の正義で裁かれる。一見、平等なようだが、現実はそう完璧なものではない。
ドン・コルレオーネが支配する世界は、法や警察を頼ってはいない。
共同体として営まれる集団には、掟を前提に、個の自由があり、相互扶助の精神があり、問題が発生した場合は、首領が判断を下すという裏社会の統治の構造を持っている。それが「ドンの裁き」なのだ。
表社会の法と秩序を不服とし、裏社会に持ち込まれる。そして組織の影響下で、例えば政治の力や暴力に訴えて問題を解決させる。小はささいな悩み相談であり、大は復讐の請負業である。
パン屋のナゾリーネの場合は、
政治的な処理であり特別立法の働きかけである。ナゾリーネはヴィトーの子供時代からの親友である。イタリア兵の捕虜としてアメリカに送られ、仮釈放で彼のパン屋で働く正直者のエンツォという若い男と娘のキャサリンが恋仲になる。
娘を寝取られた父親のナゾリーネは立腹するが、娘の方はハンサムなエンツォと添うことを願っている。イタリアへ送還されるであろうエンツォは結婚を申し込む。そのためにはアメリカの市民権を取る必要がある。
ナゾリーネはこれまでもヴィトーのために役立ってきた。ヴィトーとナゾリーネはまさに「友情」を誓う間柄である。この相談を、ヴィトーは子飼いのユダヤ人の政治家を使うことにする。部下に指示を出して市民権の取得の段取りをつくる。後にこの恩をエンツォは重大な局面で、返すことになる。
アメリゴ・ボナッセラの場合は、
法の裁きの不服と復讐の依頼である。ボナッセラの一人娘が男友達に乱暴を受ける。美しい娘の鼻はつぶされ顎は砕かれ、命に別状はないが、哀れな姿となる。加害者の若い男二人は、禁錮三年、執行猶予がつく。若者の一人は政治家の息子で忖度が働いていることも分かった。
善良な市民としてアメリカの法と秩序を信じて、ボナッセラは頑張ってきた。傷つけられた愛娘と法の罰のバランスは等価ではない。ヴィトーに会いに行き「金はいくらかかってもいいので、殺してほしい」と懇願する。しかし一人娘の名付け親はヴィトーの妻であるにもかかわらず、ボナッセラはこれまでヴィトーに友情を示すこともなく関わり合いを避けてきた。
ヴィトーは願いを断る。ボナッセラはこれまでの非を詫びて親愛の情をこめて “ゴッドファーザー” とかしづき「友情」を誓う。するとヴィトーは等価の罰を与えるべく、部下のクレメンツァに指示をだす。そしてコニーの結婚の祝いとして、いつの日か恩を返すことを約束させ、罰する行為を贈り物とした。
ジョニー・フォンテーンの場合は、
暴力による脅しの行使である。映画スターで人気歌手のジョニーは女性遍歴も賑やかだ。最初の妻ジニーと離婚するが、二番目の女房は遊び好きでうまくいかない。次第に人気にも陰りが見え、歌手の命である声帯も弱り自信を失くす。起死回生の自分にぴったりの映画の脚本があるが、映画界の権力者のジャック・ウォルツは、ジョニーを起用しない。
理由は彼が可愛がっていた秘蔵っ子の女優の卵をジョニーが寝取って恥をかかされたからだった。この成り上がりの絶対者のウォルツは大統領ともFBI長官のフーバーとも親交があり、ジョニーはすっかり意気消沈する。
ジョニーの名付け親はヴィトーである。右腕のトム・ハーゲンが事態収拾にあたるが、話は決裂する。するとウォルツが購入した六〇万ドルの愛馬の首を刎ねて、彼のベッドに忍ばせる。そのあまりの残忍さにウォルツはジョニーに主役の座を与える。
この三つの話が細やかな機微で描かれる。映画(PARTⅠ)では、暗がりのなか耳元でボナッセラの望みを聞くヴィトー役のマーロン・ブランドの存在感が暗黒の世界を一瞬で作り上げていた。
ヴィトーは、愛娘の結婚式の参列者全員を富める者も貧しい者も、権力ある者も微力のものも、わけへだてのない笑顔で迎えた。それは裏のもうひとつの共同体なのだ。
裏社会で栄華を誇るコルレオーネ・ファミリーと、違う道を歩むマイケル
若い男とアメリカ女性の二人のカップルがやってきた。男はマイケル・コルレオーネ。ドンが可愛がる三男で、マイケルはファミリーのビジネスを嫌う堅気で、普段は家には寄りつかないが、今日は恋人ケイ・アダムスを同伴し、妹コニーの祝いにかけつけた。
原作ではこの時点ですでに、ヴィトーが三人の息子を跡取りの候補として評価している。
後ろ盾も何もなく、難民船でアメリカに辿り着いたヴィトーが大切にしたものは人間関係。愛娘 コニーの結婚式においても、参列者は昔からの友人が多く、成功者にもかかわらず、多くの人々にホストとして細やかに接して受けた祝いに感謝している。
血と暴力の抗争に入る前の、平穏な風景。既に老境のヴィトーの幸せな生涯と代替わりの人物評が記されている。
長男のソニー(洗礼名はサンティノ)は、父親のような謙虚な心がなく、気が短く物事の判断を時に誤る。仕事上の頼りになる首領代理だが、後継者として疑念を抱く者もいた。
次男のフレッド(洗礼名はフレデリコ)は、忠実で従順で常に父親に仕えたが、上にたつ者に必要な力強さ、人を引きつける魅力に欠け、後継者たる器ではないとされた。
三男のマイケルは、ドンのお気に入りで、その時が来れば当然、家業の跡目を継ぐ者とされていた。内に秘めた闘志と知性が備わっていて人の尊敬を得るように行動をする。
ドンの意中は当初からマイケルだったのです。一家を運営することが如何にたいへんなことかはヴィトーが一番、良く知っている。しかしマイケルだけが父親の命令を拒否した。第二次世界大戦が勃発すると海兵隊に志願し、ドンを怒らせてしまいます。
マイケルの強い意思が際立ちます。ドンに否と言えるのはマイケルしかいませんでした。海兵隊大尉に昇進し数々の武勲も受け勇敢さもあり、国家の英雄でもあります。
なぜドンは怒るのか?それはヴィトーが国家を信じていないからです。一家のためではなく、よそ者のために勇敢であるマイケルが許せないのです。愛国者のマイケルにとってこの意見の食い違いは、絶望的な相違でしょう。しかし運命が変わり、シシリーに潜伏してマフィアの歴史を学んだときに、父を理解し、マイケルの気持ちは変わります。
しかしこの時点では、マイケルは最もファミリーのビジネスから遠い存在です。ヴィトーが跡継ぎに最も期待する三男が、誰よりもファミリーを嫌っています。
マイケルの恋人、ケイ・アダムスは痩せすぎで、肌も白く、知的すぎる顔立ちと描写されます。イタリア系の女性と全く正反対の描写であり、生粋のWASP的なアメリカ娘です。さらに開けっぴろげな態度と記され、自我を強く主張し、自由を大切にする女性像です。
個人主義のアメリカの象徴であり、彼女はマフィアの何たるかを良く知りません。二百年前に移住してきた北部、ニューイングランドの家柄。もちろんマイケルはこの時点では、ファミリーと関わる人生を拒否しています。
寧ろ、マイケルが結婚のため家族との縁を切るという点で、二人は了解しています。
この価値観がドンの襲撃によって変わります。そして二人の結婚こそが、運命に翻弄される最大の要因となります。それは幸せなことなのか、不幸なのことなのか。それとも苦難を乗り超えることこそが人生の意味であり、神の与え給うた試練なのか。 “愛ゆえ” の “憎しみ”に生きながら “名誉” と “絆” を守り続けることが物語の大きなテーマです。
コニーは美しい娘ではなかった。痩せて神経質で、いずれ口やかましい女房になることは明らかだった。ところが今日は、若さと恥じらいをみせる美しい花嫁と描写されます。
花婿のカルロ・リッツィはハンサムな男で、シシリー人の父と北イタリアの母との間に生まれたハーフ。ニューヨークでソニーと出会ったのが縁でコニーと知り会います。彼は権力者の家族の一員になれたのですが、生粋のシシリー人ではなく、ヴィトーはカルロにファミリーの仕事に就かせません。この不満が後の引き金となります。
そしてもう一人、家族同然のように十二歳からコルネオーネ家に住んでいるトム・ハーゲン。彼のみがドイツ系アイルランド人で、両親が死別しソニーが家に連れてきた。癌で亡くなったヴィトーの旧友である顧問役のジェンコ・アッバンダントに代わり、弁護士業を経て新たな顧問役となっています。
映画では養子のように描かれますが、原作は違います。トムは養子ではなく、ただ住みついたと記されています。コンシリエーレとはドンの右腕で補佐的な頭脳です。純粋なシシリー人以外が就くのは始めてでした。