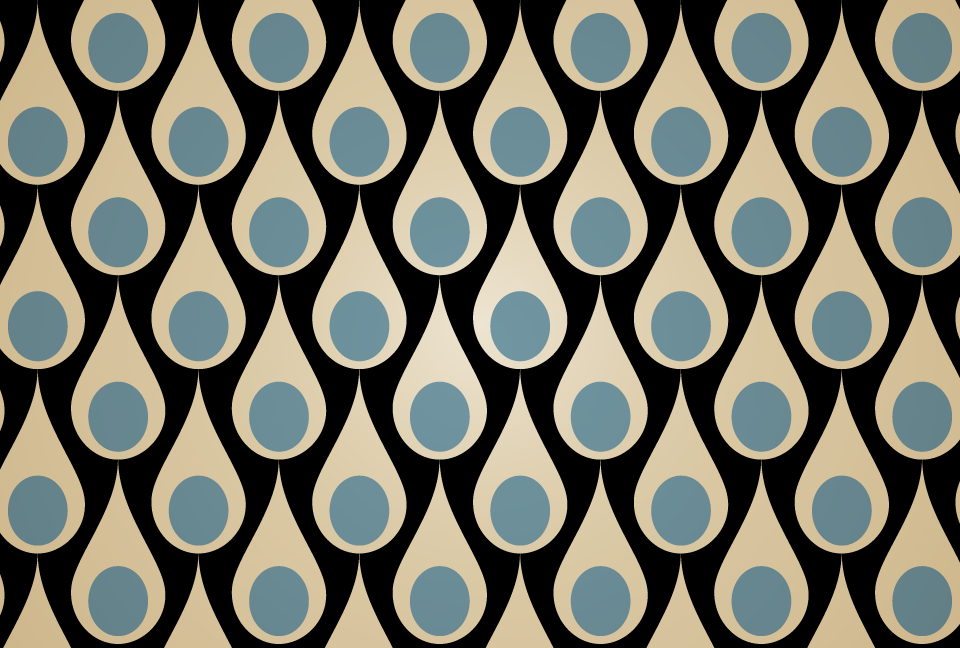メッセージと感想
自分を生体解剖をする、自伝的な私小説『仮面の告白』
三島は昭和二十四年、大蔵省入省後わずか九か月で職を辞し文学に専念します、そこで書き上げたのが『仮面の告白』でした。
作品ははじめての私小説で自伝的だが、<完全な告白のフィクションを創ろうと考えた>としている。
この作品を性的倒錯や同性愛の小説の範囲にとどめるのではなく、もう少し俯瞰的に、三島が戦争の時代に生きた想いを考えてみる。
それは男としての「肉体」「死」「エロティシズム」だろう。
そして人生そのものが計画されていたように、その最後は東京市ヶ谷の自衛隊総監室に入り自決する。享年四十五歳。「仮面の告白」から「金閣寺」「憂国」「英霊の聲」「豊饒の海」を経て自刃へと繋がっていく。
それは天皇や国家に殉じたと言えるかもしれない。そして肉体と血を捧げることが三島の美意識だったのかとさえ思えてしまう。
三島の望んだことは、美しく死ぬことだったのだろう。そして実際に「割腹自決」によって昇華させ帰結させた。
それは<人は決して告白をなしうるものではない。ただ稀に、肉に深く喰ひ入つた仮面だけがそれを成就する>という言葉と共振するようだ。
平岡公威と三島由紀夫、素面と仮面の往還、表現者としての自己演出を考えると、この小説『仮面の告白』にその予言がすでに埋め込まれていたように思えてしまう。
戦争、敗戦、戦後民主主義と昭和の時代を伴走した作家。
三島と川端康成とは師弟の関係であり、三島は川端からその才能を見出された。
三代続く東大卒のエリート官僚であり、裕福な家庭でお手伝いに囲まれて暮らすが、その肉体はひ弱で、性格は神経質。
詩を愛する少年は、大東亜戦争が始まる一九四一年(昭和十六年)、中等科五年、十六歳のときに『花ざかりの森』を発表する。そして一九四五年(昭和二十年)、三島が二十歳の時に終戦を迎える。川端と三島の年齢は二十五ほど離れている。
作品にも触れられるが、三島は肺浸潤を誤診され、即日帰京させられる。その時の部隊の兵士たちはフィリピンで多数が死傷し、ほぼ全滅している。
戦死を覚悟していた三島が医師の問診に同調したことに自問自答を繰り返し、身体の弱さから来る気おくれや、行動から拒まれているという意識が生涯のコンプレックスとなり、以降の肉体の改造と特異な死生観を抱くことに繋がっていく。
終戦後、老いへ向かう川端は「未来ではなく日本のいにしえに自分は還っていく」と言い、まさに “美しい日本の私” の世界に入っていくが、三島は、天皇を中心とした日本文化論を説きながら、政治や国防に対しても発言していく。
三島は、ある意味では、アプリオリに、言葉が肉体より先に生まれているようである。美しく構築された文章、ロマン主義であり古典主義でもある三島は、その明晰さゆえに常に言葉が先行し、その後に、ひ弱な体がついていく。
冒頭の「金色の光」と最後の「ぎらぎらと凄まじい反射」の関係は、物語的には性の倒錯した自己を発見したことになる。
しかし深入りすれば、戦後、僅か四年の歳月しか経っていない頃に、ある種のタブーを二十四歳の若い作家が、同じ世代の死の記憶が覚めないなかで自身を世に晒しているのである。
それはきっと、ひとりの男子の誕生、そしてひ弱な幼年、少年時代を経て青年となり戦場に行けなかった平岡公威の素面の現実を封印し、この作品以降は作家 三島由紀夫という仮面を被り、文学で世に問う覚悟を突き出して見せ、憧れだった屈強で美しい肉体に自身を改造し、同時に、眩いばかりの存在だった
神としての天皇を人間と宣言させた、戦後民主主義との闘いの始まりだったのかもしれない。

※三島由紀夫のおすすめ!
三島由紀夫『仮面の告白』解説|仮面による告白は、真実か虚偽か
三島由紀夫『潮騒』あらすじ|男は気力や、歌島の男はそれでなかいかん。
三島由紀夫『金閣寺』解説|世界を変えるのは、認識か行為か。
三島由紀夫『憂国』解説|大儀に殉ずる、美とエロティシズムと死。
三島由紀夫『美しい星』あらすじ|核戦争の不安のなか、人間の気まぐれを信じる。
三島由紀夫『英霊の聲』あらすじ|などてすめろぎは人間となりたまいし。
作品の背景
三島は昭和24年、大蔵省入省後わずか9か月で職を辞し文学に専念する、そこで書き上げたのが「仮面の告白」であった。「私は無益で精巧な一個の逆説だ。この小説はその生理学的証明である」として、少年期から青年期の特異な性的な目覚めを扱う。
仮面の告白のもう一つの側面として、戦中・戦後の時代をうかがい知ることができる。特に6歳から21歳、つまりは1931年から以降。練兵からかえる軍隊、36年の2・26事件、叛乱を雪景色の仮面劇とする描写、41年の大東亜戦争の開戦から終戦まじかの零式艦上戦闘機工場の「死」に向かう描写、45年8月に園子に手紙を書いたころの広島への原爆投下、そして15日の終戦の詔書が朗読、放送された時と一にしている。
特に肺浸潤を誤診され、三島は即日帰京させられるがその時の部隊の兵士たちはフィリピンで多数が死傷しほぼ全滅している。戦死を覚悟していた三島が医師の問診に同調したことに自問自答を繰り返し、身体の虚弱から来る気弱さや、行動から拒まれているという意識が生涯のコンプレックスとなり、以降の肉体の改造と特異な死生観を抱かせることになった。
発表時期
1949年(昭和24年)7月、書き下ろしとして『河出書房』より刊行。三島由紀夫は当時24歳。三島の年齢は昭和の年数と同じである。昭和の時代の胎動、興廃、戦後民主主義と重なり、時代を生きた人物として、文学のみならず思想、行動は大きく注目された。特に晩年、政治的な傾向を強め自衛隊に体験入隊し、民兵組織「楯の会」を結成。1970年11月25日の自衛隊総監室のバルコニーからの決起を促す演説と割腹自殺を決行した出来事は、社会に大きな衝撃として今現在もその思想や行動の真意について語り継がれ、作品について多くの研究がなされている。