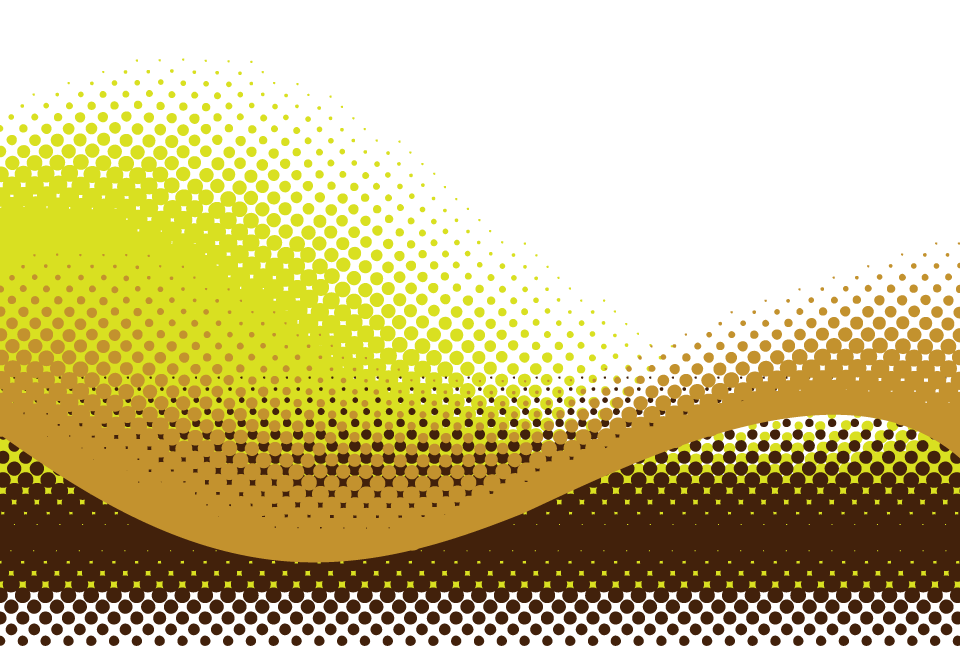本作品のメッセージと感想
飛び立ちたい自由と、巣ごもりする自由。
主人公の男は自分探しをするなかで砂の穴に堕ち、砂の女と出会う。そこでの暮らしは、日々砂を掻かなければ生存を危ぶまれる過酷で原始的な営みであり、生き抜こうとする女の姿があった。
当時の日本を考えてみます。因みに主人公、仁木順平と安倍公房は同じ歳です。
『砂の女』は1962年の作品。日本は戦後復興を経て、高度経済成長期を迎えます。国民所得倍増計画をスローガンに、東京都の人口は世界初の1000万人を突破。戦争の荒廃の記憶もまだ脳裏に色濃く焼き付いていたはずです。
人々を呑み込み変貌していく都市、次々と高さを競うビルディング、首都高速環状線が完成しモータリゼーションが始まる。眩暈とともに豊かさを追求する人々。
巨大なシステムに組み込まれ、激しい競争にさらされる。人間存在は砂粒のように小さく、人々は孤独のなかで自己の存在の意味を探す。
そして鳥のようにどこかへ飛び立ちたい自由を目指し逃避願望を起こす。此処ではない、何処かに、本当の自分があると思いたいのだ。
一方、この砂の底に沈む家は、一時も砂掻きを休むことなく、砂に塗れながら生きていくことを余儀なくされている。近代とは正反対の原始な自然だ。そこに棲む寡婦、砂の女は、黙々と砂を掻き上げる。
砂を掻きつづける不自由の中で、自己を主張せず、他者の悪口を言わず、集落を愛郷精神と捉え、運命を受け入れ、感謝すらしている。
そして男が加わることで労働力を得て、男女の営みを喜び、ビーズの内職で、鏡とラジオを買うというささやかな夢を実現し、巣ごもりの自由を大切にする。
人間と自然の闘いの中で、家族と地縁だけを信じている。
女は廃墟のなかを子供を抱え、さんざん歩かされた過去を語る、そこには、砂の女が守っていきたいもうひとつの生き方がある。
自らをよりどころとする、それが自由の意味。
男は、教師という職業、同僚たち、結婚した妻・・・と常に他者の眼を意識し、社会に縛られる窮屈さのなかで不自由を感じている。
そして砂の流動性の自由を満喫するために、休暇を取り砂丘にやってきた。
ここで日常からの強い逃避願望から、男は白昼夢を見たと仮定しよう。
ハンミョウ採集の幸せな気分から、一転、罠にはまって砂穴の蟻地獄に落とされてしまう。来る日も来る日も休みなく続く、「賽の河原に石を積む」ような砂掻き作業。決して脱出を許さない村の監視機能。これは主人公の日常そのものだ。
そして砂の女の自我を表さず、自分に隷属するような態度に、戸惑いを覚える。やがてそれは、男の妻とは違い、無垢で無知でありながら本能的な母性を感じさせる。
極めつけは砂の実相を知っての驚きだ。砂は流動する自由の象徴だが、同時に、光や風や湿度で自らその形を変え人間の手には負えない存在であることを知る。
体中に砂をかぶり生活する異常さや、口の中をはじめ目や鼻などの粘膜に砂が混じる不快さ、砂に不気味さやおぞましさを感じ、人間の無力を知る。
自由を取り戻そうともがき、必死の脱走劇を繰り返し、そして無様に敗北する。
脱出不能の絶望と喉の渇きという死の恐怖のなかで、ついに気がおかしくなりそうになるが、偶然にも溜水装置という希望と出会う。
この発見による自己実現と承認欲求から、女にも村にも、愛着が湧いてくる。
仏教では、自由とは他に由らず、独立して、自存すること。つまり自らを由りどころとすることらしい。
まさに人間存在とは何か、自由とは何か、幸せとは何かを考えさせられる。
人間の等身大を越えて永遠と続く近代化、飽くなき欲望の中で消費され続けるモノや情報の洪水の中で生きる現代人。
自由の先に不自由に囚われ、不自由の先に自由に放たれる。そんなメビウスの輪のような脱出不能な現代社会から、原始の自然のなかで再確認できるもの。そこにきっと人間の普遍的な姿を見出すのだろう。
この小説『砂の女』は現代人に救いの手を差し伸べ、脱出の回路を示してくれる。
「孤独とは、幻を求めて満たされない、渇きのこと」(28章)
であり、塩あんこと喉の渇きという極限の生存欲求のなかで、毛管現象を発見した喜びを、以下のようにあらわす。
「やっと溺死をまのがれた遭難者でもないかぎり、息ができるというだけで笑いたくなる心理など、とうてい理解できるはずがない」(31章)
そして男は、結局、どうなったのか?
村の一員となった男は溜水装置の開発で、村の人々から尊敬の念を得たのだろう。それは村への貢献であり、男の望んだ自己実現であり承認欲求がかなったのである。
これこそ生きることの喜びであり、生きがいとなる。男には逃避願望などない。
そこには「砂の女」がいて、新しく宿した命の成長を楽しみながら生きているのだろう。
それはまるでイソップ寓話のように、現代の貪欲な資本主義と溢れる情報化社会を生きる人々に「砂」をメタファーに、人間存在の普遍性を捉え、いっさいを無常と捉える前衛的な内容となっている。
作品の背景
「砂の女」の執筆のきっかけは、講演旅行中の車中で読んでいた週刊誌に、飛砂の被害に苦しめられている山形県酒田市に近い海辺の部落の写真を見たのがきっかけという。また生涯を砂の研究にかけたヨーロッパ人から教えられた日ごとに形を変える砂の独特の変化に興味を持つ。
砂の中の生活という不思議な世界を写実的に描写しながら、砂に生死を左右される村落に住む共同体、そこで生きる砂の女、そして迷い込んだ男を通して、自然や社会の構造、人間の自由とは何かの本質を問う。砂の神秘を描き、不条理とサスペンスのなかに人間存在の原始的な象徴的姿を追求する。
発表時期
1962年(昭和37年)、6月8日に『新潮社』より刊行。長編書き下ろし小説で、安部公房は当時27歳。三島由紀夫らとともに第二次の戦後作家とされる。現代文学の最良の収穫という高い評価をされている作品。海外でも高く評価され、翻訳版は、チェコ語・フィンランド語・デンマーク語・ロシア語等の二十言語で翻訳され、世界30か国で翻訳出版されている。
安部公房の名前を世界に知らしめた作品といえる。「砂の女」は二十世紀文学の古典に目されるようになった。晩年はノーベル文学賞の有力候補と目され、リルケやハイデッカーに傾倒する。