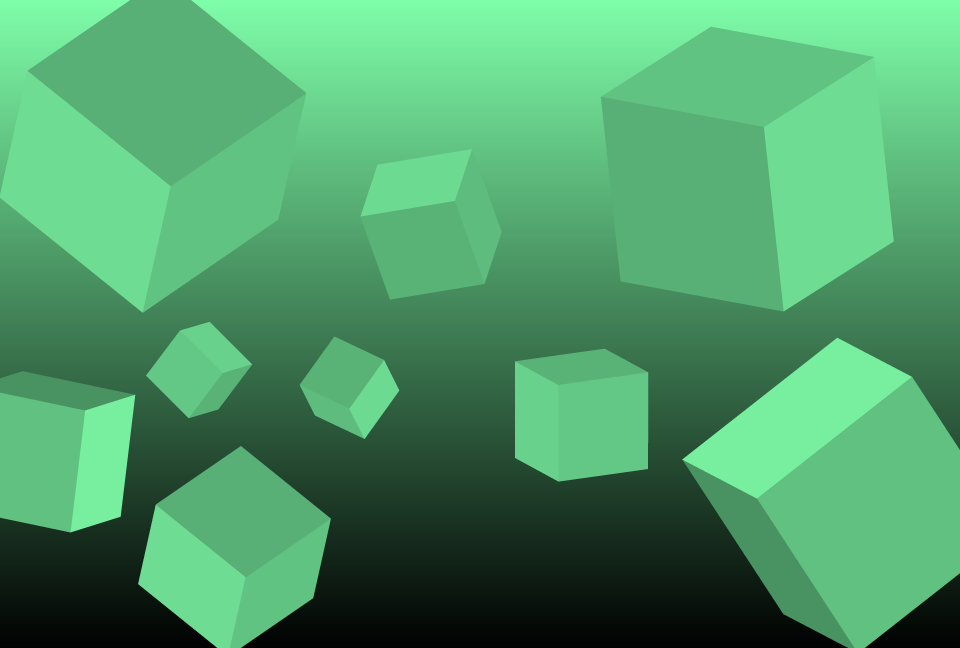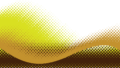贋医者/Cは安楽死を装って、軍医殿を殺す。
《死刑執行人に罪はない》(169P-183P)
遺体安置室で寝たふりをするぼく(軍医殿)のところに、君(贋医者)が箱(ぼくの棺桶)を持ってやってくる。君(贋医者)は、ぼく(軍医殿)の肩を小突いてみる。ぼくは寝たふりをつづける。
ぼくの左上膊にゴムを巻き静脈をさぐり出す。注射器のポンプは二十の目盛りいっぱいに引かれていて、中に入った塩酸モルヒネ三ccを送り込む。口に死相が現れる。さらにポンプを押しつづける。送り込まれるのは空気だけだ。
そしてぼくは死んでしまう。
溺死に見せるため大型の漏斗を口にくわえさせ、タンクの中の海水を注ぎ込む。ぼくの死体に箱をかぶせ、固定用の紐で腰に括りつける。そして死体の捨て場は、例の醤油工場裏。水面まで崖が切り立っていて、確実に流れに乗ってくれる。
【補足】遺体安置室にいる軍医殿が、贋医者/Cから殺されようとする描写を、<ぼく(軍医殿)>自らがノートに綴っている体裁になっています。
《ここに再び、そして最後の挿入文》(184P-192P)
昭和三十八年二月に名古屋高裁で出された安楽死の判例について、
一 病人が不治の病に冒され、死が目前に迫っていること。
二 苦痛が誰の目にもしのびないものであること。
三 病人の苦しみの排除が目的であること。
四 病人の意識が明白であり、本人の嘱託または承諾のなること。
五 医師の手によること。もしくは、うなずける充分な理由があること。
六 死なせる方法が倫理的に妥当であること。
ぼくが言いたかったことは、法律の届かない場所に住む人間が相手なら、すべての殺人が安楽死なのだ。戦場での殺人や、死刑執行人の処刑が罪に問われないように、箱男殺しも罪になり得ない。判例の病人という字句を箱男と置き換えて読みなおして貰いたい。
ぼく(元カメラマン)は、贋医者/Cと看護婦に会いに行く。
《書いているぼくと、書かれているぼくとの不機嫌な関係をめぐって》(92P-148P)
四つん這いになった裸の彼女の姿が瞼に焼きつけられ、吐き気がする異常な緊張。
三時一八分。ぼくは湾を隔ててT港と向かい合う市営の海水浴場に辿り着く。一週間前、傷の手当を受けに病院に行く前の身支度を整えたのも、ここだった。箱男が箱から抜け出すのにおあつらえ向きの場所なのである。
体を洗い、洗髪し、髭を剃り、下着とシャツの洗濯もすませた。下着とシャツが乾くまでのあいだ、箱の中で過ごした。
贋箱男との不意の出会い。しげしげと、腰をかかげて四つん這いになっている彼女を覗き込んでいた複製。箱をこれほど醜く感じたことはなかった。箱に未練なんかなかった、うんざりだ。このノート(記録)だって、この行を最後に破り捨ててしまってもかまわない。
さてそろそろ箱ともおさらばとするか。
箱を片付け中のものを整理することを考えた。箱暮らしをはじめた当初は、やみくもに物を貯め込んだ時期があるが、年月と経緯で所持品を単純化してしまった。
だが限界がある。たとえば小型ラジオを愛用していたものがあっさりガラクタ扱いできるのかどうか。ところがぼくは出来た。そのラジオの話だけはぜひ彼女に聞かせてやろう。
この五万円、一応、預かりはしたけれど、まだ受け取ると決めたわけじゃない。只今、考慮中。しかし箱の始末は注文通りにつけた。どうです、箱の住み心地は?ところで、ぼくという人間を知ってもらうためにラジオの話しでも聞いてもらうとするか。
実は以前、酷いニュース中毒にかかっていた。世界は湧きっぱなしの薬罐みたいなもので、ちょっと目を放した隙に、地球の形だって変わりかねない。漁りまわっても事実に近づいたわけじゃないのは百も承知していながら、ぼくに必要なのは 事実でも体験でもなく、きまり文句に要約されたニュースという形式だった。
「その五万円は、君が箱男と親しくしているとの触れ込みを信じて買い取ってもらうために預けた金だ」と贋箱男が言った。そして「たしかに、箱ってやつは見るとかぶるとでは、大違いだね。これじゃ箱男になりたがるのも無理はない」と贋箱男は穏やかな調子で噛みしめるように繰り返した。
窓のビニール幕が割れて、眼がのぞいた。見られているのもぼくだが、見ているのも同じぼくなのだ。
贋箱男は「君はこの家の中で自由にふるまってもらい、彼女とどんな関係になろうと、一切干渉しない。邪魔したり、口出ししたり目障りになるようなことは一切しない。ただ一つだけ、覗く自由を与えてほしい」と言った。無論、箱はかぶったままだ。
悪くないかもしれない。箱男が無害な存在なことは、誰よりもこのぼく自身がよく知っていることだ。
「覗き」という行為が侮りの眼をもって見られるのも、自分が覗かれる側にまわりたくないから、やむを得ず覗かせる場合には、それに見合った代償を要求するのが常識である。
ぼくがすすんで近視眼になり、ストリップ小屋に通いつめ、写真家に弟子入りし、そして箱男になったのも自然なことだった。
贋箱男は「君も煮え切らない男だな」と口早に言った。ぼくは「あんたが目障りだからさ、世間が箱男を黙殺するのは中身が誰だか分からないからさ。でもあんたの正体は、はっきりしている。ぼくは嫌だな。じろじろ見詰められるのは嫌いなんだ。」と返す。
贋箱男が「だから五万円も払ったんじゃないか」と言うので、ぼくは「覗くことには馴れっこだけど、覗かれることには、まだ馴れていないんだ…」と言った。
「君、裸になって見せてあげたら?」贋箱男が彼女に言った。彼女は白衣のボタンを外しはじめた。箱男が<専門の覗き屋>なら、彼女は<天性の覗かれ屋>なのである。
贋箱男と彼女は、彼女が一年前に子供を堕しに病院に来たのがそもそもの馴れ染めで、金がないので働いて返させてくれと言われた。そして関係を持ち、それまでの看護婦はさっさとやめていった。それまでの看護婦は贋箱男の妻だった。
ぼくは下着が乾きしだい出発するつもりでいる。箱から出るために必要なのはズボン。それと商売道具のカメラ一式を除けば、箱の中の必要かつ十分なすべての生活セットを餞別として譲ってもいい。最初のうちは小型ラジオは持っていた方がいいかもしれない。ニュース毒に完全に免疫になるまでは孤独感に襲われてしまうから・・・。
ぼくは贋箱男に物的証拠があることを話す。「せっかくだが、何をほのめかされているのやら、見当もつかないな。」と贋箱男が言い、「それじゃ、言わせてもらうよ。ぼくを空気銃で狙ったのは、誰だったっけ」とぼくは返す。
あいにく、動かしがたい証拠があってね。撃たれた瞬間、そこは商売柄、すかさずシャッターを切ったのさ。現像もその日のうちにしてみた。空気銃を脇の下に隠しながら、坂道を逃げ上っていく後姿。髪の刈り方、猫背に合わせて仕立てた服、目立つズボンの皺、スリッパ式の短靴・・・
すると贋箱男の覗き窓のビニール幕が割れて、中から空気銃が突き出た。
「身体検査しなさい」と贋箱男が彼女に言った。白衣を脱いだ裸の彼女がぼくに近づく。
ぼくは脱衣籠に引き返し、ずた袋から鰐の縫いぐるみを引きずり出す。中には海岸の砂が詰めてある。もろに殴れば頭蓋骨だってへこむだろう。筒先めがけて叩きつけてやった。すごい破壊力で覗き窓の上縁に食い込み、箱が跳ね上がった。
不意をつかれた医者のいまいましげなうめき声。弾は天井に向けて飛んだ。医者も負けずに覗き窓から腕を突き出してきた。鰐の砂袋を向う脛に叩きつけてやった。
彼女とぼくを残して、贋医者/Cの箱男は出て行った。
挿話-《Dの場合》(193P-208P)
【補足】少年Dが女教師のトイレを覗こうとして見つかり、逆に覗かれる話。
少年Dは強さに憧れていた。かねがね、もっと強くなりたいと願っていた。そして手製のアングルスコープを作り、体操の女教師がピアノの練習が終わると規則通りに行くトイレを覗き見ようとする。しかし逆に女教師に見つかり、ピアノ室でショパンを聴かされた後に、鍵穴から覗く女教師に罰として服を脱ぐことを命じられ射精してしまうところを覗かれてしまう。
《…‥・・・・・・・・・・・》(209P-221P)
やっと辿り着いた病院のドアには錠が下がり、本日休診の札がかかっている。
ぼくはベルを押す。贋箱男と思い、間違えて彼女がせかして迎え入れる。
箱を脱いでという彼女に、いま裸であることの事情を説明する。洗濯した下着が乾くのを待っていたら眠り込んでしまって、眼が覚めたら下着もズボンもどこかに消えてしまっていた。なんとかズボンだけは手に入れなきゃどうしようもない。
街の方にむかっていたら、ぼくとそっくりな箱男(贋医者/C)が歩いるのを見た。
「裸だっていいわよ、(箱男をやめる)約束は約束でしょう?」「それじゃ、私も裸になってあげる。どうせ、私の写真を撮るつもりなんでしょう。二人で裸だったら気兼ねもないんじゃない」
「白状するよ、ぼくは贋物だったんだ。」「でも、このノートは本物なんだよ。本物の箱男からあずかった遺書なのさ。」
《開幕五分前》(222P-225P)
君との間に熱風が吹いている。官能的で、妬けつくような、熱風が吹きまくっている。この熱風自体の中に終末の予感がひそんでいる。これは恋愛だけれど、まず、失恋の自覚から始まった恋愛、終わりから始まる逆説的な恋愛なんだ。ある詩人が言った。愛することは美しいが、愛されることは醜い。
《そして開幕のベルも聞かずに劇は終わった》(226P-233P)
玄関のドアが閉まる音。彼女は行ってしまった。ドアが閉まる音には深い憐れみや思いやりがこめられていた。十分だけ待ってドアを釘付けにしてやろう。玄関を終えたら、後は二階の非常階段のドアの閂だ。建物全体が完全に外界から遮断されて出口も入口もなくなるのだ。
そうした上で、ぼくは出発する。箱男にしかできない脱出だ。
ぼくが外から戻ってから彼女が立ち去るまでの間、結局一言も言葉を交わさなかった。心残りがなくはないが、言葉が役立つ段階はすでに過ぎた。もう二か月近く、彼女は裸で暮らしたのである。ぼくも箱の下は素っ裸だった。家では二人とも裸だったのだ。
一日に一度、ぼくが箱をかぶって街に出た。透明人間のように街をうろつき、食料品を中心にした日用雑貨を調達してまわった。二階の廊下で箱と長靴を脱ぐと、待ち受けていた彼女が下から裸で駆けあがってくる。一日のうちでこの瞬間がいちばん刺戟的だった。
だから今日、裸の彼女が駆けあがってくるかわりに、服をつけた彼女が黙ってぼくを見上げているのに気づいたとき振り出しに戻った落胆を覚えただけですませられた。
ぼくからやりなおしを申し出るのを待ってくれているのだろうか。しかし、何度やりなおしてみたところで、いずれまたこの同じ場所、同じ時間が繰り返されるだけのことだろう。
挿話-《夢のなかでは箱男も箱を脱いでしまっている。箱暮らしを始める前の夢をみているのだろうか、それとも、箱を出た後の生活を夢みているのだろうか・・・・・》(214P-221P)
【補足】ぼくは夢の中で町を出ていく決心をする。
目指す家は坂の上にあって、町の出口にあたっていた。町の慣習では結婚式には馬車で花嫁を迎えねばならない。馬車とは名ばかりで車を引くのは馬ではなく箱をかぶったぼくの父親だった。父はすでに六〇歳を越えていた。
本物の馬の十分の一もはかどらない。容赦ない震動でぼくの生理的欲求が限界に達しズボンの前を開いて深い解放感にひたる。しかし道端にいた花嫁は灌木に身を潜め視線が合った。彼女がぼくのペニスを眼にしたことは確実だ。
「なぁ、ショパン、あきらめが肝心だよ」露出狂の男が結婚に不向きなくらい、いまの若い娘には常識だからな。
露出狂に対する偏見と公衆便所の建設を怠った町の行政の責任さ。さぁ行こう、こんな町にもう未練はないだろう。都会に着いたぼくらはとりあえずピアノつきの屋根裏部屋を借りた。そして傷心をまぎらわせるために画用紙にペンで彼女を描き続けた。
やがて紙を節約し小さく切り刻み、肉眼で見分けがつかない細やかな線を刻み込み作業に熱中する。いつかぼくの画は世間に認められ行列を為すほど売れる。父の箱もダンボールから赤い本皮製になっていた。父は本物の馬を買った。
そんなわけで今ではぼくの名前を知らない者はいない。世界の最初の切手の発明者、製作者としてショパンの名前がない百科事典はない。だが郵便事業が発達し、国営化されるにつれ、ぼくの名前は切手の贋造者として知られ、どこの郵便局にもぼくの肖像画が飾られていない。ただ父親が愛用していた赤い箱の色は、一部、郵便ポストの色として受け継がれている。
《…‥・・・・・・・・・・・》(234P-238P)
今こそ最後の打ち明け話。彼女は今も建物の中に閉じ込められっぱなしのままでいるはずだ。箱から出るかわりに世界を箱の中に閉じ込めてやる。彼女の部屋を訪ねてみた。むろん箱を脱いで裸のままだ。
闇の奥の小さな気配を想像していたぼくは、思いがけない部屋の変化にうろたえた。
部屋の空間が、どこかの駅に隣り合った路地に変わっていた。彼女はどこに消えたのだろう。
そうだ、忘れないうちに、大事な補足をもう一つだけ。箱を加工するうえでいちばん重要なことは、落書きのための余白をじゅうぶんに確保しておくこと。じっさい箱というやつは、見かけは単純な直方体にすぎないが、内側から眺めると百の知恵の輪をつなぎ合わせた迷路のようなものなのだ。もがけばもがくほど迷路に新しい節をつくってますます仕組みをもつれさせる。
現に姿を消した彼女だってこの迷路の何処かにひそんでいることだけは確かである。手掛かりが多ければ、真相もその手掛かりの数だけ存在していいわけだ。
救急車のサイレンが聞こえてきた。