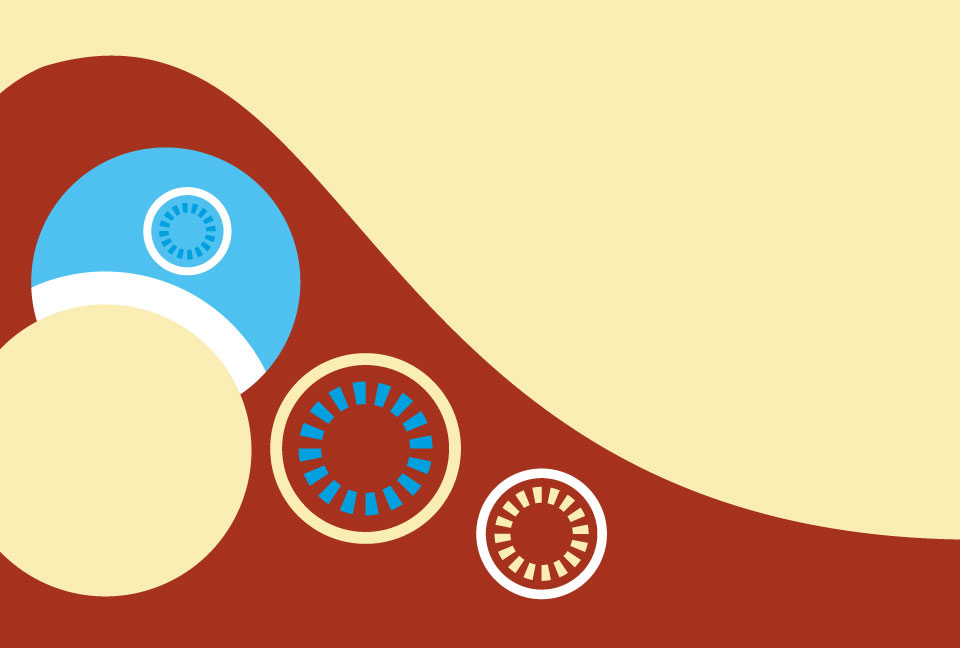人買いに売られるも逃れ、運命を拓き出世して山椒大夫を懲らしめる厨子王。中世の説教節を年代や大筋はそのままに近代にアレンジする。昔から親しまれた安寿と厨子王の話を換骨奪胎して、奴隷解放や親子愛の物語にした鴎外の創作技法の素晴らしさを味わう。
登場人物
安寿
姉弟の姉で十四歳。人買いから山椒大夫に売られ、苦役に耐え身代わりに厨子王を逃がす。
厨子王
姉弟の弟で十ニ歳。人買いから山椒大夫に売られるが、逃げ出しやがて後に丹後を治める。
母
安寿と厨子王の母。家族三人と女中を連れ父親を尋ねる旅をするが、人買いの手に落ちる。
姥竹
母と安寿と厨子王に仕える女中。親子と一緒に旅をしながら、お世話をまめにしている。
山椒太夫
姉弟を買った丹後の悪辣な地主で資産家。姉を汐汲み、弟を柴刈りの苦役につける。
二郎
山椒大夫の二番目の息子。物分かりのいい男で、安寿の願いを聞き厨子王と伴にさせる。
三郎
山椒大夫の三番目の息子。気性が激しく乱暴者で、安寿と厨子王を手荒に扱い監視する。
陸奥掾正氏
安寿と厨子王の父で筑紫(福岡)へ左遷させられており、藤原師実によって許しをえる。
曇猛律師
国分寺の住職で厨子王を匿う。後に正道となる厨子王から恩返しに僧都に任じられる。
藤原師実
関白で時の最高権力者。厨子王の守本尊のおかげで娘の病が治り、還俗させ重用する。
あらすじ
母と安寿と厨子王、女中の四人は筑紫に左遷された父親に会いに行く。
越後の春日から今津へ旅人の一群が歩いている。母は三十歳くらい、二人の子供の姉は十四歳、弟は十二歳、そして女中が一人。四人は今宵の宿を探している。
姉は弟に「早くお父さまのいらっしゃるところへゆきたいわね」と言うと、弟が「姉さん。まだなかなかいかれはしないよ」と言い返す。母は諭すように「そうですとも。今まで越してきたような山をたくさん越して、河や海をお船でたびたび渡らなくてはいけないのだよ。毎日精出して、おとなしく歩かなくては」と言い、黙々と歩く。
塩浜から帰る潮汲み女に旅の宿を尋ねると、あいにくこの土地には人を泊める所は一軒も無いという。近ごろ悪い人買いがこの辺りを立ち廻っているので国の守の掟で旅人を泊めてはならず、掟を破ればお咎めがあり向こう七軒も連座になるという。
困り果てた一群に、潮汲み女は「野宿をするしか方法は無いが、あそこの橋の下に休むのがいいでしょう。岸の石垣のところに大きい材木が立ててあり、そこなら風も通さないので、夜になったら自分が藁や薦を持ってきてあげましょう」と言う。そこで四人は橋のほうへ急いだ。
山岡大夫という男があらわれ、親切に四人を泊め食事までふるまう。
橋のたもとに来ると潮汲み女の言うとおり立札があった。母親は人買いがいるのなら探して捕まえれば良いのにと思う。旅人を泊めず路頭に迷わせるような掟をなぜ定めたのかと思うが、この土地に来合わせた運命を歎き掟の善し悪しは思わないことにした。
話の通り、河原の石垣の立てかけてある材木の中をくぐった。女中の姥竹は衣類を出し、食べものを出し、潮汲みの女のところに行ってお湯と藁と薦をもらいにまめまめしく出ていった。
しばらくして材木の蔭から四十歳ばかりの男が入ってきた。
骨格の良い筋肉質の彫の深い顔つきの男は、親子の傍に来て腰かけた。自分は山岡大夫という船乗りでこのごろこの土地に人買いが立ち廻るので、国守が旅人に宿を貸すことを禁じている。人買いを捕まえるのは国守の手に負えない。気の毒なのは旅人だと同情して見せた。
そして自分の家は街道から離れているので、人を泊めても誰に遠慮もいらない。これまで野宿する大勢の人をお泊めした。見れば子供がお菓子を食べているが歯に悪い。芋粥くらいしかもてなしができないが、遠慮せずに家に来てくだされという。
子どもの母は掟に背いてまで人を救おうとする心遣いに感謝して、誘いを受けて泊まることにした。姥竹を待って四人揃ってと言う母に、山岡大夫はお待ちましょうと影のある喜びの表情を見せた。
母は身の上を話し大夫は船路が良いと教え、舟は浮かび出た。
ここは直江の浦である。
姥竹が帰りその後、四人で山岡の宿に泊まった。山岡は芋粥をふるまい旅の行き先を尋ね、母親は身の上を語った。夫が西の筑紫へ行って帰らぬので二人の子供を連れて尋ねてゆく、姥竹は女中で伴をすることになったという。
ここまで来たが筑紫の果てに行くにはまだ遠く、山岡大夫が船乗りゆえ遠国のことを知っているので、陸を行くが良いか、船路が良いか教えてもらいたいと母親は頼んだ。山岡大夫は当然というように、ためらわずに船路をすすめた。
陸を行けば越中の境に親不知子知子という削り立てた岩石の裾に荒波が打ち寄せる海辺の難所があり、山を越えるとひとつ間違えば谷底に堕ちるような険しい道もある。陸路は西国にいくまでに難所ばかりである。その点、船路は船頭にまかせれば良いという。
自分は諸国の船頭を知っているから途中まで行って、引き渡すので乗り換えていくのが良いという。そしてしきたりだといって舟の主の大夫に有り金の入った袋を渡した。母親は大夫の言うことすべてを信じはしなかったが、それでも大夫の言葉に圧しつける強さがあり抗うこともなく船に乗った。
山岡大夫は舟を繋いだ綱を解き、舟は浮かび出た。
大夫は人買いで、四人は佐渡と丹後の二隻に売られてしまう。
越中境の方角へ漕いでいくと浜辺に舟が二艘止まっている。大夫は右の手を挙げて親指を折り四人であるという合図をする。
前からいた船頭の一人、宮崎の三郎は左の拳を開いて見せ、こちらは金の合図で五貫文をつけた。今一人の船頭は佐渡の二郎で六貫文をつけて対抗した。大夫は二人ずつ分けて取引した。二人の子供は宮崎の舟に、母親と姥竹は佐渡の舟へ。舟の主に預けた袋のお金は山岡大夫のものにされた。
佐渡の二郎は北へ漕ぎ、宮崎の三郎は南へ漕ぐ。親子主従は遠ざかって行った。
母親は今生の別れに「安寿は、守本尊の地蔵様を大切に、厨子王は守り刀を大切に」と言った。安寿と厨子王は「お母さま、お母さま」と呼ぶばかり。そして遠ざかり子供たちの声は聞こえなくなった。姥竹は「これまでじゃ」と言い海に飛び込み身を投げた。
母親も飛び込もうとしたが「うぬまで死なせたなるものか」と、くるくる巻きにして転がされ北へと漕いでいった。「お母さま、お母さま」と叫び続ける姉と弟を乗せ、宮崎の三郎の舟は南へ走っていく。
叫んでも聞こえぬ、母親は佐渡でスズメを追わされるだろうという。安寿と厨子王は母と引き分けられどうしてよいかわからず悲しさが胸にあふれた。
安寿と厨子王は、悪辣な大金持ちの山椒大夫のもとに連れてこられた。
宮崎は、越中、能登、越前、若狭の津々浦々を売り歩いたが、二人が幼く体も弱く見えるのでなかなか買い手がない。たまにあっても値段が折り合わない。宮崎は次第に機嫌が悪くなり、子供たちをぶつようになった。
丹後の由良の港に来た。ここには山椒大夫という権力者がいて、大きい屋敷を構え、田畑に米麦を植えさせ、山では猟をさせ、海では漁をさせ、蚕を飼い、機織りをさせ、金物、陶物、木の器など職人を使って作らせた。人なら何人でも買う。港にいた山椒大夫の奴頭は安寿と厨子王を七貫文で買った。
大きな家の奥深い広間に炉を切らせて、敷物を三枚かさねて敷いて山椒大夫はひじかけにもたれている。今年六十歳になる大夫は、赤ら顔で額が広く顎が張って髪も髭も銀色に光っている。左右には二人の息子の二郎と三郎が狛犬のように並んでいる。
奴頭が安寿と厨子王を連れて前に出た。山椒大夫は「珍しい子供だというから会ってみたが、色の蒼ざめたか細い童で、何に使ってよいかわからない」と言う。傍から三郎が「辞儀もせず名も名乗らないしぶとい者じゃ、奉公はじめはいつも通り、男は柴刈り、女は汐汲みと、その通りにさせなされい」と言う。そして奴頭は二人を小屋に連れ、安寿に桶とひさご、厨子王に籠と鎌を渡した。
安寿は浜に汐汲みに、厨子王は山に柴刈りに行く苦しい日々が始まる。
翌日の朝はひどく寒かった。姉と弟は朝餉を食べながらこうなっては運命に任せるしかないと話し合った。そして姉は浜辺へ、弟は山路へ行く。
厨子王が登る山は由良が嶽の裾でやや広い平地に出て雑木が茂っている。柴の刈り方を木こりに教わった。浜辺に行く姉の安寿は河の岸を北へ行く。汐の汲み方を知らない安寿は、隣の汐汲み女子の小萩に教わり、二人は仲良くなり姉妹の誓いをした。
最初の日はこんなぐあいに安寿の汐汲みも、厨子王の柴刈りも日の暮れまでに終った。
こうして一日一日と過ぎていき、姉は浜で弟を思い、弟は山で姉を思い、日暮れて小屋に帰り二人は手を取り合い筑紫にいる父を恋しく、佐渡にいる母を恋しく泣き思った。
やがて十日立って新参者の小屋を離れて奴は奴、婢は婢の組に入らねばならぬのだが、二人は死んでも離れぬといった。二郎が「童が死んでも別れぬといいます。愚か者ゆえ、引き離すとほんとうに死ぬかもしれません。人手を減らすのは損なので私に任せてください」と言う。山椒大夫は了解した。
二郎は姉と弟を一緒に置いた。そして二郎は二人に「父母が恋しくても佐渡は遠い、筑紫はそれより遠い。子供の行けるところではない、大きくなる日を待て」と言った。
火箸で額に烙印を押される夢を見て、目覚めると守地蔵の烙印の痕がある。
ある日の暮れに今度は三郎が見廻っている。安寿が「厨子王一人が逃げて筑紫へ行き、お父さまに会ってどうしたらよいかを伺い、それから佐渡へお母さまを迎えに行くのがいい」と話をしているのを、三郎が立ち聞きをしていた。
三郎は逃亡の企てに対して烙印をするという。安寿と厨子王はその日はうまくごまかして眠った。
眠りから目覚めると枕元に三郎が立っていて、両手でつかまれ引っ立てられ戸口を出る。そして最初出会った大広間に入れられ大勢の人が見ている。
炉の向かいには山椒大夫の赤ら顔があり、そこで三郎は赤く焼けている火箸を抜き出し次第に黒ずんでから安寿を引き寄せ顔にあてようとする。
肘に絡みつく厨子王を蹴倒して火箸を安寿の額に十文字に当てる。そして次には厨子王の額に火箸を十文字に当てる。
二人は傷の痛みと心の恐れとに気を失いそうになる。耐え忍んで厨子王は守り袋を取り出し仏像を枕元に据えてぬかずく。すると痛みが失せた。掌を撫でていれば傷は痕もなくなっていた。
はっと思って二人は目をさました。二人は同じ夢を見たのである。守本尊の地蔵様の額を見た。白毫の左右に鏨で掘ったような十文字の疵があざやかに見えた。
意を決し安寿は思案する、そして厨子王と一緒に柴刈りを希望する。
恐ろしい夢を見た時から安寿の様子がひどく変わってきた。顔は引き締まったままの表情になり、眉の根に皺が寄り目は遠くを見つめ何も言わない。
年が暮れかかった。奴も婢も外に出る仕事を止めて家の中で働くことになった。安寿は糸を紡ぎ、厨子王は藁をうつ。
水が温み草木が燃えるころになった。明日から外の仕事が始まるという日に二郎が見廻りついでに小屋に来た。すると安寿が「弟と同じところで仕事がしたいので、一緒に山へやってください」と言う。
二郎は「よくよく思い込んでのことと見えるので、山へ行けるようにしてやる」と言って小屋を出た。そして奴頭がやってきて、二郎のおかげで安寿は山へ柴刈りに行くようになった。
加えて奴頭は「お前さんを柴刈りにやる代わりに髪を切ろということじゃ」と言う。これは三郎が大夫に言ったことだった。
厨子王はこの言葉を胸の刺されるような思いをして聞いた。そして涙を浮かべて安寿を見た。すると安寿は「ほんにそうじゃ。柴を刈りに行くからはわたしも男じゃ、どうぞ鎌で切って下さいまし」と言う。つやのある長い安寿の髪が鋭い鎌のひと掻きにさっくり切れた。
安寿は厨子王を説得し、自分の命と引き換えに中山寺から都への運を託す。
あくる朝、二人の子供は木戸を出た。安寿は毫光のさすような喜びを額にたたえて、大きい目をかがやかせている。そして厨子王を連れ立ってずんずん登っていく。しばらくして雑木林より高い頂に来た。安寿は南のほうの中山を見た。
そして汐汲みを教えてくれた小萩は伊勢から売られてきたが、話を聞くと「あの中山を越えれば都が近い。筑紫へ行くのは難しいし、佐渡へ行くのもたやすくはないが、都にはきっと行くことができる。これまでは恐ろしい人ばかりであったが、人の運が開けるのなら良い人に出会うかもしれない」
「お前は思い切ってこの土地を逃げのびて都へ登り、神仏のお導きで良い人に出会えたら筑紫へ下った父も、佐渡の母も迎えに行くことができる」安寿はそう言い守本尊を取り出し厨子王の手に渡した。
そして「中山のお寺で隠してもらって、追手が帰った後に寺から出るのだ」と安寿は言う。
「お寺の坊さんが隠してくれるでしょうか」という厨子王に、「それが運だめし、開ける運なら坊さんが隠してくれるでしょう」と安寿は言う。
こうして厨子王の眼が安寿と同じように輝いてきた。姉の熱した心持ちが、暗示のように弟に移っていった。
二人を捜しにでた山椒大夫一家の追手が沼の端で小さい藁ぐつを拾った。安寿のくつだった。
厨子王は中山の国分時の住持曇猛律師に匿われて、三郎の追手を逃れる。
中山の国分寺の門に山椒大夫の息子、三郎が現れる。
「大夫の使う奴のひとりがこの山に逃げ込んだ。隠れ場は寺内よりほかはない、出してもらおう」と叫んだ。境内に住んでいる僧侶が出てきた。そして住持曇猛律師が本堂の戸を静かに開けた。
律師は静かに口を開き「当山で住持のわしに内緒で人は留めぬ。わしが知らぬから、その者は当山にいぬ」
そして「国に大乱でも起こったか、公の叛逆人でも出来たかと思うたが、下人を捜しているのか。当山は天皇の勅命の寺で天皇の書もかかっている。ここで乱暴をはたらかれると責任を問われ、都からどのような沙汰があるかもしれぬ。引き取られたほうが良かろう」と言う。
三郎は悔しがったが踏み込む勇気はなかった。その時、寺の鐘楼守がその奴が南へ急ぐのを見たと嘘の行方を三郎に示した。三郎は南へ走った。
厨子王は都に上り関白師実に会い、守本尊をみせ自身を語り還俗をする。
あくる日、国分寺から諸方を調べさせた。安寿は入水した。三郎の追手は南の方まで行って引き返した。中二日おいて、曇猛律師は田辺の方へ寺を出た。その後を頭を剃った厨子王がついて行く。
曇猛律師は「守本尊を大切にしていけ、父母の消息はきっと知れる」と言って別れた。都に上った厨子王は、僧形となっているので東山の清水寺に泊まった。
あくる朝、目が覚めると直衣に烏帽子を着て指貫をはいた老人が枕元に立っていた。
老人は「娘の病気を治すべく祈りを捧げに清水寺に来たところ夢でお告げがあった。寝ている童が守本尊を持っている、それを借りて拝ませると良いとのこと。自分は関白、藤原師実」という。
厨子王は「自分は陸奥掾正氏の子です。父は十二年前に筑紫の安楽寺に行ったきりで、母は、私と私の姉が大きくなって父を尋ねて旅だったのですが、恐ろしい人買いに取られて、母は佐渡へ、姉と私は丹後の由良へ売られました。姉は由良で亡くなり、私の持っているお守本尊はこの地蔵様です」と言って見せた。
師実は「これは尊い放光王地蔵菩薩の金像じゃ。連座して筑紫に左遷された平正氏の跡継ぎに相違あるまいとして、還俗の望みがあるなら聞き入れるのでまずは客分として館に来い」と言う。
関白の娘を助け師実に重用され、厨子王は正道となり丹後の国守となる。
関白、師実の娘は厨子王の守本尊で拝むと病気が回復した。
師実は厨子王を還俗させて冠を与えた。正氏の左遷の場所に赦免状を持たせ安否を確認したが、正氏はすでに死んでいた。
元服して正道と名のっている厨子王は、身のやつれるほど歎いた。
その年の秋に正道は丹後の国守にせられた。国守は最初の行政として丹後一国で人の売り買いを禁じた。山椒大夫も奴婢を開放して給料を払うことにした。
大夫が家も農作も匠も前に増して盛んになって、一族はいよいよ富み栄えた。
恩人の曇猛律師は僧都にせられ、姉をいたわった小萩は故郷に還された。安寿の亡きあとはねんごろに弔われ、沼のほとりには尼寺が立った。
そして正道は佐渡へ渡った。役人の手で国中を調べてもらったが母の行方は知れなかった。
佐渡で盲目となった母を捜しあて、守本尊をかざすと目が開き再会する。
ある日、思案に暮れながら歩いていると畑中の道にかかった。大きな百姓家があり土をたたき固めた広場に、一面のむしろがひいてある、むしろには刈り取った粟の穂が干してある。
まん中にぼろを着た女がすわり、雀が来て啄むのを追っている。女は歌のような調子で呟き、髪は塵にまみれ盲目である。
正道は女のつぶやく詞を聞いた。「安寿恋しや、ほうやれほ。厨子王恋しや、ほうやれほ。鳥も生あるものなれば、とうとう逃げよ、おわずとも」
正道は身が震って目に涙が湧いてきた。この詞に聞き惚れ、獣めいた叫びが口から出ようとするのをこらえた。
そして女の前にうつむいて右の手に守本尊を捧げ額に押し当てた。すると両方の目に潤いが出た。
女は目が開いた。「厨子王」という叫びが女の口から出た。二人はつよく抱き合った。