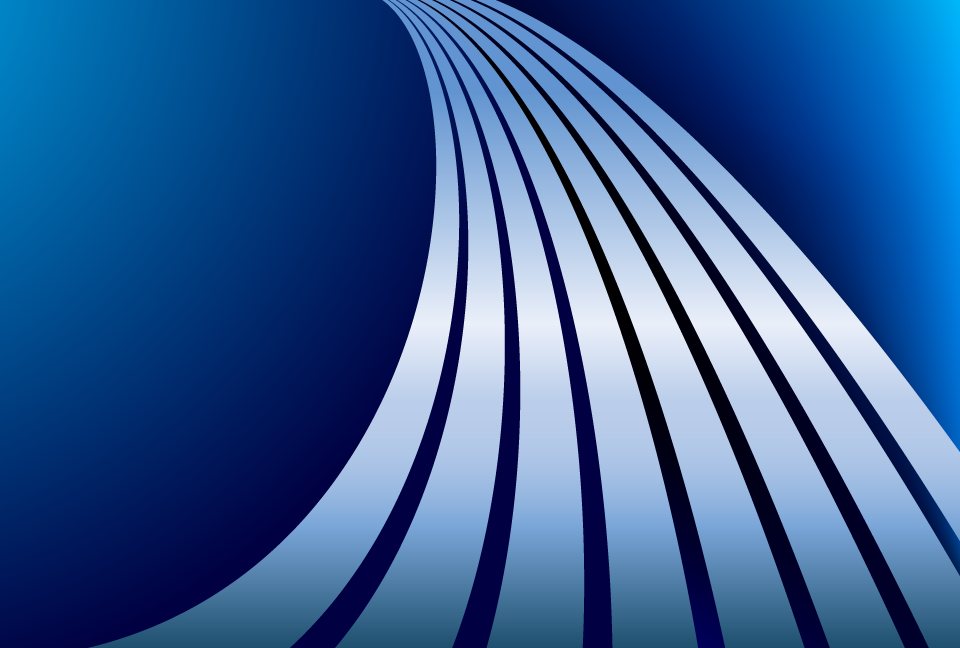解説
秋幸の複雑な出自と、繊細な精神世界が細やかに描かれる。
母系で繋がり、異父の多くの兄弟姉妹を持ち、私生児としての自分の出自に悩み、戸惑い、怒り、怖れ、常に孤独で傷ついている。
いつも「あの男」を意識して、絶えず「あの男」に視られている気がしている。いつも町で噂をされているような感覚。こうして秋幸は自分を遺伝子的にこの世にもたらした「あの男」の顔を意識する。
おれの顔は、あの男の顔だった。世の中で一番みにくくて、不細工で、邪悪なものがいっぱいある顔だ。彼は思った。その男が、遠くからいつもみている。いつもおれの姿を追っている。
秋幸は、このような環境のなかで土方という仕事を愛する。日と共に働き、日と共に働き止める。自然と向き合い、肉体がぶつかる仕事。土方の仕事が好きで、他の仕事や商売よりも貴いと思っており、自然とともにあることが、余計なものをそぎ落としてくれると考える。
なにもかも正直だった。土には、人間の心のように綾というものがない。彼は土方が好きだった。
肉体と自然が一体化する土方仕事と、同時に、自分のような繊細な感受性を持つ人間が、この路地の世界でたった一人だということが嘘のような気がする。日の光は、何のくったくもなく、彼を照らす。
ここでは、自然と共に在る土方作業の細やかな描写が中上健次の身体性の世界として描かれる。
つるはしで土を掘る筋力や照らされる肌、ほとばしる汗という自然との向き合いは、読むものに五感を揺さぶり、強く頑強な肉体と生命を感じさせる。そして中上の文章は、力まかせの腕力のようにぐいぐいと進んでいく。
しかし安雄が光子の大きい兄の古市を刺し殺し、美恵が精神を病んでいく出来事の中で、肉体と自然との調和が変化し、時間が壊れてしまう。複雑な血縁と地縁に繋がれた路地から、危険な何かが突き破って出てきそうな気配になる。
オイディプス的な「あの男」との闘いの予感と、血筋の呪縛。
『岬』には、路地で自然と生きていく人々の死の匂いや精神の憂鬱が充満している。
美恵は首を吊って死んだ長男の記憶が忘れられない。その思い出は体の弱い美恵が、現在の夫の実弘と出会う前までは、夫婦のように兄と共に路地の家に二人で暮らした思い出でもあった。
それが光子の夫である安雄が、光子の大きい兄ちゃんの古市を刺し殺したことで、長男の縊死の記憶が蘇り、仏壇を壊したり手首を切ったりするほど精神が錯乱する。
そんな美恵の姿を見て、すべてが「あの男」さえいなければ、自分は存在しなかったと考える秋幸。
虫唾が走る、反吐が出る。きれいさっぱりもともとなかったこととして、消してしまいたい。
ついに復讐心から秋幸は「あの男」が愛人に生ませた娘がいると噂のある新地の<弥生>という店に行く。そこで久美という娼婦と会う。「この血のつながりがおかしい、濁っている」と感じる。
次々と母系の血筋のなかで起こる自死や殺人、自殺未遂や精神の異常、秋幸にとってはすべて「あの男」へと繋がっていく。このことは、山と川と海に閉ざされたこの土地の熱狂のせいだと考える。
やがて美恵も落ちつき、皆で、岬に向かい、しみじみと昔を懐かしみながら楽しく過ごす。塞がれた路地から岬に行きくつろぐ。海に向かって突き出る岬。突起する岬を包みこむ海。
それは男性である岬と、女性である海を暗喩する。そこは開放なのか、危険の入り口なのか。
しかし芳子ら一家が名古屋に帰った後、美恵は汽車に飛び込んで自殺をしようとする。秋幸はこの忌まわしい血筋に、「勝手に、気ままにやって、子供にすべてツケをまわす」と思う。おまえらを同じ人間だとは思わない。「おまえら、犬以下だ」と考える。
あの男は絶えずおれを視ている。その眼を、視線を、焼き尽くしたい。
酷いことをして、あいつらに報復してやる。同じ雄として「あの男」と決着をつけてやると考える。
そしてついに秋幸は、異母妹と性的な関係を持つ。近親相姦である。それは間接的ではあるが、疑似的な「父殺し」であると考える。
女と男の心臓がどきどき鳴っているのがわかった、そして愛おしかった。秋幸は懊悩するなかで、
「いま、あの男の獣の血があふれる」と思った。
こうして物語は続編の『枯木灘』に受け継がれていく。
※中上健次の小説をもっと読む!
中上健次『鳳仙花』あらすじ|母胎に宿る命から、その物語は始まった。
中上健次『岬』あらすじ|自分はどこから来た、何者なのか。
中上健次『枯木灘』あらすじ|路地と血族がもたらす、激しい愛憎と熱狂。
中上健次『地の果て至上のとき』あらすじ|路地が消え、虚無を生きる。
作品の背景
中上健次はこれより先に『一番はじめての出来事』(1969年)と『十九歳の地図』(1973年)の2つの作品を書いている。前者は『岬』よりさらにさかのぼる小学校5年生の少年期、新宮の自然のなかで仲間たちと過ごす抒情的な作品であり、後者は高校を卒業し上京して新聞配達をしながら抑圧された自分という存在に絶望する作品である。
通底するものは孤独のなか自分とは何者かという問いかけであるが、この2つの作品を経て『岬』(1976年)は書かれた。そして以降、長いあいだ紀州・熊野サーガと呼ばれるこの地を物語の舞台にしている。
その前提となる中上の考え方を『紀州-木の国・根の国物語』に訪ねると、印象的な文章がいくつもある。新宮から熊野川を上り熊野三社のひとつである<本宮>の個所では、
神の場所とは、貴と賤、浄化と穢れが還流し合って、初めて神の場所として息づく。
とあり、<松阪>の箇所では、天皇を出すのは唐突であるがと前置きしながらも、
日本的自然において古代の天皇とは、日と影、光と闇を同時に視る神人だったように思う。
とある。中上健次は被差別部落の出身であることを通して、差別 / 被差別とは何なのかを問い続ける。
そして故郷である紀州を “根の国” として、神武東征以来、敗れた者たちが棲むもうひとつの国家であり、鬼らが跋扈する鬼州、霊気の満ちる気州であるとする。
この隠国・紀州の光と影が鮮やかにされた紀行のエッセイも読むと、日本というものが如何なる構造のなかで存在するのかを考えさせられる。
発表時期
1975年(昭和50年)に『文学界』に掲載。1976年、文藝春秋より短編集『岬』に収録され刊行。第74回、芥川賞を受賞。戦後生まれの作家で初めて受賞した中上健次は当時30歳。選考委員たちは登場人物の複雑さに読みにくさを指摘したが、この濃い血縁・地縁の人間関係こそが物語の大切な背景である。
本作の続編として『枯木灘』(1977年)そして『地の果て 至上の時』(1983年)が書かれ秋幸三部作と呼ばれる。中上健次は1946年に海と川と山に囲まれた紀州半島南部、熊野に近い新宮に生まれた。46歳で亡くなるまで、新宮の「路地」を見つめ、その原風景を神秘的な紀州の物語に投影し、小説を通してその姿を問い続けた。