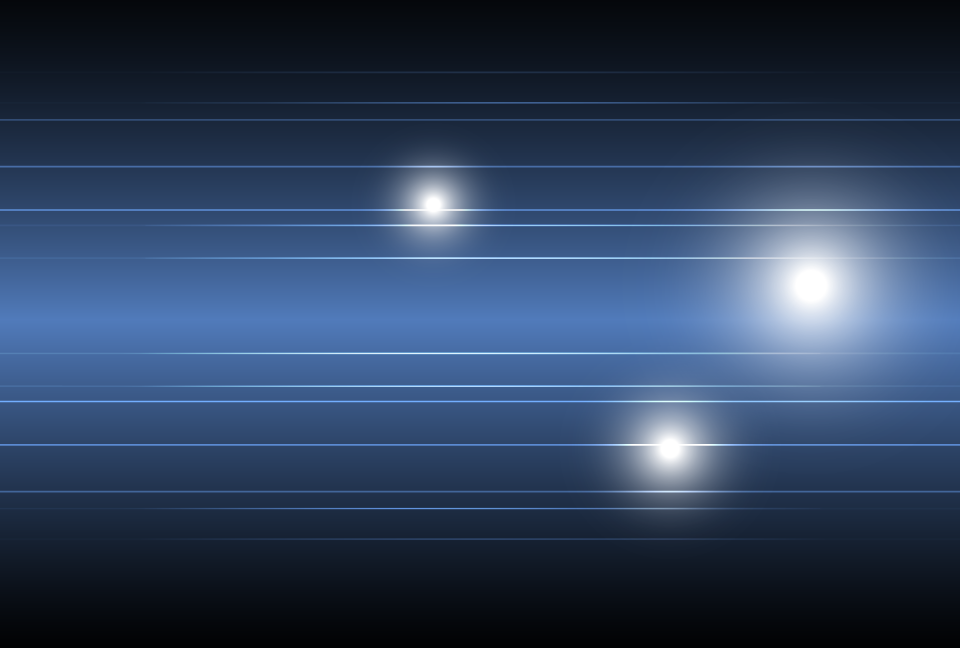決定的な死に至る場合、その死を前に苦しむ者の承諾があれば、楽に死なせてその苦を救うという死を幇助する行為、鴎外は江戸時代の随筆『翁草』の「流人の話」を題材に、「知足」つまり足るを知る考え方とともに、従来の道徳観を超えて「安楽死」の問題を提起しました。
登場人物
喜助
年は三十歳ばかり。弟を殺した罪で遠島となり、高瀬舟で京都から大阪へ送られていく。
羽田庄兵衛
京都町奉行の初老の同心。喜助を高瀬舟で護送し、なぜ罪に至ったのかを船上で聞く。
あらすじ
遠島になる罪人は、京都から大阪へ高瀬舟で回され護送人がついた。
高瀬舟は京都の高瀬川を上下する小舟である。
徳川時代に京都の罪人が遠島になると、罪人の親類が牢屋敷に呼ばれて最後の別れをすることが許された。罪人は高瀬舟に乗せられて大阪へ回される、それを京都町奉行の配下の同心が護送する、その時に親類の一人を同乗させることが黙許となっていた。
島流しの刑なので罪人は重い罪を犯した者だが、人を殺し火を放つような獰悪なものではなく、半数は心得違いの罪を犯したものだった。例えば一緒に情死をはかったが、相手の女は死んで自分だけは生き残った男などであった。
罪人と親戚の者を乗せた船は、別れを悲しみ夜を通して身の上を話し、これまでのことを後悔したり、これからのことを嘆いたりと 繰り言を語り合う。その時に、護送役の同心は表向きの話や記録では想像もつかない境遇を知るところとなる。
同心も様々だから、うるさいと思う者もいれば、しみじみと胸を痛める者もいて、時にはその境遇に涙ぐむ者もいた。そういう理由で高瀬舟の護送は、同人仲間では辛い職務となっていた。
庄兵衛は高瀬舟に乗る喜助が、欲が無く、足ることを知っていることを驚く。
寛政の春、これまでに類のない珍しい罪人が高瀬舟に乗せられた。
名を喜助といって三十歳ばかりになる、住所不定の男である。一緒だった同心、羽田庄兵衛は罪人がただ弟殺しとだけ聞いていた。
この喜助は神妙に大人しくしている。それは権力にこびているような態度でなかった。
夜船で眠ることは罪人にも許されているが喜助は横になろうともせず、月を仰いで黙っている。顔は晴れやかで目にはかすかな輝きがある。
その理由を尋ねると、喜助はこれまで経験した苦しみよりひどい所は無いと思うと答え、さらにお上の慈悲で命を助けて島へやってくださいます。その上に二百文の金までいただきましたという。遠島のものに二百文を渡すのは当時の掟であった。
喜助は「今日まで二百文ものお金を懐に入れて持ったことは無い」と言う。「仕事で貰った金はいつも右から左へ人手に渡り、借りた金を稼いだ金で返して、また借りるという生活だった。牢に入って仕事をせずに食べさせていただいていることを申し訳なく思っているうえに、二百文をいただき、使わずにすむのは始めてである。
島へ行ってこの二百文を仕事の元手にしようと思うと楽しみだ」と言う。
庄兵衛は初老に近い年で女房と四人の子供と老婆の七人暮らし、ケチと言われるほど節約をしている。妻を裕福な商人の家からもらったので、女房が里から金を借りて帳尻を合わせることもあり、自分も喜助と似たようなものだと思った。
喜助と自分の違いは数字の桁が違っているだけで、庄兵衛の場合は、喜助のありがたがる貯蓄さえなかった。
つまり庄兵衛のほうは、喜助などより圧倒的に豊かなのに、常に今の暮らしに、不満があるのです。
庄兵衛が、不思議に思ったのは、喜助の金銭に対する「そのなかでまかなう」という考え方。
庄兵衛は喜助の頭から毫光が射すように思った。
兄にすまなく思い自害をはかった弟、瀕死の苦しむ弟を救うために殺した。
庄兵衛は喜助に「人をあやめた事のわけを話してくれ」と問う。
喜助は弟を殺した理由を話し始めます。喜助は小さな時に両親が無くなり弟と二人になります。小さな時分は町内の人からお恵みをもらい、大きくなって兄弟揃って西陣の織場で働くことになります。
しばらくして弟が病気で動けなくなり、弟は喜助ひとりを稼がせていることをすまなく思います。ある日、帰ってくると弟が血だらけで突っ伏していました。
弟は病気が治らず喜助に迷惑をかけることを嘆き、剃刀で喉笛を掻っ切って自害を図ります。しかし死に損ねていました。刃を深くと思って力いっぱい押し込んだが、刃が横へ滑ったのです。その刃を抜くと出血で死ぬ状態でした。
喜助は医者を迎えに行こうとしましたが、弟が恐ろしい目で剃刀を抜くように訴えるので、苦悩した挙句に抜いてやるぞと言うと、弟の目は晴れやかにうれしそうになります。
弟もまた、十分に生きたことを、兄に訴えているのでしょう。
喜助は剃刀の柄をしっかり握ってずっと引き抜きます。その時に刃が外のほうを向いて、今まで切れていなかった外の方を切ってしまい、気がついて弟を見ると息が切れていました。
喜助はその苦を見るのに忍びなく、苦から救ってやろうとして弟の命を絶ちました。そこを近所の馴染みのばあさんに目撃され、弟殺しとして罪人となりました。
庄兵衛は、これが<弟殺し>だろうかと思いました。
しかしその判断は、上の権威に従うほかなく、お奉行様の判断に従いました。
次第に更けてゆくおぼろ夜に、沈黙の二人を乗せた高瀬舟は黒い水の面をすべって行きました。
★動画もあります、こちらからどうぞ↓
解説
ひとつは持ち分に満足し、足ることを知り、欲張らない生き方の学び。
題材となった江戸時代の随筆『翁草-流人の話』では「二百文を自分のものとして仕事の元手にしたい」と考えています。現在のお金の価値ではいくらほどか、三千円~五千円程度ではと思われます。手もとにお金が全く残らない貧乏は大変で、その生活苦の中で弟が死に向かいます。
喜助は弟を殺してしまった過ちの上に、牢屋で仕事をせずに飯まで食わしてもらえる、さらに遠島の際に二百文までいただけることに有難く、希望を持っています。
一般的に、人々はどこまでいっても限り無い欲望を持ち続けて、上昇志向で暮らしていますが、この罪人は、足ることを知っています。与えられたものを十分だと感じ、感謝をしています。
「老子」三十三章の「足るを知る者は富む」、自らの分相応を知り、それ以上、欲を張らず満足することを教えます。喜助は、苦しさに耐えて生きてきたゆえに、牢屋の暮らしも二百文を授かった遠島も、感謝の気持ちとして捉えています。
それは金額の多寡よりも、精神性の尊さが、庄兵衛との比較において描かれています。
ひとつはこの弟殺しを安楽死の視座から、テーマを投げかけています。
題材となったこの『翁草-流人の話』では「喜助は、教えのない民 (愚か者) ゆえの行為だが、悪意からではなく、死罪にはならなかった」という趣旨で書いてあります。この部分を鴎外は「高瀬舟縁起」という「高瀬舟」の解説の中で、
死にかかっていて死なれずに苦しんでいる人を、死なせてやる事である。
引用:森鴎外 高瀬舟縁起
ここに病人があって死に瀕して苦しんでいる。それを救う手段は全くない。そばからその苦しむのを見ている人はどう思うであろうか。たとえ教えのある人(賢い人)でも、どうせ死ななくてはならぬものなら、あの苦しみを長くさせておかずに、早く死なせてやりたいという情は必ず起こる。
引用:森鴎外 高瀬舟縁起
と問いかけ、教えのある人かない人か (賢いか愚かか) の問題ではないとしています。麻酔薬を与えて良いか悪いかという話になるとしています。鴎外自身が医者であり軍医総監であったことも影響しているのでしょう。
喜助は、弟は瀕死の状況と考えており、従来の道徳観と医学は、考えを異にする。つまり捉え方が違うとして「ユウタナジイ=楽に死なせる」という意味、すなわち「安楽死」の問題を提起するために、「高瀬舟」の話を書いたとしています。
鴎外は、今から百年以上前に、<知足>と<安楽死>の問題として捉えたとされている。
物と心、物心ともに豊かさを求めることは素晴らしいことですが、その前に、いかに生きるかの精神のあり方を問う作品でもあります。
※森鴎外のおすすめ!
森鴎外『舞姫』あらすじ|エリスへの愛か自己の保身か、青年の葛藤。
森鴎外『高瀬舟』あらすじ|あなたは喜助を、殺人罪で裁きますか?
森鴎外『山椒大夫』あらすじ|安寿と厨子王の童話を、現代に再生する。
作品の背景
高瀬川は京都にあります。徳川時代には京都の罪人が島流しを言い渡されると、高瀬舟で大阪へ運ばれます。高瀬舟とは高瀬川を行く曳船のことです。この船に京都町奉行の同心が同乗します。物語は「流人の話」(翁草『流人の話』巻百一七「雑話」よる) を題材にしています。
この小説は今から百年以上も前に書かれた作品です。「高瀬舟縁起」で鴎外がその解説として書いている通り、道徳観と医学の捉え方の違いを取り上げています。安楽死や尊厳死は繊細なテーマですが、鴎外はすでにこの時期に問題提起をしています。
発表時期
1916年(大正5年)1月、『中央公論』にて発表。森鴎外は当時54歳。明治、大正期の小説家であり、同時に評論家、翻訳家、陸軍軍医、官僚でもある。ドイツから帰国後1890年、「舞姫」の発表で日本における近代小説の先駆的な役割を果たすとともに1894年の日清戦争、1904年の日露戦争の時代を軍医として生きた人である。
理想や理念など主観的なものを描く理想主義を掲げた。「高瀬舟」は鴎外の晩年の作品である。