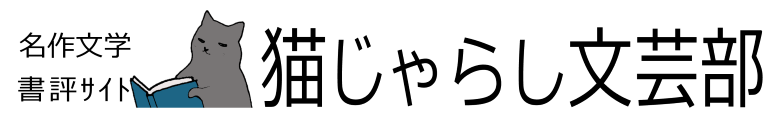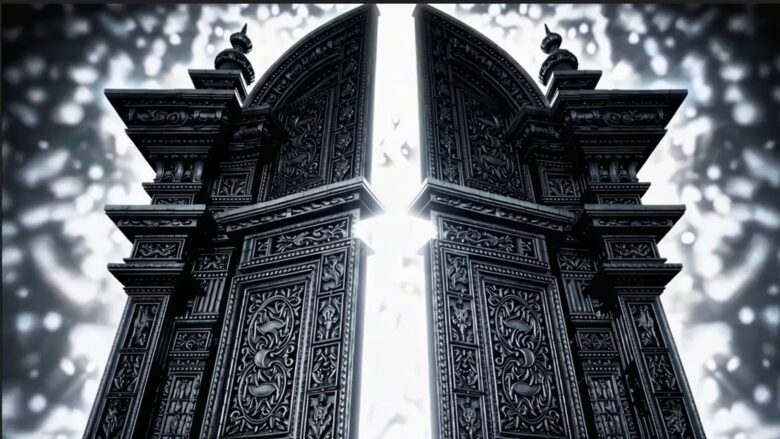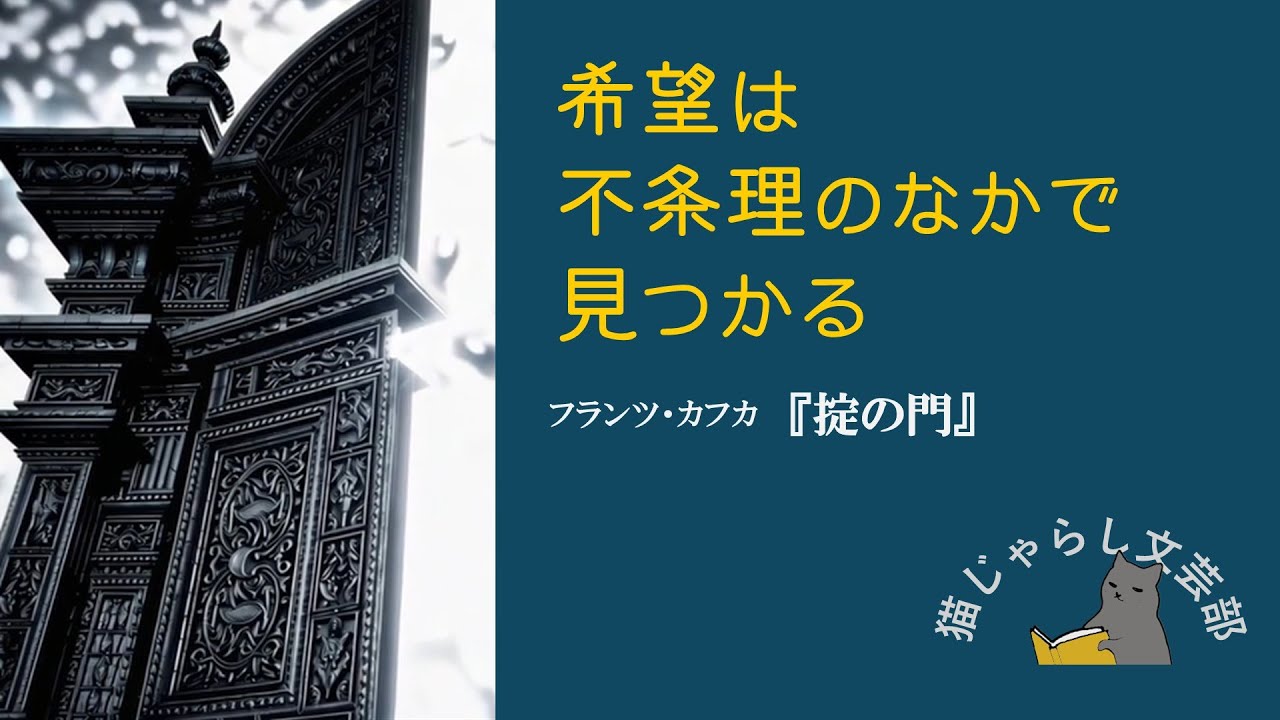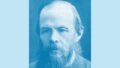このお話は、長編『審判(訴訟)』の「伽藍で(大聖堂にて)」という題の章のなかで、教誨師(聖職者)がヨーゼフ・Kにする“たとえ話” として挿入されています。その後(のち)に、この話の解釈をめぐって二人の会話が展開されます。
ヨーゼフ・Kの解釈を否定する教誨師(聖職者)は、書かれたものは不変だが、意見というものは、しばしば、そのことにたいする絶望の表現にすぎないのだ。と、語ります。
これこそがカフカの文学の特徴です。
この“たとえ話”が独立して、短編『掟の門(掟の前で)』として収録されました。
読者は、一体この話は何を言いたいのかと、カフカの文学に付き合わされるのです。この動画では、作品(書かれたもの)からの寓意を考えてみます。
★動画もあります、こちらからどうぞ↓
まず、話の内容(長編の挿話と短編は同じ)は次の通りです・・・
掟の前に門番が立っていました。ここに田舎《いなか》から男がやってきて、掟のなかへ入れてくれと頼みます。
門番は言います。「まだ入れてやるわけにはいかんな。」
男は考えてから、たずねます。「じゃ、後でなら入れてもらえるのかい。」
「ああ、そうだな」「でも、いまはだめだ」と門番は言います。
「そんなに入りたいなら、おれにかまわず入るがいい。しかし、おれは力持ちだ」
「中に入っても、次々に部屋ごとにすごいのがいる。」と、さらに門番は言います。
こんなことになろうとは男は思わなかった。掟の門は誰にでもいつも開かれているべきじゃないか、と思った。しかし門番が強そうなので、男は待つことにする。
門番が腰掛をすすめてくれた。門の脇に座ってもいいという。男は腰を下ろした。こうして何日も何年も待ちつづけた。
男は、入れてもらおうといろいろ試み、しつこく頼んで門番をうんざりさせた。
門番は尋問するような口調で、故郷のことなどあれこれ質問した。しかしそれは上から目線の気のない質問で、最後にはいつもきまって、「まだ入れることはできない」と言うのだった。
男は、この旅のためにいくらかの金品を準備してきたが、門番を買収するためにすべてを贈り物にした。その都度、門番は平然と受けとって
「おまえの気がすむならもらっておく。後でしのこしたことがあるなどと思わないようにな。しかし、ただそれだけのことだ」と、言った。
男は身の不運を嘆いた。はじめの数年は、はげしく声を荒げて、後には、ぶつぶつとひとりごとのように呟きながら。そのうち、子どもっぽくなった。
門番の毛皮の襟にとまったノミにまで、「おねがいだ、この人の気持ちをどうにかしてくれ」とたのんだりした。
そのうち視力が衰えてきたのか、あたりが暗く感じ、暗闇のなかに燦然ときらめくものがみえる。命が尽きつきかけていた。もう起きあがれない。男は、よくよく考えてこれまでしていない最後の質問をした。
「今さら、なにを知りたいんだ」と門番はたずねた。
男は「どうして何年たっても、ここにいるのは私だけなんだ、なぜ私以外の誰ひとり、なかに入れてくれといって来なかったのです?」と訊ねた。
命の火が消えかけていた。男の意識を呼びもどすかのように門番がどなった。
「この門は、おまえひとりのためのものだった。だから誰ひとり、ここには来ない。さあ、もうおれは行く。ここを閉めるぞ」
以上です。
長編『審判(訴訟)』では、ヨーゼフ・K(男の比喩)は、「門番が男を騙していると主張する」のですが、教誨師(聖職者あるいは裁判官)は、「門番は職務に厳格なだけだ」として、互いの異なる解釈が続きます。
すると教誨師は「君は書かれていることにたいする敬意が足りないぞ。物語を変えてしまっている」と、言うのです。
教誨師(聖職者)は、掟に入るのを許すことについて、門番は二つの重要な説明をしている。ひとつは冒頭、もうひとつは結末にある。と言います。
冒頭では、男に「今は入ることを許さない」と書いてあり、結末には、「この入口はお前だけのものだ」とある。ここに矛盾はない、というのです。
つまり門番は男を騙しているのではないことを証明し、次のように言います。
『ある事柄を正しく理解することと、その事柄を誤解することは、完全に排除し合うものではない』と教誨師(聖職者)は言います。
ある事柄を<正しく理解すること>と<誤解すること>は排除し合わないって、明言(迷言)だと思うのです。ひとつの事柄の善悪は見方の違いでもあるからです。
では、独立した短編『掟の門(掟の前で)』の寓意は何か。考えてみます
直感的な印象としては、
一度きりの自分の人生なのだから、何としても突破すべきだ!と言っているのだと私は考えます。
<掟>というのは、「人生の本質」というか、人生を方向づける理のようなもの、そして<・・・の前>とは、そこにはだかる困難や苦労ということにしてみます。これが「門番」です。
門番は、最初のほうで「そんなに入りたいなら、おれにかまわず入るがいい」とも言っていますよね。
確かに、門番は強そうですが、男は結局、実力行使には出てはいませんからね。
先ほどの書かれたものは不変だが、意見というものは、しばしば、そのことにたいする絶望の表現にすぎないのだ。ということですね。
そして年月が経ち、身体が衰え、男は何もせずに死んでゆき、門は閉じられようとします。確かにこうなっちゃうとすべてが終わりとなりますよね。
もう少し寄り添って、男はカフカ自身で門番は父親と仮定してみます。
カフカと父親の関係は有名です。父親は独善的で、意見は絶対に正しく、ゆずるということはありません。体も大きく(頑丈)、事業にも成功(裕福)し、絶大な自信(支配欲)を持っています。それに比べて、カフカは、身体は弱く、金儲けに興味がなく、家庭が裕福ゆえに上昇志向もなく、父親に逆らえず、青年になっても親の庇護のもとで暮らしていました。
価値観は全くあわず、暴君のような父親に対して、カフカは抵抗できないのです。しかしカフカは父の偉大さは認めています。
このようにカフカの実生活に照らして解釈しますと、将来への道を、父親(門番)が遮っている状態です。
例えば結婚をするとか作家になるという人生の岐路となる場所に父親(門番)がいて、カフカの行く手を阻んでいます。他の短編『判決』などでは、父親から婚約に反対されて主人公は川に飛び込んでしまうほどです。
『変身』を書いたカフカは、その内容を周囲にときどき笑いながら話すけれど、読者は、それを不条理と解釈(絶望の表現)するわけです。
先ほどの・・・書かれたものは不変だが、意見というものは、しばしば、そのことにたいする絶望の表現にすぎないのだ。はここでも言えますね。
何だそれだけのことか!って考えてしまうのは待ってください
では、もう少し俯瞰して、カフカの生きた時代背景から考えてみます。
そこにある-世の中の道理とか条理-それは神の掟であったり、法の掟であったり、習俗の掟であったりします。
カフカは、オーストリア-ハンガリー帝国の領土だったボヘミアの首都、プラハのユダヤ人地区の豊かな商人(父親)の息子として生まれます。ここには少数の富めるユダヤ人と貧しいユダヤ人がいます。さらに言えば、カフカの父親は貧しいユダヤ人から富めるユダヤ人へと成功した人物です。
だからこそ前述のように父親は暴君的なのでしょう。
ここは人種が混在したコミュニティです。大多数がチェコ人で、ユダヤ人は少数派でドイツ語を話す(同化)文化圏とみなされており、カフカは、自分はドイツ文化にもユダヤ文化にもなじめない半ドイツ人という感覚だったといいます。
自分は、どこから来た何者なのか? 今いる場所はどこで、これからどこに行くのか?
否が応でも実存の問題が浮かび上がります。
第一次世界大戦(欧州戦争)もカフカの生きた時代に起こっています。目まぐるしく変化する国境(版図)や国の名称。民族間の争い、ユダヤ人の思想、そこに現れる近代人の精神的な不安(病理)。いろいろなことに翻弄されたのではないでしょうか。
この短編では、男と門番が対峙しますが、私たちは生きるにあたって、顔が見えない得体のしれない社会の構造に対峙することがあります。
こちら側の正義が、異なる相手(国家、民族、宗教、法律等)には通じないのです。
民衆を痛めつけるような国家の権力や反社会的な状況のもとでは、私たちは諦めるしかないのでしょうか。いやそんなときはきっと戦うべきです。言論だったり、デモだったり、最後には革命だったり・・・
しかし現実には、そこまでエスカレートできない場合もあります。
そんなときに私たちの傍にカフカがいます。
カフカは、自分を強く主張し、利益を得るためには、手段を択ばず、他者を蹴落とし成果を誇るような、生き方はできません。そんな強さはないのです。まったく逆で、ぜんぜん弱いのです。もうだれよりも弱いのです。
そんなときはどうするのか・・・。それでも他人に転嫁したりするのは違う、社会に復讐するのは違う、罪もない人を殺めるなんて全くぜんぜん違う。
やっぱり突破しかないのです! しかしそれでもできないときには・・・
カフカの名言を以下のようにつないでみました。
あるのは目標だけだ。道はない。
われわれが道と呼んでいるのは、ためらいに他ならない。
そうですよね、そしてこんなことを言っています。
すべてお終いのように見えるときでも、
まだまだ新しい力が湧き出てくる。
それこそ、おまえが生きている証なのだ。
これって、いいですね・・・、でもこう続けています。
もし、そういう力が湧いてこないなら、
そのときは、すべてお終いだ。
もうこれまで。
そして極めつけのような言葉、
人生の意味とは、それが終わるということです。
最後は、達観(悟り)めいています。でもほら、戦うべきではないとはひとことも言っていませんよね。
権力の壁は厚く高く強く頑丈です、それに対して、ひとりひとりの人間は弱い。
しかし弱者だけが持つ強さだってきっとあるはずです。
だからカフカは書き、読者の解釈に委ねます。不条理に対して、ときには諦めて、冷笑(れいしょう)したっていいじゃないですか。不条理だからこそ、コノヤローって、心のなかで怒りをぶちまけたっていいとおもうのです。
自分のなかで闘ってみる、挑戦してみる。でも駄目だったりもする。
そんな絶望したくなる時-精神を病むほどの息苦しさや辛さ-そんな時にこそ逆に、カフカの文学を面白く笑っても良いかもしれません。
希望とは不条理のなかで生まれるエネルギーなのです。さっ、頑張りましょう!