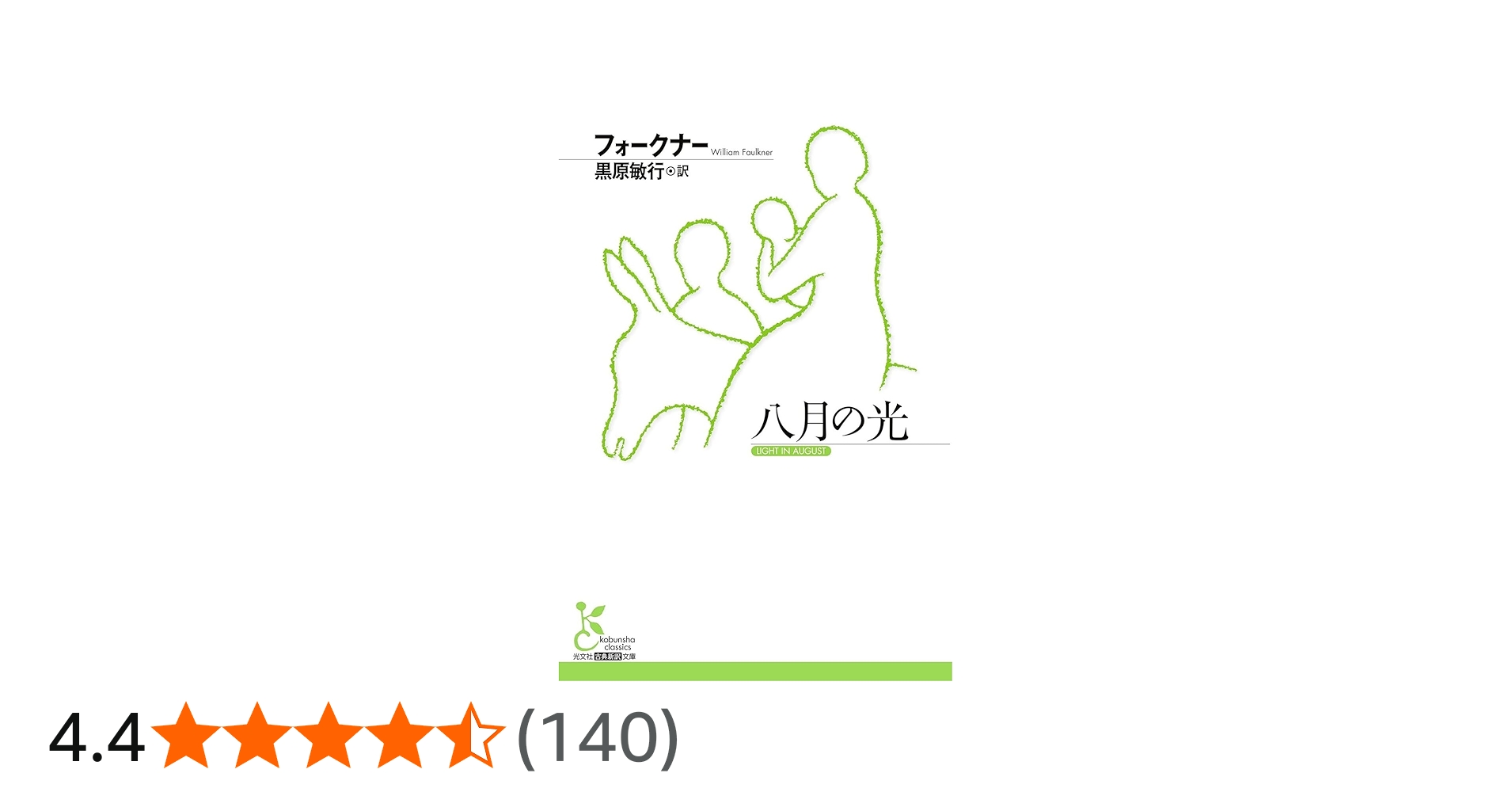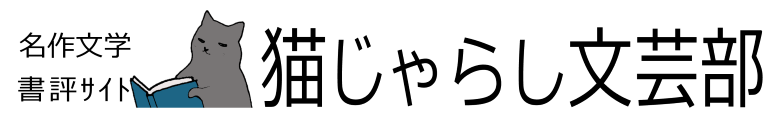最後に感想です
絶望のなかで、希望を見いだす
作品は、都会的ではなく土着的です。葬られた文化が過去から湧き上がるように、血族の熱狂や偏見があたりに充満します。
道徳や倫理という善悪の視点ではなく、歴史の事実で捉えると、始めに大地があり、先住民(ネイティブ・アメリカン)が住み、彼らの文明があった。そこにイギリス、フランスをはじめとするヨーロッパの人々が新大陸発見と叫び、入植をはじめ異文化が持込まれ、それまでの文明は葬られる。
新たな宗教(キリスト教)、暴力(武力と戦い)、狡猾な取引。さらには疫病(天然痘)と共に、白人が大地を占有する。
イギリスの植民地であった北米の13植民地が独立してアメリカ合衆国となる。さらに南西部に開拓が進み(マニフェスト・デスティニー)、インディアンは限定された居留地に追い込まれていく。
アフリカから黒人が労働力として連れてこられる。プランテーション(大規模農園-綿花やたばこ栽培)である。そこに封建制度が生まれる。そして独特の文化が形成された。白人(資本家)と黒人(労働者)の関係が色濃い共同体が基盤となる。
北部(アメリカ合衆国)は産業革命による工業化(近代化)が進み、 南部(農業と階級社会)との確執が深まる。南部には大規模農園があり黒人奴隷がいた。
自由貿易(南部)と保護貿易(北部)の経済構造の問題もあり南部(連合国)は北部(合衆国)から分かれ、南北戦争(シビルウォー)となり北部が勝利し、1865年に再統合され南部は管理下(リコンストラクション)に置かれる。
南部は、これまでと正反対の価値転換を求められる。近代化(資本)が押し寄せ、森は切り開かれ土地開発が進む。奴隷は開放されるが、現実にはさらに激しい人種差別や白人至上主義を産むことになる。
三世代(南北戦争後の70年くらい)に遡(さかのぼ)る南部の人々の敗北の記憶のなかで滾(たぎる)る熱狂と偏見の場所こそが、架空の土地ヨクナパトーファ郡ジェファソンであり、ここを舞台に、いかに人々が過去を背負って生きたかが描かれる。
まさに、トポスとしての役割を持っている。
孤独はどこから来るのか。故郷(共同体)そのものを根こそぎ喪失された時に何が起こるのか。自分がどこから来た、何ものかさえわからない。過去から断絶され、拒絶される。
日本に置換えてみます。1945年8月の敗戦で、一夜にして価値観は反転する。それまで信じていたもの全てが過ちだと否定され葬られたときに、人間の魂はどうなるのか。
作者のフォークナーは、1955年、日本に来て講演を行いました。戦後10年です。この少し前、1952年から日本はサンフランシスコ講和条約を経てGHQの管理を解かれています。「もはや戦後ではない」と1956年の経済白書は高らかに謳います。つまり日本政府は焼け跡から戦後復興を果たした、近代を取り戻したというのです。
講演で、フォークナーは語ります。
人間はみずからの忍耐と強靭さの記録を必要するものだということを最も強く人間に思い起こさせるのは、戦争と破壊である、そう私は信じています。私の国「南部」にあっても、まさに破壊のあとにこそ、すぐれた文学がよみがえってきたのですから。(中略) 私はこれととてもよく似たことが、ここ数年のうちにこの日本でも起こるだろうと信じます。あなたがたの破壊と絶望のなかから、全世界がその声を待ち望むような、日本だけの真実ではなく普遍的な真実を語るような一群の作家たちが誕生するだろうと信じているのです。
この作家たちという言葉で、私は反射的に中上健次の岬、枯木灘、血の果て至上の時という秋幸三部作、そして秋幸の母を描いた鳳仙花を思う。
因みに、極東軍事裁判(東京裁判)で戦勝国アメリカに裁かれた日本。そのとき法律家として中立な立場であったパール判事の言葉が顕彰碑に刻まれています。
「時が熱狂と偏見とをやわらげた暁には また理性が虚偽からその仮面を剥ぎとった暁にはその時こそ正義の女神はその秤(はかり)を平衡に保ちながら過去の賞罰の多くにそのところを帰ることを要求するであろう」
なぜか線上にあるはずのない海を越えたアメリア南部の戦争の歴史と日本の戦争の歴史が重なってしまうのは私だけでしょうか。
ミシシッピ州は、過去には絢爛な貴族文化が花開いた場所として壮麗なイメージを持つ反面、激しい人種的偏見の憎悪に包まれた負のイメージという光と影を併せ持つ場所なのかもしれません。
敗戦と奴隷制度の崩壊、一夜にして善と悪の価値が逆転し、その反動から過去の栄華への幻影、そのなかで古い慣習に拘ろうとして「抑圧」の概念が「ワンドロップ・ルール」というおぞましい姿で現れ、リンチ(私刑)やテロが跋扈する。
やがて近代化の波は、南部の白人たちの差別的なイデオロギーもキリスト教精神も浄化していく。そして自らの自己実現に駆り立てられる人々は、ばらばらの個人になっていく。こうしてかつての南部が、その歴史が、その時間が記憶の古層に沈んでいく。
クリスマスの魂が、安らげる場所はありませんでした。それは悲劇です。
ハインズ婦人(クリスマスの祖母)がリーナの赤子をジョーイ(クリスマス)と呼ぶと、リーナはこれを強く否定します。新しい生命(いのち)は、同じ運命をくりかえさない、新しい未来に向かって進むべきだ、という強い意志を感じます。
人間は精神や、夢、プライドを捨ててはならないことを教えられる気がします。リーナから産まれた新たな生命の誕生と、その新しい旅を寿ぐと同時に、クリスマスの死の記憶もまた忘れ去ってはならないものなのでしょう。
すべての歴史をるかのように「八月の光」は、遠いギリシアのオリンポスの神々のすむ山から、その遠い古から、淡く柔らかな光で大地を包み込んでいるのかもしれません。
そしてジェファソンというこの架空の町で起きたドラマこそが、人々の心に刻まれる故郷(ふるさと)になってほしい。
そこに存在したもの、そこから消失したもの。記憶を思い起こし、忘れ、また蘇らせ、その繰り返しのなかで、きっと人間は希望とともに新しい未来に向かって生きていくのでしょう。