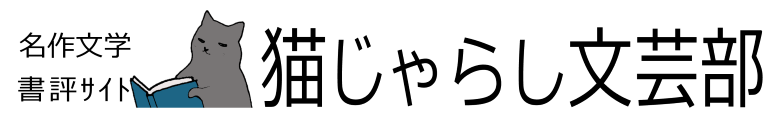著者のルース・ベネディクトは文化人類学者であり、主著である『文化の型』(1934年)は、戦前のアメリカで広く読まれた著作です。人間の信念や慣行はそれぞれの文化によるという、文化相対主義の考え方に基づいたものでした。
原型は報告書で、表題は「Japanese Behavior Patterns (日本人の行動パターン)」というものです。
コロンビア大学の助教授(1936年)だった彼女は、アメリカ軍の戦時情報局(諜報・プロパガンダ機関)に迎えられます。この組織は、軍部や各方面の優秀な人々が集められており、1944(昭和19)年6月に彼女は海外戦意分析課の日本班チーフとなります。
当時は、戦争のただなかです。アメリカはこれまでの経験が通じない日本軍との戦いをしていました。
なぜ日本人は捕虜になるよりも死を選ぶのか、なぜ天皇のために死のうとするのか、分からないなかで、アメリカ軍の被害を最小限にして、いかにして戦後の日本の統治を円滑にすすめるかが喫緊の課題でした。
そのために彼女に課せられたテーマは「日本人とは何者か?」を徹底解明した報告書をあげることでした。
そして戦後、一般人向けに加筆、出版(1946(昭和21)年)されたものが、本書『菊と刀』となります。
★動画もあります、こちらからどうぞ↓
我々は、自虐史観を植えつけられたとか、外形上は、主権は回復(1952(昭和27)年)したが、真の独立は果たしていないと言うことがあります。
ベネディクトの報告書が、どの程度、影響したかは不明ですが、少なくとも、日本の固有の文化や日本人の考え方、行動規範が分かったはずです。
GHQの戦後統治(日本の文化統治戦略)を経て、戦後80年、「日本人はどうなったのか?」について考えてみよう思います。
尚、文化人類学という学問は、現地に実際に赴き、相手の生活の中に入って、一定期間、観察をするフィールドワークによって確立されるものですが、彼女は、日本を訪れたことはありません。 その点は批判の対象となっていますが、戦時中ゆえに叶わないことでした。
しかし多くの日本の小説や映画、文献資料を読み込み、日本滞在経験のある同僚、さらには日系移民1世と2世(1世と2世では意識差が出る)へのヒアリングなどがベースとなっています。
<第1章 研究課題-日本>の部分で、疑問が集約され答えが出されています。
それは日本人の二面性です。
それまで、死を恐れぬ戦いをした日本人が、刀を置き、喜んで駐留を受け入れたことです。ここがアメリカ人にとって最大の疑問でした。
その答えとして、日本における善悪は、欧米が理解しているものと、天と地ほど異なっており、価値体系は特異なものであった、としています。仏教でもなければ、儒教でもない。それは日本的なものであった。そこに日本の強みも、弱みもあった。とまとめられています。
それは、「恩と義理」そして「恥」というアメリカ人には分からない日本人独特の価値に起因するものでした。 ここにすべてがあるのだと思います。
私たち日本人は自分たちを二面性のある国民だと思っているでしょうか?
私は、そうは思えません。しかしアメリカ人から見ればそう見えるわけです。
決定的な事実は、1945年8月15日の終戦の詔勅を境に、その前の「日本」は天皇を頂点とする「皇国史観」、その後の「日本」は国民を主権者とする「戦後民主主義」となったわけです。何の抵抗運動もなく粛々と政体の転換が行われたのでした。私たち日本人は自分たちを二面性のある国民だと思っているでしょうか?
私は、そうは思えません。しかしアメリカ人から見ればそう見えるわけです。
決定的な事実は、1945年8月15日の終戦の詔勅を境に、その前の「日本」は天皇を頂点とする「皇国史観」、その後の「日本」は国民を主権者とする「戦後民主主義」となったわけです。何の抵抗運動もなく粛々と政体の転換が行われたのでした。
それはアメリカ人にとって驚くべきことでした。
本書(『菊と刀』)では、日本人の行動パターンを、
第2章 戦時下の日本人、第3章 応分の場を占めること、第4章 明治維新、第5章 過去と世間に負い目がある者、第6章 万分の一の恩返し、第7章 義理ほどつらいものはない、第8章 汚名をすすぐ、第9章 「人間の楽しみ」の領域、第10章 徳目と徳目の板ばさみ、第11章 鍛錬、第12章 子供は学ぶ、第13章 敗戦後の日本人に分けて示しています。
ここでは ⑴ 個人主義と集団主義 ⑵ 恩と義理 ⑶ 罪と恥の3つに集約して説明し、私見をまじえてみたいと思います。
⑴ 個人主義と集団主義
私は、二面性があると捉えられる前提には、アメリカ人は個人主義と日本人の集団主義の特性の違いがあると考えます。
日本では家族という最小単位において、前近代から続く厳格な序列があり、そこには子から親への尊敬と恩の感情が強く現れます。この時点で、個人を尊重するアメリカの価値観とは異っています。この淵源には、神(西欧)VS 先祖(日本)という違いがあるようです。
鎌倉幕府から武士が権力を持つ時代が長く続きましたが、明治維新によって、御簾(みす)の向こう側の権威だった天皇が、表舞台に出てこられます。大きな転換期です。
天皇は絶対(神聖)であり、国民(臣民)は天皇の大御宝(おおみたから)で、君民一体となる。日本は、最小単位の家から始まり、隣組や共同体、行政単位(町村、市、県)から国家(中央)、そして天皇へと一直線につながる。
さらに天皇は父方の血統をたどれば2600年に遡る(万世一系)。つまり、日本とは、ひとつひとつの家の単位(家族)が集って形成された巨大で強固な有機的存在と再定義されたのです。
天皇は臣民を慈しまれている。だから天皇への恩が最高であり、皇恩に報いるのが臣民の義務である。
これは歴史の浅い、清教徒から始まった移民国家であり、WASP(ホワイト・アングロ・サクソン・プロテスタント)が中核となり多民族が集うアメリカとは異質だと考えるのは容易だと思います。
さらに、アメリカ人と日本人の<子供期>と<壮年期>と<老人期>の比較が面白い。“山”と“谷”の曲線を思い描いていただき、縦軸に“自由度”、横軸に“年齢”をおきます。
アメリカでは<子供期>と<老人期>に自由は少ないが、日本はこの時期に自由が多くある。逆に、アメリカでは<壮年期>に自由が多くあるが、日本ではこの時期に自由が少ない。正反対なのです。
アメリカでは、壮年期に選択の自由を最大化し、日本では、壮年期に個人に対する制約を最大化する。壮年期は、肉体的な力とお金を稼ぐ力が頂点に達する時期であるにもかかわらず、日本では自分の人生を思い通りにすることができない。
壮年期の制約は優れた精神的訓練(修養)になると考えている、としている。
アメリカ人は何かを成し遂げるための前提として自由を強調する。日本人は自制を貫く ことで自己の価値が高くなるという観念を受け入れている。
なるほどなぁと思う。日本人が大切にする調和という国民性も壮年期に最大化されるのだろう。そして高度成長期には一定のボリュームとして中流の所得階層が生まれたという言い方もできると思う。
私は、このあたりは個人主義と集団主義の比重の起き方の違いだと思う。
会社を家族と考えたり、個の能力よりも集団の能力を優先する考えは日本らしさだったと思う。企業のなかの雇用形態(終身雇用)や作業効率(カイゼン活動)、あるいは株の持ち合いや護送船団方式などは特徴だった。
しかし現在、欧米の基準を持ち込むことで、従来の日本の強みを失っているのではないかと思う。結果として能力主義による格差の拡大を生んでいる。これを是とするか否かは人それぞれだろう。
⑵ 恩と義理
次に日本では集団の行動規範としての道徳が社会生活のなかにある。儒教の流れから仁なども紹介されているが、焦点となるのは「恩と義理」である。中世には武士道のような厳しい所作もあった。
日本人は、親や他人に対してお世話になった、世間のおかげをこうむっていると考えているが、欧米人はこれを極度に軽視する。日本人は「恩に着る」「恩を忘れない」「恩着せがましい」などの言い方をする。
ここでの「恩」は、返すべき「借り」がある状態である。つまりは、「恩」は“貸借”を伴っているとベネディクトは指摘する。欧米人にこの考えは少ない。近いものとして「愛」があるが、愛は与えるだけのもので、返しを求めない。違うものだ。
ここで夏目漱石の『坊ちゃん』のエピソードが紹介される。
坊ちゃんは東京から松山(四国)の中学校に赴任する。いやな奴ばかりだと思いながらも、気のよさそうな同僚の山嵐と親しくなる。ある日、山嵐から氷水一杯(50円程度か)を奢ってもらったことがあったが、山嵐が坊ちゃんの悪口を言っていると噂を聞いてお金を返そうとする。坊ちゃんはあんな奴(山嵐)に「恩を着せられる」のはまっぴら、即刻、「恩を返し」清算しようとする。
これが恩の貸借の例え話となっている。分かりやすい指摘だと思う。日本人なら「まっすぐな性格で、曲がったことが大嫌い」な坊ちゃんの性格として微笑ましく読み進んでしまう。しかし、欧米人にはわからない。氷水一杯、奢ってもらったことをそう仰々しく考えない。
親と子と繋いでいくこんな言葉がある
「子を持って初めて知る親の恩」ここで日本人は両親に対する恩返し-孝-という義務があり、さらに国民として天皇に対する恩返し-忠-という義務が生じる。戦争の行動規範は皇恩を返すことに他ならないとしている。
⑶ 罪と恥
アメリカ人(西洋)は罪の文化であるが、日本人は恥の文化だとベネディクトは指摘する。欧米人は神との関係において、「罪」の意識があるのに対して、日本人は他者(世間)との関係において「恥」の意識があるというのだ。
日本人は「恩と義理」に背けば、家族や世間、社会集団から疎外される。これは恥である。だから恥をかかないように徳を積み生きなければならない。この徹底ぶりは社会学的に見て珍しいという。
例えば、日本人として民族や国家が屈辱を受けるとする。悪口や嘲笑、不名誉を強要されたとき、それを恥として、報復することが美徳とされている。ただ結果として、敗北すれば「当然の帰結」は甘受する。という。
言うまでもなく、ここで問題となったのが天皇である。天皇の地位の保全は、国体護持そのものであり、戦後日本にとって最重要の課題だった。
大日本帝国憲法では、天皇は「神聖にして侵すべからず」であり、現行の日本国憲法では天皇は「日本国民統合の象徴」となっている。
天皇はマッカーサーを訪問し、マッカーサーから神性を否定してはどうかと勧められたときに、「日本人は天皇を欧米流の意味での神とは考えていない」と答えたが、マッカーサーは欧米諸国は、天皇が自己の神性を主張していると受け止めており、日本の国際的な評判にとって望ましくないと言う
天皇はマッカーサーの説得により、誤解されるのを覚悟して自分が現人神であることを否定する。
そんな経緯を紹介している。日本人の「恩と義理」や「恥」の意識を注意深く丁寧に扱い、それでも天皇に人間宣言をさせて、しかし国体は護持したということだろう。
朕ト爾等国民トノ間ノ紐帯ハ、終始相互ノ信頼ト敬愛トニ依リテ結バレ、単ナル神話ト伝説トニ依リテ生ゼルモノニ非ズ。天皇ヲ以テ現御神トシ、且日本国民ヲ以テ他ノ民族ニ優越セル民族ニシテ、延テ世界ヲ支配スベキ運命ヲ有ストノ架空ナル観念ニ基クモノニモ非ズ— 『新日本建設に関する詔書』より抜粋
現代語訳にすると以下のようになる。
私とあなたたち国民との間の絆は、いつもお互いの信頼と敬愛によって結ばれ、単なる神話と伝説とによって生まれたものではない。 天皇を神とし、または日本国民は他より優れた民族だとし、それで世界の支配者となる運命があるかのような架空の概念に基くものでもない。
この部分は、日本人と日本文化を考える上で、最大の出来事だったのではと考える。
破滅覚悟の本土決戦を行うのならば別だが、復興し、未来の日本に希望を繋ぐために、まさに歴史の転換であり、大英断だったのだと思います。
ただし、私はアメリカ人が罪の意識が高いとは思わない。寧ろ、罪を犯せば告白し、悔い改めて、神の許しを請う、それで済むのかという感情すらもっています。
選民意識の下、他の文化を侵略した歴史はどうなるのか?アジア、アフリカ、アメリカ(ネイティブインディアンや南アメリカも含む)の文化を破壊したではないのか。
先の戦争においても、日本への原爆の投下や東京や主要都市への空爆による無辜の民の殺戮(さつりく)は、どうなるのか?
極めつけは、戦勝国による極東軍事裁判(東京裁判)という茶番を見せ物として行った。
しかし敗者である以上、勝者の論理に従うしか、その先の独立もなかったということなのだが・・・。
西洋文化を輸入し近代化を急いだ明治以来の日本の葛藤(漱石や鴎外があらわしている)そのものが、二面性なのかもしれない。
天皇が君主であり、国民は臣民である。天皇を現人神として観念化し、仏教を捨て、国家神道をうちたて、国体明徴声明から国体の本義(1937年に文部省思想局が発行)として発表し、結果的には、西洋近代と旧来日本の葛藤のなかで、平仄があわないちぐはぐな形で突き進んだ先の戦争だったのではないでしょうか。
GHQの戦後統治の方法が、日本の「集団主義」や「恩と義理」や「恥の文化」をうまく利用し、直接統治ではなく間接統治を行い、日本国民のなかに協力者(旧軍人、官僚、政治家、マスコミの一部)をつくり、彼らに実際の運営を任せることで自虐史観の装置を何重にも埋め込んだ。
戦後80年経って、アメリカの機密文書の開示などにより、事実を知り始めた一般の国民たちは、協力者たちの行為を恥と感じているでしょう。
いつかどこかでそれは断ち切られなければなりませんでした。しかし現在でも、装置は機能しているのではないかと疑いたくなるほどです。
ベネディクトの思い
終章(第13章 敗戦後の日本人)で、ベネディクトは「菊」をたとえに、これまで窮屈な植木鉢のなかで育てられてきたものが自然の状態で根を伸ばし純粋な喜びを発見すること。「期待を裏切る自由」、「恥の拘束力を疑問視する自由」を持つことで、新たな生活様式を構築できれば「個人の自制」という旧来の義務から解放され美しく咲くことができるとしています。
そして、その精神の自由が拡大するために必要なものが自己責任であるとして、
「刀」をたとえに、日本人は自己責任を「身から出た錆」を自らが防ぐことだと説明しています。人の身体を刀になぞらえて、刀を差している武士は、刀のまばゆい輝きを保つ責任がある。これからの日本人は自らの行動に対して「美徳を守る自己責任」を徹底しなければならない。として「菊」と「刀」に言及しています。
「菊」の美しさを追求しながら、「刀」という強さを輝かせるという、日本人の二面性を、戦後の新しい時代に向けて、より素晴らしく発展させてほしいという日本文化と日本人への敬意と希望をこめたメッセージと捉えるべきでしょう。
文化相対主義(文化に優劣は無い)を唱えるベネディクト博士(はかせ)の優しい眼差しであると私は思います。
・・・で、80年経った現在(2025年)を思う。
日本人の「菊」と「刀」はどうなったのか?ということである。
ベネディクトが期待した、新しい時代における「菊」-つまりは「個人の自制」からの解放については、現代の人々はかなり自由を満喫していると思う。
しかし同時に、個人の自由が、バラバラな個人の孤独という問題を生みつつあるのも事実かと思います。
もうひとつの新しい時代における「刀」-この自己責任の意味は人格形成であり、まさに自由の基盤となる誇れる日本人の姿かと思います。その意味では、刀の鋭さ、輝き、強さをもっと磨く必要があるのではないでしょうか。
「個人主義」か「集団主義」か。これはバランス感覚の問題だと思いますし、決して欧米のような個人主義だけに重点を置く必要は無いと思います。
目覚ましい戦後復興と豊かな国の仲間入りを再度なしえたのは、それぞれの産業の分野で勤勉な日本人がいたからだし、りっぱな官僚もいたのだと思います。
「罪」と「恥」の比較においても、日本人の「恥」の意識が、負の同調圧力という空気の支配や無謬性という責任回避に繋がっている場合はよくないことですが、一方で、不道徳を恥とする意識が薄らいでおり、法の範囲なら何をしてよいという人間が増えている感じがします。
「刀」の象徴である武士道の意識はすたれ、「恥」の意識はなくなり、国民の幸せよりも、権力と金が欲しいだけの日本人が増えてはならないと思います。
外面は、りっぱな先進国のようで、内面は、腐り始めているのかもしれません。売国の政治家、その手先のマスコミ、御用学者の言説、そんなエリートを自負する人びとの嘘に気づきはじめている人々は増えてきています。
私は、若者たちに多くの期待を寄せます、いつも新しい時代は若者たちが担っていると思います。
現在のグローバリズムの大波のなかで、若者たちを信じ、良識ある普通の大人たちが参加して、真に国を憂う指導者を支持し、美しくしなやかで強い日本をつくっていかなければならないと思うのです。